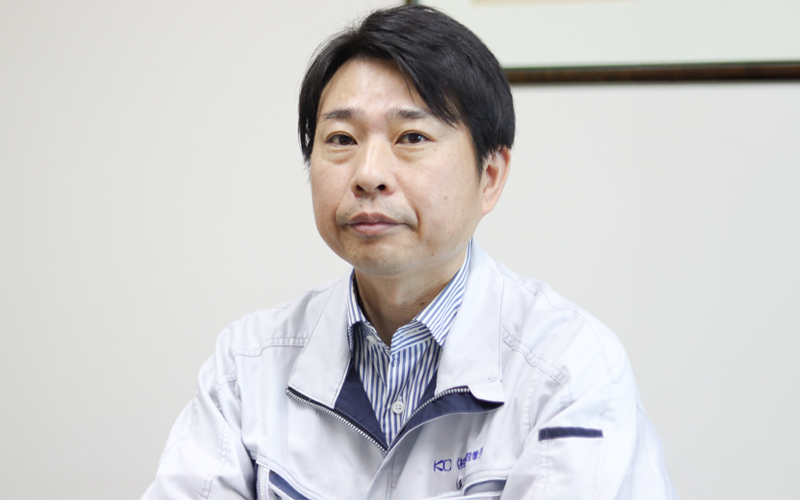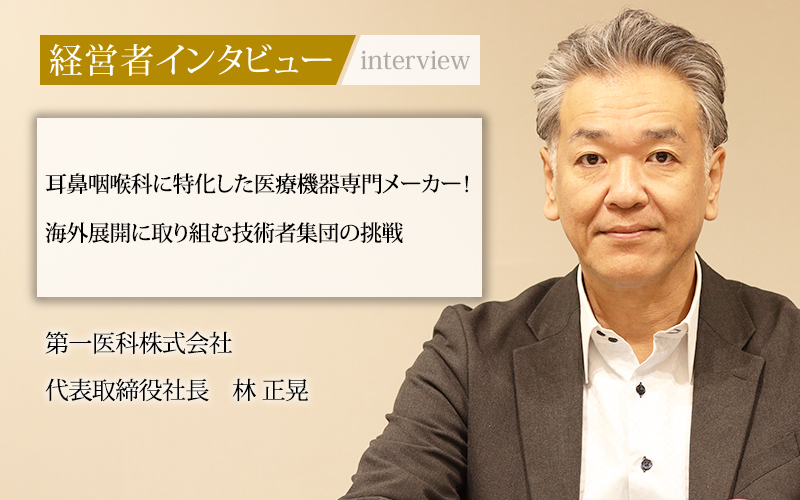
花粉症、中耳炎、難聴といった疾患に対応する耳鼻咽喉科は、多くの人々にとって身近な存在である。その耳鼻咽喉科に特化した医療機器を製造するメーカーが、第一医科株式会社だ。2025年に70周年を迎える同社は、1955年の設立以来、長年にわたり培ってきた技術を基盤に、より充実した医療を追求し続けている。
そんな同社を率いる代表取締役社長の林正晃氏に、入社に至るまでの経歴や会社の強み、そして未来の展望について話をうかがった。
突然迫られた事業承継と自分の強みを活かす経営
ーー貴社に入社するまでの経緯を教えてください。
林正晃:
弊社は父が創業した会社ですが、もともと継ぐつもりはありませんでした。ただ、耳鼻科を始めとしたお医者さんの話しを父からよく聞いていて、それが普通だと思っていました。小学生の頃は機械やパソコンが好きで、大学は理系の道に進み、就職活動もIT関係を中心に探していました。
しかしながら、製薬会社に勤める先輩が話す「人と深いコミュニケーションをとる仕事」のやりがいに惹かれたことがきっかけで、中外製薬株式会社に入社しています。
中外製薬では病院を訪問して多くの医師や看護師の方々の困り事や悩みをお聞きし、自社の薬の話だけでなく深くお付き合いすることで、充実した日々を送っていました。そんな折、父が倒れたと知り、悩み抜いた末に家業を継ぐことを決意したのです。
1998年の入社以降は、もともと勤めていた大先輩方に認めていただくため、幅広い業務を経験しました。当時、父は少しずつ回復していたものの、まだ思うように動けない状況でした。そのため、父の右腕である方々から教わりながら、機器の製造出荷業務からカタログ作成、学会展示や営業活動など多岐にわたる業務に携わりました。
また、会社にパソコンが数台しか無い時代でしたが見積り作成を支援するエクセルのマクロを自作して営業マンの生産性をあげるなど、新しい取り組みも始めました。今では当たり前かもしれませんが、グループウェアやスマホ活用などの業務効率化への取り組みは、中小企業としては導入が早かったものと思われます。
今でも、耳鼻咽喉科の医療機器という専門性が高い分野でその専門性を守りつつ、スタートアップ企業のように新しいものを生み出したり改善することにも積極的に取り組んでいます。
縁の下の力持ちとして医療を支える技術と情熱
ーー医療機器メーカーとしての貴社の使命について、どのようにお考えですか。
林正晃:
弊社は耳鼻咽喉科の医療機器専門メーカーとして、病院でドクターが外来や検査、手術で使用する機器を、画像ファイリングシステムのようなデジタル機器から治療用椅子のような設備機器、メスやピンセットまで幅広く取り扱っています。そして日々、医療機器を開発そして提供する弊社の使命として、2つの重要な柱があると思います。
1つ目はどんな時でも安定して医療機器を提供することです。かつて東日本大震災で、弊社の主要な製造拠点であった気仙沼の工場が津波で流されてしまったことがありました。このような事態で機器提供が途絶えると、困るのは患者様です。患者様がどんな時も安心して医療を受け続けられるように、サステナブルな医療機器の提供を実現することが欠かせません。
2つ目はより良い医療の追求です。医師の先生方がさらに質の高い医療を提供できるように、ともに考え、支える存在でありたいと考えています。コンプライアンス、品質、安全を徹底することは競合他社との差別化要因となり得ますが、それだけでは会社の成長にはつながりません。
弊社ではここ10年間、「他にないものをつくる」ことを大切にしてきました。医療機器の専門家として耳鼻科医療のエキスパート集団を目指す私たちですから、先生方と一緒に世の中の医療をより良いものにしたいと強く願っています。
ーー貴社の強みはどのような点にありますか?
林正晃:
弊社の一番の強みは、社員が非常に優秀であることだと思います。専門性の高い領域を扱う中で、各自がその専門性を磨き続け、高いスキルを維持していることが特長です。さらに特筆すべきは、社員一人ひとりがエキスパートでありながら、幅広い分野に対応できるゼネラリストとしての役割も果たしていることです。
たとえば、製造部門の社員が設計やメンテナンスも担当したり、営業部門の社員がマーケティングや商品開発まで手掛けられたりと職種の枠を超えて多様な業務に対応できる柔軟性が、弊社の大きな強みといえるでしょう。
海外展開で切り拓く未来。日本の技術が築く医療の新スタンダード
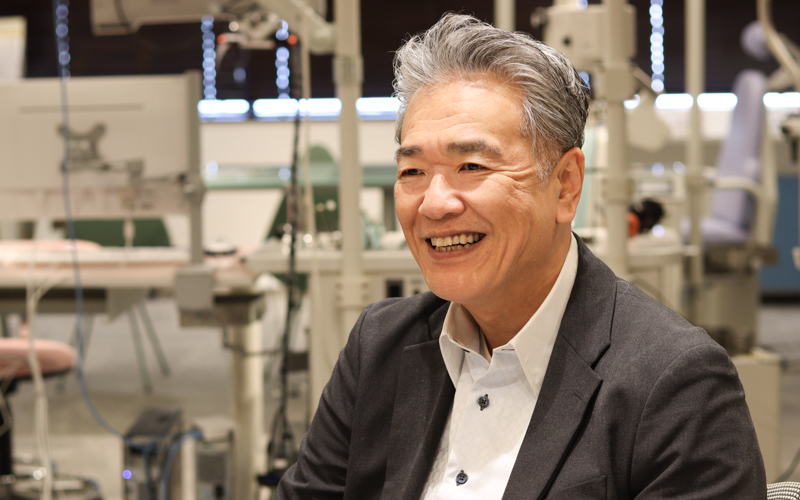
ーー最後に今後の展望について詳しく教えてください。
林正晃:
耳鼻科では、耳、鼻、喉、それぞれの疾患に加え、耳の奥にある三半規管がつかさどる平衡感覚まで、多様な症状への対応が求められます。弊社ではこれら4つの領域において、医師の先生方と共同研究を進めながら、海外の事例も参考にした新商品開発に取り組んでいます。
さらに今後は海外展開も検討しています。30〜40年前は東南アジアで日本の医療機器が普及しており、日本を訪れた医師たちが日本式の医療を導入するために機器を購入していました。しかし、私が入社した頃にはアメリカやヨーロッパで学ぶ医師が主流であり、使われる医療機器が変わっていったのです。
私も約20年前に初めて海外の耳鼻科を視察しましたが、日本の医療と異なる点が多く、そのまま機器を輸出しても受け入れられない可能性があると感じました。そこで考えたのが次の2つの方法です。1つは日本で活躍する医師との連携です。
先生方が海外で学会発表をする際に、弊社の機械も一緒に紹介していただき、少しずつ輸出の道を切り開こうとしています。そしてもう1つは現地の医療に適した機器の開発です。こちらは道のりが非常に険しく、現地のパートナー企業との連携も模索しながら検討を続けています。
さらに、AIの活用などデジタル化への取り組みも進めています。私が大会長を務めた2024年の日本医療機器学会大会でも「医療と技術の融合をマネジメントが支えDXで加速する」というテーマを掲げました。
医療機器はもともと医療と技術が組み合わさったものですが、さらに医療に関わる方たちの働き方改革などマネジメントなどもテーマとしてデジタル技術の可能性についての議論を考えました。弊社でも、一番の強みである社員がAIなどの技術を用いてさらに便利な仕組みで効率化を図れるようデジタル化を促進させていきます。
編集後記
林社長の言葉には、人への深い信頼と医療への情熱が込められていた。耳鼻咽喉科という専門領域に情熱を注ぎ、医師との信頼関係を基盤にした取り組みは、まだ未知なことが多いめまいの症状を改善させたり、日本の医療機器を世界に広めていく一助となり得るだろう。また、デジタルに強い林社長だからこそ生み出せる業務効率化の仕組みは、今後ますます同社の成長を加速させていくのだろう。

林正晃/1971年、東京都生まれ。慶應義塾大学理工学部卒業。中外製薬株式会社に入社し、大阪でMRとして勤務。父が創業した耳鼻科医療機器に特化したメーカーである第一医科株式会社に入社。2005年、代表取締役社長に就任。