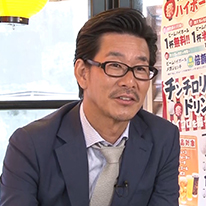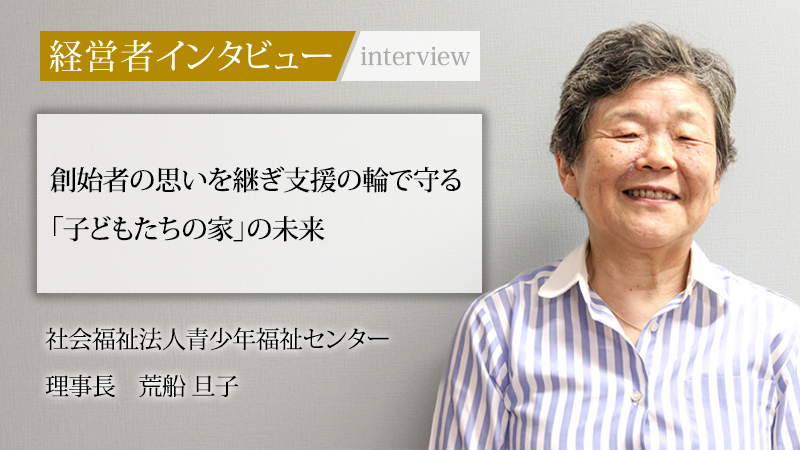
戦後の混乱期に、拠り所を失った子どもたちのために創設された社会福祉法人青少年福祉センター。創立から60余年、同法人は時代と共に変化する子どもたちの課題に向き合い、現在は主に虐待などを理由に家庭で暮らせない子どもたちを支援している。
特筆すべきは、その寄付の大部分が個人の寄付によって支えられている点だ。創始者である長谷場夏雄氏の「子どもたちの家をつくりたい」という熱い思いを継承し、5つの施設を率いるのが、理事長の荒船旦子氏である。荒船氏は、海外での豊富な経験を胸に、子どもたちの未来のために奮闘している。本記事では、法人の歩みと展望について話を聞いた。
支援の輪で紡ぐ60余年 創始者から受け継がれる「子どもたちの家」
ーー法人が設立された経緯と、創始者である長谷場氏の思いについてお聞かせください。
荒船旦子:
創始者である長谷場がこの施設を始めたのは、戦災孤児たちの「僕たちの家をつくってよ」という切実な言葉がきっかけだったと聞いています。その熱い思いが、今もこの法人には息づいているのです。創立は1958年ですが、行政から初めて補助金をいただいたのは1974年でした。それまでの間は、すべて寄付だけで運営してきた歴史があります。
ーー現在の運営は、どのように成り立っているのでしょうか。
荒船旦子:
私どもの運営は公的な措置費と多くの方からの寄付で成り立っています。今では2000人近い後援者の方々から寄付をいただいています。そのほとんどが、延べ400人ほどの個人の皆様からのご支援です。これほど多くの個人寄付で支えられている社会福祉法人は、全国的に見ても珍しいのではないでしょうか。
ーー支援者の方々との関係で、特に大切にされていることは何ですか。
荒船旦子:
皆様への感謝の気持ちをきちんとお伝えしたいという思いから、いただいたご寄付に対するお礼状は、すべて私と職員の手書きにこだわっています。先日も遠方から野菜の寄付のお申し出がありましたが、私どもでは基本的にすべて受け入れています。何事も当たり前だと思わず、感謝の気持ちで相手を思いやることが基本です。
5つの施設を一つにまとめた組織づくりの歩み
ーー理事長に就任されてから、特に力を入れてこられたことは何でしょうか。
荒船旦子:
私が常務理事になった頃、都内に5つある施設がそれぞれ別々に運営されている状態でした。これを一つの法人としてまとめたいという強い思いがあり、まずは各施設の責任者が集まる「事業所長会」を立ち上げました。今では5つの事業所の職員同士がとても協力的になり、法人全体の一体感が生まれたことは、本当にありがたいと感じています。
5つの施設をまとめるために、特別なことをしたわけではありません。とにかく各施設に顔を出して、職員たちと積極的にコミュニケーションをとるよう努めました。また、それまでなかった法人本部を新たに設立し、組織として機能するようにしました。現場の職員が子どもたちと向き合う時間を少しでも増やせるよう、事務的な負担を軽減する狙いもあります。
ーー組織運営において、どのような点を意識されていますか。
荒船旦子:
福祉業界の常識だけに囚われていると、視野が狭くなってしまいます。そのため、数年前から、全く違う業界出身の方を常務や部長として迎え入れています。さらに、理事や評議員にも弁護士、神父、医師といった様々な分野の専門家に参加いただいています。初めは戸惑いの声もありましたが、今では多様な視点から活発な意見交換ができるようになり、組織の活性化につながっています。
社会へ羽ばたく若者たちに贈る「一生のつながり」
ーーこのお仕事における、やりがいについてお聞かせください。
荒船旦子:
私たちの仕事は、子どもたちが施設を卒業したら終わりではないと考えています。だからこそ、目に見える達成感を得にくい仕事でもあります。その中で、私たちが法人全体で毎年行っている「成人式」は、職員にとって一つのご褒美のような機会です。ホテルを借りて、晴れ着やスーツに身を包んだ新成人が抱負を語ります。その姿を見ると彼らの成長を実感でき、職員も「この仕事をしてきて良かった」と感じてくれるようです。
ーー自立を目指す子どもたちに対して、具体的にどのようなサポートをされているのですか。
荒船旦子:
就労支援を目的とする自立援助ホームでは、子どもたちは働きながらお金を貯めて自立を目指します。中には日中働きながら夜間の学校に通っている子もいます。私たちは給料の使い方から教え、自立できるぐらいの貯金ができたらアパートを借りて一人暮らしを始める、という流れを支援します。行政からの補助金は施設の利用者と職員にしか使えません。そのため、卒業後に生活に困って帰ってくる子たちを支える資金は、すべて皆様からの寄付で賄っています。
「親代わり」として描く未来 目指すは施設が要らない社会

ーー法人としての夢や目標についてお聞かせください。
荒船旦子:
私の夢は、このような施設がなくなることです。子どもたちは皆、親元で安心して育つのが一番ですから。しかし、悲しいことに私たちの支援を必要とする子どもたちがいる限り、この事業を続けていかなければなりません。そのために、「東京一の施設にする」という目標を掲げ、職員全員でどうすれば実現できるかを考えています。
また、バザーやお餅つき大会などを通じて、地域の方々との交流を深め、いざという時に助け合える関係を築いていきたいです。将来的には、施設を建て替え、地域の方々が気軽に立ち寄れる相談事業の拠点も設けたいと考えています。卒業生がいつでも帰ってこられるアフターケアの場所をつくることが、私の次の夢です。
ーー最後に、子どもたちと向き合う上で最も大切にされている思いを教えてください。
荒船旦子:
私たちは、子どもたちの親代わりですが、本当の親にはなれません。あくまで、親が担うべき役割を私たちが肩代わりしているという認識です。たとえ物理的に一緒に暮らせなくても、親子が精神的にはつながっていてほしいと願っています。「産んでくれてありがとう」と子どもたちが思えるような関係が理想であり、そのために私たちは社会の基本である家族という単位を支えるお手伝いをしたいのです。
編集後記
「僕たちの家をつくってよ」という言葉から始まった法人の歩みは、そのまま日本の福祉の歴史と重なる。荒船氏が語る言葉の端々から感じられたのは、子どもたちへの深い愛情と、支援者への尽きることのない感謝の思いだ。「ボランティアはさせてもらうもの」という精神を胸に、今日も一人ひとりのお礼状を手書きする。その真摯な姿勢こそが多くの人の心を動かし、法人の未来を照らす光となっている。同法人の挑戦は、これからも続いていく。

荒船旦子/1951年7月4日生まれ。1972年、聖心女子学院専修学校保育科卒業。1973年、松濤幼稚園教諭として勤務し、1979年、結婚を機に退職。2003年、社会福祉法人青少年福祉センターへ評議員として入職。2008年常務理事、2017年には理事長として就任。その他にも、社会福祉法人東京福祉会 評議員、社会福祉法人オディリアホーム 評議員、一般社団法人日本・ラテンアメリカ婦人協会 副会長、一般社団法人アジア婦人友好会 監事を務める。