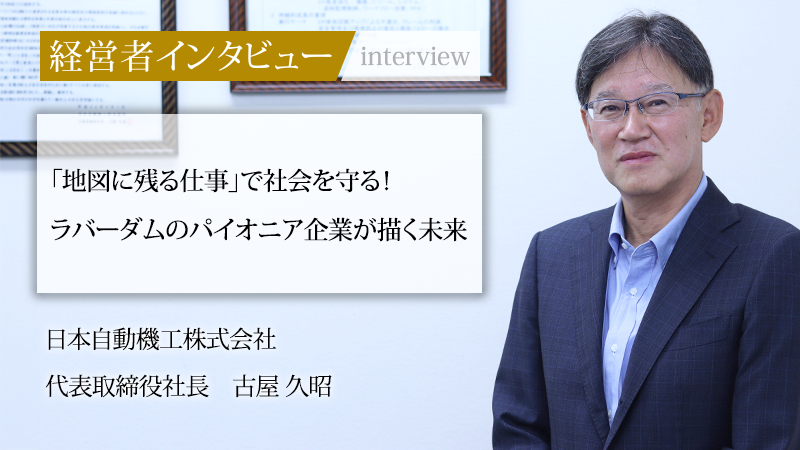
水害が頻発する現代において、河川の氾濫を防ぐ水門設備の重要性は増すばかりだ。その中で、ゴム製の水門「ラバーダム」を日本で初めて開発し、全国700カ所以上の施工実績を誇るのが日本自動機工株式会社である。代表取締役社長の古屋久昭氏は、三菱電機株式会社での勤務経験を活かし、家業の経営改革に挑戦。社員の意識変革と教育体制の整備に心血を注ぎ、会社を利益体質へと導いた。国内需要が縮小する中で、社会的役割の高い水門設備事業をいかに成長させていくのか。その経営戦略と今後の展望について聞いた。
大企業から家業継承へ 意識改革を重ねて利益体質を構築
ーー社長のご経歴と、現職に至るまでの経緯を教えてください。
古屋久昭:
埼玉大学卒業後、三菱電機株式会社で照明や空調機器などのマーケティング業務に16年従事しました。商品開発から販売計画の策定、工場勤務、販売会社への出向、本社業務まで、幅広い経験を積ませていただきました。
しかし、父の体調悪化を機に、家業を守るという責任を強く感じ、2002年に会社を継ぐことを決心したのです。
ーー大企業から家業に戻られて戸惑いやご苦労はありましたか。
古屋久昭:
父の代からの経営幹部との考え方のギャップには正直、苦労しました。最も深刻だったのがコスト管理です。コスト意識が希薄で、いわゆる「どんぶり勘定」が常態化し、営業利益がほとんど出ていない状況でした。
この体質を変えるには意識改革が不可欠でしたが、外部から来た若輩者の意見など、すぐには受け入れてもらえません。まずは実績で示すしかないと考え、中小企業診断士の資格を取得し、経営戦略やデータに基づいた改革を進めました。
評価制度の導入や会議の進め方、PDCAサイクルの徹底など、仕組みを一から構築する上で、前職での経験が大きな礎となりました。古参社員とは激しい議論も重ねましたが、やがて改革案を支持してくれる若い社員が現れ、今では彼らが会社の中心的な役割を担ってくれています。
ーー事業においてはどのような改革に着手されたのでしょうか。
古屋久昭:
弊社は日本で最初に「ラバーダム」を開発し、特許も保有していましたが、当時は残念ながら業界シェア1位ではありませんでした。そこで、事業をラバーダムに集中させ、このニッチな市場でトップを目指す戦略に舵を切りました。
同時に、主要な営業先を国(国土交通省)から都道府県へシフトしました。弊社のラバーダムは比較的小さな河川での需要が多いのですが、国の案件は書類作成や管理に多大な労力がかかります。取引の中心を県に移すことで社員の負担を軽減し、効率的に事業を進められる体制を整えました。これにより、粗利率は着実に改善し、安定した利益を生み出せる企業へと変わっていったのです。
忘れられないのが、2008年に業界大手だったB社がラバーダム事業から撤退したことです。それまで西日本はB社、東日本は弊社という暗黙の棲み分けがありましたが、その撤退によって西日本市場が完全に開かれました。当初は急増する需要への供給体制の確保に奔走しましたが、今では売上の3〜4割を西日本が占めるまでになっています。まさに、ピンチがチャンスに変わった瞬間でした。
設計から施工までの一貫体制と災害に備える人材育成

ーー改めて、貴社の事業の強みと現在の事業環境についてお聞かせください。
古屋久昭:
私たちの強みは、ラバーダムをはじめとする水門設備の設計から製造、据付、そしてアフターメンテナンスまで、すべてを自社で一貫して行えることです。小回りが利く弊社だからこそ実現できるこの体制が、お客様の信頼につながっています。
近年、公共事業の減少で新設案件は減少傾向にありますが、その一方で、頻発するゲリラ豪雨や水害への対策として、既存設備の更新や災害による緊急対応の案件が急増しています。社会的な要請はむしろ高まっており、正直なところ人手が足りていない状況です。
ーーそうした事業環境の中で、どのような人材を求めていらっしゃいますか。
古屋久昭:
新卒では、設計を担える機械・土木系の理系人材を特に求めています。中途採用では、土木工事の経験がある20代から40代の理系人材が不可欠です。素直で前向きな人柄はもちろんですが、「社会インフラを守る」という弊社の経営理念に共感してくださることが何よりも大切です。
ーー貴社で働くことで、どのような専門性やキャリアを築けますか。
古屋久昭:
国家資格である「土木施工管理技士」の取得を全社で支援しています。この資格は建設業界で高く評価され、自身のキャリアにおいて大きな強みとなります。さらに、水門設備の構造に関する特殊な知識も身につき、将来的には指導的な立場を目指せます。資格取得の費用補助や合格祝い金はもちろん、オンライン研修や現場研修、ベテラン社員によるOJTなど、早期に活躍できるよう、教育体制には特に力を入れています。
「エキスパンゲート」で世界市場へ挑む
ーー今後の展望についてお聞かせください。
古屋久昭:
2015年頃に一度インドネシアでの事業展開を試みましたが、維持管理や価格競争の壁に阻まれ、断念した経緯があります。しかし現在、新たな挑戦を始めています。B社と共同開発した下水道用の新製品「エキスパンゲート」です。これは欧米や中国のメーカーですら製造できない独自技術の製品で、現在、欧州企業と秘密保持契約を締結し、本格的な海外市場参入に向けて準備を進めています。
地図に残り社会を守る誇りある仕事
ーー最後に、未来を共にする仲間へメッセージをお願いします。
古屋久昭:
この仕事の最大の魅力は「地図に残る仕事」であることです。自分たちが手掛けた水門が、形として河川に残り、幾世代にもわたって人々の安全な暮らしを守り続けます。社会を支える誇りを胸に、未来を共につくる仲間と出会える日を楽しみにしています。
編集後記
大企業での経験を基に、データと理論で組織を変革してきた古屋社長の冷静な語り口が印象的だった。水門設備という、目立たずとも人々の安全に不可欠な社会基盤を守る事業。その分野で長期的な視点に立った人材育成に注力する姿勢は、企業の持続的な成長の鍵となるだろう。「地図に残る仕事」という言葉は、特に若い世代にとって、自らの仕事に誇りを持つ大きな動機となるに違いない。

古屋久昭/1963年生まれ、東京都出身。埼玉大学経済学部卒。1986年に三菱電機株式会社に入社し、16年間家電部門(電材住設事業部)に属し販売戦略・マーケティング業務に従事。2002年4月に日本自動機工株式会社に入社。2008年に代表取締役社長に就任。2012年に中小企業診断士登録。2014年に技術士(経営工学部門)登録。2016年に技術士(総合技術監理部門)登録。














