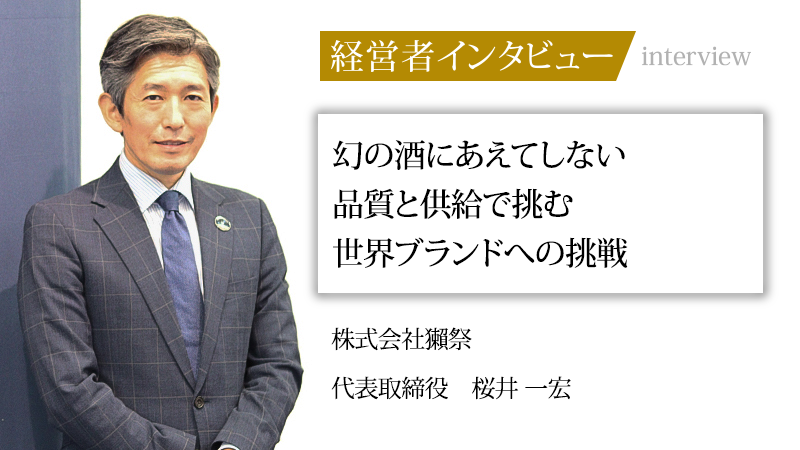
山口県岩国市から世界へ羽ばたく日本酒「獺祭」。製造元である株式会社獺祭は、伝統産業でありながら革新的な設備投資と品質追求を続け、世界的なブランドを確立した。かつて海外進出に反対派だった桜井一宏氏は、現在、代表取締役として「世界の獺祭」を目指している。同業他社が希少性を追求する中で、あえて供給力を重視し、品質を維持しながら市場を拡大してきた背景にはどのような思いがあったのか。売上1000億円という壮大な目標の真意と、日本酒の未来を切り拓く覚悟について、桜井氏に話を聞いた。
海外反対派から一転 NYで得た確信
ーー貴社入社当時のことをお聞かせください。
桜井一宏:
大学卒業後は家業に戻らず、酒造とは関係のない東京のメーカーに就職しました。転機が訪れたのは、東京の居酒屋で「獺祭」の美味しさを感じ、そこが市場に与える意味に気づいた時です。2006年、実家に戻る形で旭酒造株式会社(現・株式会社獺祭)に入社を決意しました。当時は社員がまだ10名ほどの規模の会社でした。
酒造について全く分からない状態で入社し、最初の1、2年は製造の下働きから始めました。催事の時期には百貨店や酒屋で試飲販売を行うなど、なんでもやりました。会社の規模からしても当然の流れです。その後、海外展開が始まりつつある状況で、ニューヨークの担当者として現地に行くことになったのです。
ーー海外進出についてはどうお考えでしたか。
桜井一宏:
当初、海外進出には反対していました。海外旅行などで、日本酒がまともに飲まれていないことを現場で見ていたからです。「外国人は日本酒の味が分からないのではないか」「売れないのではないか」。そう思いながらも、現地の担当者になりました。最初は現地の卸業者に同行して営業をしましたが、山口県の酒なんか誰も知らないということもあり、案の定全く売れませんでした。
しばらく売れない状況は続き、そんな中でBtoBの営業ではなくBtoCに活路を求めて何軒かのお店に協力していただき「酒の会」のようなイベントを行ったり、スタッフのトレーニングも実施したりしました。そんな中で売上も伸びるとともに、お客様の反応がダイレクトに見え、美味しいお酒は、国や人種に関係なく「美味しい」と感じてもらえるのだと分かったのです。「美味しいお酒をつくれば、そこにはマーケットがあるのだ」と確信しました。これが、ニューヨークでの大きな経験です。
あえて「幻の酒」にしない供給体制の構築

ーー貴社が成長された要因は、どこにあるとお考えですか。
桜井一宏:
根本にあるのは、やはり商品の品質です。弊社は酒造業であり、ものづくりの会社である以上、品質が何よりも大事です。まずは良いものをつくり、それをお客様に美味しい状態で届ける体制をいかに整えられるか。そこを非常に重視しています。
品質に加えて供給力も強みだと考えています。多くの地酒メーカーは、希少価値を軸に市場をつくってきた側面があります。「幻の酒」として供給を絞るわけです。しかし弊社は、お客様の元にきちんとお届けする努力をしてきました。そのためには設備投資が必要で、コストもかかります。ですが、品質を追求すると同時に量を追求し、「幻の酒」にならないよう努力を続けてきました。
ーーなぜ、そこまでリスクを冒して設備投資を続けてこられたのでしょうか。
桜井一宏:
最初から大きなリスクを冒すわけではありません。私が戻ってきた20年前は社員も10名ほどで、資源も限られていました。その中で、できる範囲の設備投資から始めたのです。一気に投資して伸びたというよりは、少しずつ改装などを進めていきました。
その中で、「供給力があれば酒は売りやすくなる」「良い状態でお客様の元にあることが大事だ」と学んでいったのです。もちろん、どこかで投資を止めた方が楽なのは理解しています。しかし、世界中を見渡せば、日本酒の市場はまだまだあると確信しています。
海外市場開拓の課題 文化の壁と物流問題
ーー海外展開における、直近の課題について教えてください。
桜井一宏:
ニューヨークにも酒蔵「獺祭ブルー」をつくり、欧米市場の開拓を進めています。しかし、まだうまくいっているとはいえません。日本酒市場はまだ一部に向けてしか出来上がっておらず、新しいお客様をつかめているとも思えない状況です。日本酒に詳しい方は知ってくださっています。一方で、一般の「美味しいもの好き」な方々には、まだ全く分かっていただけていません。ある意味0→1の市場なのです。
海外で日本酒の文化を伝える難しさとして、物流の課題もあります。たとえば、ワインの保存温度は10度から15度です。それに対し、日本酒は5度以下など、全く異なる管理が必要です。また、ワインは熟成しますが、日本酒は味わいが変わってしまうため早く飲んでほしい。根本的な違いが、まだ伝わりきっていないと感じています。ブランドを通して日本酒文化そのものを伝えていく必要があり、これが大きな課題となっています。
ーー組織づくりにおいて取り組まれていることはありますか。
桜井一宏:
組織が大きくなった状態で入社するメンバーとの意識の差が課題です。規模が小さい頃から会社と共に成長してきたメンバーとは感覚が異なります。どうしても「自分たちが入る前から獺祭は有名だった」という意識になりがちです。「今の通りやっていれば美味しいとお客さんに飲んでもらえる」と、受け身の姿勢に陥りやすいのです。
この課題に対しては、たとえば、製造チームを4つに分けて手触りのある意思の届く形で上を目指す、そしてその中でお互いが情報交換をしていく仕組みを導入しました。また、製造メンバーがお酒のイベントに参加する機会も設けています。お客様と直接触れ合い、自分たちの酒の客観的な立ち位置を知るためです。そして「お酒を一杯飲んでもらうことが、いかに大変か」を実感してもらう狙いもあります。
日本文化を世界に届ける 売上1000億円の真意
ーー今後の展望についてお聞かせください。
桜井一宏:
「世界のDASSAI」を目指したいと思っています。地方の伝統産業が、世界でブランドとしてきちんと認知される。それが私たちの実現したい未来です。
その一つとして、売上1000億円を目指しています。ただし、売上は世界のブランドになるための「手段」だと考えています。売上はお金であると同時に、商品の認知度やお客様に届いている度合いを示す指標でもあります。世界中の人々にブランドとして認知してもらうには、ある程度の規模が欠かせません。その目安として、売上1000億円を掲げています。
ーー「世界のDASSAI」を実現することで、何をもたらしたいとお考えですか。
桜井一宏:
日本酒は、日本の文化や背景、自然風土がベースになってできあがったアルコールです。それが世界中に広まることは、日本に対するリスペクトにもつながっていくと思います。私たちが世界で認知され、リスペクトされること。それにより、日本という国の文化への理解も全体的に深まっていく。そういった貢献をしていきたいです。
また、私たちが世界で挑戦できるのも、日本のブランドイメージに助けられているからです。だからこそ、勝手ながら日本の一部、山口県の一部を背負わせてもらっているという感覚を持っています。日本の文化というバックボーンと共に挑戦させてもらっている思いです。
ーーこれから貴社で活躍する若い世代には、どのようなことを期待されますか。
桜井一宏:
私たちの経験からいえるのは、分からない中で動いていくことの重要性です。失敗もありますが、その中で勝ち筋が見えてきます。全てが分かってから次の段階に進むのではなく、できるだけ早く動いて、挑戦して、失敗する方がいいと思います。
もちろん、答えのないものに挑戦し続けるのは、気持ちの面で大変なことです。私自身も「前回と同じでいいかな」と考えてしまうことが多くあります。だからこそ、あえてこうした公の場で「挑戦する」と発言するのです。会社全体をその方向へ引っ張っていく環境をつくりたいと考えています。
編集後記
「幻の酒」という希少価値に頼らず、品質と供給力で世界市場を切り拓く姿は圧巻だ。売上1000億円という目標も、単なる数字ではなく、日本文化を世界に届けるための「手段」だと言い切る。答えのない課題に対し、失敗を恐れずに動くことの重要性を説く言葉は、日々の仕事に向き合う私たちに勇気を与えてくれる。日本酒の未来を切り拓くだけでなく、私たちの働き方にも示唆を与える同社の挑戦に今後も注目していきたい。

桜井一宏/1976年山口県岩国市生まれ。早稲田大学卒業後、酒造とは関係のない東京のメーカーに就職。東京の居酒屋で「獺祭」の美味しさに気づき、2006年、実家に戻る形で旭酒造株式会社(現・株式会社獺祭)に入社。2013年より取締役副社長として海外マーケティングを担当、主にニューヨークで海外進出の礎を築く。2023年9月にNY・ハイドパークに同社初の海外拠点がオープン。2025年6月には、株式会社獺祭に社名変更した。














