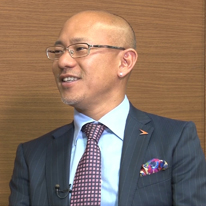【ナレーター】
創立から100年以上が経った今も、「高砂熱学工業はベンチャー企業だ」と主張する小島。その真意と、挑戦を成功させるために意識していることとは。
【小島】
当社はずっと「ないものは自分でつくる」という考えのもと、すぐに行動し、何でも自分たちでやってきた会社です。ですから、私が若い社員に伝えるのは「まず、やってみなよ」ということ。そういう文化が当社の中にあります。
当社では入社3年次、5年次の社員でも、多額の予算を扱う案件へチャレンジできるんです。設計して、機械を選定する。その上で協力会社に発注するといったすべての工程に挑戦できます。
当然うまくいかないこともありますが、失敗したことによってスキルも伸び、人間力が上がります。
それから、もうひとつ。建築現場の中を変えています。具体的には事務所の環境を良くしようという試みです。建設現場は、四角いプレハブや暗いところで働くというイメージがあると思います。でも、それを3年前から一新しました。
先日、秋田に行ったとき、テントの中で職人さんと打ち合わせをしました。そのように自由なチャレンジをしたことで新しい発想が生まれる。要は、まず行動です。
それを会社としても「いつもOK」という空気をつくっていくことが、高砂熱学工業らしい方針だと思います。
【ナレーター】
高砂熱学工業は、宇宙スタートアップ企業のispace社が主導する民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」へも参画しており、世界初となる月面での水素・酸素生成に挑戦している。参画に至った経緯について、小島はこう振り返る。
【小島】
初めてispaceの袴田ファウンダー&CEOとお会いしたとき、2040年には「月に1000人が暮らすようになります」と聞きました。
「月には氷がある。それを溶かした水から、水素はエネルギーに、酸素は生活に使いたいんだけど、小島さんどう?」と。考えると、それは楽しい、ワクワクするので「やりましょう」というのがスタートでした。
私たちはもともと水素製造装置を持っていますし、次は、太陽光発電の電気だけで氷を溶かせないかと計画中です。水電解装置を月に持って行って、世界で初めて水素をつくったということは、あくまでブランディングのひとつです。
アメリカや日本から打ち上げられたロケットが月面着陸を成功させています。将来的に月は、まさに次の大きなマーケットなのです。
それから、今考えているのは、カーボンニュートラルビジネスです。それが革新的に進んでいきます。
私たちは、日本でグリーン電力を使って、グリーン水素を提供することができる、いわばファーストペンギンです。それを今後さらに加速させていきたいと思います。
【ナレーター】
「環境革新で、地球の未来をきりひらく。」。高砂熱学工業が2023年に掲げたグループパーパスだ。この言葉に込められた思いと、その実現に向けて取り組んでいることとは。
【小島】
次の100年は、新しいパーパスで歩んでいきます。そこで、今の延長上のパーパスを社員の皆と考えました。それが、「環境革新で、地球の未来をきりひらく」です。
環境クリエイター®として建物環境のみならず、地球環境を整える革新的な技術を提供して未来を切り開いていくこと。まさにそれが、次の目指すべき100年に向けての事業展開だと確信しています。ですから今、その目標からバックキャストして進めている次第です。
人材育成も、すべての人が同じことを目指すのではなく、現場所長を目指す人もいれば、経理のスペシャリストになりたい人もいる。中にはマネジメントをしたい人もいるでしょう。
そこで、各社員のニーズに合った教育体系をつくるだけではなく、バラエティに富んだカリキュラムをたくさんつくっていく。外部の力もお借りして、いろいろな講座を開いてみる。人材育成の方法はひとつではありませんし、100個あっても良いのです。社員が自由に受けられる環境づくりを進めています。
やはり、社員が幸せにならないと、サプライチェーンの皆様も幸せにならない。みんなが幸せになるために、私たちは事業をしています。
それが環境革新であり、地球貢献であり、そして環境クリエイター®であるということです。それはもう、ことあるごとに言っています。
【ナレーター】
求める人財像について、小島は次のように語る。
【小島】
技術系、事務系、営業の方や管理の方、経理の方も、環境クリエイター®になりたいと思う方には誰でも、当社に来ていただきたいです。
技術はイメージしやすいと思いますが、たとえば経理の場合は、環境的に良くなるような財務会計って何だろうと考えてくれるような方。営業志望の方は、次の環境に進むマーケットは何だろうと考えられるような人材です。
全員が環境クリエイター®ですから、環境を徹底して意識してこだわっていく。新しい人材に会えるのが、楽しみです。
ー大事にしている言葉ー
【小島】
二宮尊徳さんの言葉で「遠くをはかるものは富み、近くをはかるものは貧す」というものがあります。
トップの役職になると、どうしても短期的な視点で考える傾向が日本企業ではありがちですが、本当に大切なのは、お客様の目先の利益のためだけではなく、長期な視点で考えていくことです。
お客様に認めていただければ、当然業績に返ってくる。それが一番高砂熱学工業らしいことだと思います。


 経営者プロフィール
経営者プロフィール