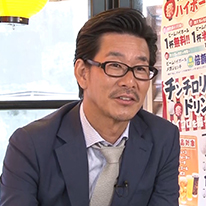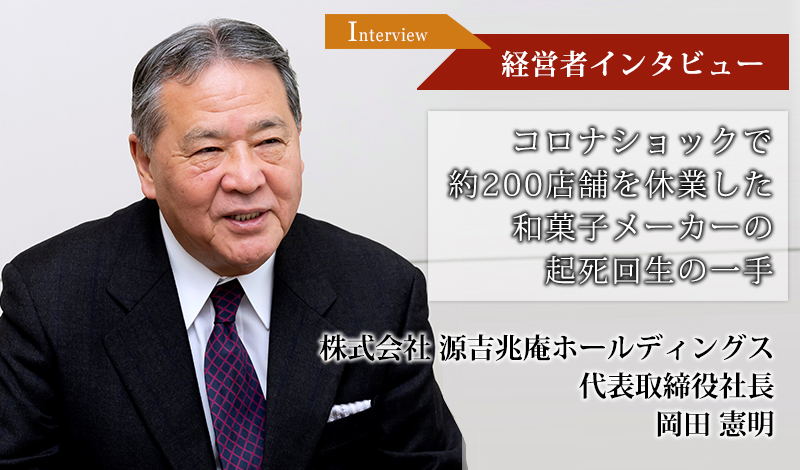
新型コロナウイルスの脅威に晒され続けている日本企業。相次ぐ倒産報道にリーマン・ショック時以上の衝撃を受けている人も多いだろう。
しかし、この逆境をむしろ好機と捉え、感染対策を万全にした上で新しい事業の展開に取り組むなど、力強く邁進している企業がある。
世界に名を馳せる創作和菓子メーカー、株式会社 源吉兆庵ホールディングスだ。
「四季の果実を和菓子に、“Wagashi”の心を世界へ」を企業理念とし、日本の文化を和菓子を通じて国内外に発信。ニューヨークを始め、ロンドンや台湾、シンガポールなど約40店舗を展開し、和菓子の可能性を追求し続けている。
コロナショックによって約200もの店舗が休業に追い込まれたものの、鮮明な「アフターコロナ」のビジョンを描いているという代表取締役社長の岡田 憲明氏。
岡田社長はどのようにこの危機を乗り越えようとしているのか。今回、そのビジョンの一片をお話していただいた。
緊急事態宣言後は「できること」を徹底

自然が育てた果実の姿・形・味わいをそのまま楽しめる、源吉兆庵ホールディングスのロングセラー商品だ。
-緊急事態宣言が発令された際、企業としてどのような対応をなさったのでしょうか。
岡田 憲明:
アルコール殺菌やマスク着用は当然ながら徹底しました。また、休みを導入したり、出張を禁止したり、打ち合わせもオンラインのビデオ会議に切り替えたりするなど、人の移動を止めることに徹底的に取り組みました。
店舗についても、運営していた約200店舗の休業を決断しました。ウイルスという目に見えない敵と戦うのですから、とにかく社員の安全を確保することが第一と考えたのです。
さらに、工場間の移動や本社から工場への視察もすべて禁止し、その工場のメンバーしか入れないような形をとりました。各支店でも昼食などを外で取ることを禁止していました。
とにかくできることは徹底して取り組みましたね。
売上3割減という危機的状況を乗り越えた英断
-岡田社長は、これまでさまざまな不況を乗り越えて来られたかと存じます。今回のコロナショックを乗り越えるために必要だと思われることは何でしょうか。
岡田 憲明:
まず、第一にやらなければいけないことは、できるだけ無駄な支出を止めるということですね。
実は、リーマン・ショックの1年前に他社で起きた食品偽装問題の影響を受け、売上が約3割、一気にダウンしてしまったことがありました。結局、その年度は赤字に転落してしまいました。
回復を図るべく、無駄な支出を止めることを最優先に取り組むことにしました。駐車場の契約や社員食堂の閉鎖、仕入れの見直しなど、経営方針の軸をぶらさずに、無駄なところをすべて整理していったのです。
その結果、何とか収益はV字回復することができました。リーマン・ショックはこれらが全て終わった後に起こりましたが、幸いにも影響はほとんど受けませんでした。
私はこの経験を通じて、有事の時こそ「今まで踏み込んでいなかった領域にもしっかりと踏み込んでいく」ということが、一番大事だと思いましたね。
11年ぶりのチャンスを活かす「成長戦略を持つ」という考え方
-方針がぶれないようにするために、御社ではどのようなことを意識されていらっしゃるのでしょうか。
岡田 憲明:
成長戦略を持つことです。
かのリーマン・ショック以上の危機と言われているこのコロナショックを乗り越えるためには、経営方針をぶらさずに、立てた戦略の方向にしっかりと進むことが大変重要だと思いました。これを実現するのが成長戦略を持つということなんですね。
そうすると、方向性は自ずと定まり、成長戦略の答えが出てきます。会社が「この方針で進む」ということを明示することで、従業員もそれについていこう、一丸となって頑張ろうと士気やムードにも良い影響を与えやすくなります。
やはりビジネスは、夢を持ってやっていくべきなのではないかと思いますね。
今はリーマン・ショック以来、11年ぶりのチャンスだと捉えています。
これまでは嗜好品のひとつであるお菓子が中心でしたが、人々の生活リズムに入るような商品や健康のサポートを目的とした商品など、時代の変化に合わせた商品の生産体制を整えるべきではないかと考えております。
その第一歩として、2020年秋よりそれらの商品開発に関する研究を本格的に始めようと検討しているところです。
新型コロナウイルスの影響を受け、今回、嗜好品の需要は「不要不急」であることを痛感しました。ですので、今後、同様の不況になったとしても、それを乗り越えられる強い企業にならなければいけないという考え方で、新しい事業を展開していきたいと考えていますね。
海外の菓子文化に適応するために

-今後の海外展開について、どのようにお考えでしょうか。
岡田 憲明:
海外にも和菓子のファンの方はもちろんおられるのですが、まだまだ増やせるのではないかと考えています。そこで、和菓子を日本文化と合わせて広めていくために、海外の店舗では「お茶会」を催しています。
食文化を理解してもらうには、やはりどうしても時間がかかってしまいます。台湾やハワイなどは、すでに日本の食文化が浸透しているので日本と同じ戦略で店舗を広げることはできますが、アメリカ大陸などの本国ではそううまくはいきません。
和の文化を世界に広めるためには、海外の方がその文化を理解し、自宅でも楽しめるようにする必要があると思います。
そういった「和の楽しみ方」を弊社が提供することにより、和菓子や和食をより多くの方に楽しんでいただけると考えています。今後はメディアを活用しながら、和菓子や和食を世界に広げていきたいですね。
「アフターコロナ」のビジョン
-今後の販売体制についてネット通販を伸ばしていこうというお考えはありますか。
岡田 憲明:
通販事業はおかげさまで対前年比が約160%増加しており、今後も注力していくつもりです。まずは、売上全体の10%程を担えるようにしていければと考えています。簡単にはいかないと思いますが、それでも目標としては持っておきたいですね。
-アフターコロナについて、どのようなビジョンを描いているのかお教えいただけますでしょうか。
岡田 憲明:
新型コロナウイルスの問題が解決したとしても、おそらく時代の変化が起こると思います。そして、食文化も変わってくるでしょう。特にギフトという儀礼的なものはゼロにこそなりませんが、徐々に無くなっていく可能性があります。
また今後は、お客様の生活圏の中に入るような直営店の強化や、日常的に親しんでいただけるデイリー商品の開発など、変化する人々の生活リズムに入るようなジャンルの開拓をしていかなければなりません。
かつて呉服屋が百貨店として大きな変化を遂げたことで生き残って来たように、我々和菓子メーカーも変化をしないと生き残ることができないと思っています。そしてやはり今は、新しい分野の開拓をするチャンスだと感じています。
景気が良いときはどの企業も良いわけです。ですから、こういった危機的状況のときに活力を出して、リーダーシップを取って、成長戦略を立てるということが大事なのではないかと思いますね。
編集後記
コロナ禍でも希望の光を見失わない岡田社長。かつて苦境に立たされた経験を活かしつつ、数年先まで見通して成長戦略を立てているその慧眼には、ただただ感服するばかりである。
多くの人の心を惹きつけ離さない『陸乃宝珠(りくのほうじゅ)』は、今年も季節限定(5月上旬~9月中旬)で販売されている。きっと、コロナ疲れを感じている私たちの心を癒やす大きな1粒になるだろう。
変化をするべく奮闘する源吉兆庵ホールディングスに、今後も目が離せそうにない。

岡田 憲明(おかだ・けんめい)/1952年岡山県生まれ。70年に父・岡田寅太郎氏が創業した桃乃屋本舗(現源吉兆庵ホールディングス)に入社。77年に別会社である源吉兆庵設立と同時に専務に就任。2008年に副社長となり、15年に兄・拓士氏からバトンを受け、持ち株会社桃乃屋本舗と源吉兆庵など参加企業の社長に就任した。