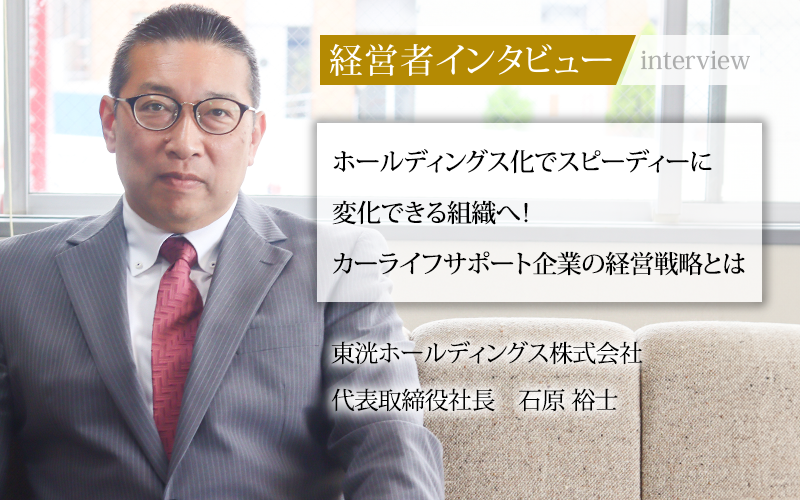
東洸ホールディングス株式会社は、ガソリンスタンド事業のほか、自動車の買取や販売、整備、保険事業などを展開している会社だ。2024年4月にグループ事業のホールディングス化を行い、大規模な組織改革を実行している。先代の急逝から経営者になるまでの経緯、ホールディングス化を決めた理由などについて、代表取締役社長の石原裕士氏にうかがった。
多くの刺激を受けたアメリカ留学の経験
ーー大学卒業後にシアトルへ留学したきっかけは何ですか。
石原裕士:
当時は就職氷河期で、なかなか思うように内定をもらえず悶々としていたときに、父から「就職することだけが選択ではないのだから、今しかできないことをしてみたらどうか」と留学を勧められたのがきっかけでした。そこで、自分でプログラムを探しはじめ、その結果大学の授業を受けながらインターンシップに参加できる内容を見つけ、アメリカ留学を決めました。
帰国後は、商社に行きたいという思いがあったのですが募集のタイミングが合わず、父の会社(当時の東光石油株式会社)の取引先でもあった潤滑油メーカーに就職し、留学経験を活かして海外営業を担当していました。そんなとき、とある業界紙の一面に父の会社の記事が取り上げられました。
その内容は東光石油が石油元売りの系列から離脱し、商社系列のガソリンスタンドに転換したことでした。かなり大々的に記事になったことを今でも覚えています。これをきっかけに、経営者になれば、地方の小さな会社でも社会にインパクトを与える決断ができると知り、「自分で会社の舵取りをする人生」もいいなと思い、父の跡を継ぐことにしたのです。
先代の逝去後、道しるべとなった京セラ創業者の哲学
ーーお父様の会社に入社してからのエピソードを教えてください。
石原裕士:
実は、現場の味方でいようとする私と、自分のスタンスを貫く父とは方向性が合わず、けんかばかりしていました。父親はガソリンスタンド業界の中でも名の通った人だったので、素人の私の意見などは簡単にねじ伏せられてしまいます。
そんなことからほとんど口を利かないまま、入社して2年が経った頃に、父が急逝してしまったのです。当時は気軽に話せる関係ではなかったので、父から教わることができず、もっと話をしておけばよかったと後悔しました。
その後SS本部長となりましたが、当時は右も左も分からない状態で昇進したため、何をしても上手くいきませんでした。その中でも大きな救いになったのは、社内が混乱している中でも従業員たちが残ってくれて、副社長だった叔父が新社長として会社を引っぱってくれたことですね。
そうして過ごす中で、自身が常務に就任することが決まり、セミナーや研修会に通いつめ、がむしゃらに経営の勉強をしました。
ーー経営の勉強はどのように行ったのですか。
石原裕士:
京セラの創業者である稲盛和夫さんの盛和(せいわ)塾で学びました。実はこれも父の影響で入塾していたものの、経営哲学を聞いても意味がないと思い、入会当時はほとんど例会に参加しない不良塾生でした。
しかし、経営破綻したJAL(日本空港)を再建した経営手腕に感銘を受け、その後は本気で学び始めました。学んでいるうちに、父が話していた経営論や手法は、稲盛さんの哲学に基づいていると気付いたのです。つまり、勉強を続ければ、父と対話できなかった部分をカバーできると思いました。
「東洸フィロソフィー」の策定。ホールディングス化を決断した3つの理由

ーー貴社の社長に就任した後はどのような社内改革に取り組みましたか。
石原裕士:
組織の原点回帰を図るため、稲盛さんの経営哲学である京セラフィロソフィーをもとに、「TOKOフィロソフィー」を策定しました。特に意識したのは、「人生と仕事の結果」=「考え方」×「熱意」×「能力」です。これは熱意や能力だけでなく、その人の考え方次第で結果が変わるという哲学です。
このようにビジョンに沿って物事を判断することで、従業員と価値観を共有することを意識しました。従業員研修ではこの考えを自分の言葉で伝え、会社全体に浸透するように働きかけています。
ーー「東光グループ」をホールディングス化した経緯を教えてください。
石原裕士:
ホールディングス化には主に3つの目的があります。1つ目は、スピード経営を実現するためです。既存の10個の事業を4会社に分け、それぞれの代表者に権限を与えることで、各自で判断できる体制を目指しています。現場の状況を熟知している者が指揮を取ることで、スピード感を持った対応が可能になると考えています。
2つ目は、ポートフォリオ経営(※)を導入して、事業の入れ替えを容易にするためです。事業の中身を入れ替えて新陳代謝を良くすることで、変化が激しい社会で長く存続できる組織にしたいと思っています。
3つ目は、各事業ごとに評価基準を設定し、従業員のモチベーションを高めるためです。会社全体で同じ評価基準を用いていたところから、事業の特性に合わせて評価ポイントを細分化する仕組みに切り替えました。
これにより公平な評価ができるようになり、従業員たちは自分が伸ばすべきスキルを判断しやすくなると考えています。
※ポートフォリオ経営:経営資源を効率よく分配し、事業の組み換えを行うことで企業の利益を最大化していく経営手法のこと。
10年後の売上高80億円達成を目指して
ーー貴社の未来について、どのような展望を持っていますか。
石原裕士:
今後はレンタカー事業とカーコーティング事業に注力していく予定です。熊本では台湾の半導体メーカーの工場が建設され、阿蘇くまもと空港もリニューアルオープンし、レンタカーの需要が伸びています。この波に乗り、サービスの拡充を図っていきたいと思います。
また、自動車の乗り換え時期が長期化する中で、愛車をキレイに維持したいと考えるお客様が増えたことで、カーコーティングの需要が急激に伸びています。将来的には自動車関連サービス以外の分野にも進出し、10年後には売上高80億円の達成を目標にしています。
ーー貴社が求める人物像を教えてください。
石原裕士:
「自身の人生を自ら舵取りでき、自分で物事を決断できる人」を求めています。考え方・熱意・能力のバランスが取れている人であれば、年齢は問いません。
働く環境を整えることにも注力している最中で、技術を極めて管理職になるコースや、10年かけて社長を目指すコースなど、新しいキャリアパスも設けました。このように、それぞれの特性に合った方法で活躍できる環境を整備しています。
さらに、20代という若い世代の方でもサービスステーションの所長になれる可能性があり、1店舗で年間億単位のお金を動かす仕事ができる、というのも弊社で働く魅力のひとつと考えています。自分で事業を運営し、どこでも通用するスキルを身に付けたいという方とともに、今後も事業拡大していきたいと思っています。
編集後記
グループ事業の法人化という大きな決断をした石原社長。そこには尊敬する父から引き継いだ会社を未来に残したいという、強い思いが垣間見えた。創業者の思いをつなぎ、新たな体制で社会の変化に挑む、東洸ホールディングス株式会社の今後に期待だ。

石原裕士/1973年生まれ。同志社大学卒業。2年間のアメリカ・シアトルでの留学を経て、1999年に日本サン石油株式会社に入社。5年間の修業期間を経て2004年、東光石油株式会社(当時)に入社。2010年代表取締役社長に就任。2024年4月ホールディングス体制に移行し、東洸ホールディングス株式会社設立。














