
1949年設立の冨士ダイス株式会社は、超硬合金を材料に使用し、摩耗しにくい工具や金型の製造を手がけている。「超硬耐摩耗工具」の分野で30%以上のシェアを誇るトップメーカーだ。素材販売だけ、加工だけをしている会社が多いなか、同社は原料の調合から合金素材の生産、加工、製品化まで一貫生産体制をとっていることが強みである。
その冨士ダイスで、2024年に新社長が誕生した。今回は、同社代表取締役社長の春田善和氏に、社内で取り組む意識改革や今後の展望について、幅広くお話をうかがった。
株式上場を通じて得た変化とスキル
ーー冨士ダイス入社後に取り組んだことについてお聞かせください。
春田善和:
1987年に慶應義塾大学を卒業後、冨士ダイス株式会社に入社し、営業職でも技術職でもない管理部門のサラリーマンとしてキャリアをスタートさせました。管理部門では経理や総務など多岐にわたる業務に携わり、その後企画部門に異動して、2010年からは業務本部企画部長を務めました。当時、会社の方針で企画部門が株式上場に向けた業務を担当することになり、私はその準備を指揮することになったのです。
私は入社したころ、あまり前向きではなく、自分から「はい!」と手を挙げるタイプではありませんでした。実は株式上場も、自ら取り組みたいと思える仕事ではありませんでした。しかし、やらなければならないのなら嫌だと考えるよりも、前向きな姿勢でなんとかしようと考え直しました。問題を解決するためにすべきことを考えると、課題が見えてきます。結果としてこの仕事は、周りに目を配るマルチタスクのスキルを磨くきっかけにもなったと思います。
一貫生産体制によるオーダーメイドが強み
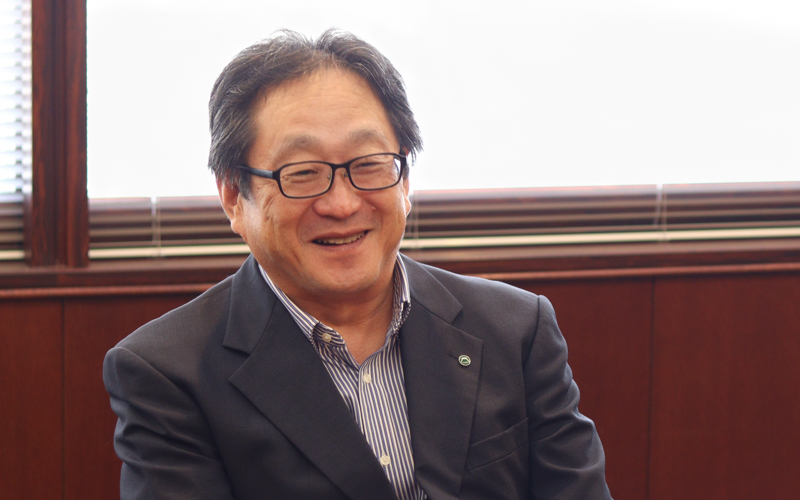
ーー貴社の事業内容と、製品の特徴について教えてください。
春田善和:
冨士ダイスは、超硬耐摩耗工具・金型を製造販売する会社です。超硬耐摩耗工具とは、一般的な鉄や鋼より硬い金属材料である超硬合金の特徴を活かした金型や工具のことで、弊社の製品は、ものづくりの様々な場面で使われています。例えば、自動車の部品や半導体の生産、身近なところではビールやコーヒーの缶、エアコンなどの家電、カメラレンズなどを作る時にも当社の金型が使われています。挙げるとキリがないくらい、たくさんのモノを作る時に使われています。
皆さんが冨士ダイスの存在を意識することはほとんどないと思いますが、実は生活のとても身近なシーンで皆さんのお役に立っている会社です。
ーー多くの企業様に信頼される秘訣は何でしょうか。
春田善和:
弊社は超硬合金製の工具・金型の材料の開発から合金素材の生産、加工、製品化まで行っています。お客様からのさまざまなオーダーに柔軟に対応するために、営業・技術担当者が製法や素材を一緒に考え、工具・金型を使用する際の温度環境、酸の有無、磁場に対する適性などを考慮して、約100種類もの⾦属粉末から選んだ材料で、お客様の要望に応じた製品を提供しています。どんな分野の依頼でもほぼ対応できるため、グループ全体で、約3,000社の幅広い業種のお客様とお取り引きさせていただいています。
新材料や新設備に対応、海外進出でものづくりを守る
ーー今後の事業展開や海外進出についてお聞かせください。
春田善和:
脱炭素・循環型社会への移行に向けて、それらに貢献する製品を積極的に開発、市場投入したいと考えています。そのうちの一つは、従来から取り組んでいる次世代自動車関連製品への注力です。車載用モーターコアの金型に適した材種のラインナップ拡充や、車載用電池缶向けの金型の拡販に向けた取り組みを、より一層強化してまいります。加えて、次世代エネルギー分野に向けて、当社の強みである粉末冶金技術を活かした触媒や電極の開発も進めていきます。
一方、日本では少子高齢化が進み、ものづくりの現場が減少する傾向にあります。日本の製造業がまだ世界のトップグループにいる今こそ、東南アジアなど海外へ進出し、ものづくりを守る必要があります。現在、タイとインドネシアに工場を持ち、特にタイでは生産能力が大きく向上しています。海外事業で最大の市場である中国は、今年3⽉に開設した新しい営業拠点を中心に、営業活動を強化し、次世代自動車関連製品や素材の拡販を進め、景気回復にあわせて受注拡大を図っていきます。日本からの輸出が伸びているインドは、現在休眠させている拠点再開の基盤を固めたいと思っています。今後の3年間で中国とインドでの拡大を目指すとともに、北米もインドの次となる新しい市場候補として市場調査等を進めています。
ーー生産性を向上するための取り組みは進んでいますか。
春田善和:
これまでは働く人々に焦点を当て、社員がスキルアップできるように個々の能力を見える化し、効率の改善を図ってきました。さらに生産性を向上させるためには、機械化や⾃動化が重要になります。人の動きをビデオで撮影・分析し、機械化や⾃動化できる工程を検討するなど、設備の改善に⼒を注ぎたいと考えています。個々の能⼒を⾼めるための⽅策を考えつつ、機械化や⾃動化を進めてまいります。
冨士ダイスのビジネスは少量多品種なので難しい面もありますが、少しずつ改善を進めていきます。
トップダウンからチームプレイへ、求めるのは「明るく前向きに考えられる人」
ーー社長就任後は、どのようなことに注力していますか?
春田善和:
会社の雰囲気を変え、全員で一体感を持とうというムードの醸成に力を入れています。私は自分ひとりで物事を決められるほど能力があるわけではありません。だからこそ、社員のみんなには、今まで以上に活躍してもらいたいのです。そのための雰囲気づくりに力を注いでいます。例えば、これまで「春田社長」と呼ばれていたのを、「春田さん」と呼んでもらうようにするといった具合です。
弊社は創業者のリーダーシップに引っ張られて事業が拡大したため、トップダウンの雰囲気がありました。しかし、変化の激しい時代を生き抜くためには、社長も社員も、みんなが同じように意見を言い合い、もっとも良いものをとり入れていくべきだと思っています。私を「社長」ではなく、「春田さん」と呼んでもらうことで、会社の雰囲気がより柔軟なものに変わります。今後もさらに、意識改革を進めていくつもりです。
ーー求める人物像を教えてください。
春田善和:
明るく前向きに考えられる方が一番良いと思います。あまり悲観的にならず、物事を楽観的に捉えられる方が良いですね。何かあっても逃げずに一歩を踏み出してほしい。明るく前向きで積極的な性格が、周りの人たちと楽しく仕事する上で大切です。創業100年に向けた新たな挑戦に取り組むために、社員一人ひとりが個性を活かして力を発揮し、互いに協力する一体感のある職場環境を作っていきたいと思います。
編集後記
トップダウンからチームプレーへ。社内の意識改革を進める一方で、冨士ダイスの持つ強みを大切にしようとする春田社長。「顧客奉仕」を第一に、細やかなサービスを提供することで知られる冨士ダイスの強みは、社員全員が一丸となって顧客と向き合う姿勢にあることがわかった。今後も海外展開が本格化し、アジアや米国など新たな舞台で日本のものづくりを支えていくはずだ。
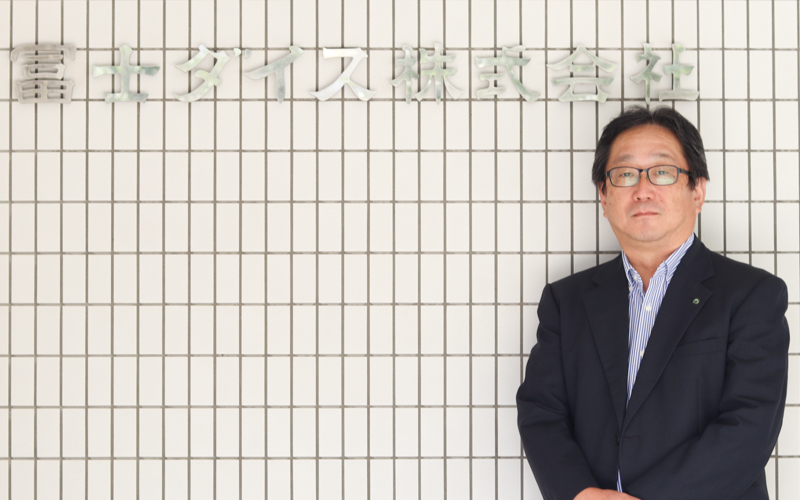
春田善和/1963年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学卒業後の1987年、冨士ダイス株式会社に入社。管理部門で経理や財務の経験を積んだ後、企画部門に異動。2010年から業務本部企画部長として、冨士ダイスの株式上場関連業務を担当し、2015年に東証2部(現:東証プライム)に上場させた。2024年に代表取締役社長に就任。














