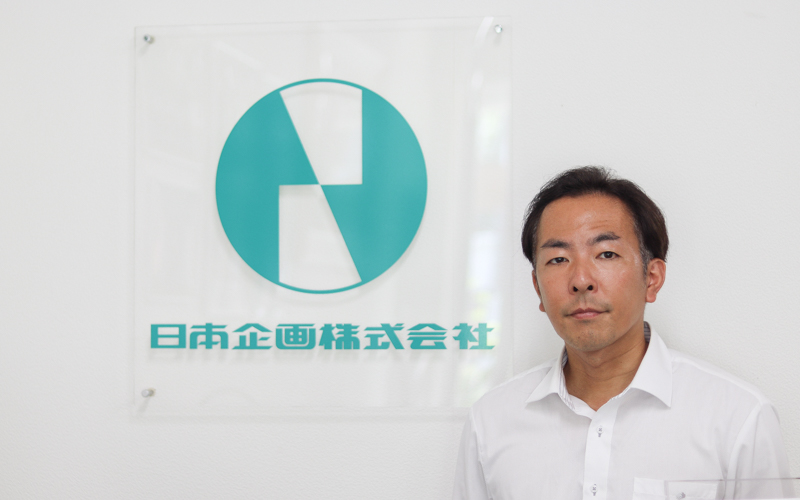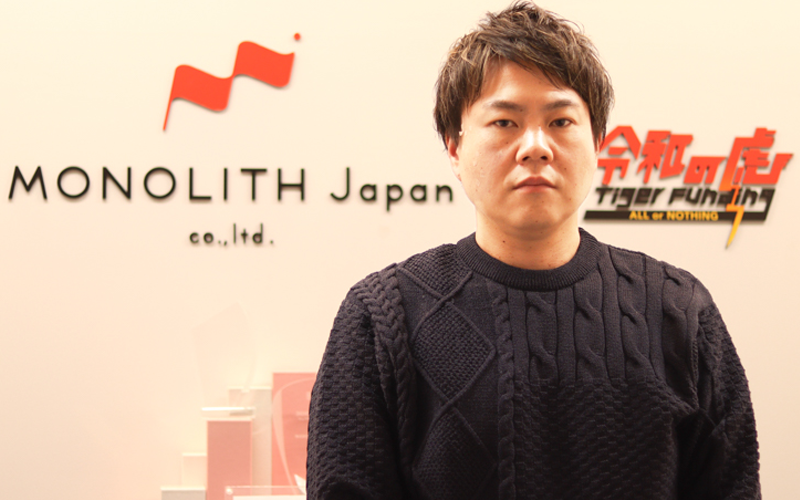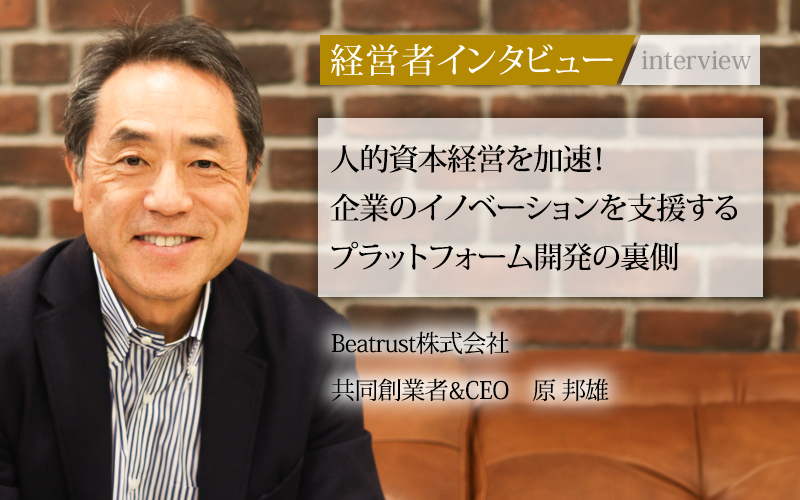
社会環境が複雑化するVUCA時代(※)において有効な経営戦略の一つである「人的資本経営」は、2022年に「人的資本可視化指針」が示されるなど、未来の日本企業において重要な意味を持つ。そうした状況のなかでタレント・コラボレーションプラットフォーム「Beatrust(ビートラスト)」を提供し、創業期から大企業の組織開発・イノベーションを支援してきた企業がBeatrust株式会社だ。同社は現在、この人的資本経営にフォーカスしたプラットフォーム「Beatrust(ビートラスト)」と2024年11月に提供開始した生成AI技術を活用した「Beatrust Scout(スカウト)」「Tag Extraction(タグ抽出機能)」(両サービス共に特許取得済)に注力しているという。
同社のCEOである原邦雄氏は、コロンビア大学でMBA取得後、日本企業の雇用スタイルに疑問を抱き、自己成長のためには実力主義、ジョブ型雇用の環境に身を置くことが望ましいと考えるようになった。その後、大企業での勤務経験を経て、日本企業が抱える組織改革の課題と、イノベーションの必要性を感じて、事業を立ち上げたという。
原氏が感じた日本企業の問題点はどのようなものだったのか。また、同社のサービスによって日本の企業はどのように変わるのか。これまで歩んできた道のりと、同社サービス開発の経緯、将来の展望について、原氏に話を聞いた。
(※)VUCA:変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の頭文字をとった言葉。先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態。
インターンシップ参加でキャリアの価値観が変化
ーー新卒で住友商事に入社したあと、転職したのはなぜですか?
原邦雄:
入社後、米国留学で価値観が変わったことが大きな理由です。そもそも私が住友商事に就職した理由は、総合商社なのでグローバル規模の仕事ができることに魅力を感じました。グローバル人材になるための登竜門としてのMBAには学生時代から興味があり、住友商事の海外留学制度を利用させていただき、アメリカの大学院でMBAを取得しました。
私は入社後、その制度を利用してコロンビア大学に留学し、MBAを取得しています。さらに留学先で、「サマージョブ」という、一流企業がMBAの学生を採用するインターンシップ制度に応募しました。このサマージョブでの体験をきっかけに私の価値観が大きく変わり、「実力主義の世界で働きたい」と考えるようになったのです。
もちろん、会社から派遣されていたこともあり、帰国後はMBAを活かした仕事で貢献するつもりでした。MBA取得後、3年間は住友商事で働き、海外企業とのジョイント・ベンチャー、M&A案件など、やりがいのある仕事を任せていただいたのですが、やはり一度芽生えた気持ちは簡単には消えてくれません。最終的に、1992年に大学時代の先輩の紹介で、ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社/以下、ソフトバンク)に入社することになりました。
ーー米国でのサマーインターンシップに参加したことで、どのように価値観が変わったのですか?
原邦雄:
当時、大部分の日本企業が採用していた、「年功序列・終身雇用」という制度に疑問を抱くようになりました。私が実習先に選んだソロモン・ブラザーズという投資銀行では、そのような考えはありません。ソロモン・ブラザーズに限らず、アメリカの金融業界、特にウォールストリートは実力がものを言います。このような企業での実力主義本位の働き方を体験したことで、実力主義の世界が非常に魅力的なものに感じられるようになったのです。
当時、ソフトバンクは、まだそれほど規模も大きくなく、ベンチャー気風を色濃く残したステージだったので、大企業とは違い、オープンな社風で、若手でも実力を発揮しやすい環境でした。さらに、先輩に紹介された孫正義社長が、今まで会ったことがない、高いビジョンと行動力を持つ、優秀な経営者だったので、「この人と働きたい」と思ったのです。
何かを生み出す仕事を目指して渡米

ーーソフトバンク入社後も起業や転職をしていますが、その際はどのような経験をしましたか?
原邦雄:
当時のソフトバンクは出版、流通、展示会運営というインフラ的なIT業界の発展と共に着実に成長する素晴らしいビジネスモデルでしたが、革新的なテクノロジーやサービスを生み出す側の会社ではありませんでした。そこで、テクノロジーを生み出す側でも仕事をしてみたいという思いが強くなり転職を決意し、ITのメッカであるシリコンバレーで急成長している会社をリサーチし、シリコングラフィックスという会社に出会いました。その後運良く、1995年にシリコングラックスの日本支社に採用され、1年後にアメリカ本社に転勤したのです。
この会社で「グローバルカンパニーのマネージャーロールを経験する」という自身の目標を達成し、自分の中で一つの区切りがついたことで、「次は独立して、自分で事業を立ち上げよう」と考えるようになりました。そして、シリコンバレーのスタートアップに向けて、国際ビジネス開発の支援業務を提供するコンサルタント会社を2000年に立ち上げることになったのです。この会社では、最先端の技術を必要とする日本の大企業と、魅力的なテクノロジーを開発しているシリコンバレーのスタートアップ企業をつないで、技術ライセンス契約、資本提携、海外事業進出などをサポートするサービスを始めました。
その後、2006年に帰国してデジタルマーケティングのスタートアップ企業を立ち上げたのですが、リーマン・ショックの影響で資金調達が難しくなり、大手企業に事業を譲渡しました。そこで、「大手のグローバルカンパニーでもう一度、グローバルマネジメントの修行をしなおそう」と考え、2009年に日本マイクロソフトに入社し、さらに2012年にグーグルジャパンに転職したのです。
Googleで感じた日本企業との風土の違い
ーーGoogleに入社してからは、どのような仕事をしましたか?
原邦雄:
デジタル広告の営業責任者を務めたほか、中長期的な社会貢献プロジェクトのチームリーダーとして、日本のスタートアップ支援や、東京オリンピックのスポンサー契約といったプロジェクトを担当していました。他には、Googleが成長の過程で学んできたことや開発したテクノロジーを日本の大企業に支援するという、イノベーション支援のプロジェクトにも携わりましたね。
ーーGoogleで仕事をしている中で感じたことをお聞かせください。
原邦雄:
日本企業は、社員の能力が高いにもかかわらず、組織としてのスピード感に欠けていると感じました。私が在籍していた当時のGoogleの社員数は、12万人です。それにもかかわらず、Googleがスピード感を持って事業を成長させることができたのは、オープンなカルチャーが育っていたからだと考えています。フラットなコミュニケーションや、組織をまたいだコラボレーションを推奨する社内方針、失敗を承認することにより心理的安全性を確保する風土が根付いていたのです。
Googleでは、このような風土を活かすデジタルインフラを内製化していました。これは、デジタルツールを外注化しがちな日本企業ではあまり見られない方法です。ツールを外注化してしまうと、自分たちがほしいものがすぐには手に入らず、必要な機能がすべてそろっているとも限りません。
このような状況を踏まえて、Googleで学んだノウハウや体験から、イノベーションを後押しできるようなデジタルツールの提供を通じて、日本企業のカルチャー変革の支援ができるのではないかと思ったのです。この発想が、現在の事業立ち上げにもつながっていますね。
多彩なソリューションで人材活用を促進

ーー事業を立ち上げる際に原社長が感じた、日本のスタートアップの課題とはどのようなことですか?
原邦雄:
まず、グローバル化を目指す企業が少ないことが気になりました。海外進出するためには英語が重要ですが、英語でビジネスができる経営者が少なかったのです。その背景には、SaaS領域において国内市場にまだまだビジネスチャンスのスペースが多く、海外進出しなくても十分成功できたことがあります。
ただ、日本市場にとどまっているだけではどうしてもスケールのあるビジネスに成長させにくいので、日本市場全体の活性化という意味でもスタートアップ企業のグローバル化は必然と考えました。そこで最初から世界に通用するテーマとして人を活かすソリューションに取り組もうと考え、個と個のつながりを作り、交流し、お互いが成長・発展しあうことを目的としたタレントコラボレーションプラットフォーム「Beatrust」を構想しました。
ーータレントコラボレーション・プラットフォーム「Beatrust」について、詳しくお聞かせください。
原邦雄:
「Beatrust」は、個人の経験やスキル、強みを可視化し、適切なマッチングを通じて社員同士の自律的・共創的な協業を促進させるプラットフォームです。もともと、このサービスは、2020年の創業当時に、社内の横のつながりを強化する「組織開発ツール」として開発しました。
日本企業は組織がサイロ化(※)している上に、心理的安全性が一般的に高くないこともあり、風土的に横につながりにくいのが現状です。イノベーションのためには横のつながりが重要だと考えているので、まずは組織内で横のつながりをつくることにフォーカスした「タレントコラボレーション」というソリューションを提供することにしたのです。
(※)サイロ化:組織やシステム、データなどが別々に管理され、連携がとれていない状態のこと。
もちろん、それだけではイノベーションは起きにくいので、新しいソリューションをどんどん提供する必要があります。新たなアイデアを模索する中で、日本の大企業の経営者の方々とお話しした際に見えてきたのが、「人的資本経営」に課題を感じているケースが多いということです。そこで、第2弾のソリューションとして、社員のスキルやキャリアを生成AIを活用して可視化し、最適な人事を提案できる「Beatrust Scout」及び「Tag Extraction(タグ抽出機能)」を開発しました。
この「Beatrust Scout」及び「Tag Extraction」の提供により、組織開発の理念に共感して「Beatrust」を利用してくださっていたクライアント企業に加えて、より幅広い企業にアプローチできるのではないかと期待しています。それと同時に、すでに「Beatrust」をご利用いただいているクライアント企業にも、新しいサービスとして「Beatrust Scout」及び「Tag Extraction」を提案していきたいですね。同サービスは、人的資本の最大化を支援するサービスの第一歩ですが、今後はさらに多様なサービスを展開したいと考えています。
ーー「Beatrust」はどのような企業に最適だとお考えですか?
原邦雄:
積極的にジョブ型にシフトしている企業や、社内公募による社内人材の流動性活性化によって社員の成長を支援しようとされている企業には大変向いていると思います。こういった形態は、アメリカではすでに珍しい形ではありません。社員の方の自律的なキャリア形成を後押ししたいという企業が増えておられますが、まだ風土面、制度面等が整っておらず、試行錯誤されている段階だとよくうかがいます。そのような企業のニーズに応えることができるよう、様々なデジタルソリューションを開発、提案していきたいと思っています。
海外進出を目指して新サービスを開発したい
ーー貴社の今後のビジョンをお聞かせください。
原邦雄:
グローバル市場に通用する新サービスを積極的に開発し、海外進出したいと思っています。社内・社外の人材がクロスボーダー的に人的資本経営を最大化できる環境づくりを支援できたら素晴らしいですね。企業間や産学連携でタレントを紹介しあえるようなプラットフォームがつくれれば、さらに国境を超えたオープンイノベーションが進むのではないかと考えます。
ーー最後に、これから社会に出る方に向けてメッセージをお願いします。
原邦雄:
自分軸を大事にして自分がワクワクすることに全力で取り組んでほしいと思います。なお、弊社でも人的資本経営への取り組みや海外志向を持たれている若手の方に活躍の場を提供できるよう今後、事業を加速していく方針です。
編集後記
少子高齢化社会の企業では、社内にいる人材の潜在能力を高めながら、新しい事業にも適応できる「人材ポートフォリオ」を作成することが重要だと原CEOは語る。その一方で、従来のメンバーシップ制の日本企業では、社員のスキルが定義されておらず、人的資本の把握や可視化が難しいのだという。そのような日本企業における人的資本経営の課題を的確に見抜き、そこに対するソリューションサービスを展開した原CEOは、素晴らしい慧眼の持ち主と言えるだろう。
昨今では、一部の大企業でジョブ型雇用人事制度が導入され始めるなど、日本企業の在り方が大きく変わっていくことは間違いない。Beatrust株式会社のサービスの重要性も、今後ますます高まることが予測される。未来の日本の雇用にアプローチする同社の新サービスへの期待に胸が膨らんだ。

原邦雄/慶應義塾大学卒業後、1983年に住友商事株式会社へ入社。1989年、米国コロンビア大学でMBA取得後、ソフトバンク株式会社へ入社し、事業開発に従事。1996年より、シリコンバレーで起業や米企業勤務を経て、2009年、日本マイクロソフト株式会社に入社し、広告営業の日本代表を務める。2012年、Google入社。執行役員として広告営業を統括後、2020年にBeatrust株式会社を共同創業。現在は、タレントコラボレーションツールを中心とした多彩なソリューションを提供している。