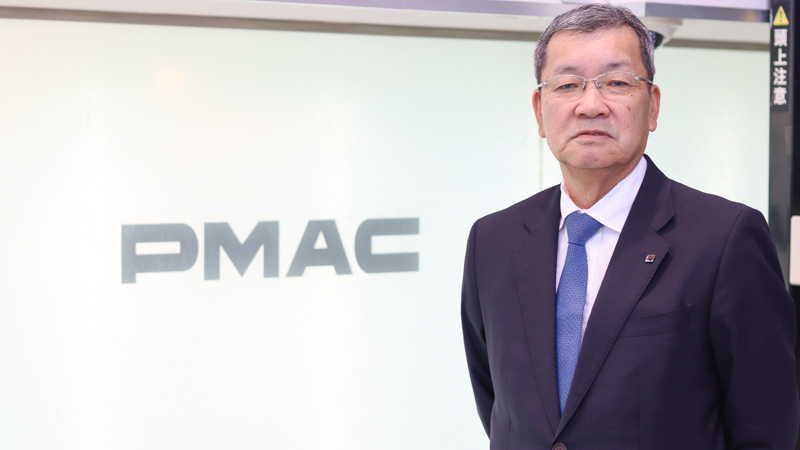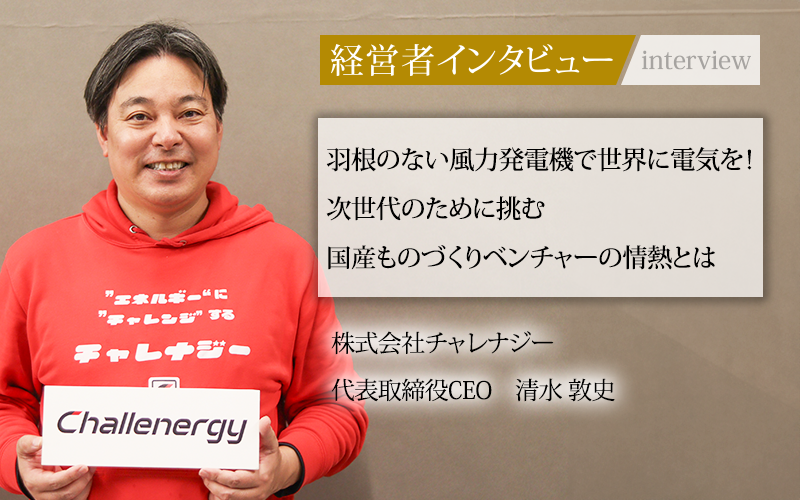
風力発電といえば、回転する大きな羽根を思い浮かべる人も多いだろう。だが、場所によっては、羽根が弱点になることもある。この課題に対し、羽根のない「垂直軸型マグナス式」というユニークな風力発電機を開発したのが、株式会社チャレナジーの代表取締役CEOである清水敦史氏だ。ものづくりの原体験と震災での気づきが育んだ技術と思いについて詳しく話をうかがった。
遊びを通じて「つくる喜び」を知った少年時代
ーーものづくりの原点になっているエピソードがあれば教えてください。
清水敦史:
私は岡山の田園地帯で育ちましたが、自宅にはゲーム機のような娯楽はありませんでした。そのため、子どものころは自ら何かをつくって遊ぶのが当たり前で、発泡スチロールで船をつくって用水路に浮かべたり、裏山にツリーハウスの秘密基地をつくったり、手作りの弓矢を携えて探検したり、幼いころからものづくりに夢中で、このころは「エジソンみたいな発明家になりたい!」なんて思っていましたね。
中学生になると、ロボットコンテストに憧れて、高専に進学。その後、東大に編入し大学院まで進みました。勉強を進めるうちに、「自分の手で開発したものを社会に届けたい」という思いが強まっていきました。
大学卒業後、株式会社キーエンスに就職し、FA用(※1)センサーなどの開発を担当。コンセプトの提案から量産立ち上げまで、さまざまな経験をさせていただきましたが、たとえば特許調査の経験は、差別化や実用化の見極めといった視点を育て、起業後の風車開発でもとても役立ちました。
(※1)FA:Factory Automation(ファクトリー・オートメーション)の略で、生産現場で人が行っていた作業を機械で自動化し、生産性や品質の向上を実現する仕組みのこと
震災で価値観が一変し、再生可能エネルギーの道へ

ーー起業のきっかけはどんなことでしたか。
清水敦史:
2011年の東日本大震災のとき、原発事故のニュースに強い衝撃を受け、私自身の価値観が大きく変わりました。それまでは、二酸化炭素の問題や電力の安定供給の観点から、原発は一定の必要性があると考えていたのですが、その考えを改める大きなきっかけとなりました。
そして、私たちの世代は、当たり前のように受けてきた電力の恩恵の代償を次世代に押しつけるのではなく、エネルギーシフトの道筋をつくらなくてはならないと感じました。自分がエンジニアとして貢献できることがないか、震災の翌週には再生可能エネルギーの入門書を買い、平日は本業に励みながら、夜間や休日を利用して調査を始めました。
ーー貴社商品「羽根のない風力発電」に辿り着くまでの過程を教えてください。
清水敦史:
再生可能エネルギーの中でも、太陽光発電は個人レベルでの開発は難しいため、当初から風力発電に注目していました。そして、調べていくうちに、日本は風力エネルギーのポテンシャルが大きいにも関わらず風力発電が少ないこと、その理由として、既存の風力発電には、羽根に起因する問題が多いことを知りました。日本の風力エネルギーのポテンシャルを生かすため、「羽根のない風力発電」を実現できないか、という探求を始め、「垂直軸型マグナス式風力発電機」を発明したのが2011年の4月でした。特許調査したところ、既に大手企業の2社が、私とは異なる方式で特許を申請していましたが、実用化には至っておらず、自分の発明を実用化することが使命だと確信し、起業を決意しました。
現在、創業時から開発してきた「垂直軸型マグナス式風力発電機」の大型化に挑戦しつつ、公園や建物の屋上など、人と近い場所にも設置できる風車として、方式の違う「小型風力発電機」を開発し、販売しています。
羽根のない風力発電でイノベーションを起こす

ーー既存の風力発電の課題とは具体的にどのようなものでしたか。
清水敦史:
日本の気候は、風向きや風速が不安定なのが特徴です。加えて、毎年来襲する台風により破損するリスクがあります。また、高速回転する羽根が発生する騒音や、野鳥が羽根に衝突するバードストライクの問題も抱えています。
日本は海外とは環境が異なるので、海外で主流となっている既存の風力発電とは違う仕組みが必要なのです。逆に、日本の環境に耐えられる風車なら、世界中の離島や山岳地域に普及させることができます。
ーー貴社商品の強みを教えてください。
清水敦史:
垂直軸型マグナス式風力発電機には、羽根の代わりに円筒がついており、マグナス効果という野球の変化球などと同じ物理現象を利用します。既存の風車の1/10程度の低速回転のため、騒音が少なく、鳥が視認しやすいのでバードストライクも発生しにくくなります。
また、台風や突風で暴走したり破損したりするリスクも低減できます。小型風力発電機も、安心安全を第一優先とした発想で、サボニウス風車というローテクな技術をあえて採用しています。この風車も羽根がなく、既存の風車の1/10程度の低速回転のため、騒音が少なく、羽根のように先端が尖っていないので恐怖感を与えにくい構造になっています。頑丈で壊れにくく、風速80m/sの風を実際にあてて壊れないことを確認しています。
さらに、雪が積もりにくく、積もったとしても破損しにくく、アイススロー(※2)も起きにくいため、豪雪地帯である青森県六ヶ所村での実証試験では3年以上、ノートラブルで安定稼働を実現しています。次なる過酷環境への挑戦として、今年は三宅島で島嶼環境における実証試験を開始しています。
(※2)アイススロー:羽根に付着した氷が飛散し、周囲を傷つける現象のこと。
地域に適した風力発電を世界中に届ける
ーー今後の展望についてお聞かせください。
清水敦史:
チャレナジーの強みは安心安全を追求した独自性の高い風車であり、私たちは常に“チャレナジーの風車しか置けない場所”を探しています。たとえば、離島や山岳地帯、豪雪地域など他の電源の設置が困難な過酷環境です。
都市部など、人の生活圏に近い環境も、過酷環境と同等の安全性が求められます。今年から高層ビル屋上での実証試験を開始していますが、これも過酷環境での実績があったからこそ取り組めた事例です。防災公園や津波避難タワーなど、地域の防災拠点における常用兼非常用電源としての活用も、風車そのものが災害で破損しにくいことが前提になります。また、小型風力発電機は人が運搬可能なサイズなので、未電化地域や被災地に運んで必要な期間だけ活用することも可能です。
国内のみならず、ノルウェーやウクライナ、フィリピン、フロリダ、モーリシャスなど、海外からの問い合わせも多く、海外市場へも展開していく予定です。
私たちが開発した風力発電機は、かつてボタン操作が主流だった携帯電話がスマートフォンへと進化したように、これまでの風力発電の当たり前を根底から覆す存在になると信じています。「羽根のない風車」が珍しいのは今だけで、いずれはそれが常識になる。まずは実績を重ね、1台でも多く普及させたいと考えています。
編集後記
「好きに勝るものはない」と語る清水社長の姿勢には、経営者というより、幼少期から変わらぬ発明少年の面影を感じた。過酷な環境に挑むタフさと、優しさをあわせ持つ風車は、社会のインフラのあり方を問い直す存在になっていくのではないだろうか。

清水敦史/1979年、岡山県生まれ。高専から東京大学に編入し、大学院まで進学。大学卒業後、キーエンスに入社し、約8年間FA用センサーの開発に従事する。2011年の東日本大震災を機に再生可能エネルギーの必要性を痛感し、起業。現在は、あらゆる環境に対応可能な風力発電機の開発・普及に挑戦している。