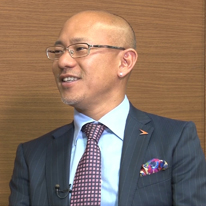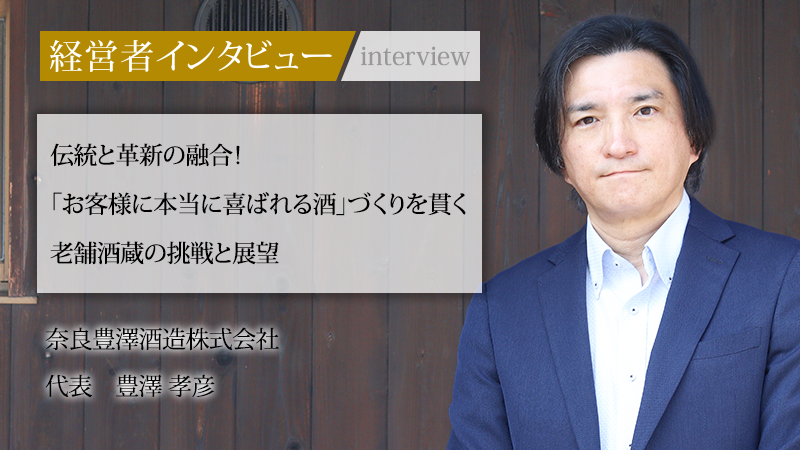
明治元年創業、150年以上の歴史を誇る奈良豊澤酒造株式会社。伝統的な酒づくりを守りながらも、時代の変化を捉えた革新的な取り組みを続けている会社だ。「お客様目線の酒づくり」を企業理念に掲げ、純米酒への特化や蔵元直営の飲食事業という新たな価値を創造してきた。同社代表の豊澤孝彦氏に、その歩みと哲学、そして未来への展望をうかがった。
受け継がれる酒づくりのDNAと新たな挑戦の始まり
ーー豊澤社長のこれまでの経歴をお聞かせください。
豊澤孝彦:
私は創業者から数えると5代目にあたります。父が次男ということもあり、幼い頃は酒づくりが身近な存在ではなく、酒づくりの仕事を意識し始めたのは高校生の頃です。
大学は、東京農業大学の醸造学科に進学しました。学生の2、3割が醸造関係者の子どもで、彼らと過ごすことで刺激を受け、業界にもより興味を持つようになりました。
大学で発酵の魅力や微生物の力による奥深さに触れましたが、それはあくまで机上の理論にすぎません。現場で酒づくりを学びたいと考え、卒業後は熊本県の酒造メーカー「香露」さんで3年間、蔵人として修業しました。
そこでは、まさに教科書通りともいえる真面目な酒づくりが行われており、私もその丁寧な工程を一つひとつ徹底的に学びました。大学で学んだ発酵や微生物に関する知識が、実際の酒づくりの現場で活きた瞬間でもありましたね。特に、麹のつくり方を始めとする基礎的な技術は、現在の製造においても変わらず、私の酒づくりの根幹を支えています。熊本での3年間の経験は、私にとってかけがえのない財産です。
ーー奈良豊澤酒造入社後のことも教えてください。
豊澤孝彦:
弊社に入社したのは平成11年のことです。当時の製造部門は、但馬杜氏とそのチーム、そして地元採用の社員で構成されていました。但馬杜氏とは、兵庫県但馬地方を拠点とする杜氏集団で、日本の四大杜氏のひとつに数えられています。高度な技術と豊富な経験をもち、各地の酒蔵へ出向いて仕込みを担っています。昔ながらの酒蔵では経営者が製造に直接タッチすることは少なく、職人さんに製造を完全に依存している時代でしたね。
しかし、私が入社する少し前から、先代の杜氏さんの提案で、地元採用の社員が但馬の職人さんと一緒に酒づくりを学ぶ体制が始まっていたのです。
但馬杜氏さんが平成24年に引退される際、「自分の後継者として育てた社員がいるので彼に任せてほしい」というお話があったのです。私は良いタイミングだと考えましたが、製造経験のない父は心配していました。
しかし杜氏さんの後押しもあり移行が決まり、その新しい社員杜氏のもとで全国新酒鑑評会で金賞を受賞することもでき、うまく引き継ぎができたと感じています。現在は完全に地元採用の社員による酒造体制です。
逆境を越えて挑んだ二つの転換期

ーー経営における最初の大きなターニングポイントは何でしたか。
豊澤孝彦:
大手メーカーへの「桶売り」から脱却し、純米酒を中心とした自社ブランドでの販売へと大きく舵を切ったことです。昭和50年代、関西の酒蔵のほぼ100%が桶売りでしたが、昭和48年をピークに日本酒の生産量は減少し始め、大手メーカーも地方の酒蔵からの買い取りを減らしていきました。危機感を抱いた父は、大手があまりつくっていなかった純米酒に活路を見出そうとしたのです。
きっかけは、ある大手外食チェーンの創業者の方と父との出会いです。「日本酒本来の姿は純米だろう」という言葉からでした。当時の酒税法では純米酒は品質に関わらず「2級酒」扱い。つまり、高品質な純米酒を2級酒の価格で提供できるというメリットがあったのです。
父は「良いものを安く提供しよう」と純米酒づくりに注力し、昭和51年に純米酒の販売を開始しました。現在では当社の出荷量の約85%が特定名称酒で、そのうち60%近くを純米酒が占めています。
ーー第2のターニングポイントについてお聞かせください。
豊澤孝彦:
2004年に始めた蔵元直営の飲食事業です。近鉄奈良駅の駅ナカに立ち飲み形式のアンテナショップ「蔵元豊祝」を出店したのが始まりです。当時は焼酎ブームのあおりも受け、日本酒業界は厳しい状況でした。
これからは酒問屋や酒販店だけに頼るのではなく、自分たちで消費者との接点を築いていくことが必要だと考えるようになりました。実際に飲食業を始めてみると、想像していた以上にお客様の声がダイレクトに届くようになり、それが何よりの収穫となりました。
搾りたてのお酒をその日のうちに提供し、お客様の反応を直接見ることができるのは、商品開発にとって非常に大きな助けとなっています。新商品を出す際のリスクを低減でき、店舗限定で試験販売し、評価が高ければ本格的に市場投入するという流れができました。
お客様とのコミュニケーションから新たなお取引先を紹介いただくこともあります。現在、直営店と姉妹店を合わせて11店舗展開し、売上の約35%を占める重要事業となっています。
「お客様目線」を貫き、地域と未来を醸す

ーー人材育成や採用についてはどのような考えをお持ちですか。
豊澤孝彦:
お酒や食に興味があり、熱意を持って取り組める方に来ていただきたいと考えています。商品知識が豊富な方も歓迎です。製造・営業・飲食といった各部門が互いに支え合っていることを理解し、広い視野で行動できる方を求めています。
製造部門では、次世代を担う若手の育成に取り組む一方で、シルバー世代の雇用も積極的に進めています。
人材育成においては、社員の個性を伸ばせる会社でありたいですね。「こうでなければならない」と型にはめず、本人の自主性やスキルを最大限に活かせる部署で活躍してもらうことを重視しています。
部門間の交流を促し、会社全体としての一体感を高めると同時に、年齢や経験にかかわらず、誰もがやりがいを感じながら活躍できる環境づくりを目指しています。
ーー今後の展望や、地域社会への貢献についても教えてください。
豊澤孝彦:
「お客様目線の酒づくり」という企業理念のもと、地域やお客様にとって必要不可欠なメーカーでありたいと考えています。
どれだけこだわったお酒をつくっても、消費者に選ばれなければ意味がありません。常にお客様のニーズを的確に捉え、それに応える商品やサービスを提供しつづけることが重要です。
直営店はその理念を実践する場であり、お客様の声を直接聞き、それを商品開発や営業活動に活かすことで、お客様に満足していただき、選ばれ続けるための好循環を生み出すでしょう。当社のお酒を通じて、お客様の笑顔や幸せにつながる体験を提供できれば嬉しいです。
直営店もまた、人と人とがつながるコミュニティの場として親しんでもらえる存在を目指しています。とくに、奈良は日本酒発祥の地でもあり、私たちはこの素晴らしい文化を守り、育て、次の世代へと受け継いでいくことを使命としています。その使命のもと、これからも真摯に取り組み、邁進してまいります。
編集後記
150年以上の歴史を持つ奈良豊澤酒造は、常に「お客様」と真摯に向き合い、変化を恐れず挑戦を続けている。伝統を重んじつつ現代のニーズを捉え、新たな価値を生み出す強い意思が感じられた。二度の大きな転換期を乗り越え、純米酒の販売や直営店の展開など、新たな柱を築いてきた。同社の「お客様目線の酒づくり」という理念と地域貢献の姿勢は、日本酒業界に新たな価値をもたらしていくだろう。

豊澤孝彦/奈良豊澤酒造株式会社代表。創業者から5代目。東京農業大学醸造学科卒業後、熊本県の酒造メーカーで3年間修業。平成11年に奈良豊澤酒造株式会社に入社。杜氏制度から社員による酒づくりへの移行、純米酒への注力、蔵元直営飲食店の展開など数々の改革を主導。