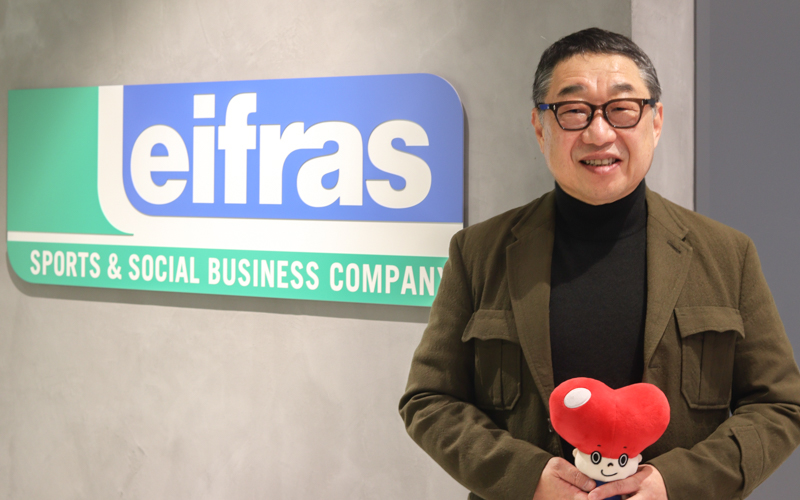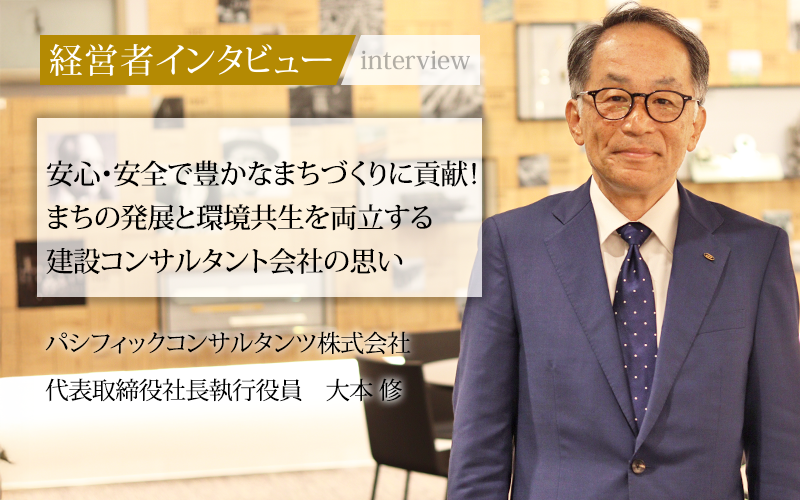
パシフィックコンサルタンツ株式会社は、多様な社会インフラへの技術サービスを提供している建設コンサルタント会社だ。国土基盤や交通基盤、都市・地域開発のほか、エネルギー、上下水道、建築、デジタルサービスなど、その領域は多岐にわたる。建設プロジェクトの企画・調査・計画・設計から施工管理・維持管理まで一貫して携わる。利用者目線を第一とした東京・渋谷再生プロジェクトなど、大規模なまちづくりプロジェクトにも参画している。
今回、同社を率いる代表取締役社長執行役員の大本修氏に、建設コンサルタント業界に入ったきっかけや、まちの発展と環境共生を掲げた企業理念に込めた思いなどについて、話をうかがった。
「もっと災害に強いインフラを」人生を変えた阪神・淡路大震災
ーーこれまでのご経歴を教えてください。
大本修:
京都大学の耐震工学研究室で橋梁の耐震性について研究しており、その知見を活かそうと思ったのが、建設業界に入ったきっかけです。大学院修了後は株式会社鴻池組に入社し、土木技術本部に配属されました。そこは研究・開発を行う部署で、トンネル掘削のシミュレーションプログラムの開発や新しい杭の開発などを担当しました。
当時、私は技術士という資格を取得しました。きっかけは、隣の部署の課長から「君たちに技術士の資格は取れないよ」と言われたことでした。技術士は主にインフラの調査、計画、設計を行うのに必要な資格です。そのため、そうした業務に直接かかわる技術者が取得しやすく、研究・開発が中心の私の部署からはしばらくの間合格者が出ていませんでした。
しかし、課長からの言葉に、「それなら取得してみせよう」と奮起し、休日を返上して猛勉強しました。私の姿に刺激を受けたのか、同じ部署の先輩や同期も試験勉強に熱が入り始めました。結果として、同じ部署から5名が合格しました。社内では前代未聞の出来事となりました。
思い返せば、この頃から負けず嫌いな性格と、周りを巻き込む力を発揮していたんですかね。
ーー今の会社に転職したきっかけをお聞かせいただけますか。
大本修:
大きな転機となったのが、兵庫県在住時に発生した阪神・淡路大震災です。自宅の被害は大きくありませんでしたが、神戸の中心地付近では多くの家屋や建物が倒壊し、多数の死傷者が出ました。
とりわけ衝撃的だったのは、阪神高速道路の倒壊です。大学時代の恩師である教授が、テレビのインタビューで、「耐震工学は、経験工学です」と話された言葉が、強く印象に残っています。「なぜ高架橋が倒壊したか」という質問に対し、「高架橋の設計は、過去の記録から想定した大きさの地震動に対して行うが、今回はそれを上回るものだった」という主旨の説明をされていたのです。
説明は理解できるものの、多くのインフラが崩壊し、甚大な被害を招いたのは事実です。この震災を機に「もっと災害に強いインフラの整備に関わりたい」と強く感じました。そして、インフラの調査・計画から維持管理まで、全工程を担う建設コンサルタント業界への転職を決めたのです。
慣習を打ち破る技術者出身の組織改革

ーー貴社に入社した時の印象についてお聞かせください。
大本修:
同じ建設関連業界でも、前職とは180度雰囲気が異なり、「会社によってここまで違うのか」と驚きました。以前勤めていたのは当時でも120年以上の歴史がある老舗企業です。オフィス勤務の男性はスーツにネクタイ、女性は制服で、上下関係もしっかりしていました。
一方、弊社では男性でもスーツを着ていない人は多く、女性も私服です。呼びかける際も役職はつけずに「●●さん」「●●くん」と呼び合うフラットな社風です。私にはこうしたフランクな職場の方が合っていたようで、のびのびと働ける環境を居心地良く感じました。
ーー入社後はどのような業務に携わってきたのですか。
大本修:
大阪で地盤技術分野の技術者として15年ほど勤務し、大阪・関西万博の会場となった人工島、夢洲へのアクセストンネルの情報化施工などに関わりました。東京の本社にある業務推進部に異動したのは50歳のときです。
業務推進部では、会社の事業計画を策定して進捗を確認する役割を担いました。また、業務が円滑に進むよう、積極的に改革も進めました。これまで手間がかかっていた作業の見直しやDXの推進など、さまざまな視点から業務の効率化を実現しました。
技術部門から管理部門への異動に加え、役員の隣で仕事をする環境に、はじめは強いプレッシャーを感じていました。ただ、技術出身だからこそ先入観がなく、慣習化していた業務の無駄に気づけた点は良かったと思います。
2年半の本社勤務の後、九州支社長に就任し、九州エリアを統括することになりました。
九州支社を過去最高業績へ導いた組織論
ーー支社長として組織を運営する立場になり、意識したことを教えてください。
大本修:
私は従業員の意思を尊重し、一人ひとりのモチベーションを高めて組織全体の士気を引き上げることが、トップの役割だと考えています。そのため、従業員の意欲を引き出し、楽しく働ける環境づくりを意識しました。
まずは200人近い従業員全員と面談し、一人ひとりが望む働き方や仕事内容、将来像などをヒアリングしました。そこで明らかになった課題や改善点を部門長に共有しながら、働きがいを感じられる職場づくりに努めました。経営者になった今も、一方的に仕事を与えるのではなく、各自の意見を尊重するよう心がけています。
九州支社長を2年間務める中で、他支社の社員から「九州支社は楽しそうだから転勤したい」という声が聞こえるようになりました。さらに、過去を大きく上回る業績をあげることもできました。今では首都圏に次ぎ、大阪と業績を競うほどの大きな支社に成長しています。
ーーこれまでのキャリアの中で特に印象に残っていることは何ですか。
大本修:
九州に赴任して間もなく発生した熊本地震の際、異例の方法で進める新設の道路プロジェクトに関わったことです。地震で主要幹線道路が被災し、交通に大きな影響が出ていました。一刻も早い復旧のため、トンネルを含む新しいルートを短期間で開通させる必要がありました。そこで、国土交通省の要請を受け、調査・設計から施工までを一括で管理するPM/CM(※1)方式で業務を担う事になりました。
これまでにない新しい試みで、失敗の許されない難しい挑戦でしたが、プロジェクトは無事成功しました。交通網の復旧、被災地の復興に貢献できたと考えています。
(※1)PM/CM:プロジェクトマネジメント/コンストラクションマネジメントの略
自らの力で変わる決意の組織改革と理念策定

ーー社長就任の経緯と当時の意気込みについて教えてください。
大本修:
前社長の辞任を受け、急遽、私が社長に就任しました。解決すべき課題も多く、「自分たちの力で変わらなければならない」と強く決意したことを覚えています。そこで、大きく2つのことを進めました。
1つは、「変化と成長」をキーワードとした改革です。弊社の自由闊達な企業文化は長所ですが、時に闊達というよりも奔放になっていた部分もあると反省しました。そこで、企業のガバナンスを見直し、基本ルールを明確にしました。また、社外取締役による指名報酬委員会の強化や役員の定年制導入、報告経路の明確化など、経営・執行組織体制を刷新しました。
もう1つは、弊社のステートメントを再定義しました。目指すべき方向性を明確にするため、役員が中心となり議論を重ねました。「世界中の誰もが脅かされない、格差がない豊かなくらしを、実現すること」。そして、「すべての生命の源である美しい地球、その環境を守り、未来へ引継ぐこと」。この2つを両立させ、持続可能な社会をつくることが私たちの使命であるというステートメントには、私たちの存在意義が込められています。
私自身、判断に迷ったときは、このステートメントに立ち返りますし、従業員にも事あるごとに話しています。徐々に浸透しつつあると感じています。
インフラの全てを担う総合力が最大の武器
ーー貴社の強みについてどうお考えですか。
大本修:
強みの1つ目は、総合力です。弊社は国土基盤や交通基盤、都市、エネルギー、上下水道など、あらゆるインフラに関する技術を有しています。都市開発や地域開発に必要な技術をすべて網羅しているのが、他社との差別化要因だと考えています。
2つ目は、市民が平和で安心安全に暮らせる環境をつくる「シビルエンジニアリング」を得意としている点です。これにはインフラの調査や設計だけでなく、建築や都市計画、住民との合意形成なども含まれます。さらに、インフラ整備に必要な資金の確保や、途上国に対する技術協力・移転なども担います。
こうした強みを活かし、東京・渋谷再生プロジェクトなどの大規模なまちづくりプロジェクトにも参画しています。弊社は東急東横線の地下化を機に始まった渋谷駅周辺の大規模再開発に大いに関わっています。⼤⾬時の地下街の浸⽔、駅施設の⽼朽化、交通機関の乗り継ぎの不便さなど、渋谷というまちが抱える課題を解決するため、弊社の技術力を結集して、駅を動かし、川の流れを変え、新たな歩行者ネットワークをつくりあげました。
また、住民や駅を利用する方々の視点に立ったまちづくりを提案し、多くのステークホルダーとの協議や調整・調整役を担いながら、誰もが納得できる形での開発に貢献しました。こうした大規模プロジェクトは、高い技術力とソフトスキルを持つ弊社だからこそ実現できたと自負しています。
ーー今後のビジョンについて教えてください。
大本修:
100年企業を目指すにあたり、「中期経営計画2028」を策定しています。弊社の事業は、国内インフラプロジェクト・海外インフラプロジェクト・インフラビジネス・デジタルソリューションの4つで構成されています。今後はそれぞれの事業を成長させ、さらなるビジネスの拡大を目指す方針です。
従来どおり国内インフラプロジェクトが主軸であることに変わりはありません。それに加え、今後は特に海外インフラプロジェクトに注力したいと考えています。地球温暖化への対応など、私たちが向き合う社会課題に国境はなくなっています。この問題の解決に向け、部署やグループ会社の垣根を取り払い、グローバル企業グループとして海外事業を拡大したいです。
また、今まで国や自治体が担ってきた公共サービスを民間事業者が行う、新たなインフラビジネスへの取り組みも重要です。国や自治体が管理しきれなくなったインフラを効率よく管理する、新しいサービスなどを提案・提供していきたいと考えています。さらにデジタルソリューションもかけ合わせ、弊社が持つ技術力の価値を最大化していきます。
未来を生きる子どもたちに豊かな世界を残したい
ーー貴社の採用方針についておうかがいできますか。
大本修:
私たちのステートメントを実現するため、先ずは中期経営計画の目標達成に向けて、人材の多様化を進めていきたいと考えています。性別や国籍を問わず、多様な価値観を持った人材を受け入れ、一つのチームとして機能する組織を目指しています。
この目標を踏まえ、弊社が求めるのは、専門性を持ちつつも柔軟性のある人材です。近年では、例えば私が専門とする地盤技術分野ひとつをとっても、能登半島での広範囲の液状化対策や熱海の土砂災害を契機とした盛土の法規制など、新たな対応が次々に求められています。そのため、一つのことを極めるだけではなく、さまざまな課題や状況の変化に柔軟に対応できる方に来ていただきたいと考えています。
ーー最後に、経営者として事業にかける思いをお聞かせください。
大本修:
弊社はインフラ整備にかかわる技術コンサルティングが主力事業ですが、持続可能な社会を後世に残していくことも意識しています。
現代社会は、環境破壊や食物の生育不良の深刻化など、多くの課題を抱えています。こうした状況の中、これからを生きる子どもたちが暮らしやすい世の中にすることが、私たち大人の大切な使命です。今後もまちの発展に寄与しながら、人々の幸せな未来を守る活動を続けていきたいですね。
編集後記
阪神・淡路大震災で、安全とされた高速道路が倒壊したのを目の当たりにし、「もっと災害に強いインフラをつくりたい」と建設コンサルタント業界に足を踏み入れた大本社長。以来、数々のプロジェクトの成功に導き、この国のインフラ整備を支えてきた。安全かつ便利で豊かな社会を残すため、環境にも配慮した社会基盤整備を進めていく同社の挑戦は、これからも続く。

大本修/1961年愛媛県生まれ。京都大学大学院(工学研究科交通土木工学専攻)修了後、株式会社鴻池組に入社。1996年に35歳でパシフィックコンサルタンツ株式会社に入社し、地盤技術分野の業務に携わる。本社業務推進部長、九州支社長などを経て、2016年に取締役就任。2022年に代表取締役社長執行役員に就任。現在、一般社団法人建設コンサルタンツ協会会長も務める。