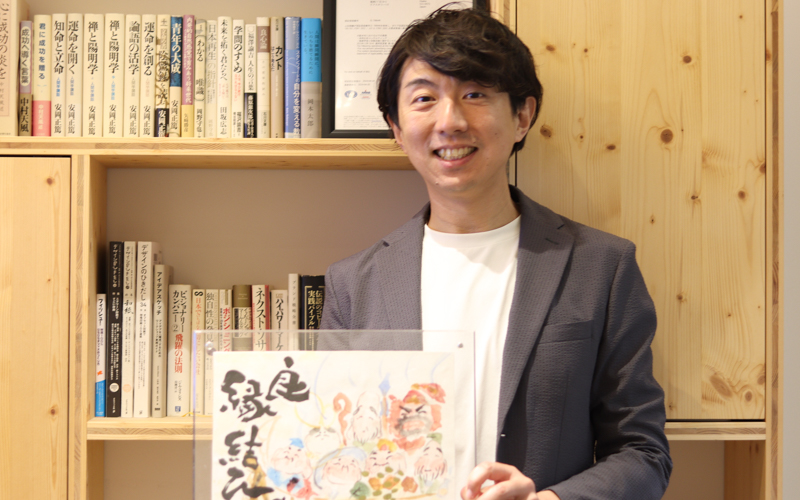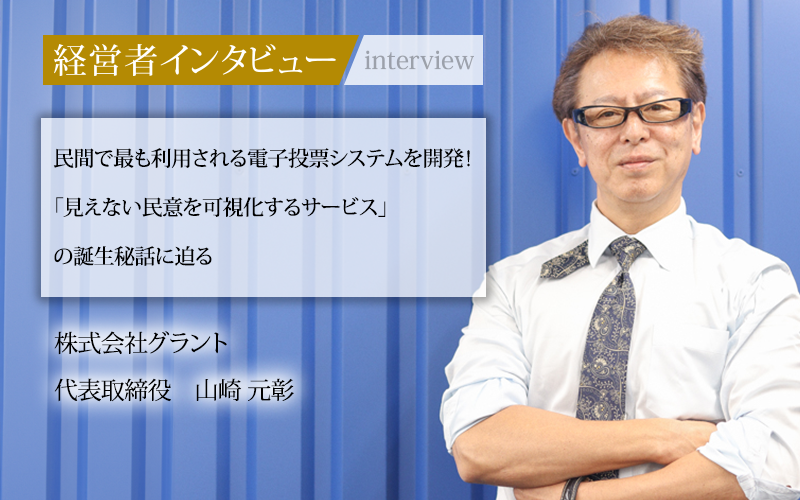
ERPシステム(統合基幹業務システム)や基板設計の分野で事業を展開する株式会社グラント。付加価値の高いIT技術を提供する集団としても知られており、特に同社の開発した電子投票システム「e投票」の利用延べ人数は約700万人の実績を誇る。
今では多くの場所で必要とされている「e投票」だが、代表取締役の山崎元彰氏によると当初は社内外から「こんなサービス誰も使わない」と反発も多かったとのこと。今回、山崎氏に同社の事業や「e投票」の誕生から成功までの経緯、今後の目標などを聞いた。
ERPシステム導入・基板設計・電子投票の3つを軸に事業を展開
ーー起業から現在に至るまでの道のりを聞かせてください。
山崎元彰:
大学では好きだった物理の知識を活かして原子力を学びました。卒業後は自分に適したフィールドを探しながら、電線の研究職やシステムエンジニア、訪販での洗剤販売、百貨店のシステム運用まで幅広く経験しましたね。
そして、契約社員のエンジニアとして働いていた会社でERPを学んだことをきっかけに、グラントを創業したのです。エンジニアは私一人という状況から営業を開始し、少しずつ実力をつけ、組織を拡大してきました。
その後、ERPに加えて基板設計、さらに13年前から「e投票」という電子投票システム事業も始め、現在はこの3つを主な事業として展開しています。
「皆の声を投票に反映させたい」という思いで電子投票システムを開発

ーー「e投票」とはどのようなものなのでしょうか。
山崎元彰:
「e投票」は、公平な投票や集計を実現する弊社独自の電子投票クラウドサービスで、主要顧客は労働組合や学術学会、健康保険組合などです。たとえば代表選出をする際、このシステムの導入で、驚くほど簡単かつスムーズに運営と参加を行うことができます。
まず運営側が、システムから参加者へメールを一斉送信するだけで、案内は完了です。案内状の準備や輸送といった煩雑な手作業から解放されます。
参加者は、受け取ったメールのQRコードをスマートフォンで読み込むだけで、選出会への出欠連絡や投票方法(電子または手書き)の選択が瞬時に完了します。さらに電子投票を選べば、パソコンやスマートフォンから、時間や場所に縛られずに投票が可能になります。これにより、忙しい中でも誰もが参加しやすく、より多くの意見を反映した代表選出が実現します。
つまりこのシステムは、運営の手間を最小限に抑え、参加のしやすさを最大限に高め、より公正で効率的に投票ができる画期的な方法なのです。
「e投票」はただ紙票をデジタル化したものではありません。弊社のERPシステム導入と基板設計の技術を活かし、セキュリティを維持しながら、総会や選挙を運営する事務局の業務フローを最適化していることが特徴です。
ーーどのような経緯で「e投票」のサービスは誕生したのでしょうか。
山崎元彰:
サービス開発のきっかけは、マンション管理組合の理事長になったときに感じた、ある出来事です。
あるとき、「絵画をレンタルして共用スペースに飾りましょう」という提案が理事会で可決されたのですが、一人の住民がやって来て「私の周りは全員反対しています」と強く抗議したのです。それならば、紙のアンケートを取ってみようということになったのですが、ほとんどの人が賛成という結果でした。
総会会場に来て実際に投票をする人の中には、日頃から何かしら鬱憤が溜まっており、クレームを言いたいだけというケースが残念ながら少なくありません。その一方、これといった不満や意見がない人はそもそも総会会場に来ないため、総会に参加する人に議決権を委任するケースがよくあります。
「e投票」というサービスは、このときの「もっと簡単に全員の声を集める仕組みをつくり、民意を正しく反映させたい」という思いが発端となっています。
ーー実際に「e投票」を開発してみて、周りの反応はどうでしたか。
山崎元彰:
当初はマンション総会用のサービスとして開発したのですが、管理会社の中には新しいサービスを使うことに抵抗感を覚える人も多く、最初は誰も使ってくれませんでした。
当時はNTTドコモの携帯電話(ガラケー)向けネットサービス「iモード」の全盛期で、スマートフォンはおろか、QRコードを“読む”という行為すら珍しい時代です。また「高齢化社会に逆行している」「一体、通信料は誰が払うんだ?」「そもそも管理組合は、“声の大きい人”の意見を直接把握しなきゃダメなんだよ」と否定の声のほうが多かったですね。
しかし、私は「e投票」を普及させることを諦めませんでした。ユーザーに寄り添ったサービスにするために、マンション総会以外の場でも活用できるよう改良しました。その結果、「e投票」はどんな団体でも使えるサービスになりました。
そうした努力が実を結んだのか、「e投票」の公平性や透明性などが評価され、学術学会での導入が決まったのです。ついに「e投票」が、日の目を見ることになった瞬間でした。
その後、「学術学会でも使えるなら、労働組合でも使えるだろう」と労働組合にも広まり、サービスを使ってくれる人が徐々に増加していきました。
そして、奇しくもコロナ禍という未曾有の事態が、“感染リスクゼロ”という新たな価値を市場に吹き込み、私たちのサービスにとって強力な追い風となったのです。
今や、電子投票は当たり前の選択肢として社会に浸透し、多くの場面で活用されています。かつて多くの反対意見に見舞われたサービスが、こうして社会の“当たり前”をつくり上げたのです。
自分の信念に従った行動と、あらゆる困難を乗り越えてきた道のりを思うと、言葉では言い尽くせないほどの熱い誇りが胸に込み上げてきます。
会社経営で大切なのは「オールを漕ぐタイミングをそろえる」こと

ーー今後の目標や思いを聞かせてください。
山崎元彰:
弊社では、主力事業の一つである「e投票」サービスのさらなる発展と利便性向上を目指し、AIの活用を積極的に進めています。現代においてAI技術の進化は目覚ましく、この大きな波に乗り遅れるわけにはいきません。この危機感と将来への期待感から、AI技術の導入と活用は会社全体の重要な方針となっています。
その一環として、昨年には「Design 2 ABAP Squad(デザイン・ツー・アバップ・スクワッド)」というChatGPTのGPTs機能を活用したツールを開発しました。このツールにより、従来プログラマーが1日かけて行っていたコーディング作業がわずか1時間ほどで完了するなど、劇的な工数削減を実現しています。
こうしたAIを活用することでローコストかつフレキシブルなシステム開発を目指しています。将来性のある電子投票業界でトップを走り続けるためにも、また他の事業領域においても、AI技術を積極的に活用していくことが今後の成長の鍵となると考えています。
そして、新たな方針や目標を掲げ進んでいく上で何よりも大切なのは、全社員が同じ方向を向いて力を合わせることです。私は、過去10年ほど木造船レースに参加した経験があります。そこで痛感したのは、どんなに個々の能力が高い漕ぎ手が集まっても、全員のタイミングや意識が合わなければ、船は決して前に進まないということです。「こっちへ行く」と定めた目標に対し、全員が心を一つにして取り組む。この姿勢こそが、変化の時代を乗り越え、会社を成長させる原動力になると信じています。
編集後記
「少数派が多数決を制してしまう状況を変えたい」という思いこそが、「e投票」誕生の原点だ。優秀なエンジニアによって形になったサービスではあるが、それ以上に同サービスには、山崎氏の信念が込められていることを強く感じた。AIの活用も含めて、これからの社会を支える新しい「仕組み」を生み出す同社の今後の展開から目が離せない。

山崎元彰/1960年生まれ、北海道出身。近畿大学理工学部原子炉工学科を卒業後、研究職やシステムエンジニアを3年ほど経験。その後、フリーランス・システムエンジニアの活動を経て、1995年12月有限会社グラントを設立。当時、日本に入ったばかりのERP専門企業として活動開始。2002年12月、株式会社グラントに社名変更。