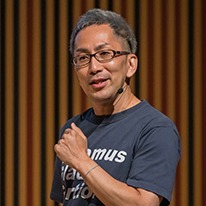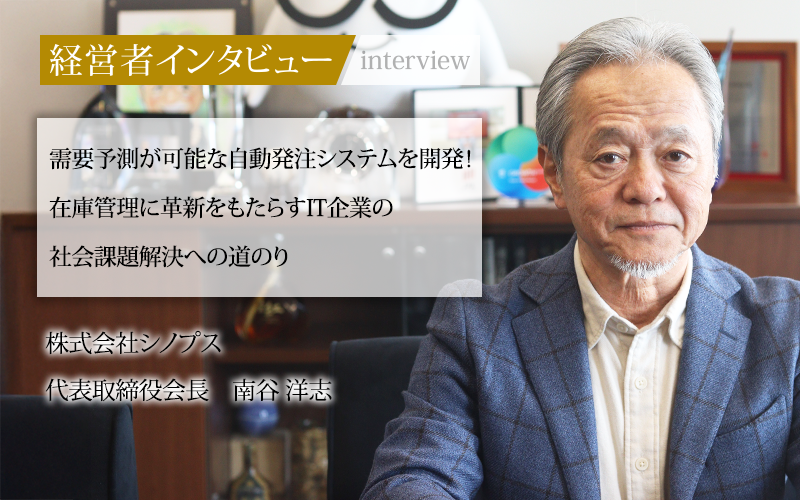
小売業や製造業において、適切な在庫管理は企業の存続を左右する極めて重要な要素である。だが、その実現には、需要予測の精度を高めることが不可欠であり、長年にわたり業界の課題とされてきた。
そんな中、市場に適切な在庫管理ソフトが存在しないことを勝機ととらえ、独自のソフトを開発して課題解決に挑んだのが株式会社シノプスだ。業界のパイオニアとして活躍する同社の代表取締役会長の南谷洋志氏に、創業の経緯や成長の軌跡、そして未来を見据えたビジョンについてお話をうかがった。
在庫管理のスペシャリストから起業家への転換
ーー創業までの経歴をお聞かせください。
南谷洋志:
就職氷河期で就職活動が非常に難航していた時期に受けたのが、大都商事株式会社(現:ダイトロン株式会社)でした。入社面接には創業者が同席し、私の卒論の研究テーマを見て「在庫が多くて困っているから、在庫管理をやってもらえないか」とお誘いを受け、迷わず入社を決めました。
ただ、両親が果物屋を営んでいた影響もあり、いずれは独立するつもりでした。その考えは入社後も変わらず、3年ほど経ち、独立に向けて準備を進めました。そんなときに、当時お世話になっていた方から株式会社須磨電子産業への転職を勧められたのです。結婚を控えていたこともあり、経済的な安定とメーカーでの経験を積める機会であることを重視して転職を決意しました。数年間同社でお世話になった後、長年の夢であった独立を1987年に実現し、株式会社リンクを創業。2019年には社名を株式会社シノプスに変更して、現在に至ります。
ーーどうやって独立を果たしたのですか?
南谷洋志:
須磨電子産業に入社して6年目に、画像処理装置のソフトウェアを開発していた会社の経営者から「1年間の注文書を出すので、独立して経営者にならないか」と声をかけていただいたことが、独立の決め手でした。ありがたい申し出でしたし、これまでの仕事が認められたような気がしたのを覚えています。独立後は、プリント基板をメーカーに発注し、部品を調達して組み立て、完成品に仕上げてからエンドユーザーに納品するという事業形態で、経営者としての道を歩み始めたのです。
在庫管理革新への第一歩!独自システム「sinops(シノプス)」の開発

ーー創業後は、どのように事業展開したのですか?
南谷洋志:
創業当初は、画像処理ソフトを開発していた企業から全面的に業務を委託され、主にハードウェアの制作を手掛けていました。プリント基板は須磨電子産業の工場で製造し、その他の部品も複数の工場から調達して組み立てるファブレス(工場を持たない生産)型の事業形態でのスタートでした。創業当初は順調でしたが、5年目に取引先企業の業績が急激に悪化し、弊社の売上も減少したのです。
この状況を打開すべく新規開拓を進める中で、物流事業者から「入荷検品システム」「出荷検品システム」の開発依頼をいただいたことが大きな転換点となりました。弊社との打合せ後、先方の社長が担当者に『在庫が増えている!』と厳しく詰問されているので、「昨年出たWindow’s95版の在庫管理パッケージソフトで解決出来るでしょう」と提案しましたが、当時の在庫管理はエクセルのような簡易ツールが主流で、必要な機能を満たすものが見つかりませんでした。「それなら自分で作ろう」と、大学時代に研究していた需要予測の知識を活かし、大学時代の資料をもとに学び直して、独自にソフトを開発しました。そこで生まれたソフトが、現在の製品の原型です。同製品の販売は、次第に弊社の主力事業へと成長を遂げていきました。
ーー貴社の事業内容を教えてください。
南谷洋志:
弊社は「世界中の無駄を10%削減する」というビジョンのもと、需要予測型自動発注システム「sinops(シノプス)」を独自開発しました。このシステムは、食品小売などの在庫を抱える多くの企業で導入され、業績改善に大きく寄与しています。
商品欠品による販売機会の損失は、企業の業績悪化に直結する一方、過剰在庫は資金繰りを圧迫し、最悪の場合は倒産につながる重大なリスクとなります。したがって、需要予測の精度向上は、企業活動の最優先課題のひとつなのです。
さらに、2020年頃からは日配食品や惣菜といった賞味期限が短く、需要予測が難しいカテゴリーのシステム化にも成功しました。多くの食品小売業様に採用いただき、非常に高い評価をいただいています。
ーー貴社の強みはどのようなところだと分析していますか?
南谷洋志:
弊社のサービスが小売業で高いシェアを占めているのは、長年にわたる工夫と鍛錬の成果です。商品がどのくらい売れるかを正確に予測するために、天候や気温、イベントの有無、価格設定、売り場の配置など、多くの不確定要因を考慮し、仮説と検証を繰り返しながら、連立方程式を使って数多くのパターンを確立してきました。
このように専門的な知識と技術を駆使して構築された仕組みでなければ、需要予測は困難です。弊社は、20年以上にわたる研究と開発を重ねた結果、多くの企業から信頼されるシステムを提供できているのです。この長い積み重ねこそが、弊社の最大の強みだと考えています。
未来を変えるプラットフォームの構築を目指す
ーー最後に、今後のビジョンについてお聞かせください。
南谷洋志:
弊社は「在庫に関わる“人”、“もの”、“金”、“時間”、“情報”を最適化するITソリューションを提供し、限りある資源を有効活用することで、広く社会に貢献する」という理念のもと、これまで成長してきました。今後は、開発した「sinops」を通じた「もの」を管理する戦略的な在庫最適化をさらに進化させつつ、「人」の最適化にも注力していきたいと考えています。
具体的には、小売業やサービス業などで働く従業員の「作業ログ」データをスマートフォンで収集、分析することで、従業員の「働き」の実態を把握し、最適な勤務計画の予測や教育を支援する「sinops-WLMS」というサービスを構築中です。「人」と「もの」の予測をかけ合わせることで、さらなる正確性を追求し、実用化に向けた調整を進めています。
また、もうひとつの重要な取り組みが、大手総合商社と共同で進めている食品バリューチェーン最適化サービス「DeCM-PF」の構築です。このプラットフォームは弊社の需要予測システムを活用することで、ディマンド側である小売業の需要予測データを、卸売業や製造業につなげる仕組みです。生産や物流、調達、食品ロスといった食品流通の課題を解決し、バリューチェーンの最大化を目指しています。社会的インフラとしての可能性を持つこのプラットフォームによって、より大きな社会課題の解決に貢献できると考えています。
編集後記
南谷会長のこれまでの歩みと独自の経営哲学には、情熱と挑戦の歴史が凝縮されている。その揺るぎない信念が生み出した「sinops」は、業界全体の効率化を牽引する革命的な存在だ。小売業や物流業界にとどまらず、幅広い分野でその可能性を広げていく技術は、社会の課題を解決する未来を切り拓くに違いない。

南谷洋志/1954年、大阪府生まれ。関西大学工学部管理工学科卒業。1978年、大都商事株式会社(現:ダイトロン株式会社)に営業職で入社。1984年、株式会社須磨電子産業に転職。1987年に株式会社リンクを創業し、2018年、東証マザーズ(現:東証グロース)に上場。2019年、社名を株式会社シノプスに変更。