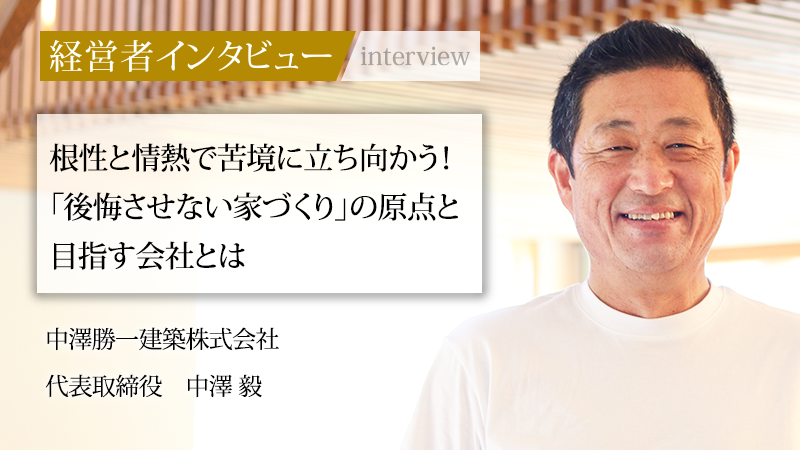
長野県で注文住宅やリフォーム、BtoBの建築事業を手掛ける中澤勝一建築株式会社。同社は大工の伝統と技術を受け継ぎながら、お客様に寄り添い、時代と共に進化を続けてきた。大工職の人材が減少し、自社で大工を雇用する企業も少なくなる中、同社は「大工魂」を掲げ、社員として迎えている職人の高い技術力と機動力を強みとしている。厳しい下請け時代を乗り越え、自社で仕事をつくり出す体制を確立した代表取締役の中澤毅氏に、その軌跡と事業へのこだわり、そして今後の展望を聞いた。
苦境の事業承継「ひたすら仕事を探す日々」
ーーこれまでのご経歴についてお聞かせください。
中澤毅:
大学卒業後、ゼネコンの守谷商会に入社し、現場監督として働きました。幼少期から「跡継ぎだ」と言われて育ったので、継ぐつもりがなかったわけではありません。しかし、当時は両親と大工が数人いる程度の小さな会社でした。そのため、学生時代は実家に戻って何をするのか、具体的なイメージは持てませんでした。
2000年に弊社へ入社するのですが、その時期はバブルが弾け、世の中は不景気の真っ只中でした。1998年には長野オリンピックがありましたが、その恩恵を受けることはなく、会社は厳しい状況に置かれていました。守谷商会で9年ほど働いた頃「いつ戻ってくるのか」という話が出て、弊社へ入社することになったのです。
ーー社長に就任された当初のことをおうかがいできますか。
中澤毅:
入社して3年目に社長に就任しましたが、会社が厳しい状態は続いていました。特に、もともと住宅の仕事をいただいていた会社が、不景気で倒産してしまった影響は大きかったです。それでも年間で数千万円の売上を上げ、なんとか生活していくことはできましたが、常に損益分岐点ギリギリの状態でした。まさに、激務なのに利益が出ない大変な日々でした。
私は「とにかく職人さんたちを食べさせていかなければならない」という一心でした。彼らに稼いでもらわないと、私たちの給料も出ません。そのためには、まず大工の仕事をつくることが最優先でした。BtoBの仕事を大切にし、設計事務所の入札に参加するなどして仕事を探しました。
当時は「社長が一番仕事をする人」だと考え、私一人で営業も担っており、入社して3〜4年はがむしゃらに働き続けた記憶しかありません。
下請けからの脱却を決意し自ら道を拓いた大きな転換点

ーーその厳しい状況をどのように乗り越えたのですか。
中澤毅:
2010年頃から、「このまま下請けを続けていては、元請けの影響を直接受けてしまう。自社で営業して仕事をつくらないといけない」と強く思うようになりました。待っていても仕事は来ませんから、自分の仕事は自分で見つけるしかないと覚悟を決めたのです。
ーー転機となった出来事は何だったのでしょうか。
中澤毅:
2011年の震災が大きな転機となりました。ある見学会に、被災されたお客様がいらっしゃいました。予算が2000万円とのことでしたが、設計事務所は「その予算では厳しい」。私は「2000万円でできる図面を描いてくれればやります」と伝えました。しかし、設計事務所から返ってきたのは、「そこまで言うなら、中澤さんのところで直接やっていい」という言葉でした。その時、私は「お客様はあなたを頼って来たんだから、それはないでしょ」と、その対応に強い憤りを覚えました。この出来事を通して、「設計事務所の仕事を頼りにしていても仕事はつくれない」と、自社で道を切り拓くことを決意したのです。
その流れから、2011年に、自社で集客から行う「R+ハウス」という組織に加盟しました。しかし、営業の経験がなかったため、最初の3〜4年は年に2棟ほどしか仕事が取れず、費用倒れの状態でした。税理士からも「辞めたほうがいい」と言われましたが、ここでやり方を変えなければ会社が立ち行かなくなると思い、諦めずに続けました。その時の粘りがなければ、今の体制はつくれなかったと思います。
模倣できない「大工魂」で実現する顧客に後悔させない家づくり
ーー改めて、貴社の現在の事業内容と強みを教えてください。
中澤毅:
弊社は主に、木造在来工法による住宅の新築やリフォームの設計・施工を行う会社です。売上の構成としては、新築の注文住宅が約50%、リフォームが30%、そしてゼネコンなどからのBtoBの仕事が20%という割合です。
強みは複数あります。中でも社員として大工を抱えていることによる技術力と機動力が最大の強みです。特に古民家再生のような専門技術が求められるリフォームや、まとまった人数が必要なBtoBの案件にも対応できるだけの人員が揃っています。最終的な差別化要因は「人」だと考えています。
ーー特にこだわっている点はありますか。
中澤毅:
現場の管理で、どこまでクオリティを上げられるかにかかっています。担当者が「これでいいか」と思えばそこまでです。しかし、「もっとこうしよう」とこだわれば、最終的な仕上がりは全く変わってきます。簡単な仕事ではありませんが、そのこだわるポイントがお客様のご要望と一致したときに、より良いものが生まれるのです。技術や商品は模倣できても、こだわりは模倣できませんから。
ーー提供されている住宅のコンセプトについてお聞かせください。
中澤毅:
まず大切にしているのは性能です。具体的には、国が定める断熱等級で最高ランクの「7」を基準としています。これは、エアコン1台で家中の快適性を保てるほどの高い断熱・高気密性能です。そこに建築家が加わることで、お客様一人ひとりのライフスタイルに合った、デザイン性の高い住宅を提供します。家は人生で一番大きな買い物です。だからこそ、今ある一番良いものを提供し、お客様に後悔させない家づくりを心がけています。
業界の未来を見据え、「人」へ投資し続ける理由
ーー現在、注力されていることは何ですか。
中澤毅:
現在、BtoBの事業拡大に注力しています。理由は2つあります。1つは、将来的に個人病院や店舗といった中規模の木造建築を自社で手掛けられるようになるための布石です。そしてもう1つは、社員である大工の仕事を年間通じて安定的に確保するためです。長野は冬に仕事が減りがちなので、BtoBの仕事で仕事量を平準化し、職人が安心して働ける環境をつくりたいと考えています。
ーー建設業界全体の課題については、どのようにお考えですか。
中澤毅:
一番は、やはり職人不足・人手不足です。良いものをつくろうにも、担い手がいません。弊社はまだ社員大工が10名、専属が3名いますが、今後を見据えて20人体制を目指しています。そのためには採用と育成、特に人材育成が最重要課題です。若手が求める労働環境に応えるため、休日数を増やすなどの改革も進めています。
ーー最後に、今後の展望をお聞かせください。
中澤毅:
数字の上では、現在の新築年間20棟から80棟、100棟へと拡大し、売上50億円規模の会社に成長させたいです。しかし、数字の達成だけが目的ではありません。一番はお客様に喜んでいただくこと。お客様の喜びが社員の喜びにつながり、それが給料や職場環境の向上という形で社員に還元される。この好循環を生み出すことで、本当の意味でお客様に楽しく貢献できる会社になれると信じています。
編集後記
家業を継ぐことに明確なビジョンを持てず、ゼネコンでの9年間の修業を経て、父の会社へと戻った中澤氏。折からの不景気、そして主要取引先の倒産。利益の出ない激務の中、「職人を食べさせなければ」という一心で、たった一人で営業に奔走した。下請けからの脱却を決意し、幾多の失敗を乗り越えて自社ブランドを確立した中澤氏の歩みは、挑戦し続けることの価値を雄弁に物語っている。顧客に後悔させないという実直な「大工魂」と、社員の未来を守るという強い責任感。その両輪で、同社はこれからも確かな道を切り拓いていくだろう。

中澤毅/1969年生まれ。大学卒業後、ゼネコンの株式会社守谷商会へ入社し、現場監督として約9年間勤務する。2000年、父が経営する中澤勝一建築株式会社に入社。営業として手腕を振るい、2003年に同社の代表取締役に就任。以来、下請け中心だった事業構造からの脱却、高性能住宅の開発、そして「大工魂」を宿す職人集団の育成に尽力し、地域社会に貢献する企業づくりを推進している。














