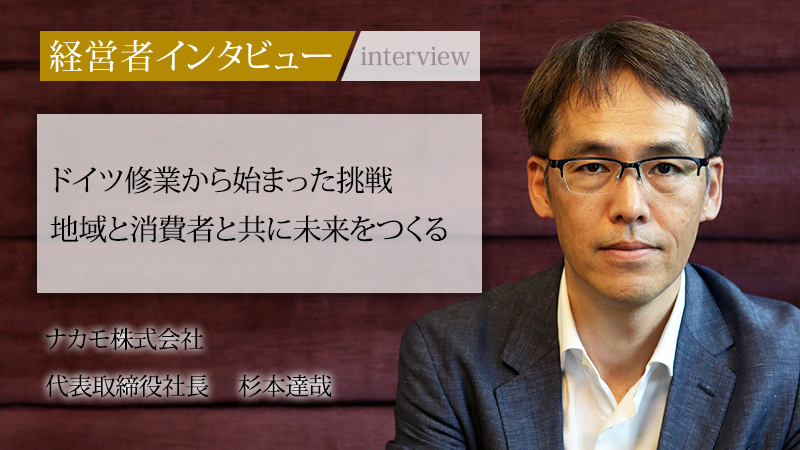
愛知県で「つけてみそかけてみそ」をはじめとする数々の食品を手がけ、地域に深く根ざすナカモ株式会社。同社を率いる代表取締役社長の杉本達哉氏は、家業を継ぐ予定のない次男として、ドイツでのビール修業を経てキャリアをスタートさせた経歴を持つ。「真摯に 謙虚に」という信条を胸に、醸造業特有の難しさと向き合いながら数々の苦難を乗り越えてきた。近年は、地域に開かれた工場づくりを推進。社員の主体性を育みながら、消費者と直接つながる新たな挑戦へと舵を切る。偶然の連続から始まったというその歩みと事業にかける熱い思い、そして地域と顧客と共に描く未来への展望をうかがった。
ドイツでのビール修業が導いた家業への道
ーーこれまでのご経歴をお聞かせください。
杉本達哉:
私は次男ということもあり、もともと家業を継ぐ意識はありませんでした。大学院で理系の研究をしていましたが、思うように成果が出ず、このまま研究を続けるべきか、将来に悩んでいた時期があったのです。
そんな折、転機が訪れます。当時、家業であるナカモが新規事業として、日本では「地ビール」と呼ばれ始めたクラフトビールの事業化を検討していました。そして「ドイツでビールの醸造を学べる者はいないか」という話が、偶然にも私の耳に入ってきたのです。ビールそのものへの興味はもちろん、研究がうまくいかない現状を打破したいという思いも強く、海外経験が全くなかったにもかかわらず「行きます」と手を挙げました。
ーードイツではどのようなご経験をされたのですか。
杉本達哉:
ドイツのレストランに8ヶ月間滞在し、見習い同然のスタートでした。最初は醸造タンクの洗浄といった下働きから始め、マイスターのもとでビールづくりの神髄をイチから学びました。しかし帰国後、地ビールが一過性の流行で終わる可能性も考慮し、会社はビール事業への参入を見送ります。
私自身は一度大学院に復学し、卒業後に就職活動を始めようと考えていました。しかし、その矢先、会社から「ドイツに行っている間も社員だった」と告げられ、予期せぬ形でナカモに入社することになったのです。
会社の危機を乗り越え手にした最大の財産
ーー事業を行う上で、大切にされている信条についてお聞かせください。
杉本達哉:
メディアに取り上げていただく機会が増えても「テレビに出ているからすごい」というような思い上がりは絶対にしない、という姿勢を大切にしています。ありがたいことに、私たちの実際の会社規模以上に大きく見ていただくことも多いのですが、私たちはあくまでも50名規模の中部地方のメーカーであるという謙虚な気持ちを忘れないようにしています。
醸造は自然が相手の仕事であり、決して人の力だけで思い通りになるものではありません。過去には、生産が追いつかずお客様に大変なご迷惑をおかけした苦い経験もあります。その時の悔しさやお客様への申し訳ない気持ちを忘れず、常に真摯な心で仕事と向き合うことを、社員にも伝え続けています。
ーーその苦しい時期を乗り越える、ターニングポイントはあったのでしょうか。
杉本達哉:
2007年にあるテレビ番組で取り上げていただいたことが、会社にとって最大のターニングポイントになりました。放送直後から注文が殺到し、1日の生産量を超える注文書が全国から届くという、まさにパニック状態に陥ったのです。
最初は「1週間もすれば落ち着くだろう」と見込んでいたのですが、注文の勢いは一向に衰えませんでした。お客様からの期待に応えるため、私たちは3ヶ月間にわたり工場を24時間体制で稼働させるという決断をしました。社員たちが交代で本当によく頑張ってくれ、私自身も会社の応接室で寝泊まりするような日々でした。
この経験を通じて、商品の知名度は全国的に高まり、会社として大きく成長するきっかけを得られました。何より、この苦労を共に乗り越えてくれた社員との一体感は、今も変わることのない弊社の最大の財産だと考えています。
地域に愛される工場へ まちに開かれた体験の場
ーー理想とする工場の姿について、お聞かせいただけますか。
杉本達哉:
「工場をできる限り、まちに溶け込ませたい」という思いが強くあります。閉鎖的になりがちな食品工場ですが、弊社ではガラス越しに製造工程が見えるようにしたり、少人数での工場見学を積極的に受け入れたりしています。ものづくりの現場を見ていただくことが、お客様の安心につながると信じています。
また、将来的には今後はものづくりを体験できる、より開かれたスペースもつくりたいと考えています。そして、究極の理想は、地元の人が「あそこはいい工場だよ」と自慢してくれる存在になることです。ただ製品をつくるだけでなく、地域の方々にとって身近で愛される場所になることが、私たちの目標です。
社員の主体性が未来をつくる

ーー組織としての強みは、どのような点にあるとお考えですか。
杉本達哉:
本当に、社員には恵まれていると心から感じています。特にここ数年で、各部署の担当者が驚くほど自律的に動いてくれるようになりました。正直なところ、最近は私が把握しきれないくらい、現場の判断で物事が進んでいくことも珍しくありません。「以前はどうやってこの業務を行なっていたんだっけ?」と、自分の記憶を疑うほどです。
もちろん、意図してこのような組織をつくってきたわけではありません。私の性格上、ある意味で「放ったらかし」にしてしまった部分もあります。しかし、課題が山積みの会社だからこそ、彼らは「社長が何もしてくれないなら自分たちでやるしかない」と、自ら考えて動く力を発揮してくれたのかもしれません。
そして、いざ会社が大変な時には、誰からともなく一致団結してくれます。かつて3ヶ月間、工場を24時間体制で稼働させた時もそうでした。過酷な状況にもかかわらず、文句一つ言わず力を貸してくれました。そんな彼らの主体性とチームワークこそが、会社の成長を支える最大の力であり、私の誇りです。
消費者と共創する新たな挑戦 次世代に味噌を繋ぐために
ーー最後に、今後の展望についてお聞かせください。
杉本達哉:
既存のヒット商品に安住するつもりもありません。社内では常々「『つけてみそかけてみそ』をぶっ壊せ」と言っています。あの商品を越えるような、全く新しい柱をつくる挑戦も続けていきます。
今まではスーパーへの卸売りを事業の柱としてきましたが、これからは消費者の皆様と直接関わる場を積極的に増やしていきたいと考えています。その一つが、お客様を巻き込んだ参加型の商品開発です。
これまでは、私たちの頭の中で考えた商品を世に送り出してきました。しかし今後は、お客様を招いて「実験室(ラボ)」のような空間で一緒に商品の使い方を考えたり、試作品への率直な意見をいただいたりしたいです。そこで生まれた小さなアイデアを少量生産し、試験的に販売(テストマーケティング)してみる。SNSなども活用しながら、お客様の声をダイレクトに吸収し、共に悩み、考え、一つの商品を育て上げていく。そうしたプロセスの中からこそ、これまでにない新しい価値が生まれると信じています。
固定観念にとらわれず、さまざまな形で味噌の可能性を広げ、次の世代へと繋いでいく。それが、これからのナカモが目指す姿です。
編集後記
「真摯に 謙虚に」。インタビュー中、杉本社長が何度も口にしたその言葉は、決して単なるスローガンではない。ドイツでの予期せぬキャリアの幕開けから、24時間工場を稼働させた苦難の時期、そして現在の「開かれた工場づくり」まで、すべての取り組みの根底に流れる哲学そのものだ。社員を信じ、地域を愛し、これからは消費者をも巻き込んで未来をつくろうとする姿は、謙虚さの先にある本物のリーダーシップを感じさせる。地域と、そして消費者と共創するナカモの新たな挑戦から、ますます目が離せない。

杉本達哉/1972年愛知県生まれ。1996年名古屋大学大学院に入学後、1997年4月〜12月にドイツへ留学する。その後、1998年4月に復学し、1999年3月に修了。1999年ナカモ株式会社に入社。2006年代表取締役社長に就任し、現在に至る。














