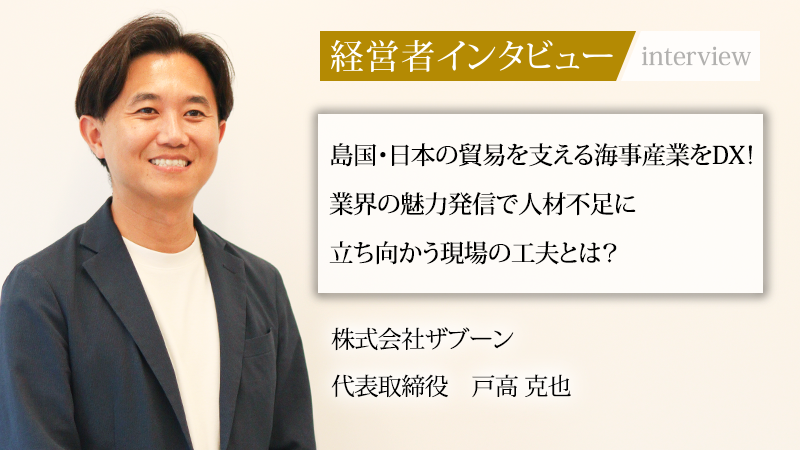
日本の経済活動と国民生活を支える大動脈、海事産業。その貨物輸送シェアは国内の約4割、輸出入に限れば99%を船舶輸送が占めている。にもかかわらず、これほど重要な役割を担いながら、一般の認知度は低いのが現状だ。
この状況に対し、株式会社ザブーンは船舶管理のDXを推進することで、業界の魅力向上と課題解決に挑んでいる。IT業界での経験と家業で培った深い知見を持つ同社の代表取締役の戸高克也氏。今回同氏に、業界が抱える課題の本質と未来を切り拓く同社の戦略を聞いた。
コロナ禍がDXを加速 海事産業の非効率を変える使命感からの挑戦
ーーはじめに、起業した経緯をお聞かせください。
戸高克也:
大学卒業後、IT系の人材サービス企業に新卒で入社し、法人向け営業を経験しました。約2年で退職して一度起業したのですが、残念ながらこれは失敗に終わりました。その経験から「自分だけの武器」の必要性を痛感し、以前から関心のあった家業に戻る決断をしたのです。
ーーなぜ船舶管理のDXに着目したのでしょうか。
戸高克也:
家業では約10年間、現場の隅々まで経験を積みました。海外派遣や、東京の船舶管理会社への出向も経験しています。担当業務は船のメンテナンス、新造船の監督、法律関連など多岐にわたりました。新卒で入社したIT業界とは全く異なるアナログな世界で、効率化できる部分が多くあると感じたことがきっかけです。
海事産業は独特で、業界知識がないとビジネスモデルを思い描くことすら難しいのが実情です。そのため、スタートアップも参入しにくい状況でした。しかし、私にはITと海事の両方の知見があります。「ここでなら自分の強みを発揮できるのではないか」と考えたのです。特にコロナ禍でリモートワークが注目され、海事産業のDXは待ったなしの急務となりました。この状況が、現在の事業を立ち上げる大きな後押しとなったと感じています。
「誰でも使える」が鍵 徹底した現場主義とUI/UXで船舶管理に革新を

ーー船舶管理クラウドサービスについて詳しく教えてください。
戸高克也:
私たちは、船の運航業務を支援する船舶管理クラウド「MARITIME 7(マリタイムセブン)」を開発・運営しています。もともとは船員の勤怠管理機能からスタートしましたが、現在では船舶管理業務を幅広く支援する多数の機能を搭載。数万点に及ぶ部品や消耗品の購買・在庫管理機能や、運航日報などのレポートのペーパーレス化などが可能です。
導入前はメールやExcel、FAXで行われていたバラバラな情報管理も、弊社のサービス上で一元管理できます。これにより、情報の分析が容易になりました。CO₂排出量の可視化や、輸送効率の把握も簡単に行えます。
最近では、船員の乗船履歴、資格、健康診断情報などの基本情報を管理する機能もリリースし、これまで属人化していた情報を会社全体で共有できる体制づくりを支援しています。
ーー高齢化が進む現場に新しいサービスを導入する上で、どのような工夫をしていますか。
戸高克也:
最もこだわっているのはUI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)です。70代の船長でも導入初日から直感的に使えるよう、シンプルで分かりやすいデザインを目指しています。実際にサービス導入の際は、ほとんどの場合、私たちが直接船を訪問します。そして、船員さんと対話を重ねながら丁寧に進めることを心がけています。
最初は「ITなんて使えるか」と言われることもありますが、30分から1時間ほどお話しすると、「これならできそうだ」と感じていただける場合がほとんどです。現場の声を丁寧に拾い上げ、それをサービス改善に活かす。この繰り返しが、高い支持に繋がっているのだと思います。
ーー貴社のサービスの強みは何でしょうか。
戸高克也:
私たちの最大の強みは、徹底した現場主義にあります。そこから生まれるサービスの使いやすさと、手厚い導入支援が、高い顧客満足度につながっているのです。その結果として、継続率は99%を維持しています。
船の上ではインターネット環境が常に安定しているわけではありません。そのため、オフラインでも使える機能を開発しています。このように、実際の運用環境に即したサービスを提供できる点も大きな特徴です。機能ごとに見れば競合するサービスも存在します。しかし、包括的な使いやすさとサポート体制では負けない自信があります。
船員の半数がシニア層!日本の物流を揺るがす海事産業の人材危機
ーー海事産業は日本の経済や生活に不可欠ですが、その重要性は十分に認識されていると感じますか。
戸高克也:
日本の国内貨物輸送の約4割は、船が担っています。石油や食料品など、輸出入貨物に至っては99%以上が船舶輸送です。皆さんが毎日使う電気の燃料も、スーパーに並ぶ食品もその多くが船によって届けられています。もし船の動きが止まれば、私たちの生活は文字通り成り立たなくなるでしょう。
しかし、この事実は残念ながら一般の方々にはほとんど伝わっていません。この「見えないインフラ」であることの課題は非常に大きいと感じています。
ーー海事産業における人材不足は、どの程度深刻なのでしょうか。
戸高克也:
他の業界とは比較にならないほど深刻です。特に船員さんの高齢化は著しく、今や50%以上がシニア層といわれています。若い世代のなり手が極端に少なく、そもそも海事産業が就職先の選択肢として認識されていないのが実情です。このままでは、日本の物流を支える現場が維持できなくなるという強い危機感を持っています。
この人材不足の最大の理由は、業界自体が一般に知られていないことだと考えています。「船員になるには専門の学校を出る必要がある」といったイメージも強いですが、必ずしもそうではありません。そうした実情も十分に伝わっていないのです。
例えば、就職フェアに参加しても、多くの学生は初めから「海運」や「船員」というキーワードが頭の中に入っていません。そのため、私たちのブースで話を聞いてもらうことすら難しいのです。「船員とは、どんな仕事なのか」。そういった本当に基本的なところから、認知を広げていく必要があると感じています。
島国日本の海事産業を「想起させる」採用戦略とは?
ーー海事産業全体が人材を確保するために、何が必要だとお考えですか?
戸高克也:
業界の魅力や重要性を、もっと積極的に社会に向けて発信していくことが不可欠だと考えています。まずは学生や求職者の方々に「海事産業」という選択肢を思い浮かべてもらう、想起してもらうことがスタートラインです。
そして、若い世代が魅力を感じられるような働きがいのある環境やキャリアパスの提示も重要になります。私たちの世代が、先人たちが築いてきたこの産業を、次の世代にしっかりとつないでいく責任があると感じています。
ーー貴社では、海事産業の人材不足に対してどのような取り組みを行っていますか?
戸高克也:
海事産業には、海上と陸上の両方に人材不足の課題があります。まず、海上では船員の人手不足が深刻です。そこで私たちは2024年より、船員に特化した求人サイト「FUNAGUNI(フナグニ)」を運営しています。業界内での人材マッチングを通じて、少しでも貢献できればと考えています。
一方、陸上の船舶運航管理者の人材不足という課題もあります。これに対しては、「MARITIME 7」で業務効率を大幅に改善し、少ない人員でも安全運航を維持できる体制の構築を目指しています。
加えて、業界の魅力を伝える活動として、イベント登壇や講演、SNSでの情報発信などにも積極的に取り組んでいます。DXの力で、若い世代が魅力を感じられる業界へと変えていきたいと考えています。
ザブーンが求める人物像とは?
ーーこのミッションをともに成し遂げるために、どのような人材を求めていますか?
戸高克也:
海運業界の経験は問いません。むしろ、SaaSやIT業界での法人営業経験など、異業種の視点を持った方に新しい波を起こしていただきたいと考えています。
ITのバックグラウンドがあればスムーズに業務に入っていただけると思いますし、船に乗って営業したり、地方の経営者と直接対話するなど、これまでにない経験を楽しめる方には非常に向いている仕事です。年齢で言えば、社内の平均年齢が30代後半なので、30代前後の方がなじみやすいかもしれません。
何よりも、日本の重要なインフラを支えるという仕事にやりがいを感じ、「業界を変えたい」という情熱を持った方と一緒に働きたいと思っています。
多角化とグローバル展開、次のステージへ
ーー今後の事業展開やビジョンについてお聞かせください。
戸高克也:
まずは、船舶管理業務をすべて支えられるような機能拡充を進めていきます。まだまだ足りていない機能が多くありますが、これまでと同様に現場のお客様と一緒に作り上げていく姿勢で、満足度の高いサービスを目指します。
また、船舶管理業界は世界単一市場です。そのため、今年からは海外展開にも注力しています。まずはアジア市場からスタートし、将来的には世界中に展開していく計画です。
将来的には造船や舶用工業、港湾荷役といった海事産業全体のDXに貢献できる企業へと成長していきたいと考えています。
その先に、1日の始まりを「MARITIME 7」でスタートする世界をつくり、「船舶管理のスタンダードをつくる」というビジョンを実現します。
ーー最後に、海事産業の未来を担う若い世代や求職者へメッセージをお願いします。
戸高克也:
日本は島国であり、その経済と生活は海運なくして成り立ちません。海事産業は、まさにその根幹を支える非常に重要な仕事です。今、この業界は大きな変革期を迎えており、デジタル化の進展とともに新しいことにも挑戦しやすい環境が生まれています。
決して楽な仕事ばかりではありませんが、社会への貢献を実感できる大きなやりがいがあります。もし少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ一度、この業界の門を叩いてみてください。私たちと一緒に、日本の未来を支える仕事をしましょう!
編集後記
「日本の物流の99%を担う」と聞いても、多くの人はその実態を具体的にイメージできないのではないだろうか。私たちと海事産業との深い関わり、深刻な人材不足に直面していることを改めて認識させてくれた。しかし、戸高社長の目には、その困難な状況の先にある、業界再生の確かな光を見据えている。株式会社ザブーンの今後の挑戦と、海事産業の新たな可能性に期待したい。

戸高克也/2009年に大学卒業後、IT系人材サービスのBtoB営業を経て起業を経験。その後10年間、家業の船舶管理会社で外航船の管理に従事。実務を経験する中で、業界が抱える課題解決へ取り組みたいと考え、2018年に株式会社ザブーンを設立。「船舶管理のスタンダードをつくる」をビジョンに、DXによる船舶運航の業務効率化を目指す。














