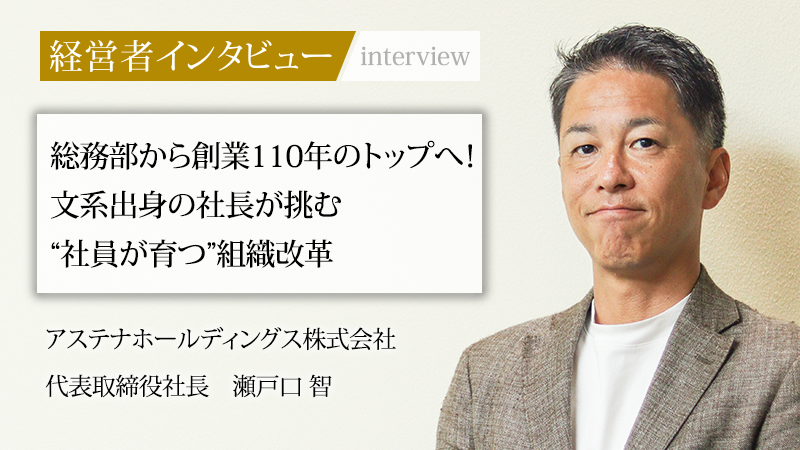
医薬品原料調達・開発・製造の幅広いサービスを提供するファインケミカル事業を主軸に、5つの事業領域で人々のヘルスケアに貢献するアステナホールディングス株式会社。同社は昨年、創業以来110年の歴史の中で、初めて創業家以外の人物を代表取締役社長に迎えた。
その大役を担うのが瀬戸口智氏である。文系出身で総務部からキャリアを始め、新規事業の立ち上げで手腕を発揮。社長就任の決断の裏にある思い、そして社員と共に「明日のあたりまえを創り続ける」未来をどう描くのか。瀬戸口氏の情熱と哲学に迫る。
就職氷河期の選択、父の勧めで歩み始めた「イワキ」への道
ーーまずは、アステナホールディングス(旧:イワキ株式会社)に入社された経緯からお聞かせください。
瀬戸口智:
私が大学を卒業したのは1995年で、まさに就職氷河期の真っ只中でした。大学は東京でしたが、卒業後は札幌の実家に帰るつもりで父に電話したところ、「札幌に就職先はないぞ」と言われてしまい、そこで初めて、東京で腰を据えて就職活動を始めることにしたのです。
私の祖父が動物用医薬品の製造会社を創業・経営しており、父もそこで働いていたため、自然と医薬・メディカル系の業界を志望していました。
弊社に縁があったのは、父の勧めがきっかけです。祖父の会社は、弊社から原料を仕入れ、製造した製品を弊社の系列会社(のちにM&Aで売却)に販売するという、売り買い双方の関係があったのです。私が医薬系を回っていることを知った父から「イワキに行ってみたらどうだ」と勧められ、面接を受けたことが始まりでした。
ーー当時は、文系から医薬品関連の業界に進む方は少なかったのではないでしょうか。
瀬戸口智:
私の大学の同級生も少なかったですね。最終的に6社か7社から内定をいただきましたが、大半がメディカル系の企業で、外資系含む製薬会社2社からも内定をいただいたものの、当時は不況ということもあり、教育コストのかからない化学式が分かる学生を優先する風潮が強く、文系だった私は製薬会社の道を諦めました。
その点、弊社は商社ということもあり、入社の段階でそこまで専門的な化学の知識は求められませんでした。もちろん、今入社してくる社員は皆優秀で、化学式も理解している者も多くいますが、当時は私のような文系でも活躍できる土壌があったのです。商社なら何でもできるだろうという期待もあり、最終的に弊社への入社を決めました。
総務から新規事業へ。30歳で飛び込んだ「人の命を救う」仕事
ーー入社後はどのような業務から始めたのでしょうか。
瀬戸口智:
最初に配属されたのは総務部庶務課で、車両や備品の管理、購買の窓口業務といった、まさに「庶務」が主な仕事で、5年ほど担当しました。
ちょうどその頃、Windows95が登場し、パソコンが個人でも手軽に買える時代になり、当時の社長から指示を受け、ノートパソコンを購入したのです。まだインターネットもない時代でしたが、車両管理や支払い関連の書類をExcelで作成して業務の効率化を図りました。自分なりに工夫して仕事が一段落し、もう一つの部署を経験していた頃、新しい部署の立ち上げに携わることになりました。
ーーその新しい部署についてお聞かせください。
瀬戸口智:
その新規事業は、新生児用の人工呼吸器を扱うものでした。ある時、社長から「医療機器の新規事業を立ち上げるから準備を手伝って欲しい」と言われ、総務の経験があったので、予算・設備面などの段取りなどを任されたのです。
徐々に、この事業は命を預かるがゆえ、トラブル対応などで昼夜を問わず呼び出されるような大変な仕事だということが分かりました。「これをやる人は大変だな」と思いながら立ち上げ準備を進め、すべての段取りを終えて社長に「これで万事整いました」と報告に行きました。
すると、社長から返ってきたのは「お前が一番この事業に詳しいのだから、お前がやりなさい」という言葉でした。そうして30歳のとき、自ら立ち上げた医療機器部門で初めて営業に出ることになり、最後は責任者を務めるまでになったのです。
ーー新規事業に対して、どのような楽しさややりがいを感じていましたか。
瀬戸口智:
私が扱っていたのは、人工呼吸器の歴史に関する本があれば必ず載るような、世界的に見ても非常に優れた人工呼吸器でした。海外ではつくれない特殊な換気法で動く機械で、日本でのシェアは4割ほどに達していたと思います。
製品を買う人(医師や事務方)、使う人(医師や看護師)、そして使われる人=患者(新生児)がすべて違う。私たちが扱っていたのは、時にニュースになるような、出生児体重が300グラムという非常に小さく生まれるケースもある赤ちゃんの命を救うための機械です。保育器の中で、動いているかも分からないような小さな命が、私たちの機械によって肺の機能を支えられ、体を大きくして卒業していくお手伝いができることに、大きな使命感を感じていましたね。
「この子を助けるんだ」「この子を助けるために働く人々を支えるんだ」という思いが、日々の原動力でした。現場で「あの子が元気になった」と聞くと心から嬉しかったですし、人の命を助けるという素晴らしい仕事に誇りを持っていました。13年間この仕事に携わりましたが、ずっと続けてもいいと思えるほど、充実した時間だったと言えます。
「番頭役」から経営の中枢へ!グループ全体を率いる立場に

ーーその後、異動した経営企画部ではどのような役割を担っていたのでしょうか。
瀬戸口智:
43歳の時に本社に戻り、経営企画部に配属されました。もともと総務にいた経験から、会社全体を俯瞰して見る習慣が身についていたので、セクショナリズムに陥ることなく仕事に取り組めました。
とはいっても、経営企画に関わる知識・経験はありませんでした。私の役割は、いわば「番頭」で、当時の社長であった岩城慶太郎が打ち出す方針やアイデアを社員に分かりやすく伝えて、具体的な形に落とし込んでいくことだと理解することにしました。社長が時に皆を惑わせるようなことを言った際には、その意図を汲み取って「翻訳」をすることも重要な仕事でした。
実務は優秀なスタッフに任せつつ、経営トップの思いと現場をつなぐ役割を担う中で、自分はこの番頭役が向いているのではないか、と感じ始めたのもこの頃です。
ーーその後、ホールディングスの副社長、そして社長へと就任したのは、どのような経緯があったのでしょうか。
瀬戸口智:
経営管理部長を務めた後、私は赤字に陥っていたHBC・食品事業部(現:イワキ株式会社)の立て直しを任されました。コロナ禍という厳しい逆風のなか、祖業であった事業の撤退という大きな決断も下し、なんとか黒字化を達成しました。
そして「さあ、これからだ」と意気込んでいた矢先、今度は「ホールディングスに戻ってほしい」と声がかかり、副社長に就任することになったのです。
ただ、そのわずか1年後に自分が社長になるとは夢にも思っていませんでしたね。きっかけは、社外取締役から「経営と執行は分離すべきだ」という意見が強まったことでした。
当時は、岩城と私が関連会社の代表を複数兼務する状況であったためです。前社長が「ホールディングスの社長を続けるか、事業会社の経営に専念するか」という選択を迫られ、立て直しが急務であった事業会社の経営を選びました。「では次の社長は誰だ」という話になり、思いがけず私に白羽の矢が立ったのです。
ーー社長就任の打診を何度も断られたそうですが、最終的に大役を引き受けた決め手は何だったのでしょうか。
瀬戸口智:
はい、お断りしました。しかし、最終的に引き受けたのには2つの理由があります。1つは、創業110年にして、創業家ではない人間が社長になる姿を社員に見せることは、「君たちも社長になれるよ」というポジティブなメッセージになると考えたからです。
どんなオーナー企業も、いずれはそういう時が来ます。私の能力というより、社員に新しい可能性を示すことに意義があると思いました。社員に新しい姿を見せることで「私も頑張ってみよう」と思ってくれる人が一人でも出てくれば嬉しいと思ったのです。
もう1つは、私がもし失敗したとしても、まだ若い岩城が戻ってこられるという安心感があったことです。この2つの理由から、大役を引き受けました。
5つの事業と三つの社訓 アステナグループの根幹
ーー貴グループの事業内容と、その強みについて教えてください。
瀬戸口智:
私たちのグループは、大きく5つの事業で構成されています。ファインケミカル、HBC・食品、医薬、化学品、そしてソーシャルインパクトです。社名であるアステナは「明日(未来)」と「サステナブル(持続可能)」の造語であり、それぞれの事業分野において、「サステナブル」に基づく3つの戦略で、特徴的な強みを発揮しています。
主軸であるファインケミカル事業では、研究受託から商用製造までを一貫してサポートできるバリューチェーンが整っていることが大きな強みです。また、HBC・食品事業は原料を含めて機能性食品や化粧品などを扱う「プラットフォーマー」機能の拡充を進めています。
また、医薬事業はジェネリック医薬品を中心に皮膚科領域での高いプレゼンスを発揮、化学品事業においては、世界的シェアを持つニッチな製品を販売しているほか、その開発力を武器に半導体分野への投資を進めています。ソーシャルインパクト事業においては、我々のこれまでの知見と本社機能の一部がある能登地域の素材を活用したヘルスケア商品の開発及び販売を行っているほか、農業にもチャレンジして、地域のみなさんと「共に儲ける」ことを目指しています。
ーー事業運営において、特に大切にしている考え方やカルチャーはありますか。
瀬戸口智:
弊社の基本的理念として古くから伝わるのは「誠実」「信用」「貢献」という3つの言葉です。これは私個人としても非常に大切にしており、何か判断に迷ったときに立ち返る原点になっています。私たちの仕事はお客様に貢献できているか、会社の信用を高めるものか、そして真面目に、嘘なく取り組んでいるか。この3つを常に自問自答すれば、進むべき道は自ずと見えてくると考えています。
SDGsやダイバーシティといった現代的な言葉も、突き詰めればこの3つの精神につながっていくのだと思います。これらの言葉が生まれる前から、111年の歴史の中で先人たちが紡いできたこのカルチャーこそが私たちの基盤です。だからこそ、新しいことにも安心してチャレンジできるのです。全世界の社員と対話する「オープントークキャラバン」でも、必ずこの話をしています。
社員と共に描く未来。対話と人的資本で新たな挑戦へ

ーーこれからどのような会社をつくっていきたいとお考えですか。
瀬戸口智:
社員一人ひとりが主体性を持って自ら物事を考え、課題を発見し、チームで解決に向かうような組織をつくっていきたいです。これまでは、ともするとオーナーのリーダーシップに甘え、「社長が答えを出してくれるだろう」という雰囲気がなかったわけではありません。
これからは、社員みんなで会社を動かしていくのだという当事者意識を根づかせたいです。そのためにも、教育や処遇改善を含め、人的資本、つまり「人」に関わることには手厚く投資していきたいと考えています。
ーーその組織風土を醸成するために、具体的にどのような取り組みを行っていますか。
瀬戸口智:
先ほども申し上げました、少人数の社員と直接対話する「オープントークキャラバン」を全世界の拠点で実施しています。また、匿名で何でも意見を言える「デジタル目安箱」という仕組みも導入しました。これは毎月の朝礼で、私から全社員へ回答することをルールにしています。
始めて1年ほどで200件以上の意見が寄せられ、当初は厳しい意見に心がえぐられることもありました。しかし最近では「どうすれば人を育てられる人材になれますか」といった建設的な質問が来るようになり、先日、そうしたテーマに関心のある社員を集めてセッションも開きました。地道な対話の積み重ねが、組織を変える力になると信じています。いつかこの目安箱への投稿がゼロになる日が来たら、私の役割は終わりでしょうし、それが理想の会社の姿だと思っています。
ーー最後に、今後の事業の展望と、会社の未来像についてお聞かせください。
瀬戸口智:
事業面では、各事業の強みをさらに伸ばしていきます。例えば、ファインケミカル事業では研究から商用生産までのバリューチェーンを拡充、また長い歴史で培った卸売事業を「プラットフォーム事業」と称し、M&Aなどを通じ、強化を継続しています。また、半導体関連ビジネスも大きく期待しているところです。それと並行して、ソーシャルインパクト事業のような社会性のある取り組みもまさに「サステナブル」に展開していきたいと思います。
そして、私たちが目指すのは、何十年先も人々の当たり前の生活に寄り添い、それを支え続けられる会社であることです。朝起きてから夜寝るまで、皆さんの日常に私たちの製品やサービスが当たり前のように溶け込んでいる。そんな一日を50年後も私たちが支えていく。そのために、弊社の強みを最大限に活かし、社員という最も大切な資本と共に、これからも変革・成長し続けることをお約束します。
編集後記
総務部からキャリアをスタートし、新規事業の立ち上げ、事業部長を経て、創業110年の歴史で初となる“創業家以外”の社長となった瀬戸口社長。現在、瀬戸口社長が注力しているのが「対話」による組織変革だ。「デジタル目安箱」などを通じ、社員の声に耳を傾け続ける姿勢には覚悟がにじむ。「明日のあたりまえを創り続ける」というパーパスを掲げる、アステナホールディングスの挑戦から目が離せない。

瀬戸口智/1972年、北海道出身。大学卒業後、アステナホールディングス株式会社(旧イワキ株式会社)に入社。取締役経営管理部長、イワキ株式会社代表取締役会長などを経て、2024年2月アステナホールディングス株式会社代表取締役社長に就任。














