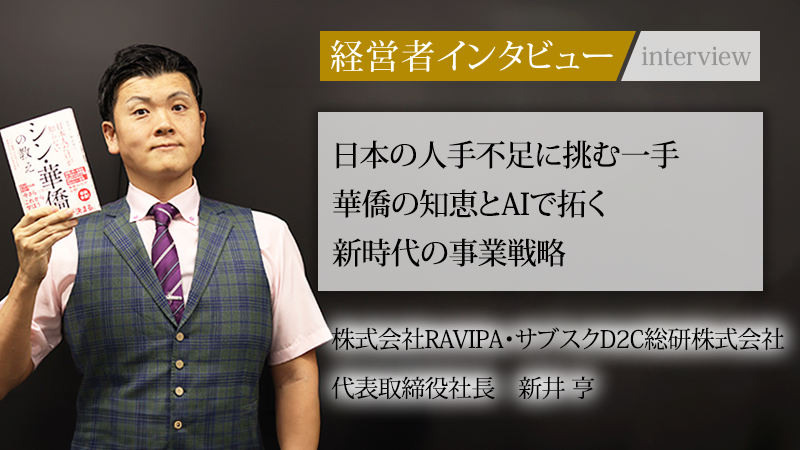
「私には特定の得意分野がない、全てが得意分野だ」。そう語るのは、少数精鋭で高利益率のストック型ビジネスを複数展開する株式会社RAPIVAの社長、新井亨氏だ。あらゆる業界で応用可能という経営手法の根幹には、学生時代に中国で体得した「華僑のビジネス哲学」がある。
社会人経験ゼロからの起業、社長不在でも自走して利益を生むという組織の仕組み、そして日本が抱える人手不足という課題にAIロボットで挑む現在地。その全ての原点はこの華僑の教えにあるという。再現性のあるビジネスモデルで絶え間なく成長を続ける同社の経営の核心に迫る。
偶然の出会いから起業へ 中国で学んだ「稼ぐ」ための視点
ーー社長が起業に至るまでの歩みについてお聞かせください。
新井亨:
私を起業に導いたのは、SARS流行中の中国(北京)での留学体験でした。もともと海外(中国)に特別な興味があったわけではありませんが、これから成長する国に行こうというシンプルな動機から、2003年頃に中国へ渡りました。ところが、到着してすぐにSARSが流行して学校が閉鎖(休校)になるという不運に見舞われます。しかし、その期間を利用して語学を独学しつつ、現地の経営ノウハウを学ぶ中で、私の価値観は一変しました。
最も衝撃的だったのは、現地で出会った人々の「熱量」です。特に、大学進学率がわずか1%の中で狭き門を突破してきた学生たちのハングリー精神は、想像を絶するものでした。彼らのようなやる気がみなぎる若者がひしめく中国と比べ、日本は起業する人も少なく、競争相手もずっと少ないことに気づきました。このように、日本では起業に関する正しい考え方があれば、圧倒的に有利な状況でビジネスを始められると感じ、北京から帰国後、インターネットを使って学生起業しました。
ーー学生時代はどのようなビジネスから始め、どのように拡大されたのですか。
新井亨:
最初の事業は、自分が習得した中国語をオンラインで教えるサービスでした。月額2000円ほどのシンプルなサブスクサービスでしたが、「中国語を学びたいが学ぶ場所がない」という潜在的な需要を捉え、3000人以上ものお客様に利用していただけるサービスとなりました。この経験から、考え方一つで大きく稼げるのだと実感しました。
その後、ウェブ制作、貿易仲介、さらには中国で美容室やホテルの開発まで、全く異なる分野の事業に次々と携わりました。私自身に得意分野はありませんが、あらゆる事業で間に入る経験を積むことで、現地の富裕層、つまり華僑のビジネスのやり方を間近で学ぶことができたのです。
再現性を生む経営の神髄 あらゆる業界に通じる華僑のビジネス哲学は強い
ーーあらゆる事業に通じるという「華僑のやり方」の基本について、詳しくお聞かせください。
新井亨:
華僑のビジネスには、いくつかのルールがあります。まず、お客様の「最大公約数」を狙うことです。ニッチな層には手を出さず、最も需要があり誰もが必要とするものだけを扱うことが「鉄則」です。商品は、人気商品だけに絞り、価格はお客様がイメージしている金額より少し安く設定します。メニューや商品を絞るからこそ価格を抑えることができ、結果としてより多くのお客様を呼び込めます。
ビジネスモデルという点で特に重要視しているのは、購入回数(リピート購入者)を増やす仕組み、つまりストック型のビジネスを構築することです。たとえば美容室なら、高品質なサービスを低価格で提供し、「2~3ヶ月に1回ではなく毎月来た方がおしゃれですよ」と提案する。するとお客様は会計時に次の予約を入れてくださいます。常に新規顧客を追うフロー型ビジネスでは広告費がかさみますが、リピート顧客を増やすことを狙うストック型ビジネスでは、売上は安定して右肩上がりに伸ばすことができます。
ーー社員が自発的に動く組織は、どのようにつくるのでしょうか。
新井亨:
各社員が生み出した利益額に応じて、還元率が階段式に上がるインセンティブ制度を設けています。利益が100万円なら10%、200万円なら20%と、成果が上がるほど社員への還元も大きくする。すると社員は自ら利益を意識して動き、成果を出す人のやり方を自発的に学ぶため、社長がいなくても自走する組織が出来上がるのです。
社長よりお客様 社員が自走する組織のつくり方
ーー経営者として、人を大切にする上で譲れないことは何でしょうか。
新井亨:
社員のベクトルが、社長の方を向いている会社は社長がいなくなった時に自走することが難しいと考えています。また、社長の顔色をうかがうような組織では内向きになってしまい、成長できません。社員は、お客様の方を向き、お客様を喜ばせることに集中する。そして社長の役割は、社員が集中してお客様のために働きやすい環境をつくること。このサイクルを正しく保つことが、最も大切です。また、もし独立したい社員がいれば応援します。さらに、社員は社長のものではありませんから、社長の給与が社員の取り分を圧迫するようなことがあってはならないと考えています。
ーー経営における「お金」については、どのようにお考えですか。
新井亨:
お客様から何かをいただくとき、それは「感謝」をいただくことだと考えています。「感謝の対価がお金」なのです。しかし、今の日本ではお金にネガティブなイメージを持つ人が多い。「お金持ちは悪いことをしている」という思い込みのせいかもしれません。そのような考え方こそが、「感謝」の正当な対価であるはずのお金を敬遠する態度を生み出し、日本全体の成長を押し留めるブレーキになっているのではないでしょうか。
日本の未来を切り拓く AIロボットとサブスクリプション事業への挑戦

ーーそのような問題意識から、現在最も注力されている事業は何でしょうか。
新井亨:
私は日本の抱える問題が「物理的な人手不足」と「企業自体の構造」にあると考え、それぞれに対処するための事業を行っています。まず、AIロボット事業では、人手不足の問題に対処するため、農業、医療、介護、物流といった、需要があるにもかかわらず働き手が見つからない業界に注力しています。後継者不足などの課題も、AIロボットが解決できる可能性があります。
また、私が学んだ華僑ビジネスの仕組みを日本の経営者に伝えるサブスク事業(ストック型ビジネス)を通して、日本の起業の構造自体を変革することを目指しています。そのためのオンライン講座などをつくりました。ビジネスにおけるリスクの9割は「知らないこと」からおきるのです。正しい知識を持つことが、何よりの防御になるのです
編集後記
「私には得意分野がない」と、新井氏はインタビュー中に何度も口にした。しかし、その言葉とは裏腹に、彼の語る経営哲学は、あらゆる事業の成功法則を貫く、鋭い本質に満ちていた。その源泉は、学生時代に体得したという華僑の教えにある。売上と利益の構造を徹底的に理解し、再現性のある仕組みに落とし込む合理性。その一方で、社員や顧客、ひいては社会全体にベクトルを向けるべきだという温かい人間観。日本の未来を憂い、AIという新たな武器を手に構造変革に挑むその姿に、次代の経営者のあるべき姿を見た。

新井亨/1981年生まれ。Unuversity of Wales MBA卒業、北京に留学後に起業し不動産、美容、貿易など複数ビジネスを立ち上げ成功へ導く。上場企業の相談役など、複数会社の経営に携わる。サブスクの第一人者として、サブスク事業やSaas事業などのマネタイズ実績は累計1000億円以上。2024年1月、東京証券取引所へ新規上場を果たす。海外経営実績が豊富で、財閥企業や華僑系企業とのネットワークを豊富に持っている。














