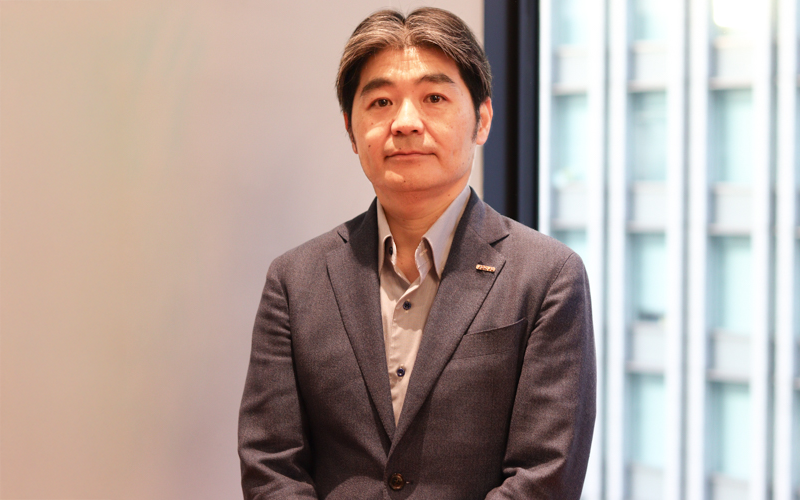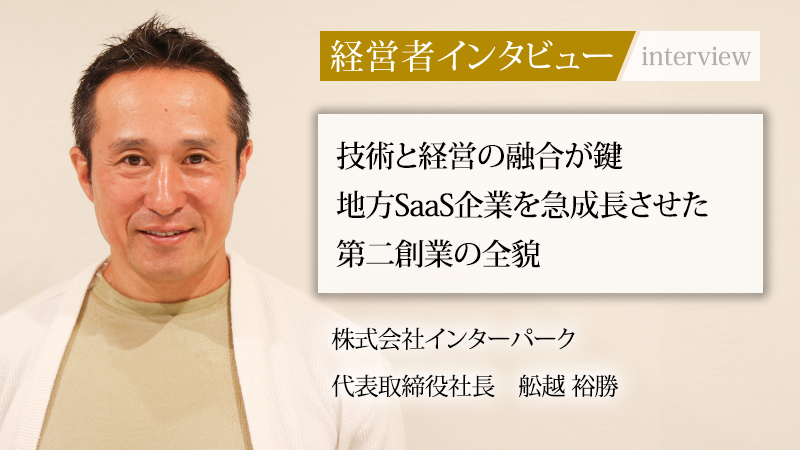
札幌を拠点に、中小企業の業務効率化を支援するSaaS企業、株式会社インターパーク。顧客管理システム「サスケ」や電話アプリ「サブライン」など、ゼロからイチを生み出す高い開発力を武器に、数々の自社サービスを展開している。同社を率いる代表取締役社長、舩越裕勝氏は、「世の中の役に立ちたい」という一心で安定した道を離れ、起業した。常に“中小企業のインフラになる”という熱い信念を胸に、挑戦を続けてきた同氏に、起業の原点や、第二創業期を生んだ転機、そして未来への展望を聞いた。
安定した未来より「世の中の役に立つ」道へ 起業家精神の原点
ーー起業に至った経緯や、当時抱いていた思いについてお聞かせください。
舩越裕勝:
以前は半官半民の財団法人に勤めていました。いわばレールが敷かれたような将来に疑問を感じ、一度きりの人生だからこそ、自分の可能性に挑戦し、もっと世の中の役に立つ仕事をしたいという思いが強くなったのです。また、事業を営む祖父の姿を幼い頃から見ていたため、商売への憧れがずっと心の中にありました。父は公務員でしたが、私は祖父のような生き方を選びたいと考えたのです。
ーー最初の事業を長野県で始められたのは、どういった理由からでしょうか。
舩越裕勝:
私が起業を考えた2000年頃は、インターネットが世に出始めた時代でした。この技術は間違いなく世の中を大きく変えると感じ、インターネットを活用したビジネス支援に挑戦しました。
最初に事業を立ち上げたのは、大学時代の友人と共に、長野県の諏訪地域で挑戦しました。この地域は、ケーブルテレビ網の発達で東京より早くインターネットの使い放題が実現しており、地方における将来のモデルケースになると考えたからです。しかし、実際に事業を始めると、インフラが整っていても、そこに住む人々の意識がなければ物事は動かないという現実に直面しました。この経験から、事業の根幹に関わる大きな教訓を得ました。いくら優れた技術や環境があっても、受け入れる側の意識が伴わなければ価値は生まれないということです。
本田宗一郎と藤沢武夫のように 第二創業を生んだ運命の出会い
ーーこれまでのご経歴で、最大のターニングポイントは何でしたか。
舩越裕勝:
間違いなく、今の副社長と共に仕事をすると決め、2つの会社を1つにしたタイミングです。2015年か2016年頃のことです。もちろん、悪い意味での転機は他にもありました。しかし、インターパークという会社が良い方向に生まれ変わった“第二創業”と呼べる出来事は、この会社統合に尽きます。
ーー会社を一つにする際、どのような理想の関係性を描かれていたのでしょうか。
舩越裕勝:
当時、副社長とは本田技研工業の創業者である本田宗一郎と、その経営を支えた藤沢武夫の話をよくしていました。技術者の本田宗一郎と、経営の舵取りを担った藤沢武夫。この2人のような関係性を築き、技術と経営の両輪で会社を成長させたいと、互いの理想を語り合いました。
ーー2社が統合したことで、会社にはどのような変化がありましたか。
舩越裕勝:
会社を一つにする直接のきっかけは、大手電機メーカーとの取引でした。当時、私たちは2社体制で事業を行っており、決算書を2社分提出したところ、その点を問われたのです。そのとき、営業担当の役員から「トップが腹をくくらないと契約が決まらないのはおかしい」と強く進言され、統合を決意しました。そこからの会社の伸びは、目を見張るものがありました。
価値の本質は数歩先ではなく、「一歩先」となる 中小企業のインフラを目指す開発哲学

ーー経営者として、またサービス開発において最も大切にされている価値観を教えてください。
舩越裕勝:
“多くの人に使っていただき、価値を感じてもらうことが正義である”という考え方です。私たちは、自社のサービスが中小企業にとっての“インフラ”になることを目指しています。そのためには、ただ良いものをつくり続けるだけでは不十分です。つくったものをお客様のもとへ届けるだけでなく、使って価値を感じていただける体験を提供できて、はじめて意味があると考えています。
ーーサービスを普及させる上で、どのような点に難しさを感じますか。
舩越裕勝:
サービスを普及させる上で、世の中は常に“一歩先”のものしか価値を認めてくれないという点に、難しさを感じています。二歩先、三歩先を行き過ぎたサービスは、新し過ぎて誰にも理解されません。これは、創業当初の長野での失敗から学んだ、私の事業における哲学の根幹です。人々が理解できる範囲にまでサービスを近づけ、まずはそれが当たり前になる状況をつくり出すこと。そこにこそ、事業として価値を生むヒントがあるのだと思います。
ゼロからイチを生む開発力と、若手が育つ組織文化が強み
ーーご自身が考える、株式会社インターパークの最大の強みとは何でしょうか。
舩越裕勝:
事業面でいえば、サービスをゼロからイチで生み出すのが得意な点に尽きます。また、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)やプライバシーマークを取得し、お客様に安心してサービスを使い続けていただくための信頼を積み重ねてきた自負もあります。“インフラ”になるためには、信頼と安定性が何よりも重要ですから。
ーー組織的な強みについてはいかがですか。
舩越裕勝:
若い人材が中心となって活躍していることです。社員の平均年齢は34歳(2025年8月現在)で、10年以上にわたり新卒採用を継続しています。会社の基盤となっているのは、新卒で入社し、会社の文化と共に成長してきた社員たちです。彼らの可能性を最大限に引き出し、伸ばしていける環境があることは、私たちの大きな強みだと感じています。
「サブライン」を軸に仕組み化を推進 1を100にする未来戦略
ーー今後、会社として社会にどのような価値を提供していきたいですか。
舩越裕勝:
現在、特に成長しているのが「サブライン」です。月々500円で、スマホにもう一つ電話番号が持てるアプリサービスで、これを活用すれば会社の電話番がいなくても代表電話の対応が可能になります。今後はこのサービスを通じ、ビジネスの世界だけでなく教育現場や自治体など、さまざまな場所で業務効率化や仕組み化を実現するお手伝いをしていきたいと考えています。“私たちのツールを使うことで、誰もが簡単に新しい価値を生み出し、体験できる”。そんな存在になるのが目標です。
ーービジョン実現に向けた具体的な戦略を教えてください。
舩越裕勝:
ビジョンの実現に向けて、具体的には3つの戦略を考えています。
1つ目は「事例の強化」。成功事例を軸にターゲットを絞り込んだマーケティングです。2つ目は「代理店戦略」。私たちのサービスを共に広めてくださるパートナーとの連携強化です。そして3つ目が「リファラル(紹介制度)」の構築。紹介者に直接感謝を還元できる仕組みを整えます。この3本柱で、私たちのサービスをより多くの方に届けていきたいと考えています。
編集後記
「世の中の一歩先のものしか価値を見出してもらえない」。舩越社長の言葉には、理想だけでは事業は成り立たないという、厳しい現実を知る経営者の実感がこもっていた。しかし、その上でなお「中小企業のインフラになる」という壮大な目標を掲げ、ゼロからイチを生み出すことにこだわり続けている。その姿からは、困難さえも楽しむかのような、真の起業家精神が感じられた。着実に、しかし大胆に次のステージへと向かう同社の未来から目が離せない。

舩越裕勝/「ビジネスや日常をシンプルに、効率的に、より価値のあるものにする」をミッションに掲げ、全国の自治体や中小企業の業務改革を支援する業務用ノーコードWebアプリ開発プラットフォーム「サスケWORKS」を展開する株式会社インターパークの代表取締役を務める。あわせて、一般社団法人ノーコーダーズジャパン協会、ノーコード推進協会、北海道IT推進協会の理事も務め、地方創生とDX推進、地域課題の解決を通じて、持続可能なデジタル社会の実現に取り組んでいる。