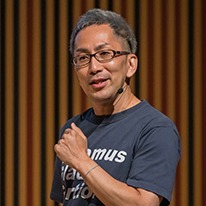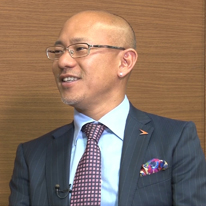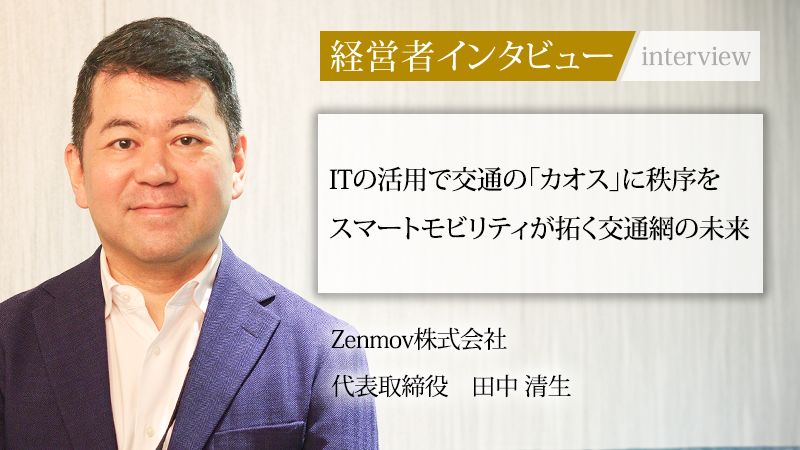
現代社会において、交通網をとりまく課題は多い。たとえば日本では、交通渋滞による経済損失が年間12兆円に相当するという。また、東南アジアの新興国では公共交通機関の無秩序な運行が原因で無駄が生まれ、環境負荷も大きい。こうしたモビリティに関連する課題をテクノロジーで解決しようとしているのが、Zenmov株式会社だ。大手通信企業でのノウハウを活かし起業した代表取締役の田中清生氏に、サービス提供の背景や今後の展望を聞いた。
フィリピンの交通渋滞から見出した使命
ーーこれまでのご経歴をお聞かせください。
田中清生:
1998年に日本ヒューレット・パッカード合同会社に入社し、サプライチェーンマネジメントのシステム構築と法人営業を担当しました。その後、国際的なマーケット開拓や商品開発にも挑戦したいと考え、MBA取得のためにオランダへ留学しました。
帰国後、ボーダフォン株式会社に転職した同僚から、当時立ち上げていたMVNO(仮想移動体通信事業)事業部へ来ないかと誘いを受けました。大企業で新規事業の立ち上げに携われるのは得難い機会だと考え、入社を決意しました。
会社がソフトバンクモバイル株式会社に買収された後は、複数の事業立ち上げを担当しました。一つは「ディズニーモバイル」で、オリジナルの端末デザインやコンテンツを用意し事業化しました。その後、トラックの運行管理を行うクラウドサービスを企画・運用しましたが、当時はスマートフォンの普及やクラウドに対する認識が追い付いておらず、拡販には至りませんでした。
そうした時、フィリピンで交通効率化事業を担当した同僚から相談を受けました。私が培ってきた車両管理のノウハウが役立つのでは、ということで私も参画しました。交通量が非常に多い環境でのプロジェクトに、IoT(※1)デバイスとして大きな可能性を感じました。
(※1)IoT (Internet of Things):家電、自動車、センサーなど、これまでインターネットに接続されていなかったさまざまなモノがインターネットを通じて相互に通信する仕組み
ーー貴社を設立された経緯を教えてください。
田中清生:
きっかけはフィリピンでの実証実験です。現地の交通量は供給過剰な状態で、統制がとれていませんでした。そこで小型のバスを用意してドライバーの稼働状況をモニタリングし、乗車人数に合わせた配車計画で運用しました。すると、交通に信頼が生まれて生産性も2倍以上に向上したのです。この経験から「ITを使った交通の効率化は社会貢献性が高い」と実感。そして、誰もが移動しやすい社会をつくるため、2019年に弊社を設立するに至りました。
参入障壁の高い領域で発揮される独自の強み

ーー貴社の事業内容や強みを教えてください。
田中清生:
移動サービスをより便利に効率的にする「スマートモビリティ」を支援するためのIoTプラットフォームを開発しています。現在は日本、東南アジア、中東、アフリカ、北米でサービスを展開中です。
国内では、固定路線のバス事業に対するシステム開発に特化しています。バスの運行管理は複雑です。さらに、すでに10社以上がオンデマンドバス(※2)を提供しています。そのため、スマートモビリティの運営に必要な機能を網羅したソフトウェアを開発・提供しています。具体例として、ウェアラブル端末でドライバーの健康状態を確認する仕組みが挙げられます。その他にも、カーシェアやレンタカーの予約システムなどを開発しています。物流倉庫で個別の積み込みを行った後の、配送を効率化するシステムの開発も行っています。
海外では、幹線道路から街に接続する物流業界が主な対象です。幹線道路には既得権を持つ方が多くいらっしゃるためです。最終拠点からエンドユーザー(消費者)に商品が届くまでの「ラストワンマイル」に対して、サービスを提供しています。
(※2)オンデマンドバス:利用者の予約に応じて運行する、従来の路線バスとは異なる公共交通サービス
ーー貴社サービスの強みについて、どうお考えですか。
田中清生:
公共交通に関わる事業は、政府や自治体、運行事業者、住民、乗客など利害関係者が多く、参入障壁が高いといえます。そのため、GPSやキャッシュレスなど機能単位で導入されることは多いです。しかし、弊社のように運行に直接関わり、効率を管理する仕組みを提供している企業は多くありません。この点が弊社の強みです。
また、ソフトバンク株式会社での実証実験では、NEDO(※3)の支援を受けていました。加えて弊社の事業も、経済産業省や国土交通省などを巻き込んだ国のプロジェクトとして立ち上げています。この背景から、企業様にも導入をご検討いただきやすいと考えています。海外においても「日本の支援を受けている」という文脈で説明できるため、展開しやすいのだと思います。
(※3)NEDO:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
国籍や場所を問わない自由で主体的な挑戦環境
ーー今後の展望をお聞かせください。
田中清生:
移動に関する課題は、新興国でも先進国でも数多く存在します。収益性とビジョンのバランスを取りながら、それらの課題に対するソリューションを提供し続けたいと考えています。
弊社が開発したクラウド型の交通管制システムが「SMOC」です。これには5つの機能段階があります。移動の可視化、データ蓄積、需要予測、最適なリソース配分、そして運用モニターと分析です。このうち可視化の部分では、エッジコンピューティング(※4)の活用を検討しています。たとえば、人が倒れたり不審者がいたりする場面で、現場に即した運用ができるようにするためです。
(※4)エッジコンピューティング:データが発生する場所(エッジ)の近くでデータを処理する技術
ーー現在、貴社ではどのような人材が活躍されていますか。
田中清生:
「自ら行動し、物事を形にしたい」という思いを持つメンバーが多いです。また、自身の働きかけに対する反応が返ってきやすいスタートアップならではの環境に、価値を感じて集まっています。
「何かに挑戦して経験を積みたい」「社会的意義があることを世界規模で成し遂げたい」。今後も、このような志を持った方をお待ちしています。挑戦に必要な環境は用意します。自ら新しいサービスを立ち上げることも、海外でリモートワークをすることも可能です。
弊社では日本だけでなく、アジアや中東といった発展著しい地域にも価値を提供しています。社員には海外出身者も多く在籍しています。そのため、多様な国籍のメンバーと自由なスタイルで働きたいという方を歓迎します。
編集後記
日本でも海外でも、都心部は極端に渋滞し、地方は過疎化が進んで公共交通が廃止されるなど、移動に関する問題は山積みだ。データに基づいて交通を最適化するZenmovのサービスは、そうした課題と真正面から向き合うものだ。スタートアップならではの自由な風土は、チャレンジする心を後押ししてくれることだろう。

田中清生/1974年東京都生まれ。東京工業大学卒業後、株式会社日本ヒューレッド・パッカードに入社し、エンジニアと法人営業を経験。その後のオランダ留学を経て、2005年にボーダフォン株式会社(現・ソフトバンク株式会社)に入社。3つの新規事業の立ち上げを経験し、2019年にZenmov株式会社を設立し、代表取締役に就任。「技術革新を通じて社会の発展と人々の幸せに貢献する」をミッションに掲げ、スマートモビリティを推進するため、日本をはじめ、東南アジア、中東、アフリカ、北米にて活動中。