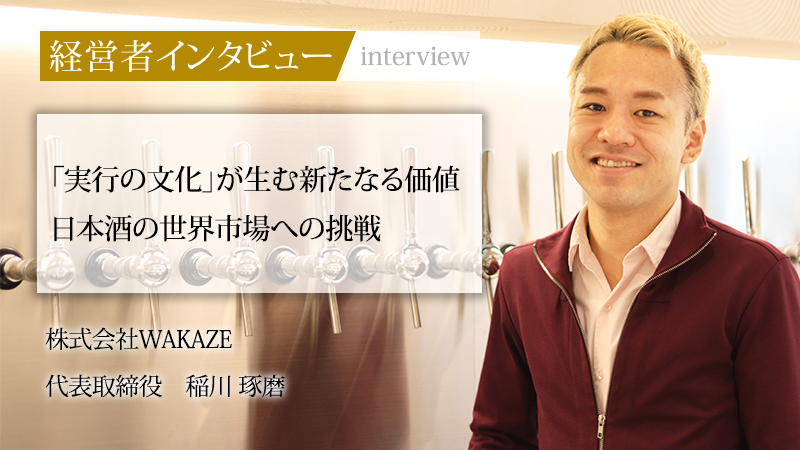
「日本酒を世界酒に」を掲げ、伝統産業に論理的思考とイノベーションをもたらす株式会社WAKAZE。同社は、フランスに酒蔵を設立するという前例のない挑戦を敢行した。消費者起点のものづくりで、これまでの常識を覆す新感覚の日本酒を次々と生み出している。同社を率いるのは、代表取締役の稲川琢磨氏。同氏は慶應義塾大学で工学を修め、ボストン コンサルティング グループ(BCG)で経営戦略を磨いた経歴を持つ。今回は、経営哲学と世界を見据えた壮大なビジョンについて話を聞いた。
論理的思考と揺るぎない使命感 経営を支える二つの原動力
ーー日本酒の分野で起業された経緯について、詳しくお聞かせいただけますか。
稲川琢磨:
きっかけは、大学時代のフランス留学と、その後のコンサルタントとしての経験です。慶應義塾大学を選んだのも、フランスのトップスクールと2年間学べるダブルディグリープログラム(※)があったからです。
留学中、エンジニアリングやテクノロジーの分野でアメリカや中国のスマートさとスピード感に触れ、同じ土俵で勝負するのは難しいと感じました。それならば、自分たち固有の文化、アイデンティティに根差すもので勝負したいという思いが強くなったのです。
その思いを胸にBCGへ入社し、多様な業界に携わる中で、古い業界にこそイノベーションの好機があると感じました。たとえば、アパレル業界が斜陽産業といわれる中でユニクロが独り勝ちしたように、変革期にある業界は非常に面白いと感じます。
留学で得た「日本固有のもので勝負したい」という思いと、コンサルタントとして見出した「大きな変革を起こせる業界」という事業機会。この二つが重なったのが「日本酒」でした。日本の発酵文化と技術に根差した日本酒には、他国が容易に模倣できない優位性があり、これなら世界で勝負できると確信して起業に至りました。
(※)ダブルディグリープログラム:複数の大学で学ぶことで、それぞれの大学から学位を取得できる制度
ーーどのような哲学を持って経営にあたっていますか。
稲川琢磨:
第一に「日本の伝統文化を広める」という使命感があります。千年続く日本酒の歴史、そのバトンを受け継いでいるという意識です。ただ、文化は時代に合わせて進化しなければ廃れてしまいます。そのためには、しっかりと経済的に回る仕組みをつくることが不可欠だと考えています。
また、社内では常に「傍観者にならないように」と伝えています。評論家になるのではなく、自らがオーナーシップを持って行動する「実行の文化」を何よりも大切にしています。
パリ醸造所の狙い 消費者起点で生む競争優位

ーーフランスに酒蔵を設立した狙いは何だったのでしょうか。
稲川琢磨:
フランスに設立した酒蔵が「KURA GRAND PARIS」です。パリという大消費地の近くに蔵を構え、お客様の声を製品開発へ直接反映させる狙いがあります。消費者からのフィードバックを早く得て迅速に改善します。そして、現地の嗜好や食文化に合わせたお酒をつくり上げます。この「消費者起点のものづくり」こそが、私たちの競争優位性の源泉です。
実際に、パリの中心地でレストランも営業し、お客様の反応を見ながら評価の高かったものを製品化するなど、開発サイクルを速めています。
ーーフランスでの事業立ち上げの際に、苦労したエピソードがあれば教えてください。
稲川琢磨:
人生で最も大変な時期でした。億単位の投資をして醸造所の準備を進めていたところ、一部の近隣住民から騒音などを懸念する声が上がり、最終的に市長からプロジェクトの停止命令が通達されました。まさに目の前が真っ暗になりました。
しかし、ここで諦めるわけにはいかないと2カ月もの間、毎日市役所に通い詰めました。ようやく実現した住民との対話の場では、20人ほどに囲まれて厳しい質問を浴びせられましたが、私たちの思いを懸命に伝え、最終的に理解を得ることができました。この経験が、「何があっても諦めない」という今の姿勢の礎になりました。
ーー商品の独自性についてもお聞かせください。
稲川琢磨:
伝統的な製法だけに固執せず、山椒やゆずといったボタニカル素材を取り入れた「その他の醸造酒」という新しいカテゴリーを日本で初めて確立しました。国税庁から初めてその定義を認めてもらうなど、まさにフロンティアの開拓でした。「手軽に飲める日本酒」をコンセプトにした「Summerfall」は、ローソンやミニストップなどで全国展開しています。こうした既成概念にとらわれない商品開発力が弊社の強みです。
ーー品質を保つ秘訣はどこにあるのでしょうか。
稲川琢磨:
ブランドイメージと、お客様が最終的に価値を感じる「味」については、必ず私自身が最終判断を下すようにしています。特に味は、10年かけてようやく分かることもあるほど繊細で、経験が必要な領域です。感覚的な要素で測りにくいからこそ、CEOである私が最後の砦となってブランドの一貫性と品質を守り抜くべきだと考えています。これは今後も変わりません。
ビール、ワインの次へ 「世界酒」の実現に向けたグローバル戦略

ーー今後のビジョンについてお聞かせください。
稲川琢磨:
私たちの目標は「日本酒を世界酒に」することです。ビール、ワインに続く「第三のクラフトドリンク」として、世界中で日本酒が楽しまれる文化を創造したいと考えています。そのために、まずは日本、アメリカ、アジアを事業の「三本柱」と位置づけ、それぞれの市場での拡大を加速させます。特に日本市場は、増え続ける海外からのお客様に、私たちの商品を直接お披露目できる場所です。そのため、特に重要な市場だと考えています。
ーー具体的なグローバル戦略は、どのようにお考えですか。
稲川琢磨:
ただ商品を輸出するのではなく、現地に合わせたブランド展開が重要です。たとえばアメリカでは、カリフォルニアの市場に合わせて「Summerfall」という新ブランドを立ち上げました。このデザインは現地のトップエージェンシーと協業し、80〜90年代のコンピューターゲームを彷彿とさせるレトロでポップな世界観を構築しました。また、従来の瓶ではなく「缶」という手軽な形態を積極的に採用することで、日本酒に対する固定観念を覆し、新たな顧客層にアプローチしています。
ーー今後はどのような展開を考えていらっしゃいますか?
稲川琢磨:
単にお酒を製造・販売するだけでは、本当の意味で日本酒という文化を根付かせることはできません。今後は日本で、これまでにない新しい業態の店舗事業も計画しています。醸造所が近いからこそ味わえる生酒の提供など、そこでしかできない体験を重視します。美味しいお酒はもちろん、食事や空間を含めた「体験」そのものを提供することで、「WAKAZE」のファンを世界中に増やしていきたいと考えています。
編集後記
コンサルタントとして培った論理的思考と、日本の伝統文化への深い敬意。稲川氏の話からは、この二つが絶妙なバランスで融合し、「WAKAZE」の推進力となっていることが伝わってきた。パリでの酒蔵設立や斬新な商品開発。これらは緻密な戦略と、「世界酒を創る」という揺るぎない信念に裏打ちされている。同社の挑戦は、日本酒業界の未来を照らす。それだけでなく、日本のものづくりが世界へ羽ばたくための新たな道筋を示すものだと感じた。

稲川琢磨/1988年生まれ。慶應義塾大学理工学研究科にて修士課程修了。ボストン コンサルティング グループに入社後、経営戦略コンサルタントとして多様な業界のプロジェクトに携わる。2016年に株式会社WAKAZEを設立。2018年には東京・三軒茶屋に都市型醸造所「WAKAZE三軒茶屋醸造所」を設立。2019年からはフランスに移住し、パリ醸造所の陣頭指揮を取る。2023年からはアメリカ・カリフォルニアで「Summerfall」ブランドを立ち上げ、世界市場へ挑戦中。














