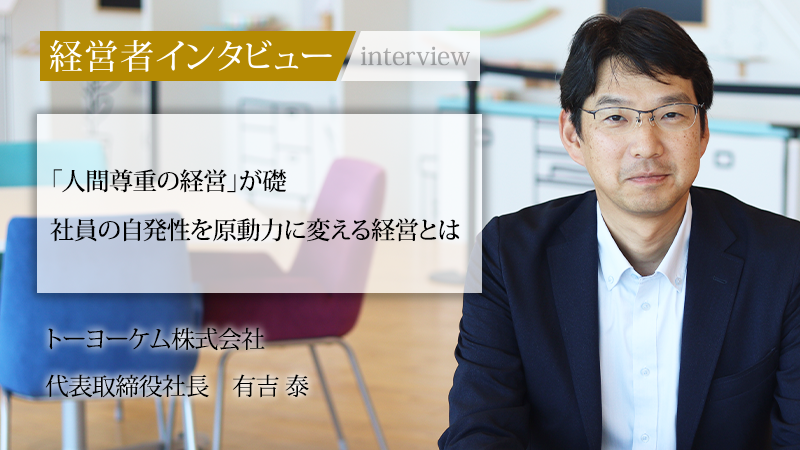
ポリマー設計技術を基盤に、包装・工業材やエレクトロニクスなど幅広い市場に、自社開発製品を供給しているトーヨーケム株式会社。同社はartienceグループの事業会社で、身近な包装材料向けの粘着剤から、最先端のスマートフォンや半導体向けのシート材料まで、独自の技術力で幅広い製品を世に送り出している。さらには、アサヒビール株式会社と生ジョッキ缶用の塗料を共同開発したことでも知られている。
2024年に代表取締役社長に就任した有吉泰氏は、長年技術者として会社の成長を支えてきた人物だ。「つくれない」と言われた壁に対し「つくれるようにすればいい」と発想を転換してきた経験を原点に、現在は「支援型リーダーシップ」を掲げ、社員が主役となる経営変革に挑む。技術者から経営者へ、その軌跡と未来への展望を聞いた。
困難を乗り越える思考法の原点となった経験
ーー社会人としてのキャリアの原点をお聞かせください。
有吉泰:
大学院では高分子材料の研究をしていたため、その研究が役立つ会社を軸に就職先を探していました。当時、恩師である教授が弊社の技術顧問を務めていたご縁もあり、東洋インキ製造株式会社(現・artience株式会社)へ入社を決めました。入社後は、研究で培った知識が本当に活かせると実感し、即戦力として初めから仕事を任せてもらえたという印象です。
また、教授から「よい会社だよ」と聞いていましたが、入社して「人間尊重の経営」という理念を肌で感じました。人に対して優しく、人を軸に経営をする社風がそこにはありました。お会いした方もよい方が多く、それは今入社してくる社員に聞いても同様であり、弊社のDNAとして受け継がれているのだと思います。
ーー技術者としてのキャリアで、転機となった出来事はありましたか。
有吉泰:
入社3、4年目の頃のことです。ある粘着剤の開発を担当したのですが、製品の性能が良い分、非常に粘度が高く、当時の社内製造設備では「つくれない」と判断されました。しかしそのとき、「設備を変えるという発想があっても良いのでは」「つくれないなら、つくれるようにすればいい」と強く思い、後々の経験も含めてプロセスの制約を、製品開発者の発想の制約、さらには会社の成長の制約にしてはいけないと思うようになりました。この時の経験が、私のターニングポイントになっており「今できないことを、どうすればできるようになるか」という考え方に変わった瞬間でした。
会社の成長を牽引した液晶材料開発という成功体験

ーー貴社の事業内容や強みを教えてください。
有吉泰:
artienceグループは、設立時の「東洋インキ製造」の名前が示す通り、もともと印刷インキから始まった会社です。インキは主に3つのコア技術で成り立っています。色の元となる「顔料」、それを固着させる「ポリマー」、そして顔料を安定させる「分散」です。その中で、ポリマーを切り出して分散と塗加工の技術を駆使し、成長させてきたのがトーヨーケムです。そのため、粘着剤や接着剤、飲料缶の内外面を守るコーティング剤など、色のついていない製品を多く扱っています。ポリマーをつくる技術を応用し、フィルムに塗ることで多彩な製品に展開しています。両面テープからスマートフォンの高機能シートまで、その領域は多岐にわたります。
ーー技術者として印象に残っているエピソードをお聞かせいただけますか。
有吉泰:
経営企画部に移る前、液晶ディスプレイのカラーフィルタに使われる材料開発に携わった経験は、よい思い出として残っています。当時は液晶テレビが大型化していく勢いのある時期で、画質の鍵を握る顔料分散剤という材料を社内で開発することになりました。私がリーダーを務めたこの開発がうまくいき、会社の成長に大きく貢献できたと感じています。この功績は会社からも表彰されました。開発メンバーと屋形船で宴会をしたのは、忘れられない思い出です。
現場を信じ下から支える支援型リーダーシップ
ーー社長へ就任された際の思いや、特に力を入れている点についてお聞かせください。
有吉泰:
東洋インキからartienceへと社名を変更し、会社全体が大きく変わろうとする中での社長就任でした。比較的若い年代で抜擢されたからには、「会社を変えることを実行しなければ、私が社長を務める意味はない」。そのように強く感じています。そのために私が力を入れているのが、経営のアップデートと社員のマインドセットです。会社と個人は対等であり、社員にはもっと自発的に社会貢献に取り組んでほしいという思いがあります。
ーーその実現に向けて、具体的にどういったことに取り組んでいらっしゃいますか。
有吉泰:
「支援型リーダーシップ」と「自律型マネジメント」という二つの考え方を重視して、トーヨーケム社内に浸透させようと取り組んでいます。現代は、将来の予測が困難なVUCA(※)の時代です。このような時代では、現場に近い人たちが最も世の中の変化を捉えているはずです。その現場の社員を課長が支え、部長が支え、最後に社長が支える。逆三角形の形で組織を支えるのが「支援型リーダーシップ」です。
そして「自律型マネジメント」は、やらされるのではなく自ら手を挙げていくことを推奨する考え方です。たとえば「この業務は無駄が多い」と感じた社員がいれば、その人に改善を任せる。そうした成功体験が「この会社は言いたいことが言えるんだ」という文化を育むと考えています。
(※)VUCA:「変動性(Volatility)」「不確実性(Uncertainty)」「複雑性(Complexity)」「曖昧性(Ambiguity)」の頭文字をとった造語。
グローバル展開と新たなブランド構築に向けた覚悟
ーー5年後、10年後を見据え、どのような会社の未来像を描いていますか。
有吉泰:
事業面では、既存分野の強化と新分野への挑戦を両輪で進めます。粘着剤や缶コーティングは、インドや東南アジアなど海外での成長が著しいため、グローバル展開をさらに加速させます。同時に、新しいポリマー材料の開発にも注力しています。これからの自動運転やAI半導体といったエレクトロニクス分野で役立つ材料です。特に、高速通信に貢献できる低誘電率のポリマーとそれを活かしたシート製品などは、弊社の技術を活かせる分野だと期待しています。
artienceへ社名を変更したことで、正直なところ認知度は下がりました。しかし、この新しいブランドをアピールする一翼を、事業会社である弊社が担いたいと考えています。製品が売れて「この会社はすごいものをつくっている」と評価されることが第一です。
また、人材採用の面でも、弊社の「人がいい」という良さを伝え、ミスマッチの少ない採用につなげる「全員リクルーター作戦」といった取り組みも進めています。
ーー最後に、社長として最も大切にしている思いをお聞かせください。
有吉泰:
世の中で選ばれる製品をつくること。これが何よりも重要です。そして、それをつくる人たちが自発的な思いを持つことも欠かせません。上司の指示ではなく「これを世に出したい」「社会に貢献したい」という情熱です。この二つがセットであって初めて、会社は継続的に成長できると考えています。そうした思いをベースに、ものづくりをしていきたいです。
編集後記
若き日に抱いた「つくれないなら、つくれるようにすればいい」という技術者としての純粋な探求心。有吉氏の話の根底には、揺るぎない信念が一貫して流れている。その思いは今、「社員の自発性を信じ、下から支える」という支援型リーダーシップへと昇華された。技術への深い知見と、人を尊重する温かな眼差し。この二つが融合したとき、組織は最大の力を発揮するのだろう。やらされるのではない、一人ひとりの「つくりたい」という情熱を原動力に変える同社の挑戦に、未来を切り拓く企業の姿を見た。

有吉泰/1997年慶應義塾大学大学院 理工学研究科修了。専門は高分子界面科学。同年4月に東洋インキ製造株式会社(現・artience株式会社)に入社。R&D本部にて粘着剤や顔料分散剤の開発に携わる。2009年4月より経営企画部、2015年にグループ会社のトーヨーケム株式会社 技術本部 技術3部 部長に就任。2021年に同技術本部長に就任し、川越製造所ポリマーパイロット棟計画を牽引。2022年に執行役員、2024年1月にartience株式会社常務執行役員 兼 トーヨーケム株式会社の代表取締役社長に就任。














