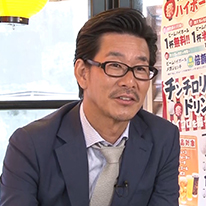日本の教育現場は、集団授業が主流だった時代から、子どもたち一人ひとりに寄り添う個別指導が広がりを見せるなど、そのあり方は多様化している。そんな中、従来の教育業界が抱える働き方や学習方法の課題に真正面から向き合い、地域に根差した個別指導塾「ベスト個別」を展開するのが、株式会社ベストコだ。代表取締役社長の井関大介氏は、集団授業では成績が伸びにくい生徒を個別にフォローしたいという思いから、33歳で起業した。地域に貢献し、子どもたちの人生を応援するという揺るぎない信念を持つ同氏に話を聞いた。
地域に根差した個別指導塾の原点
ーー教育の世界へ足を踏み入れたきっかけについてお聞かせください。
井関大介:
大学時代に塾講師のアルバイトをしたことが、教育業界に進むきっかけでした。当時、担当した中学3年生の生徒は、志望校の偏差値に7ほど足りていない厳しい状況でしたが、短期間で成績が上がり、無事合格を勝ちとることができたのです。そのとき、生徒さんとお母さんが泣いて喜んでくださり、誰かの役に立ち、貢献する仕事ができることに大きな喜びを感じました。
もともと家業を継がなかったことに負い目を感じていた私にとって、この経験は「誰かの役に立てるなら、別の形で社会に貢献できる」という新しい道を示してくれたのです。その気づきから、学校の教師も選択肢の一つでしたが、生徒の成績や合格に直接関われる学習塾の方が自分に合っていると感じ、この道に進むことを決めました。
ーー教育現場で感じた課題と、創業に至るまでの経緯についてお聞かせください。
井関大介:
学習塾で働き始めて、二つの大きな課題に直面しました。一つは、働く環境の問題です。当時、学習塾の現場は長時間労働や非効率な業務が多く、教育が好きなのに長く続けられない人と思う人が多い業界でした。二つ目は、学習に悩みを抱える生徒たちへのサービスがマッチしていないことです。集団授業では成績が伸びにくい生徒も、個別のフォローをすれば学力向上につながります。しかし、個別指導は人件費がかさむため、どうしても授業料が高くなり、本当に必要としている生徒たちに提供することが難しいという課題がありました。これらの課題を解決するために、非効率な業務を効率化し、新しいやり方を導入することで、古い業界をリモデルしようと考え、33歳で起業しました。
ーー貴社を創業された直後はどのような状況でしたでしょうか?
井関大介:
創業から2年目の終わりに、東日本大震災が起きました。私は福島で起業していたため、原発の問題もあり、子どもたちが県外に避難するなど、多くの生徒が授業を受けられない状況に陥りました。当時、年間の売上高が2億円ほどの会社でしたが、売上が減少したこと以上に衝撃だったのは、未就学児を中心に子どもたちの県外への避難によって、10年後の市場が半分くらいになるという未来が見えてしまったことです。
しかし、地元のことは地元の人がやらなければならないという強い思いから、子どもたちの学びの場や日常を取り戻す手助けをしたいと考えました。不安もありましたが、地域貢献になるという確信のもと、当時15校しかなかった校舎を、さらに10校増やす決断をしました。
独自のビジネスモデルで教育現場の未来を切り開く

ーー経営者として特に大事にされていることは何でしょうか。
井関大介:
震災の経験から、外部環境や時代の変化によって課題は必ず出てくると思っています。そのとき、どうすれば打開できるのかを徹底的に考え、行動に移すことが重要だと考えています。たとえば、アルバイトの採用が難しくなれば、教室を閉めるのではなく、ICTを活用して少人数でも運営できる仕組みを構築するといった取り組みです。この「もがく」ことを大事にする体質は、震災の経験が会社のカルチャーとして根付いているからこそだと思います。また、どれだけ便利なオンライン教育が普及しても、中高生という多感な時期には、学習の場やコミュニティをリアルの形で残していくことにこだわっていきたいですね。
ーー従来の教育業界が抱える課題を解決するために、具体的にどのような取り組みをされていますか。
井関大介:
教育現場の非効率な部分を改善するために、徹底的に業務を仕組み化し、テクノロジーを導入しました。例えば、講師に一任してカリキュラムを組むのではなく、データに基づき、各人の学力に合わせて最も伸びる教え方を全体で共有し、実行しています。
また、保護者へのお知らせ等の事務作業を本社で一括管理し、教室運営における事務的な要素を徹底的に排除することで、講師が本来の仕事である生徒と向き合う時間や、成績を上げることに集中できる環境をつくりました。その結果、残業は大幅に減り、キャリア採用者の離職率も低くなっています。働き方改革という言葉がまだない段階から、教育に携わる人が長く働けるよう、労働環境の改善に取り組んできました。
ーー教室の拡大においてこだわっていることはありますか?
井関大介:
共働き家庭が増える中で、送り迎えなく子どもが一人でも通える場所に塾があることが非常に重要だと考えています。そのため、駅前ではなく、住宅地の近くに小さな教室を開校しているのです。駅前と比べて競合が少ないため、ビジネスとして成立しやすいという側面もあります。ドミナント戦略(特定の地域内に集中的に展開すること)によって地域での認知度を高め、口コミでの集客も安定させることができています。地域に密着した取り組みは地域貢献度も高く、社員からも「地元を助けたい」という声が聞かれるほどです。
教育の可能性を追求し、描く未来への挑戦
ーー今後の事業の展望についてお聞かせください。
井関大介:
少子化によって今後は塾業界全体は縮小傾向になると思いますが、教育の必要性は今後も変わらないと考えています。現在120校ほどですが、10年後には500校を目指したいですね。特に、首都圏以外の地域での出店を加速させたいと考えています。
また、ICTを活用し、先生の数が少なくても成り立つモデルをさらにブラッシュアップしていく予定です。生徒の状況に応じて、例えば週に一度はリアルの塾に通い、他の日はオンラインで学習するなど、オンラインとオフラインを行き来できる環境を整え、場所や時間にとらわれない新しい学びの形を提供していきたいです。企業理念「B with you 君のベストを一緒につくる」のとおり、勉強だけでなく、子どもたちの人生を応援できる場所を目指しています。
ーー今後、どのような方と一緒に働きたいと考えていますか。
井関大介:
教育現場が抱える課題を解決したい、自分の経験を教育に生かしたいという方はもちろん歓迎します。また、社会的な構造へのテコ入れにチャレンジしてみたいという志のある方、そして地元に貢献したいという思いを持つ方も大歓迎です。これから500教室を目指し成長する会社ですので、教室での経験を積みながらも、プロダクト開発など新しい分野にもチャレンジできる機会がたくさんあります。若い人たちにも積極的に新しいことを任せているので、デジタルネイティブ世代の方にもやりがいを感じていただけるはずです。
編集後記
学習塾という身近な存在の裏側にある課題に、真正面から向き合う井関氏の姿勢に感銘を受けた。特に、創業直後に襲いかかった未曽有の災害を、事業拡大のきっかけに変えたエピソードは、単なるビジネスの成功談ではなく、子どもたちへの深い愛情と地域に対する揺るぎない思いが根底にあることを示している。未来の教育を担う同社の飽くなき挑戦は、これからも続く。

井関大介/1975年秋田県生まれ。大学卒業後、集団学習塾にて教育現場を経験。2009年に株式会社Global assist(現・株式会社ベストコ)を創業し、地域の子ども一人ひとりの学習課題解決を目指す。現在は地方でも持続可能な学習塾モデルの開発と拡大に尽力している。