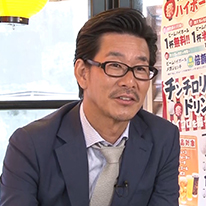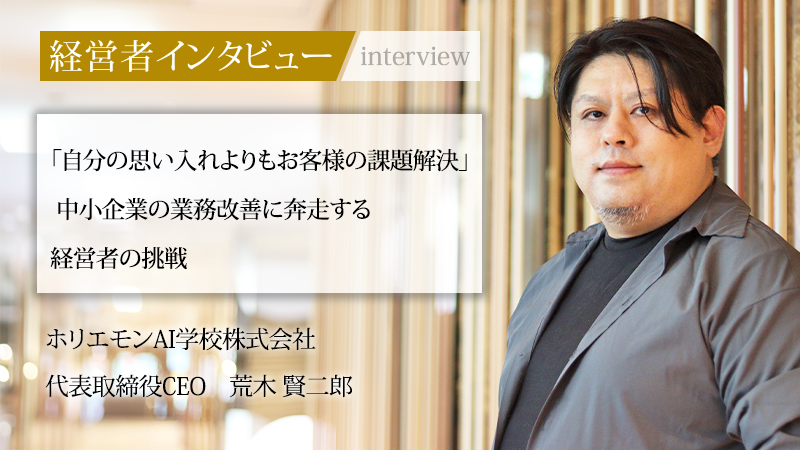
中小企業のAI・DX推進を最前線で支援するホリエモンAI学校株式会社。同社は、IT活用に苦手意識を持つ成熟業界の中小企業に対し、AIを“教える”のではなく、“使いこなして業績を上げる”ための伴走型生成AIスクールを提供している。代表取締役CEOの荒木賢二郎氏は、堀江貴文氏との共同創業という華やかなイメージとは裏腹に、失敗と成功を繰り返す中で独自の信念を築き上げてきた。今回、同社がなぜ中小企業にとって不可欠な存在となり得るのか、その情熱と戦略を深掘りする。
消極的起業からMBAで得た新たな事業観
ーー起業家としてのキャリアをスタートされた経緯についてお聞かせください。
荒木賢二郎:
最初の起業は、大学時代にアルバイトで毎月50万〜100万円ほど稼いでいた私にとって、“仕方なく”選んだ道でした。就職活動で提示された「全国転勤あり、給料は22万円スタート」という条件は、私は受け入れられなかったのです。考えた結果、大学3年生の頃から準備を進め、起業することにしました。それまでビジネスの経験も知識もなかったため、「社会に必要なものは何か」を考え、将来性を感じ、私自身も興味を持てたIT分野を選びました。
ガラケー向けホームページ制作事業で起業したものの、最初の2年間は売上がほぼなく、赤字が続きました。会社からの給与だけでは生活が厳しく、昼間はアルバイト、夜中から朝方まで仕事をするという生活を送っていました。2年ほどでようやく毎月の売上が立つようになり、会社らしい状況へと変わっていきました。
ーー貴社設立の経緯について教えてください。
荒木賢二郎:
2023年の3月ごろ、私たちは「オフィス版Airbnb」ともいえる、オフィスのシェア事業を展開していました。しかし、その頃になると社会全体に「テレワーク関連のブームは終わりつつある」という空気が漂い始めていました。
そこで、「テレワーク以外に、企業が抱えている課題はないか」と模索を始めたんです。その中で見えてきたのが、テレワークをしている社員と出社している社員のエンゲージメントデータが社内に蓄積されているにもかかわらず、誰もそれを分析できていないという問題でした。「Pythonなどを使えば分析できるのでは」と考えて確認してみたのですが、そもそも会社にはPythonを学ぶ研修制度が存在していませんでした。
こうした背景から、企業向けにPythonを扱えるAI人材を育成する研修事業を立ち上げたことが、当社設立のきっかけです。その後、時代の流れに合わせて、PythonではなくChatGPTなどの生成AIを活用した業務効率化研修へと進化し、2024年3月の当社設立へとつながりました。
失敗から学んだ顧客ニーズ起点の事業哲学
ーービジネスを続ける中で大きく変わった点はありますか。
荒木賢二郎:
最も大きな変化は、価値観の変化です。かつては強い想いや原体験を持つ起業家を好んでいましたが、今振り返ると彼らの多くは失敗しています。私自身も想いを重視したことで、意思決定を失敗したこともありました。想いが強すぎると、サービス提供後にお客様の困りごとに合わせて内容を変えられない。それが原因だと考えています。
自分がやりたいことよりも、他者が求めていることに柔軟に合わせる姿勢。社会に役立つことこそが重要だという学びが、今の私の根幹を成しています。
ーー堀江貴文氏との共同創業に至った経緯についてお聞かせください。
荒木賢二郎:
実務現場での活用に特化したAI人材育成事業を始めると周囲に告知していたところ、堀江氏から「それは非常に将来性が見込めるから事業を一緒にやらないか?」と連絡があり、共同創業が決まりました。試行錯誤を重ね、わずか1ヶ月強で売上150万円の商談が取れた際、「これはいける」と確信しました。
専門部署なき中小企業に伴走するDX支援

ーー貴社が提供するAI活用支援の強みについてどうお考えですか。
荒木賢二郎:
弊社サービスの強みは「中小企業のDX部長」というコンセプトにあります。クライアントは建築や不動産、介護といった、IT化が比較的進んでいない業界の企業が多くあります。そして社員1〜50人程度の小規模な会社が、お客様の約8割を占めているのが特徴です。
これらの企業には、そもそもIT推進部などがありません。そこで、まずはスクール受講で基礎知識を習得していただき、その後は「貴社のDX部長ですから」と毎月面談を行い、徹底的に伴走します。受講中も、スクールの受講内容に限らず、システム開発やコンサルティングなど、あらゆる困り事に対応しています。単なるAIスクールではなく、課題解決型のソリューションを提供している点が評価されています。
ーー顧客の具体的な成功事例についてお聞かせください。
荒木賢二郎:
ある派遣会社で、毎月1300件の入力作業をAIで全自動化した事例が印象的です。その会社では8つの媒体から来る求人応募メールの情報を、担当者が毎日手動でコピー&ペーストしていました。この作業が、毎月1300件も発生していたのです。
受講生は当初「AIに何ができるかわからなかった」ため、この困り事を相談リストに書いていませんでした。しかし基礎講座を通じて、AIでどのような業務が自動化できるのか、どのような仕組みで動いているのかを理解したことがきっかけで、業務改善のアイデアに気づくことができました。その結果、この膨大な業務をAIで全自動化することに成功。AIの用途がわからない中小企業の潜在的な課題を解決し、大幅な時間削減につながることを証明できた好例です。
中小企業に不可欠な存在を目指す事業成長の全貌
ーー今後の展望についてお聞かせください
荒木賢二郎:
中小企業が抱える人手不足という根幹課題を解決し、「困ったらあの会社に頼めばどうにかなる」と圧倒的に頼られる存在になることを目指しています。その実現のため、まず営業手法を転換します。AI活用による「売上3倍」といった具体的な成功事例を数多く生み出し、その実績で顧客を引き寄せる「ソリューション営業」を確立する計画です。
さらに、事業拡大の柱としてフランチャイズ展開を強力に推進し、100の業界、そして地域密着の課題解決を可能にする全国47都道府県へのネットワーク拡大を目標に掲げています。
これらのビジョンを実現する重要な戦略として、3年以内のIPO(新規株式公開)を計画しています。上場で得た信用力と資金力を元にM&Aを積極的に行い、コンサルティングや人材紹介といった多角的なサービスを全国へ一気に展開する考えです。
編集後記
荒木氏のキャリアは、安定を嫌い、常に新しい価値を追求する挑戦の連続である。過去の失敗から得た「自分の思い入れよりもお客様の課題解決」という教訓は、同社の課題解決型という独自の姿勢に深く根付いている。その戦略からは、「顧客の真の課題解決こそが、結果として企業の成長につながる」という強い信念が感じられた。この情熱と戦略をもってすれば、3年後のIPO、そして100業界への展開という目標も決して夢物語ではないだろう。「中小企業のDX部長」として同社が創出する未来に、今後も注目したい。

荒木賢二郎/1980年長崎県生まれ。大学卒業後、ガラケー向けホームページ制作事業で起業。ウェブ制作、システム開発など複数のビジネスを展開し、2016 年に会社を売却。その後、早稲田大学 MBAで経営を学び、複数のスタートアップに出資、参画。2023 年以降は生成 AI 領域に注力し、2024 年に「ホリエモン AI 学校」を設立。著書は堀江貴文氏との共著「堀江貴文の ChatGPT 大全」。