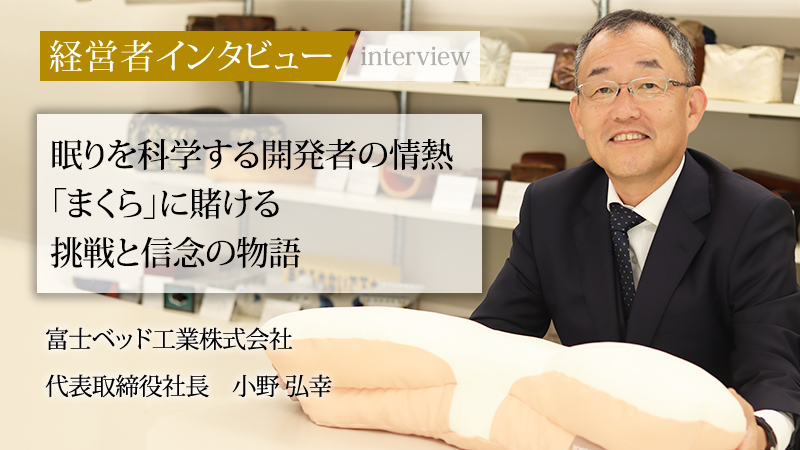
快適な「眠り」を届けることを使命に、今年で創業69年目を迎える寝具メーカー、富士ベッド工業株式会社。創業当初はマットレス製造販売が中心であったが、後に枕の生産を開始し、日本初の機能枕「ツーウェイピロー」を考案し実用新案登録している。社名に「ベッド」と冠しながらも、その事業の柱は一貫して「枕」であり、機能枕のパイオニアとしても知られている。
2019年に代表取締役社長に就任した小野弘幸氏は、コロナ禍という未曾有の危機を乗り越え、企業のあり方や事業の方向性を見つめ直す機会を得た。そして現在、メイドインジャパンのものづくりを守り、さらに発展させるため、新たな挑戦を続けている。ものづくりへの深い愛と、人を想う純粋な気持ちを原動力に、社員やパートナーを巻き込みながら「心地良い毎日」を届けようとする小野氏の歩みと未来への思いに迫る。
異なる業界で見つけたものづくりの「真髄」
ーー社会人としてのキャリアはどのようにスタートされたのでしょうか。
小野弘幸:
物心ついた頃から、工務店を営む祖父の手伝いをしていました。家を建てるという「ものづくり」に触れるのが楽しく、いつかこの世界で働きたいと思い、建築系の学校に進学したのです。卒業後は中堅の建設会社に入社し、現場で働きました。当時はちょうどバブル時代。家を建てる仕事に大きなやりがいを感じていたのです。
ーー建設業にやりがいを感じていた中、どのような転機が訪れたのでしょうか。
小野弘幸:
建設会社で働いて2年半ほど経った頃、先代の会長とご縁があり、「一緒にやろうよ」と誘っていただいたことが、この業界に足を踏み入れたきっかけです。正直なところ、当時の私は転職を考えていませんでしたが、会長の熱意に触れ、「新しい世界に挑戦してみよう」という気持ちになったのです。
入社後、これまでの常識が通用しないことに驚きました。建設業界ではミリ単位の正確さを求められますが、寝具業界ではサイズに1センチほどの許容範囲があったり、柔軟に対応することの大切さを学び、諦めずに商品を作り続ける道を選びました。
枕に込められた、人々の暮らしを豊かにする思い
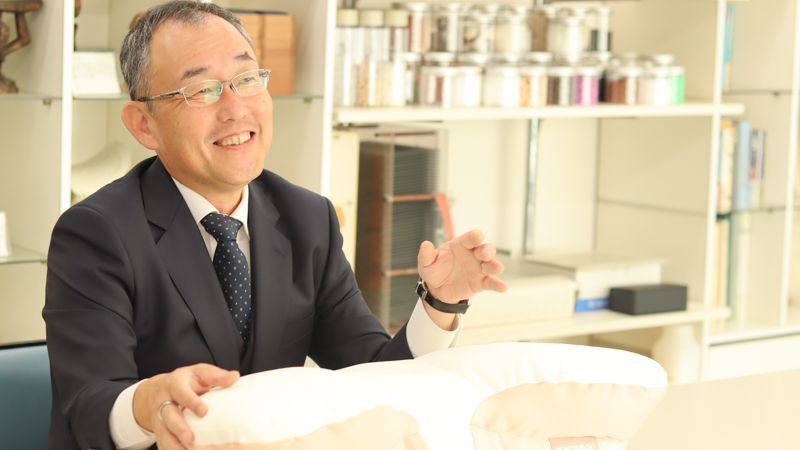
ーー入社後は、どのようなお仕事を経験されたのでしょうか。
小野弘幸:
入社後、私はまくら課に配属されました。当時の枕は消費者の認知度がほぼゼロに等しかったため、社内でも花形部署ではありませんでしたが、私にとっては運命的な出会いでした。というのも、創業以来、枕を主力事業としてきた会社なので、私自身は非常にやりがいを感じていたからです。ただ、当時は寝具専門店や量販店を中心に販売していたものの、お客様に「良い枕とはどういうものなのか」という概念自体が浸透していない状況でした。
ーー枕の開発において、貴社ならではの強みや特にこだわっている点についてお聞かせください。
小野弘幸:
枕を研究するチームをつくり、整形外科の先生や大学の先生方と「良い枕をつくろう」と研究開発を始めました。弊社の強みは、創業から68年間、毎日欠かさず商品の試作を続けていることにあると考えています。また、東京科学大学(旧:東京工業大学)と共同で開発した測定機器を用いて、品質の検査や検証を繰り返し、科学的な根拠(エビデンス)に基づいた商品開発を行っているのです。現在、枕難民の多くが抱える「首こり」や「肩こり」の解決につながる、横向き寝の枕開発に注力しています。仰向け寝の枕はすでに一定の完成形に達しているため、横向き寝の課題を克服することが、寝返り、さらには睡眠の問題を解決することにもつながると信じて、研究を進めているところです。
社長就任とコロナ禍を経て掴んだ新たな挑戦
ーー社長就任後、どのような課題に直面しましたか。
小野弘幸:
2019年に社長に就任後、コロナ禍に襲われました。弊社の商品のほとんどは店頭販売が中心だったため、店舗のロックダウンによって売上が半減してしまったのです。社員の安全を守るため、会社には来ないよう指示を出し、先の見えない状況に社員も私も初めての経験に戸惑うばかりでした。
この危機を乗り越えるため、私たちはオンラインでの販売戦略に舵を切り、Webサイトの強化やECでの販売を加速させました。また、社員一人ひとりが「どうすれば良いのか」を考え、SNSを活用した情報発信や、顧客とのオンラインでのコミュニケーションを積極的に行うなど、業務内容を良い方向に変えるきっかけになったと思います。
ーーコロナ禍を乗り越え、貴社は現在、どのような新たな挑戦をされているのでしょうか。
小野弘幸:
コロナ禍を経験し、何があっても自分たちで生産できる体制を整えることの重要性を感じました。そして、国内の生産工場が減少していく中で、協力工場とともに「メイドインジャパン」の旗を掲げてものづくりを続けることを決意し、2023年、埼玉に新工場を建設したのです。
当初、建設費はロシアのウクライナ侵攻の影響で当初の予定から1.5倍に膨れ上がり、未経験の若い人材を採用したため、最初の半年間は製造にかかるコストが売上を上回る赤字が続きました。しかし、従業員たちの尽力によって工場はプラス経営を実現し、今では弊社の主力工場になっています。この経験から、逆境にあっても自分たちの力で生産を守り抜くことの大切さを改めて感じています。
組織と人、そして地域を繋ぐ「球体」の考え方
ーー仕事をする上で大切にしている価値観を教えていただけますか。
小野弘幸:
私の仕事における価値観は、「全てを一人でやろうとしないこと」です。多くの人を巻き込み、チームで物事を成し遂げようと考えています。私はこの考え方を「球体」と表現しています。私が球体の中心となり、様々な人を巻き込みながら、この球体を広げていく。球体が広がれば、全ての物事がうまくいくと考えています。この「球体」の考え方は、誰かを信じること、そして信頼関係を築くことから始まります。私は一度信じたらとことん信じ抜き、裏切られても気にしないと決めているのです。
ーー多くの人を巻き込む「球体」の考え方は、どのような形で社会と繋がっているのでしょうか。
小野弘幸:
社員や協力会社の方々とのつながりはもちろん、弊社は本社がある大田区に根ざし、地域とのつながりも大切にしています。たとえば、小学校の工場見学を定期的に受け入れているのも、子供たちが外に出られないコロナ禍をきっかけに始めた取り組みです。最近では、小学6年生を対象に「スマートフォンを超える枕」というミッションを出し、子供たちが睡眠について主体的に考える機会を創出しています。このような活動を通して、地域社会との信頼関係を築き、球体を広げていきたいと考えているのです。
枕の可能性を世界に伝える、未来への展望
ーー今後のビジョンについてお聞かせください。
小野弘幸:
弊社のビジョンは、生産数も技術力も日本一の枕メーカーになることです。そして、良質な枕を世界中に届けたいと考えています。その実現には、一人の力ではなく、組織としての力が不可欠です。今後は経営計画に基づいた採用活動を計画的に行い、理念に共感し、同じ方向性を向いてくれる人材を確保することで、ビジョンを実現できる組織基盤を構築したいと思っています。
編集後記
「ものづくりがとても好き」と語る小野氏の言葉から、根底にあるものづくりへの純粋な情熱と愛を強く感じた。そして、その愛は枕という製品だけに留まらず、社員、協力会社、ひいては枕を使う全ての人々へと向けられている。特に、小野氏が語った「球体」という考え方からは、独りよがりな経営ではなく、人と人とのつながりを何よりも大切にする姿勢が伝わってきた。この球体がさらに広がり、多くの人々を巻き込みながら、メイドインジャパンの枕が世界中の人々の「心地良い毎日」を支えていく未来が楽しみである。

小野弘幸/1969年生まれ、東京都大田区出身。1990年東京工業専門学校卒業。祖父が工務店を経営していたことから建設会社に入社するも、先代の会長と出会い、1993年富士ベッド工業株式会社に入社、まくら課に配属。営業部長、取締役常務を経て、2019年代表取締役社長に就任。現在、一般社団法人 日本寝具寝装品協会(JBA)役員理事も務める。
※公式ショップ、公式X(旧Twitter)、公式Instagram、楽天市場、Yahoo!ショッピングは各リンクよりご覧ください。














