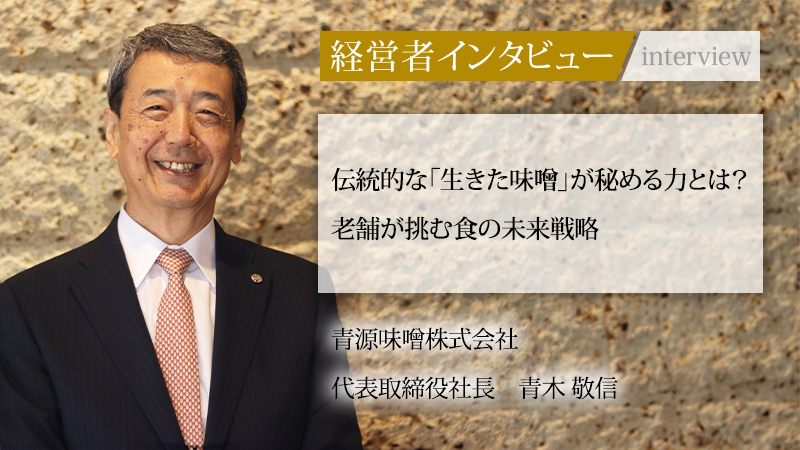
1625年の創業以来、400年近い歴史の中で味噌の製造・販売を続け、その伝統を守りながらも新たな挑戦を続けている青源味噌株式会社。「日本が誇る伝統的発酵技術でお客様の健康に貢献する」というミッションを掲げ、現代人の健康課題に対し、「生きた味噌」という視点から解決策を提示している。
同社を率いる代表取締役社長、青木敬信氏は、「古くから日本の食卓を支えてきた味噌は、日本の伝統的な食文化において欠かせない存在だ。しかし、現代社会の食文化は、その利便性や安全性を追求するあまり、本来の食が持つ力が失われつつある」と語る。
本記事では、味噌が持つ可能性を広げる同社の取り組みと、未来への確固たる展望に迫る。
創業400年 挑戦を続ける味噌屋の歩み
ーー貴社に入社されてから取り組まれたことはどんなことですか。
青木敬信:
私が入社してすぐに抱いたのは、「味噌がお味噌汁の素としてしか受け止められていない」という強い危機感でした。当時は味噌の消費量のほとんどがお味噌汁のためで、本来の多様な使い方やおいしさが忘れられているように感じたのです。
そこで、味噌汁だけではない味噌の可能性を広げる取り組みに着手しました。餃子を味噌で食べたり、ラーメンに味噌を使ったりといった提案もその一つです。味噌には、味の濃い料理をあっさりまろやかにする力があります。そのおいしさを感じていただくことで、味噌の新たな可能性を発見してもらいたいと考えました。
ーー特に印象に残っている製品開発のプロジェクトについてお聞かせください。
青木敬信:
昭和に誕生した「味噌キャラメル」(現在は販売終了)は、私が最初に携わったプロジェクトです。味噌を気軽に摂取してもらうための手段として開発しました。お湯を沸かして具材を切る手間が省けます。運転中や乗り物の中でも手軽に味噌を摂れるようにと考えた商品です。
味噌と牛乳や乳製品は相性が良いため、水飴で固めてキャラメル状に仕上げました。口に放り込んで手軽に食べられます。3粒で味噌汁1杯分の味噌を摂取できるという商品でした。
品質を支えるものづくりの哲学

ーー製品の品質へのこだわりについてお聞かせください。
青木敬信:
良い味噌をつくるためには、良い原料と良いつくり手が不可欠です。原材料は農産物ですから、常に完璧な状態とは限りません。だからこそ、つくり手の人間の質の高さが問われます。味噌は生きている微生物が時間をかけてつくるもの。つくり手の思いが品質に現れると考えています。単なる技術や手先の器用さだけでなく、微生物への愛情や関心、思いやりが大切です。人として誠実でなければ、良いものはできません。
また、原料価格が高騰したとしても、国産原料へのこだわりは持ち続けています(※)。品質を落とさず、良い原料を使い続けるという強い覚悟があるからです。この姿勢は、従業員が高い原料を大切に扱う意識にもつながります。結果として製品の品質を高めていくと信じています。「生の発酵食品を体に摂り入れることの大切さをお伝えしたい」という思いで手造り味噌教室なども開催しております。
(※)味噌のこだわりについて
ーー味噌づくりの仕事をどのように捉えていますか。
青木敬信:
味噌づくりは、長い年月をかけてようやく本質がわかる、非常に深い仕事です。実際にやってみて初めてわかることや、いまだに正解がまだわかっていないことばかりです。同じように作業をしても、毎回出来上がりは異なります。それは、原材料や微生物が生き物だからにほかなりません。
私たち人間は、「自分の力でつくっている」と勘違いしがちです。しかし実際は、微生物がいなければ味噌は完成しません。いわば、微生物とともに仕事をしているのです。だからこそ微生物の力を信じ、素直に任せることができれば、良い結果につながります。その真髄を理解し、微生物と向き合い続けることこそ、この仕事の醍醐味だと感じています。
世界を見据えた事業展開と展望

ーー現代の健康面での課題について、どうお考えですか。
青木敬信:
現代の食は衛生的で便利になり、いつでも手軽に食べ物を入手できます。しかしこの便利さの裏側で、私たちは口から生きた微生物を摂取する機会が減ってしまいました。たとえば小学校では、食物アレルギーがない子どもはクラスの2割にも満たないという話を聞きます。これは食の欧米化や、加熱殺菌された加工食品ばかりを口にするようになったことも一因でしょう。
安全な食べ物は増えましたが、問題点もあります。栄養素を摂取するだけで、消化のための酵素をすべて自前で用意しなければなりません。また、穏やかな感染という形で免疫を学習する機会も減っていると考えられます。
ーーその課題に対して、貴社はどのように貢献していきたいとお考えですか。
青木敬信:
弊社のミッションは「日本が誇る伝統的発酵技術でお客様の健康に貢献する」ことです。昔ながらの「生きた味噌」を、生きたままお客様にお届けするという使命を強く感じています。味噌のような発酵食品には生きた微生物が含まれます。それには現代人が失いつつあるものを補う力があると考えています。
腸内環境の改善や免疫力の向上など、お客様の健康に貢献できる価値を提供していきたいです。400年という歴史を持つ伝統的な技術を活かし、現代の食卓の課題に寄り添うことが私たちの役割だと認識しています。

ーー今後の事業の展望についてお聞かせください。
青木敬信:
目指すのは、お客様に喜んでいただき、健康に貢献できる会社。そして、社員が働きがいを感じられる会社です。今後はECサイトの強化などを通じ、新たな市場へ商品を展開していきます。地域に限定されず、全国、そして世界へ。「生きた食べ物」に関心を持つ方々に商品を届けるためです。さらに、他社との協業も積極的に進め、味噌の新たな可能性を広げていきたいです。
弊社は現在、若い世代の力も求めています。キャリアや学歴は問いません。味噌が好きで、その思いをお客様に届けたいという気持ちがあれば、あなたの力は必ず役に立ちます。その実感が、働く喜びにつながるはずです。
(※)ご興味ある方はこちらの採用応募フォームよりご連絡お待ちしております。
編集後記
400年の歴史を背負う青木氏の言葉には、揺るぎない覚悟と未来への情熱が満ちていた。特に、現代の食文化が抱える課題に対し、伝統的な発酵技術で解決策を提示する姿勢。そこからは単なる老舗の継承者ではない、経営者としての強い使命感が感じられた。微生物の力を信じ、良い原料を使い続けるという哲学は、企業の根幹となる深い信頼を築く。そして、お客様の健康という目に見える形での貢献へとつながっていく。同社はこれから日本の食文化を未来へとつなげ、私たちの食卓に新たな価値をもたらしてくれるだろう。















