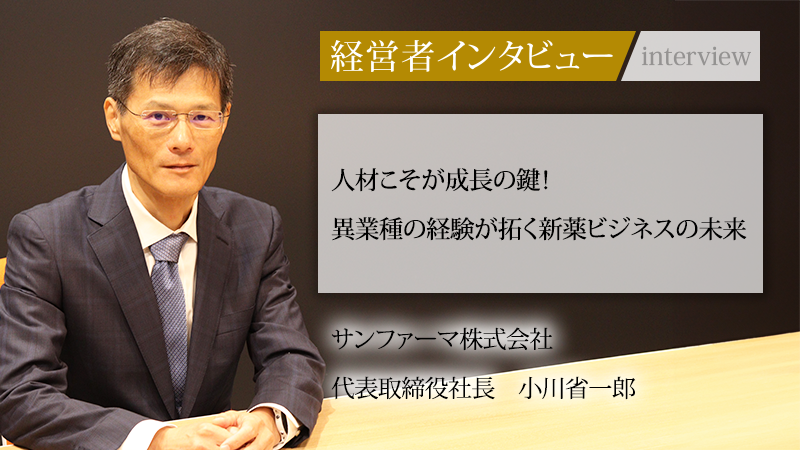
インドを本拠地とするグローバル企業であり、日本では皮膚科領域の新薬事業に注力するサンファーマ株式会社。同社は今、事業の転換点を迎え「第二創業期」ともいえる重要な局面にある。その舵取りを担うのが、代表取締役社長の小川省一郎氏だ。JR東日本での現場経験、ボストン コンサルティング グループでの結果主義、外資系製薬企業でのチームビルディングと、多彩の経歴を持つ同氏に、独自の経営論と会社の未来像について話を聞いた。
すべての答えは現場にあり 多様な経験が育んだ信念
ーーこれまでのご経歴と、キャリアの中で得られた学びについてお聞かせください。
小川省一郎:
私の考え方の土台は、キャリアの初期に経験した3つの出来事によって築かれました。今でも、基本的にはその時に学んだことを繰り返しているような感覚です。
キャリアの始まりはJR東日本でした。東京大学大学院を修了し、理論ばかりで実践を知らない「頭でっかち」な状態で入社しました。最初の4年間は車両の車検工場に配属され、油まみれで働く毎日でした。大学で理論を学んでも、現場では何もできません。高卒の先輩方の方が、はるかに機敏に働いていました。
当時のJRでは、東大卒は「超特急組」と呼ばれ、いずれ現場を離れ本社で働くことが決まっていました。そのため現場の先輩たちからは「君はいつか私たちの上司になるだろう。だが、電車を動かしているのは現場の私たちだということを忘れるな」と、その言葉を強く叩き込まれました。この経験から「世の中は現場が動かして初めて動く」ということを学びました。これが私の仕事の原点です。
その後、ボストン コンサルティング グループへ転職しました。ここでは、「知りません」「やったことがありません」が一切通用しない世界で、結果がすべてだと学びました。また顧客の本当の課題を知るには、結局は現場に潜り、社員やお客さんの声を聞くしかありません。ここでも「現場がすべて」という考えが活きました。
そして、製薬会社であるヤンセンファーマに籍を移します。MR未経験者を含む多様な経歴のメンバーで独立部隊を率いました。バーテンダーや僧侶といった、製薬業界の常識にとらわれないメンバーばかりでしたが、彼らは厳しい環境で生きてきた経験から人間的な深みがあり、医師から見ても面白い存在でした。
狭い世界しか知らない人間よりも、違う観点や経験を持つ人たちが集まることで、素晴らしい相乗効果が生まれる。一人ひとりに専門分野を割り当てて教え合うことでチームは大きく成長し、「チームの作り方」や「メンバーの育成方法」を深く学びました。これらの経験が、今の私の経営者としての基盤となっています。
新薬ビジネスへの転換 第二創業期に懸ける覚悟
ーーサンファーマ社長へ就任された経緯を教えていただけますか。
小川省一郎:
お声がけいただいた当初はお断りするつもりでした。当時、私はコンサルティング業界に戻り、企業再生を手がけていました。製薬業界からも少し距離を置いていたので、今さら戻るのもどうかという気持ちがあったのです。また、サンファーマは特許が切れた「長期収載品(※)」や「後発医薬品」だけを扱っている会社だと誤解していたのです。
しかし、「既に本社は新薬ビジネスに舵を切った」と聞き、「この挑戦は面白いかもしれない」と考えが変わりました。新薬ビジネスであれば日本市場でも成り立つと考えたからです。
サンファーマはちょうど、事業内容も人材も切り替える「第二創業期」のタイミングでした。私はこれまで、課題を抱えた会社の立て直しを多く経験してきた、いわば「立て直し屋」です。この挑戦は自分に合っているだろうと思い、社長就任を決意した次第です。
(※)長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)が既に存在する、特許期間が満了した先発医薬品。
ーー仕事をするうえで、大切にされていることはどんなことですか。
小川省一郎:
私は社員に「自分のお客さんは誰かを考え、仕事をしてほしい」と常に伝えています。製薬会社で言えば、最終的なお客様はもちろん患者さんです。しかし、私たちは直接会うことはありません。では、会えるお客様は誰かというと、医師です。その医師に日々会っているのは、現場のMR(Medical Representative:医薬情報担当者)にほかなりません。
では、そのMRをお客様にしているのは誰か。それは上司であるエリアマネージャーです。そして、エリアマネージャーをお客様にしているのは部長、営業チーム全体をお客様にしているのはマーケティングチーム、というように貢献の連鎖が続いていきます。
世の中で多い勘違いは、「上司になったから偉い」と思い、メンバーに自分へ貢献させようとする姿勢です。これは貢献の向きが完全に逆だと考えています。上司はお客様(メンバー)に貢献すること、メンバーが成果を出すために働きやすい環境を整えるのが仕事です。ですから、私は社員に「社長の顔色を伺うな」と言っています。私の方を向いて仕事をしても意味がありません。みんなが向くべきは、自分の「お客様」であり、その連鎖の先にある「現場」であり、最終的に患者さんです。
JR時代に叩き込まれた「電車を動かしているのは俺たちだ」という現場のプライド。あれがすべてです。本社にいる人間は、現場の人が働きやすくなるように環境を整えるのが仕事。それ以外の価値はありません。
この考えを会社全体に浸透させ、全員がお客様のことを第一に考える会社にすること。それが、社会から本当に必要とされるサービスを提供できる、良い会社になるための唯一の道だと信じています。
会社の未来を創る源泉 すべての成長の鍵は人材

ーー改めて、貴社の事業内容についておうかがいできますか。
小川省一郎:
サンファーマ株式会社は、皮膚科学領域、オンコロジー(※2)領域を中核としてスペシャリティ医薬品事業を展開しています。
皮膚の病気は、命に直接関わらないために軽視されがちですが、患者さんの人生に大きな影響を与えます。外見に症状が現れることで社会活動に消極的になったり、周囲との関係に悩んだりする方は少なくありません。私たちの使命は、優れた新薬を通じて患者さんの苦しみを取り除き、その人らしい人生を送れるよう手助けをすることです。
しかし、ニキビですら正しい治療法が知られていない現状があります。病気に関する正しい知識を広める啓発活動にも、学会などと協力しながら力を入れていきたいと考えています。
(※2)オンコロジー:「腫瘍学」とも呼ばれ、がん(癌)や肉腫などの腫瘍の原因究明や治療法などを研究する学問分野。
ーー会社の今後のビジョンについてお聞かせください。
小川省一郎:
患者さんへの貢献を第一に、会社として成長していきたいと考えています。現在の弊社は、かつて欧米の大手製薬企業が日本に進出してきたばかりの「黎明期」にあたります。当時は小さかった企業が、25年を経て巨大企業へと成長したように、私たちも大きな未来を描いています。幸い、インドの親会社は資金が豊富で投資意欲も旺盛です。この基盤を活かし、日本の市場で大きく飛躍していきたい。これから入社する仲間には、会社が大きく成長していくダイナミックな過程を経験してほしいです。
ーービジョン実現のために、どのような戦略をお考えですか。
小川省一郎:
短期・中期・長期、いずれの視点でも鍵となるのは人材です。短期的には、最前線で働くMRの強化が欠かせません。私自身も毎週のように現場に同行し、会社全体で現場をサポートする姿勢を示しています。中期的には、幹部の育成です。私は幹部社員の評価を、そのメンバーたちからのフィードバックによって行います。幹部候補は私ではなく、メンバーのために仕事をすべきだからです。そして長期的には、採用が最も重要になります。製品やサービスよりも、まずは人材への投資を惜しみません。
ーー最後に、貴社に興味を持つ求職者へメッセージをお願いします。
小川省一郎:
弊社の環境は面白いと断言できます。チャレンジしたい人、自分の意見をはっきり言える人には最高の環境です。組織のしがらみの中でもどかしい思いをしている人は、ぜひ挑戦しに来てください。また、インドの親会社は非常に論理的で、こちらの意見を尊重してくれる文化があります。ロジックを持って主体的に挑戦したい方にとっては、大きなやりがいを感じられる職場だと思います。
編集後記
「世の中は現場が動かしている」。小川氏の言葉は、JR東日本時代に叩き込まれたこの信念に貫かれている。上司はメンバーのために、本社は現場のために。貢献のベクトルを顧客へと正しく向けた時、組織は初めて社会的な価値を生む。その言葉には、多様なキャリアで培われた確かな実感がこもる。「第二創業期」を迎えたサンファーマは、大胆なだけでなく、極めて論理的かつ人間的なリーダーを得て、新たな成長曲線を描き始めるだろう。

小川省一郎/1968年東京都生まれ、1994年東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学修了、2000年カーネギーメロン大学MBA修了。東日本旅客鉄道、ボストンコンサルティンググループを経て、ヤンセンファーマ、アボット(現アッヴィ)、アルコン、アボット、アルコンファーマ、BMSにて事業本部長や社長、その後アリックスパートナーズでパートナーを務めた後、サンファーマの代表取締役社長に就任。














