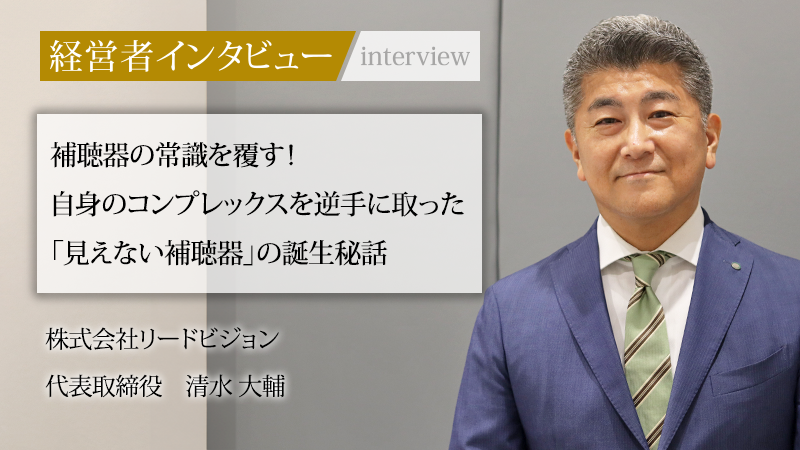
「見えない補聴器」を軸に、業界の常識に挑み続ける株式会社リードビジョン。同社は、補聴器ユーザーでもある創業者自身が難聴と補聴器というコンプレックスを原点とし、徹底したユーザー目線で製品や店舗のあり方を革新してきた。その事業は単なる機器の販売にとどまらず、日本の深刻な社会課題である少子高齢化問題の解決にも貢献する。
自身の経験を、社会をより良くする力へと昇華させ、社員一人ひとりが主役となる組織を築き上げた代表取締役、清水大輔氏に、その歩みと哲学、そして描く未来像について話を聞いた。
コンプレックスが原動力に!悔しさを使命に変えて
ーー経営者を志したきっかけについてお聞かせください。
清水大輔:
実家が小さな書店で、両親が働く姿を見て育ちましたから、漠然と経営者への憧れはありました。ただ、両親が懸命に働く一方で当時の経営は厳しく、子どもながらに大変な思いもしました。だからこそ、創業の時には社員とその家族を絶対に幸せにできる会社にしようと、固く心に誓っていました。
ーーなぜこの事業を立ち上げようと思われたのでしょうか。
清水大輔:
私は中学生の頃から耳の病気を患い、手術を繰り返す中で聴力が落ち、やがて補聴器が手放せない体になりました。当時、補聴器をつけることは大きなコンプレックスでした。職場で悪気無く言われた「耳に何つけてるの?」という一言が心に深く刺さり、「なぜメガネは良くて、補聴器はこんなに嫌な思いをしなければいけないんだ」という、社会に対する憤りに似た感情が込み上げてきたのです。
母から「人はこの世に何かしら役割があって生まれてきている」と幼いころから言われていたことから、補聴器のイメージを変えることが自分の役割ではないかと販売店について調べることにしました。あるメーカーに相談したところ、「あなたのように、ご自身が補聴器を使いながらお店を始める方は、全国で他にいません」と言われました。その言葉を聞いた瞬間、これまでの苦しみはこの事業を始めるためにあったのだと、自分の使命と確認しましたし、そうであれば同じ悩みをもつ多くの方の受け皿にならなければと、人口の多い東京での創業を決意しました。コンプレックスの塊で自暴自棄だった私が、初めて自分に価値を見出せた瞬間でした。
緻密な計画で「補聴器のイメージ」に変革を

ーー起業を決意されてから、どう準備されましたか。
清水大輔:
まずは起業の仕方、事業の作り方を学ぶことから始めました。当時は富山で会社勤めをしながら、通信教育の起業家養成スクールで学び、休日には東京に何度も足を運び事業計画を固めていきました。
ーー貴社のオリジナル製品には、どのようなこだわりが込められているのでしょうか。

清水大輔:
“日本一補聴器が嫌いな男”を自認していましたから、とにかく「見えない補聴器」を作りたいという思いがすべてでした。ドイツのメーカーに直接その思いを直接伝え、共感してくれた日本の担当者と共に企画を進め、自社オリジナル製品として世に送り出すことができたのです。
ーー店舗づくりで心がけたことはありますか。
清水大輔:
私自身、人目を気にして補聴器店へ通うことに抵抗がありました。その経験から、創業当初はお客様のプライバシーを重視して路面店ではなくビルの2階以上に出店していました。
しかし、10年ほど前、大手百貨店に出店する際に、百貨店の社長自ら「これからの補聴器店は、もっとオープンであるべきだ」とご指摘いただいたのです。この一言が、私の固定観念を打ち破ってくれました。内装を開放的なデザインにしたところ売上が大きく伸び、補聴器のイメージを変えるには、隠すだけでなくオープンにする視点も不可欠だと気づかされました。今では、お客様が気軽に集える多目的スペースを併設した店舗も展開しています。
リードビジョンが「働きがい」と「成長」を生む仕組み

ーー組織が大きく変わる転機について教えてください。
清水大輔:
創業から10年ほどは、明確な羅針盤がないまま、手探りで航海を続けるような日々でした。その状況を変えるきっかけとなったのが、京セラ創業者・稲盛和夫さんの「アメーバ経営」との出会いです。各店舗が独立採算で経営を行うこの仕組みを導入した目的は、社員一人ひとりが自社の経営者として、自律的に動ける組織をつくることでした。
ーーアメーバ経営の導入によって、社員の変化はありましたか。
清水大輔:
全社員に、まぎれもない経営者意識が芽生えました。各店舗の店長は、毎月の売上から経費、時間あたりの利益までを自ら算出します。数字の裏側にある意味を理解し、どうすればもっと効率的に、もっとお客様に喜んでいただけるかを一人ひとりが真剣に考えるようになったのです。結果として無駄な残業も減り、今の時代に合った働き方にも繋がっています。
ーー貴社ならではの組織文化は、どう育んでいますか。
清水大輔:
私たちは、良好な人間関係は自然に生まれるのではなく、意図的な「仕組み」によって育まれると考えています。たとえば月1回の食事会では、他店他部門のメンバーと関係を構築するために担当者が予め席を決めています。こうした地道な取り組みが「従業員の仲が良い」という社風につながり、新卒社員の高い定着率も実現できているのだと思います。
「日本の未来」を共に創る、リードビジョンの展望

ーー今後の展望についてお聞かせください。
清水大輔:
私たちはミッションとして「日本中の60歳以上を元気にする」と掲げています。そのためにもまずは補聴器がメガネのように抵抗なく使われる社会の実現を目指しています。
この価値を日本中に広めるため、まずは発信力のある東京で直営店展開を加速させ、補聴器の普及率を現在の約15%から30%に引き上げることが目標です。そして地方については、私たちの理念に共感してくださるパートナー企業様と共に、フランチャイズ展開を進めていきます。
ーー貴社の事業が持つ、社会的意義とは何でしょうか。
清水大輔:
私たちの仕事は、日本の最も大きな課題である少子高齢化問題に、真正面から貢献できると確信しています。“聞こえ”をサポートすることは、認知症予防やシニア世代の社会参加を促し、結果として国の医療費・介護費の抑制に繋がります。また、まだまだ元気なシニア層が働き続けられる環境を提供することで、労働力不足という問題にも貢献できます。この社会的意義の大きさが、今の若い世代に強く響いていると感じます。
ーー最後に、どんな仲間と未来を創りたいですか。
清水大輔:
何よりもまず「素直」な人ですね。うまくいかないときに他人のせいにせず、自分の課題として受け止められる素直さ。そして、チームで成果を出すための「協調性」。私は特別な経営学を学んだわけではなく、ゼロから素直に学び、実践してきただけです。まっさらな状態で物事を吸収できる人なら、必ず大きく成長できる。そんな仲間と共に、日本の未来に貢献していきたいと考えています。
編集後記
自らのコンプレックスを、社会課題を解決する事業へと昇華させた清水氏。その言葉の端々からは、経験者だからこその強い覚悟と、利用者への深い愛情がうかがえる。特筆すべきは、その情熱を「アメーバ経営」という具体的な仕組みに落とし込み、社員一人ひとりが主役となれる組織文化を築き上げている点だ。個人の課題意識を、社会を動かす力に変える。同社の挑戦は、自らの仕事に大きな意義を見出したいと願う多くの若者にとって、キャリアを考える上での大きな道しるべとなるだろう。

清水大輔/1969年富山県生まれ、富山商業高校卒。27歳の時、耳の病気の後遺症で補聴器を使い始める。自身のコンプレックスをバネに、補聴器のイメージを変え、メガネのような身近なツールとするべく、2002年に上京し株式会社リードビジョンを設立。














