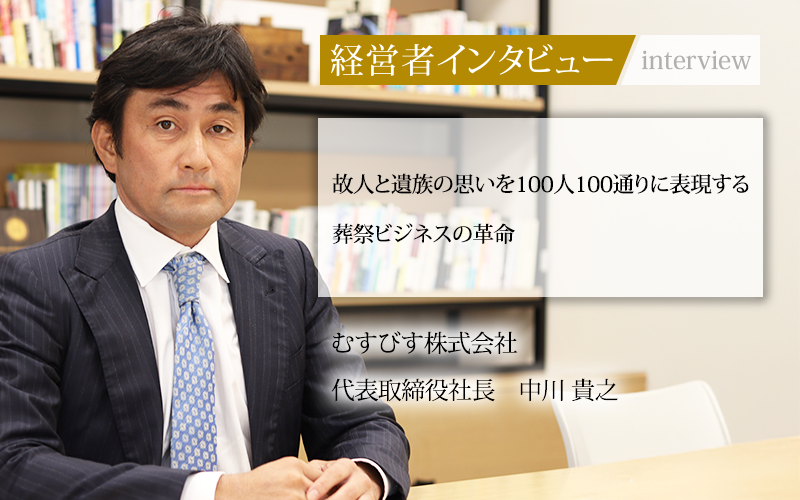
葬儀に参列しても故人の人となりに触れる場も時間もなく、遺族の気持ちも内に秘められたまま。そんな葬儀とは一線を画し、故人の思い出と遺族の気持ちを汲み取って最良の葬儀を提案するむすびす株式会社。ブライダルからフューネラルの世界に転身した中川貴之代表取締役社長に葬祭業界のニュースタイルについて話を聞いた。
ブライダル事業の創業パートナーから葬祭業界の創業者への転身
ーー起業までのいきさつについて教えてください。
中川貴之:
大学卒業後は電子部品メーカーに就職しましたが、実家が小規模ながらも会社を経営していたため、「働くこと=経営」というイメージを抱いていました。そのため、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの創業時に声をかけられたとき、迷わず参画しました。1998年10月に創業し、2001年12月12日にナスダック・ジャパン(現:東京証券取引所JASDAQ)市場へ上場を果たしています。その後、数カ月して退職し、自ら会社を立ち上げることにしました。
ーー葬祭業界を選択した理由は何だったのでしょうか?
中川貴之:
ブライダル業界に携わる中で、ライフイベントへの関心が深まりました。当時、挙式スタイルが大きく変わりつつありましたが、同時に葬儀にも変化の波が押し寄せていました。私はその変化を先取りし、新たな形を模索したいと考えるようになったのです。
そんな折、立地や外観に課題があり、業績が低迷していた結婚式場に出会い、必要最低限の工事で葬儀会館にリニューアルしました。しかし、地元の方々に受け入れてもらうまでには時間がかかり、当初は集客に苦戦する状況が続きました。
故人の個性を大切にした葬儀を提案し、遺族の思いを形にする

ーーそうした苦境からの転機は何でしたか?
中川貴之:
ある時、全国紙の取材を受け、その記事がきっかけでテレビの密着取材へとつながりました。この放送がとくに50代以上の女性の関心を強く引いたのです。おそらくこれまでの葬儀とは違う、故人の人柄や趣味、ご遺族の気持ちを汲み取った葬儀の様子に視聴者が興味を持ったのではないかと思います。これを機に問い合わせが急激に増え、懸念されていた経営も徐々に軌道に乗り始めました。
ーー「葬儀の変化を先取りする」とは、具体的にどのようなことですか?
中川貴之:
葬儀に参列しても、故人の生前の様子や遺族の思いが何も伝わらないまま終わってしまうことが多く、もどかしさを感じていました。亡くなった方が遺したものや、見送る方々の大切な思い出に寄り添い、それを表現する葬儀があっても良いのではないかと考えたのです。
つまり、100人の方の葬儀があれば、それぞれの個性や家族関係、友人関係に応じて、100通りのスタイルがあって良い。それを具現化しようとするのが、私の理念でした。
この「100通りの葬儀」は、提案自体はお客さまの興味を引きましたが、従来通りの一般的な段取りで行われるお葬式を選ぶご遺族がほとんどでした。しかし、葬式が終わると「もっと故人の思い出を形にしたお葬式にすれば良かった」と後悔される方が多かったですね。
そこで、弊社ではサプライズの要素を取り入れた葬式を考えました。確かに、葬儀の場でサプライズという提案に驚かれるご遺族が多かったですが、式が終わると「とても良かった」と喜んでくださることが増えてきたのです。
現在では、弊社のWebサイトで葬儀の様子をご覧いただいたうえで利用される方が多く、ご遺族のお話を丁寧に汲み取りながら、お互いに意見を交換し、思い出に残る葬儀を一緒につくり上げています。

Webマーケティング主体の営業戦略でお客さまの安心と信頼につなげる
ーーお客さまとの接点はどのようにされていますか?
中川貴之:
Webサイトの有効活用です。弊社は、葬儀の費用、祭壇の飾り方や式の進め方、お布施のことなど、お客さまが知りたい情報をWeb上でわかりやすく開示しています。
質の高い情報をWebサイトで提供したうえで、電話でのお問い合わせに親切に対応することがお客さまの安心と信頼につながっています。今後もIT系のビジネスノウハウを蓄積し、Webマーケティングのさらなる体系化を図りたいですね。
(※)葬儀の様子などはこちらをご覧ください。
・公式サイト
・YouTube
・Instagram
・TikTok
労働集約型の葬祭業界に必要なのは人事制度の整備とリブランディング
ーー葬祭業界にどのような課題を感じていますか?
中川貴之:
葬祭業界全体の課題は人材の確保と育成、そして人事評価です。
お客さまのお気持ちを汲み取って飾り付けや段取りを担うスタッフ、不安や疑問を抱えるお客さまとの最初の接点となるコールセンターのスタッフ。いずれも葬儀事業のキーとなる人材です。これらの人材の確保と育成は喫緊の課題です。葬祭業のイメージ改革も含めて取り組みが必要だと考えています。
もう一つの課題は、人事評価制度の整備です。ご遺族に満足していただける葬儀を行うために必要な知識やスキルを体系的に整理し、各スタッフが自分の力量を正しく把握できる制度の構築は急務です。
目標が曖昧なままではモチベーションを維持するのは難しいですし、評価制度が明確でないと人材の定着も困難になるでしょう。この点は、葬祭業界全体で考えるべきものだと感じています。
ーー最後に、貴社の事業と葬祭業界の今後についてお聞かせください。
中川貴之:
日本の総人口は減少していますが、高齢者の数は減少していません。2050年の葬儀件数は2015年の1.8倍に達すると予測されているので、現在の弊社の1都3県の受注件数約2500件を、1万件まで上げていきたいですね(※2024年10月)。
また、これまでの葬儀会館に縛られた葬儀のあり方からの脱却も目指しています。たとえば、人口減少によって使われなくなった施設を活用し、葬儀を執り行うスタイルを定着させ、より広いエリアで心に残る葬儀をお手伝いできる会社にシフトしたいと思っています。
大切な方との最後のお別れの場を、ご遺族が心から満足できるものにするために、葬儀のあり方をリブランディングしていきたいと考えています。
編集後記
これまでの葬儀の慣習やスタイルにとらわれず、葬祭会館という場所的制約からも自由になり、それぞれの故人と遺族に最もふさわしい葬儀を提案する。そのため、ウェブマーケティング主体の事業展開を進めている、むすびす株式会社の中川社長。この取り組みは、葬祭業界全体のイメージ改革だけでなく、高齢化が進む日本における葬儀ビジネスそのものに、大きな変革をもたらす可能性があることを強く実感させるものである。

中川貴之/1973年、東京都生まれ。1996年明治大学政治経済学部卒業。結婚式プロデュース会社、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。役員として株式上場に携わる。2002年10月葬祭業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。














