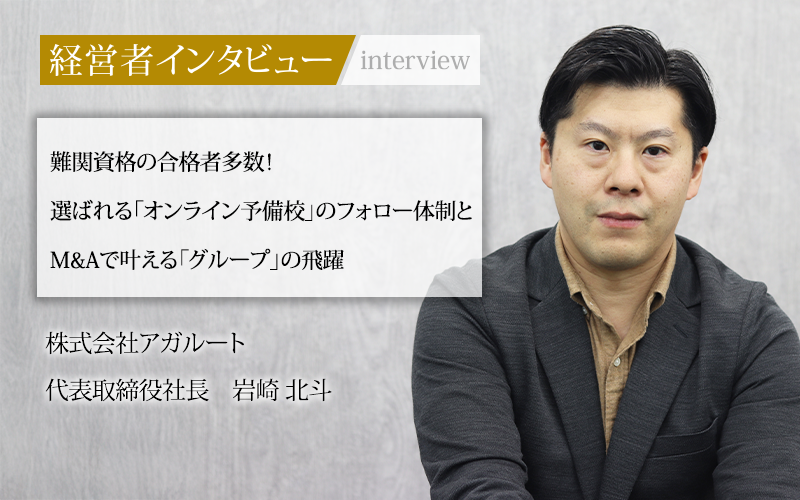
2013年に設立された株式会社アガルート。司法試験をはじめとする、国家試験・検定試験のオンライン予備校「アガルートアカデミー」を運営する企業だ。Webを活用した教育事業は多岐にわたるほか、M&Aを機に人材紹介業やシステム関連事業にも進出している。今回は、代表取締役社長の岩崎北斗氏に、創業のきっかけや事業の強み、今後の展望についてうかがった。
予備校講師が見つけた、「時間」を犠牲にしない合理的な講義の形
ーーまずはご経歴をお話しいただけますか。
岩崎北斗:
早稲田大学法学部に入学後、当時「法科大学院の卒業生の7割は弁護士になれる」と聞いたことから、法科大学院入学を目指して司法試験の予備校に通い始めました。弁護士は、「かっこよくてラクで高収入な仕事」という漠然としたイメージがあり、それに7割の高確率でなれるのであれば、なんてラッキーなんだと思いました。
しかし、そんなにうまい話があるわけもなく、司法試験の合格率は当時25%程度でしたし、何よりも司法試験受験後、法律事務所への就職活動を始めてみると、実際には、弁護士業は想像以上に多忙を極める仕事だということが徐々にわかってきました。私は基本的に怠け者なので、自分に弁護士業は無理だと考え、方向転換することにしました。
具体的には、急遽民間企業への就職活動を始め、ネット銀行の法務部から内定をいただくことができたことから、そこに勤務。また、運よく司法試験に合格でき、順位も50位くらいと悪くなかったことから、アルバイトをしていた予備校から声を掛けられ、講師としても兼業をすることになりました。
一般的には、法科大学院を卒業し、司法試験に合格した人は「司法修習」という研修期間に入るのですが、私は異なる道を選んだことになります。
メガバンク系の子会社であるネット銀行で大企業やサラリーマンのイロハにふれ、講師を勤めていた予備校でオーナー中小企業ならではの経営術を学べた経験は、自身の経営やBtoB事業にとても役立っています。
ーーどういった経緯で貴社を設立したのでしょうか?
岩崎北斗:
約1年後、時間的に兼業が難しくなってきたため、よりやりがいのある講師業を選択しました。予備校講師として4年間働き、その後に独立しました。「自分が納得できる働き方をしたい」というのが最大の理由です。
毎日のように教壇に立っていた頃は、時間を拘束されている感覚が否めませんでした。決まった時間に校舎に行って講義を行わなければならないので、長期の旅行などに行くこともできません。講義内容も毎年ほぼ同様なので、無駄が多いとも感じていました。一方で、受講生側も、社会人などは仕事の都合で講義を欠席せざるを得ないことも多いのが実態です。講師は時間を、受講生は学習の機会を失っているのです。
そこで、自分がオーナーになれば非合理を変えられると考え、起業することにしました。具体的には、共同創業者と3ヶ月働き、9ヶ月ゴルフをして遊ぼうという目標を立て、オンライン専業の予備校を設立することにしました。
いざ起業してみると、比較的順調に事業が成長し、従業員も増えていきました。そのような中で企業として社会的責任が伴ってきており、当初の理想像とは正反対に、1年中ほとんど仕事をして過ごすという生活を送っています。
「効率的なオンライン学習×手厚いフォロー」のハイブリッドが強み

ーー事業の強みを教えていただけますか。
岩崎北斗:
メイン事業は、資格試験・国家試験の受験者を対象とした「アガルートアカデミー」というオンライン予備校・通信講座の運営です。医学部・看護学校に特化した「アガルートメディカル」というオンライン予備校などもあり、「オンライン教育」を軸にプラットフォームを構築しています。
受講生はいつでも・どこでも講義を見られて、自分のペースで勉強を進められるというのがオンライン配信型の魅力です。基本はすべてオンライン上で完結するように、質問制度や添削システムも自社開発していますが、「コミュニケーション」は人で補完することを意識しています。
授業後に質問の順番待ちが発生するオフライン型(通学型)よりも、受講生フォローはむしろ手厚いといえるでしょう。たとえば、勉強が進まない人や質問がある人は「バーチャル校舎」に集まり、実際にその場にいる感覚で講師と交流しています。オンライン配信に一本化するのではなく、フォローアップ体制に注力した仕組みが合格率の高さにつながり、多くの生徒に選ばれているのだと思います。
ーー集客方法や講師の採用基準もうかがえればと思います。
岩崎北斗:
Web広告をはじめ、比較サイト、SNS・YouTubeの運用、SEOなど、Webで可能なことはすべて実行しています。受験ノウハウなどを配信している公式YouTubeは特に反応が良く、今後も伸ばしていきたい領域ですね。
Webだけでなく、TVCMや交通広告などのマス広告にも取り組んでいます。こちらは直接的な集客というよりは、ブランディングや認知拡大といった効果を見込んでいます。
講師の採用においては、講義の分かりやすさや熱意に加え、コミュニケーション能力を重視しています。弊社では、教材チームと映像チームが協力して一つの講座を作り上げるので、社会人としてのコミュニケーション能力は欠かせません。
「単体」よりも「グループ」の可能性でさらなる飛躍を
ーーM&Aにも注力されていますが、成長事例をお話しいただけますか?
岩崎北斗:
2019年頃からM&Aに積極的に取り組み、教育関連だけでなく、人材関連システム関連、マーケティング関連の企業がグループに加わりました。
基本的には経営者の方にそのまま残っていただき、大きな組織変更もせず、必要な機能を相互に提供し合う「自律分散」が弊社のスタンスです。必要な機能という意味では、弊グループには法律事務所もあり、コンプライアンスや労務面、バックオフィスのサポートで経営者の方に喜ばれるケースも多いです。
2020年にグループインしてもらった転職エージェント業の「株式会社ファンオブライフ」(以下「ファンオブライフ」)は、現在に至るまで、売上・利益ともに約10倍に成長しています。もっとも、決して順風満帆というわけではありませんでした。
M&Aが成立してしてまもなく、新型コロナウイルスが蔓延し、緊急事態宣言が出されるなどの非常事態が発生しました。一般的に企業は、非常事態下では採用活動をすべて又は一部停止します。
転職エージェントは、クライアント企業の求人をお預かりして、転職者とマッチングしてフィーを頂くビジネスですので、企業が採用活動を停止してしまうと、事業が成り立ちません。コロナ禍では転職エージェントをはじめとした人材業界は大打撃を受けました。
このような危機的な状況を乗り越えるため、私が銀行と交渉していわゆるコロナ融資を調達するなど、キャッシュフローを補完しました。また、コロナ禍で、リモートワークを導入しましたので、それに伴う職業安定法への適合などリーガル的な整理も弊グループの法律事務所がバックアップしました。
2022年以降コロナ禍が明けて経済活動が再開されると、一転して人材不足の企業が増えました。人材不足は、転職エージェントの事業には追い風になりますので、2022年以降、ファンオブライフの事業は成長を続けています。
一方コロナ禍では、いわゆる巣ごもり需要を受け、弊社の祖業であるオンライン講座の需要が急増しましたが、需要の先食い的な要素も強かったため、コロナ禍が明けると事業の伸びが緩やかになってきました。このように、弊社とファンオブライフは、事業の停滞と成長が真逆であるため、事業ポートフォリオとしては、相互補完のような関係になっているといえます。
ーー今後の展望をお聞かせください。
岩崎北斗:
私は、創業オーナー兼経営者ですので、その2つの側面から考える必要があります。経営者としては、「企業価値の向上」が最重要のミッションです。ファンオブライフの成功事例からも、仲間を増やしてグループ全体でスケールアップすることが継続的な成長に効果的だと実感しました。今後もM&Aを進めつつ、「教育×IT」と周辺領域を強化したいと思います。
一方で、創業オーナーとしては、事業承継に目を向けなければいけません。企業は、その社会的責任を果たすため、サステナブルに成長していくことが何よりも重要ですので、事業承継は早ければ早いほどいいと考えています。ちょうど自身が40歳ですので、40代を一つの区切りにしようというのが現在の考えです。
編集後記
「オンライン空間」に無機質なイメージを抱く人は少なくない。学習の効率化を図る過程でデジタルに依存しすぎず、画面の向こうに「人」の体温があるシステムを構築したアガルートは、オンライン講座の正解に辿り着いたといえる。M&Aにおいて、「意気投合した『人』との付き合いを大切にしている」と語った岩崎社長も印象深い。

岩崎北斗/1984年生まれ。2007年に早稲田大学法学部を卒業。2009年、慶應義塾大学法科大学院既修者コース修了。同年に(新)司法試験合格、大手予備校で司法試験講師として登壇。2013年、株式会社アガルートを設立。代表取締役に就任。














