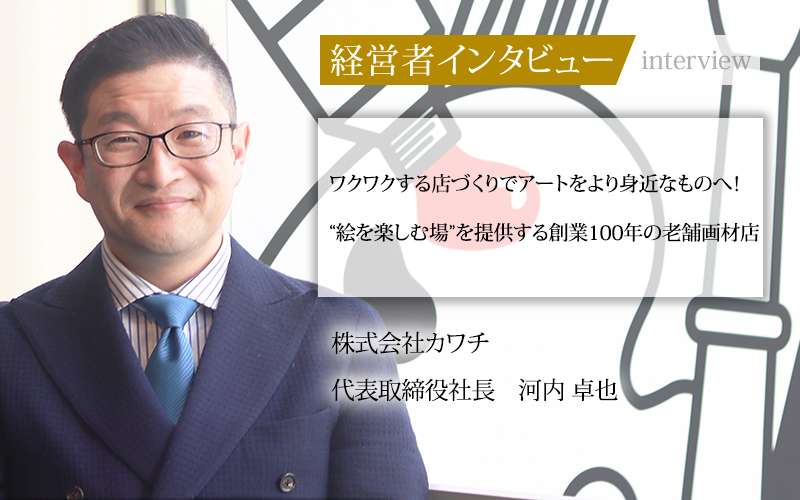
株式会社カワチは、大阪の主要エリアに3店舗ある画材専門店を運営している会社だ。同社は1920年の創業以来、100年以上にわたり、プロのアーティストから初心者の方まで幅広く支持されている。代表取締役社長の河内卓也氏に、距離を置いていたアートに興味を持つようになった経緯や、デジタル時代の画材店経営にかける思いなどについてうかがった。
100年近く続いてきた画材店を引き継ぐことのプレッシャー
ーーまずはこれまでのご経歴からお聞かせください。
河内卓也:
先代である父から「違う釜の飯を食べてこい」と言われ、修行のために同じ小売業界で働きました。お客様からのクレーム対応をしていたので理不尽なことも言われましたが、おかげで度胸がつきましたね。今の仕事でクレーム対応をする際に臆せず堂々と振舞えるのは、このときの経験があったからだと思っています。
ーー家業を継ぐことは以前から意識していたのでしょうか。
河内卓也:
姉が2人いる末っ子長男のため、子どもの頃から私が継ぐものだと思っていました。ただ、絵が下手なことがコンプレックスで、画材屋を継ぐことにプレッシャーを感じていましたね。
学生時代、私が描いた絵を見た先生が眉間にしわを寄せたのを見て、「画材屋の息子なのに絵が下手だと思われた」と勝手に思い込んでしまったのです。この日を境に絵が嫌いになってしまい、アートとは距離を置くようになりました。
ーーそのような経験があったのにもかかわらず、知識を身に付けられた方法を教えてください。
河内卓也:
お客様から受けた質問に対し、一つひとつメーカーに確認して回答していくうちに、自然と知識が身についていきました。また、お客様の作品を見る機会が増え、自然と興味が湧くようになり、美術館へ足を運ぶようになったのです。このように仕事にまつわる知識を増やすには、実務を通じて勉強を重ね、自分自身が興味を持つことが一番の近道だと思います。
デジタル化時代だからこそ際立つ手書きの魅力。アートを楽しむ空間を意識した店づくり

ーーアート分野でもデジタル化が進む中で、画材店の存在価値はどこにあるとお考えですか。
河内卓也:
アートやデザイン、漫画業界でデジタル化が進む中、あえて手書きにすることで、他者との差別化になります。そのため、アート業界のデジタル化が進んでも、画材店のニーズはこれからもなくならないと考えています。
また、絵具やキャンバスなどを使って絵を描く場合、画材店はデジタルにはない体験を与えられます。それは、画材の使い方や用途に合った画材を店員から直接聞けることです。さらに画材は質感が重要なので、実際に手に取って試せるのもポイントですね。このようにデジタル化が進めば進むほど、実店舗の価値は高まっていくと考えています。
ーー画材を購入する方が減少する中で、経営面で工夫している点について教えてください。
河内卓也:
弊社ではいち早くPOSシステム(※)を導入し、データに基づいた仕入れを行っています。画材は色のバリエーションが多く、需要がない商品は売れ残ってしまうため、在庫効率が悪くなりがちです。そのため、データを活用して不良在庫を減らし、効率的な運営を意識しています。なお、店長クラスのスタッフには店舗の売上や利益状況を公開し、各自で利益を出す工夫をしてもらっています。
また、私たちが特にこだわっているのが、店内のディスプレイです。私自身、アートに関してはもともと素人だったので、初心者の方が画材の専門店に入るハードルの高さがよくわかります。そのため絵のサンプルやPOPをたくさん並べ、普段あまり絵を描かない方も入りやすい雰囲気づくりを心がけています。さらに、毎月ディスプレー賞を設け、店内のPOPや展示を工夫しています。
(※)POSシステム:販売実績や在庫情報をリアルタイムで確認できるシステム。
丁寧な接客と実際に画材を使う方を意識したラインナップ
ーーその他に行っている業務改善策を教えてください。
河内卓也:
現在力を入れているのが、業務のDX推進です。従来の紙のポイントカードをアプリに移行し、勤怠管理をデジタル化するなど、業務の効率化を進めています。そして効率化により捻出した時間を、売り場の改善や接客の質の向上に充てています。
また、この他に業務改善策として行っているのが、商品選定と提案力の向上です。私たちが特に心がけているのが、お客様一人ひとりに合った商品を提案することです。そのため従業員には、誰にこの商品を買ってもらいたいか想像しながら商品選定をするよう伝えています。
ーー来店されるお客様にはどのような方が多いのですか。
河内卓也:
遠方からお越しいただくお客様が多いですね。「美術館の後に立ち寄るのを楽しみにしています」というお声をいただいています。また、「来店を機に初めて絵画に挑戦してみました」という方や、「ここに来ると創作意欲が湧く」と言われる方もいらっしゃいますね。これからも「用事がなくても何となく足が向いてしまう場所」であり続けたいと思っています。
ーー新商品開発や個展の開催などについてお聞かせください。
河内卓也:
アーティストの方が描いた絵をカレンダーやキーホルダー、オリジナルスケッチブックなどに商品化し、少ロットで販売しています。さらに若手アーティストの方の作品を多くの方々に見てもらえるよう、定期的に個展も開催しています。こうしてみなさんがアートに触れる場を提供し、もっと多くの方に興味を持っていただきたいと思っています。
画材店の3代目が考えるこれからの人とアートの関わり方
ーー今後さらに店舗を拡大する予定はあるのでしょうか。
河内卓也:
アパレルや雑貨店などが立ち並ぶ中、アートは差別化になるという理由でショッピングモールへの出店のお話しをいただくことも多いです。ただ、出店のオファーをなかなか引き受けられないのが現状ですね。
その理由は、画材店の経営は収益性が低い割に、コストがかかるためです。たとえば絵具の中にはあまり売れない色もありますが、必要とされるお客様がいる以上、店頭に並べる必要があります。また、額縁は単価は高いものの、それほど売れるものではないので、回転率が悪いのです。
また、お客様に詳しい商品の説明ができるようスタッフが常駐しているため、人件費もかかります。そのため、今は店舗の拡大よりも業務の効率性を高め、利益を確保することを最優先にしています。
ーー最後にアート業界の未来についての考えをお聞かせください。
河内卓也:
AIによって多くの仕事が代替されていく中で、一から新しいものを生み出すクリエイティビティーが重視されると考えています。そのため、柔軟な発想力を養えるアートは今後注目されることでしょう。
また、絵を描くことは脳の活性化につながるので、ヘルスケアの分野でも注目されると思います。アートが趣味の域を超えて、人々の健康や創造性を養う重要な役割を果たしていくのではないかと期待しています。「カワチさんがなかったら困る」と言ってくださるお客様のために、これからも精進していく所存です。
編集後記
絵が上手くない自分が、画材店を引き継ぐことに引け目を感じていたという河内社長。そんな河内社長だからこそ、初心者の方の気持ちを汲むことができ、現在の誰もが気軽に入りやすい店づくりにつながっているのだと感じた。株式会社カワチはこれからも直接アートに触れる場を提供し、多くの方に絵を描く楽しさを伝え続けていくだろう。

河内卓也/1973年兵庫県生まれ。甲南大学経営学部卒。マツヤデンキに入社し2年間修行した後、カナダ・モントリオールへ留学。その後株式会社カワチに入社し、2016年に社長就任。














