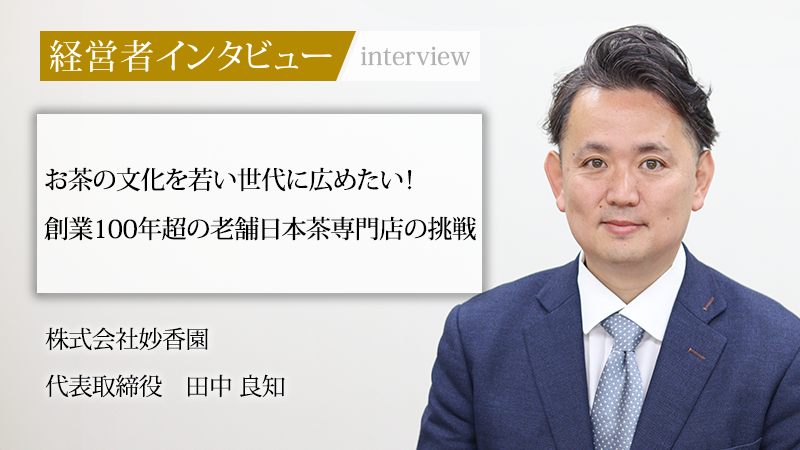
日本国内のお茶市場では、消費構造の変化が顕著である。ライフスタイルの変化に伴い、手軽なペットボトル飲料の需要が拡大する一方、茶葉の消費は縮小傾向にあるのだ。そんな現状に対して、「このままでは急須でお茶を淹れて飲む文化が失われてしまう」と危機感を抱いているのが、株式会社妙香園の代表取締役である田中良知氏だ。1916年に名古屋で創業して以来、100年以上お茶の販売を続けてきた老舗が、文化継承のためにどのようなチャレンジをしているのか、話を聞いた。
幼少期に祖父から帝王学を学び、コロナ禍で社長に就任
ーーご経歴からお聞かせください。
田中良知:
私が生まれた頃は、祖父が妙香園の社長をしていました。長男である父と祖父は2人ともお茶への思いが非常に強く、意見が衝突して喧嘩しているのを、幼い頃よく見ていました。そこで父は独立して東京を拠点に新たな会社を興し、名古屋では祖父と母と私と弟で暮らすようになったのです。そのような背景から、祖父からは「良知が妙香園を継ぎなさい」といつも話をされていました。
祖父は厳格かつ一徹な人で、弟にはなんでも買い与える一方、私には「お前には会社があるのだから、我慢しろ」というような人でした。いま思えば、その頃から帝王学を教えていたのかもしれません。
妙香園に入社したのは、高校を卒業してすぐのことです。最初の2年は店舗で働き、それから営業部に入りました。その後は工場の製造部門に移って、お茶のパッケージなど資材の受発注や包装、発送などの責任者を2年ほど担当し、役員、専務を経て、2020年の3月に社長に就任したという経緯です。
ーー社長に就任されたときには、どのような心境でしたか。
田中良知:
就任した2020年はいわば「コロナ禍元年」だったので、とんでもない時期に社長になってしまったなというのが当時の正直な気持ちです。ただ、店舗を閉めてしまったら事業が立ち行かなくなると考え、「とにかく開け続けよう」と決断しました。そこで、就任直後の4月1日には栄の店舗をあえてリニューアルして、スタンドカフェ形式の「MYOKOEN TEA STORE」をつくったのです。大変な時期だからこそ、あえてそうした挑戦に踏み切れたので、コロナ禍は必ずしもネガティブな影響ばかりではなかったと感じています。
また、「新しいお客さまを取り込もう」と意識し始めたのもその頃です。20代の方々にとって「お茶を飲む文化」の入り口になることを目指すようになりました。
柔軟な考え方を取り入れ、新たな顧客層の獲得に成功

ーー具体的にはどんな取り組みをされましたか。
田中良知:
実は社長就任前から、お茶を使ったスイーツやドリンクの開発、ワンコインで買える小ぶりでかわいいパッケージ茶の発売など、取り組みは継続的に行っていました。これは、ある企業の社長から「どうしてお茶のラテを出さないの?」と言われたのがきっかけです。「あなたたちなら人気のカフェチェーンよりもおいしくつくれるでしょう。そこは柔軟に考えないと生き残れないよ」と。そう指摘されて、「ああそうか!」と納得し、スイーツ開発などに取り組むようになりました。
そういう種まきがあった上で、最後に拍車をかけたのが「MYOKOEN TEA STORE」のオープンです。おかげさまで弊社の顧客層が大きく変わり、それまで50代から70代が中心だったものが、今では20代、30代の方にも来ていただけるようになりました。SNS上でも「妙香園」について投稿されることが増えています。
ーー現在の貴社の強みは何でしょうか。
田中良知:
「合組(ごうぐみ)」、つまりお茶のブレンドと「ほうじ茶」です。
一般的に「ブレンド」というと「ストレートよりお値打ちのもの」というイメージでしょう。しかし、私たち妙香園の考えは全く逆です。「合組」こそ、茶葉の可能性を最大限に引き出し、お客さまに「妙香園ならではの味」を届けるための、最も重要な工程だと考えています。「妙香園だけのオリジナルのお茶」をつくり、それを愛してくれるお客さまの心をつかもう、という戦略をとっているため、合組には非常にこだわっています。
また「ほうじ茶」も弊社の強みです。戦後間もない頃から名古屋で一番の繁華街・栄の路面店でほうじ茶を煎っており、その後は名古屋駅と栄の地下街で煎っていて「名古屋といえばこのお茶の香り」と認知されているのが強みですね。
「急須でお茶を飲むのはかっこいい」というイメージを創出したい

ーー今後、新たに目指す目標はありますか。
田中良知:
1つは、「名古屋はお茶どころである」というブランディングの確立です。名古屋はかつて尾張藩の城下町として発展し、茶道が盛んでした。そのような背景から「日常生活の中で頻繁にお抹茶を飲む地域」として、金沢、松江にも引けを取らないという自負があり、それをもっと明確にブランディングしていかなければと考えています。
もう1つは、お茶のイメージを高めることです。「紅茶やコーヒーを自宅でこだわって淹れている」と聞くと、かっこいいイメージがありますよね。しかし、「お茶を急須で淹れている」と言われても、特にかっこいいとは思わない人が多いでしょう。私はそれを変えたいのです。「趣味はお茶です」というのが「かっこいい」と感じられるようにしたいと、業界各社の皆さんにも呼びかけているところです。
インバウンドも重要ですね。近年、海外からの注目がお茶に集まっていて、抹茶は世界的に品薄です。ただ、ほうじ茶はまだ知名度が低いので、海外に売り出したいというビジョンがあります。先日やっと、北米のAmazonに商品を並べられる目処が立ちました。ヨーロッパからも、いくつか引き合いをいただいているところです。
弊社には、「茗茶潤心(めいちゃじゅんしん)」という社訓があります。「いいお茶は人の心を潤す、人と人をつなぐ接点になれる」という意味です。これからも、妙香園にしかないお茶をお客さまに届けていきたいですね。
編集後記
近年、確かにペットボトルのお茶はよく手にするものの、急須で淹れる機会は減ってきたと感じる。一方で、抹茶ブームは世界的に加熱中だ。お茶の楽しみ方が多様化する現代にあって、ほうじ茶を武器に新たな市場を開拓しようと意気込む田中社長。伝統や文化をどのように未来へつないでいくのか、期待が膨らむインタビューだった。

田中良知/1979年、愛知県名古屋市生まれ。名古屋学院高校(現:名古屋高校)卒業後、株式会社妙香園に入社。直営店舗勤務から営業部を経て、取締役本社工場長に就任。その後は専務取締役から2020年に代表取締役に就任する。地域振興にも尽力し、「あつた宮宿会」(副会長)や「金山駅前まちそだて会」(初代会長)の立ち上げに携わった。














