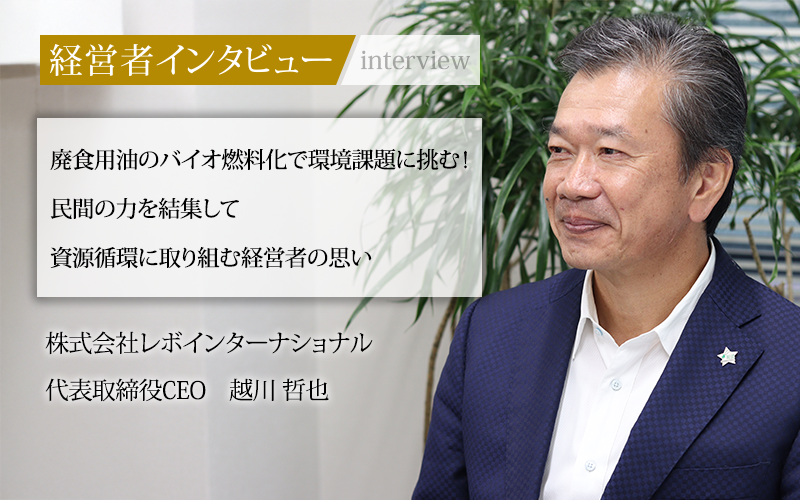
自動車や暖房器具の燃料の元として使われてきた石油。昨今では石油の燃焼時に大量の二酸化炭素が排出されるとして、環境への負荷が問題視されている。そんな中、使用済みの食用油(以下、廃食用油)を活用し、環境への負荷が少ないバイオ燃料事業を行っているのが、株式会社レボインターナショナルだ。廃食用油のバイオディーゼル燃料化に興味を持ったきっかけや、環境保護への思いなどについて、代表取締役CEOの越川哲也氏にうかがった。
バイオ燃料の開発を始めたきっかけ。起業の決め手となった震災での出来事
ーーバイオディーゼル燃料に興味を持ったきっかけについてお聞かせください。
越川哲也:
私はもともとレーサーを目指し、レーシングドライバーの松本恵二が運営する会社に勤めていました。そのときに京都大学の清水剛夫教授(当時)から「レーシングカーに廃食用油からつくったバイオ燃料を使えるか試してほしい」と依頼されたのがきっかけです。
その話を聞き、当初は「天ぷら油から車の燃料をつくれるのか」と驚きましたね。そこから廃食用油のバイオディーゼル燃料化に興味を持ち、清水教授のもとで研究開発を始めたのです。
ーー起業に至った経緯を教えてください。
越川哲也:
会社のオーナーである松本が引退することになり、自分の行く先を模索していた頃、阪神淡路大震災が発生しました。私は、以前土木の仕事をしていたことから、重機の運転ができたため、復興ボランティアに参加しようとしました。
しかし、地震で道路が分断され、重機を動かすための燃料が不足し、思うように活動ができませんでした。そこで清水教授に教わった通り、廃食用油でバイオディーゼル燃料をつくったところ、問題なく利用でき、復興支援に携わることができたのです。
このときの経験から廃食用油のバイオディーゼル燃料化に可能性を実感し、起業を決断しました。
事業の可能性を確信したゴミ収集車へのバイオ燃料の活用
ーー事業を本格稼働したのは、いつ頃だったのでしょうか。
越川哲也:
大きな転機となったのが、震災の2年後に京都で開催されたCOP3(国連気候変動枠組条約第3回締約国会議)です。そこで廃食用油を活用した弊社の事業が注目され、京都市に全面的にご協力いただけることとなりました。
その後、市から「精製した燃料を220台ある京都市のゴミ収集車に活用したい」と提案を受けます。220台のゴミ収集車が使う分を集めようとすると、1日5000リットルもの廃食用油が必要でした。
それでも、市のバックアップとボランティア団体の協力により必要な量を集めることができ、プロジェクトは成功を収めることができました。これを機に、バイオ燃料事業に本格的に取り組み始めることになります。
自立した事業運営に向けて地道に活動を続けた日々
ーー事業を展開する上で苦労した点をお聞かせください。
越川哲也:
私たちは国の補助金に頼らないと決め、自分たちで原料を集めることにしました。そこで特に苦労したのが、廃食用油の調達です。前回は市の協力もあって目標量を調達できたものの、イチから自分たちの力だけで集めるのは本当に大変でしたね。
まずは自治会を回り、一般家庭から出た廃食用油の回収に協力してもらえないか相談しました。その際、回収した油は燃料化した後、市バスなどの公共交通機関にも使うと伝えるようにしました。
すると、廃棄する油が住民の交通手段に活用される点が肯定的に受け止められ、少しずつ賛同を得ていきました。それから、廃食用油が多く出る個人経営の飲食店に協力を仰ぎました。すると「使い終わった油の処理に困っていたから助かる」と、多くの方が協力してくださいました。
最初は軽トラックにドラム缶を積んで収集していましたが、次第に大型車両が必要なほど大量の油を集められるようになりました。
ーー会社を経営する上で大切にしていることを教えていただけますか。
越川哲也:
地に足の着いた経営を行うことを常に意識していますね。中には地球に優しいエコな活動をアピールし、話題性だけで注目を集める企業もあります。ただ、こうした企業の多くは長続きしません。
一方で弊社は石橋を叩いて渡るように、技術を確実なものにしてから実用化しています。こうして地道に研究を重ね、事業の継続性も踏まえた上で運営を行っています。
自分たちの活動を通じて、同じ志を持つ企業を増やしたい

ーー環境に優しい燃料をつくる企業として、自然保護に対する思いをお聞かせいただけますか。
越川哲也:
時代はどんどん進化し、私たちの生活は豊かになりました。その一方で環境破壊が急速に進み、これまであった自然が失われつつあります。私たちは今一度、本当に大切なものは何かを見直すべきときだと思います。
この自然環境を守るために重要なのが、化石燃料に頼らず自分たちでエネルギーを自給自足することです。実際に京都府の京丹後市にある限界集落では、バイオガス発電施設を設置し、発電の際に出た液肥を農業用の肥料として活用する資源循環の取り組みを始めています。
このように地産地消型のエネルギー供給の取り組みが、日本全国に広がることを期待しています。弊社は会社の規模を拡大するよりも、今ある美しい自然を後世に残すことに注力したいと考えています。私たちの活動がモデルケースとなり、環境保護に取り組む企業が増えていってほしいですね。
ーー最後に読者へのメッセージをお願いします。
越川哲也:
弊社が今後力を入れていきたいのが、さまざまな業界の方の協力を得ながら、エネルギーの循環システムを構築することです。そのために、ともに歩んでいただける人材を募集しています。持続可能な社会の実現に向け、一緒に頑張ってくれる仲間をお待ちしています。
編集後記
震災で物資の供給が滞る中、現地で調達した廃食用油を燃料として活用できた経験から、バイオ燃料の重要性を確信したという越川社長。そこから実用化に向けて地道な研究を続け、周囲の協力を得てきたからこそ、今につながっているのだと感じた。株式会社レボインターナショナルは、豊かな自然を次世代へ引き継ぐため、環境保護の大切さを世の中に発信し続けていく。

越川哲也/1964年、京都府生まれ。大阪工業大学短期大学部土木工学科卒業。廃食用油のBDF(バイオディーゼル燃料)化技術に出会い、1999年に株式会社レボインターナショナルを設立。技術顧問を経て2003年、代表取締役に就任。2023年、東京証券取引所の東京プロマーケットに上場。バイオ燃料のパイオニアとして循環型社会の推進を目指し、環境問題の解決に取り組む。














