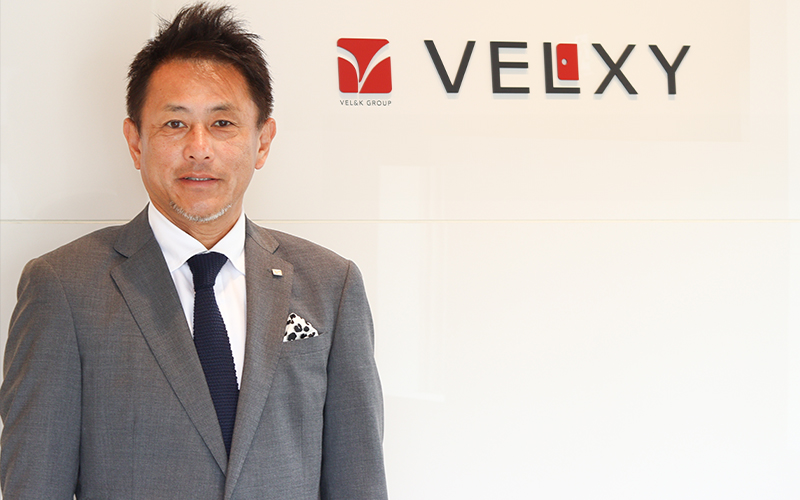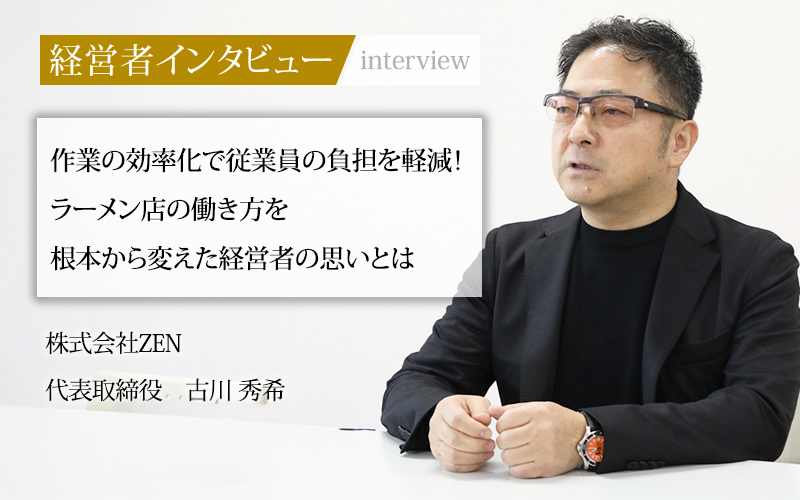
1952年(昭和27年)創業の久留米ラーメン店「清陽軒」は、地元の方々に惜しまれつつ2006年に暖簾を下ろした。その後、地元の味を残そうと店を復活させ、清陽軒の運営を引き継いだのが、株式会社ZENだ。
店を引き継ぐときの葛藤や、ラーメンの質を維持し、スタッフの負担を軽減するバックオフィスの効率化、企業理念に込めた思いなどを、代表取締役の古川秀希氏にうかがった。
インターネット関連事業で成功後、飲食業界へ参入した経緯
ーーまず古川社長の経歴についてお聞かせください。
古川秀希:
学生時代はハンバーガーチェーンでアルバイトをしていて、飲食店の基本である「QSC(※)」を徹底的に学びました。このときの経験が、今の事業の基礎になっていますね。そこからいずれ自分で店を開きたいと思うようになり、飲食ビジネスを学ぶため大学卒業後は中華料理チェーン店に入社しました。
その後、人事部に異動となり、責任者として採用活動に携わるようになります。採用パンフレットを一新するなどさまざまな施策を行った結果、採用人数を80人から130人にまで増やすことができました。
26歳のときに、マネジメントを学ぶために学生時代にアルバイトをしていたハンバーガーチェーンに転職します。ここで経営の知識を習得した後、デジタル化で人々の生活を便利にしたいと思い、独立してインターネット事業の会社を起業したのです。広告代理業や化粧品の通販事業などを手がけ、順調に業績を伸ばしていきました。
※QSC:Quality(料理の品質)・Service(接客の質)・Cleanliness(清潔さ)の略。
ーーそこからラーメン店の経営を始めたきっかけは何だったのですか。
古川秀希:
はじめのうちは楽しかったのですが、次第にお客様の顔が見えないことに物足りなさを感じるようになりました。そんな中、人気の久留米ラーメン店「清陽軒」が閉店することになり、友人から店を復活させてほしいと頼まれたのです。
私は自宅で豚骨スープをつくるほどラーメン好きだったので、この店の味が無くなってしまうのは確かに惜しいと思いました。ただ、飲食業は体力的にハードな仕事です。スタッフの確保が難しいと考えたことから、すぐには返答できませんでした。しばらく悩みましたが、どうしても久留米ラーメンを全国に広めたいと思い、暖簾をお借りして清陽軒の運営を始めることになったのです。
ーー実際にラーメン店の経営を始めてみていかがでしたか。
古川秀希:
スタートから半年間は会社に一度も出社せず、一日中店にいて飲食事業に全力を注いでいました。毎日15時間以上立ちっぱなしで、体力的に本当につらかったです。ただ、ラーメンの試食を繰り返し、夜中にホテルに戻ってすぐ寝ていたので、痩せることはなかったですけどね(笑)当時はとても大変でしたが、このときに苦労したからこそ今があると思っています。
セントラルキッチンの導入により、スタッフの負担を軽減しながら本格的な味を提供

ーー貴社ならではの特徴をお聞かせください。
古川秀希:
弊社では各店舗で提供する食事を一括で調理する、セントラルキッチンを導入しています。久留米ラーメンは博多ラーメンと異なり、継ぎ足しながらスープを熟成させます。そのため管理が難しく、専門店は福岡でも10店舗程度しかありません。
しかし、弊社はセントラルキッチンでスープを8割ほど仕込んでいるため、アルバイトスタッフでも同じ味を再現できます。また、IT企業の特色を活かし、バックオフィスのシステム化を進め、スタッフへの負担が軽減できるよう工夫しています。
ーーその他に飲食店を経営する上で意識していることは何ですか。
古川秀希:
弊社では労働環境の整備を徹底し、3K(きつい・汚い・危険)をすべて排除しています。セントラルキッチンの導入により作業負担を軽くし、労働時間の短縮につなげているのです。
また、食材を工場で処理するため、飲食店でありながら店舗には包丁を置いておらず、ケガのリスクがありません。さらに、ドライキッチンを導入し、安全かつ清潔な環境で作業できるようにしています。トイレや床、テーブルもこまめに清掃を行い、女性のお客様が入りやすい店づくりを心がけています。
ーー貴社が開発された社内コミュニケーションアプリ「minacone(ミナコネ)」について教えてください。
古川秀希:
「今日の感謝は未来を創る」という企業理念のもと、お互いに感謝の気持ちを伝え合う文化から生まれたものです。このアプリでは「ありがとう」や「おめでとう」、「グッジョブ」といったメッセージをスタッフ同士で送り合うことができます。現在は他企業にも提供し、従業員のエンゲージメント向上に活用いただいています。
マネジメント力を育て組織体制を強化。今後目指す方向性について

ーー経営幹部の育成についてはいかがですか。
古川秀希:
別の業態や業種でも活躍できる、経営者感覚を持った人材を育成したいと考えています。そのため、私が求めるのは職人ではなく、マネジメントができる人材です。現在、期待を寄せている若手社員が何人もおり、彼らを育ててさらに組織体制を強化していこうと考えています。
ーー今後の展望についてお聞かせください。
古川秀希:
私たちが目指しているのは、3世代で楽しめる「ラーメン業界のファミリーレストラン」です。そのために、家族でお食事を楽しんでいただけるよう小上がり席を設ける、会員の方には900円以上の食事をした場合に、お子さまラーメンを無料で提供するなどの工夫をしています。
また、フランチャイズ展開についても検討中です。高級食パンのフランチャイズで失敗したときの反省点を活かし、加盟店と双方がWin-Winになれる仕組みづくりを模索しています。
コロナ禍で気付いた飲食店経営で大切にすべきこと

ーー最後に今後の意気込みをお願いします。
古川秀希:
企業理念の「お客様への感謝」「働く仲間への感謝」「地域社会への感謝」を指針とし、日々の仕事に取り組んでいきたいですね。この企業理念は、コロナ禍以降に決めたものです。弊社は緊急事態が発令されて以降、3ヶ月間休業しました。営業再開日には私も店の入口に立ち、お客様に「ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」と頭を下げました。
すると、70歳くらいのご夫婦から「大変でしたね」と労いの言葉をかけていただいたのです。この瞬間、「飲食の仕事をしていて本当に良かった」と思い、お客様からの温かい言葉に思わず涙が出てしまいました。
この経験を経て、もっとお客様から愛される店になりたいと思うようになりました。また、働ける場所があることがどれだけ幸せか実感するとともに、仲間の大切さを再認識するようになったのです。このときの気持ちを忘れず、地域に貢献し社員が輝ける環境づくりを進め、地域で一番の店を目指していきます。
編集後記
新型コロナウイルスの蔓延で休業を余儀なくされたものの、「おかげで大切なものに気付けた」と話す古川社長。逆境となったこの出来事が、経営の方向性を見直す大きな転機となったようだ。心を込めた接客サービスを提供すると同時に、働きやすい職場づくりもさらに進める株式会社ZENは、久留米ラーメンを全国に広めていくことだろう。

古川秀希/大学卒業後、餃子の王将を運営する株式会社王将フードサービスの本社にて採用業務を担当。26歳のときに株式会社ロッテリアに転職。入社3年後に福岡姪浜デイトス店の店長に昇進し、店舗運営マネジメントの基礎を学ぶ。34歳でインターネット関連事業を立ち上げる。48歳のときに新規事業として飲食事業「久留米ラーメン清陽軒」を開業。