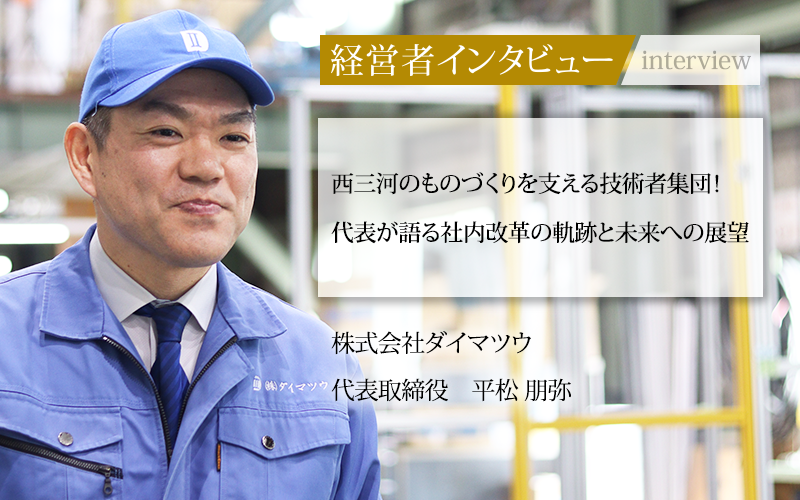
ものづくりが盛んな愛知県三河地方にある株式会社ダイマツウは、製造業の生産設備や機械装置の設計・製造・据付を手がける企業だ。父親から事業を引き継いだ代表取締役の平松朋弥氏は、人事評価の見直しや生産管理の自動化など、社内改革を進めている。
家業を継ぐ気はまったくなかったという幼少期のエピソードや、同社の経営改革にかける思いなどについて平松氏にうかがった。
高いスキルを求められる職場を経て気付いた家業の課題
ーー家業を継ぐことは幼少期から意識していたのですか。
平松朋弥:
中学生の頃までは、製造業に対して「汚い、臭い」というネガティブなイメージを持っていました。週末に工事が入ることも多く、土日は父がいないのがほとんどだったため、「自分はこれを当たり前の生活にはしたくない」と思っていましたね。
ただ、兄2人はそれぞれ自分の進みたい道を選び、家業を継ぐ気はなさそうでした。そこで、父から「後継者になってくれないか」と頼まれたら引き受けようか、とぼんやり考えるようになりました。
そうなると経営のノウハウを貯めておく必要があるため、大企業でなく裁量権のある職場で働こうと決めます。こうした背景があり、システム開発を行う300名程度の中小企業に入社しました。会社の分裂から新会社側の創設メンバーとして、プロジェクトリーダーを任されるなど、とても鍛えられましたね。
ーーそこから会社を辞めて家業に入った経緯をお聞かせください。
平松朋弥:
父の体調不良により会社を取り仕切る人間が必要になり、家業に入ることになったのです。
前職は東大や京大出身のエリートが集まる会社でした。ビジネスの基本を徹底的に叩き込まれ、効率とスピードが求められる、ビジネスパーソン養成道場のような厳しい職場でした。
一方で家業の方は、いまだにFAXや紙ベースでの業務がほとんどで、前職との大きなギャップを感じましたね。大企業であればバーコードによる照合で自動化されている作業も、注文書と納品書を目視で照らし合わせてチェックしており、この状況は改善しなければと危機感を覚えました。
公平かつ的確にスキルを評価できる仕組みを構築

ーー社長就任後の取り組みについてお聞かせください。
平松朋弥:
まず着手したのが、人事評価制度の見直しです。社員の能力を適切に評価するため、一連の業務を各工程に細分化し、それぞれの工程に必要なスキルを評価する項目を作成しました。たとえば図面の読解では、型式の文字と数字から部品の寸法や仕様が想像できるかなど、細かく設定しており、評価項目数は約600となります。
こうした詳細な評価基準を設定したのは、前職の人事評価制度に疑問を持っていたからです。前職では多くの企業と同様に、A~D判定で評価していました。このとき「何をもって自己評価すればいいのか、上司は何を基準に判断しているのか」と、もやもやした思いを抱えていたのです。
そこで評価基準を明確にし、本人と上司が評価しやすく、誰が担当しても同じ評価を下せるよう工夫しました。前回の評価との差分もわかりやすいため、査定時間を大幅に削減でき、評価面談に多くの時間をかけることができます。
設計の担当者が客先で工事も行うなど、多能工を推奨している弊社では、どの職種でも同等の評価ができるようにしています。こうして出した評価内容を給与に直接反映させることで、社員の成長意欲とモチベーションアップにつなげたいと考えています。
ロボットコンテストで学生と企業の接点を増やす
ーー貴社では小学生向けのロボットコンテストを定期的に開催しているそうですね。
平松朋弥:
募集定員は親子で50組、計100名以上が参加する一大イベントとなっています。発想力を働かせ、ものづくりの楽しさを知るきっかけになると、親御さんたちも積極的に参加してくれています。
こうして地域貢献につながるイベントを開催することで、スポンサー企業の獲得にもつながっています。また、地元の工業高校の生徒さんにコンテストの審査員として参加してもらい、そこでスポンサー企業の事業内容や仕事内容を紹介し、企業PRを行っているのです。
また、名古屋工業大学のソーラーカー部へ弊社の製品を提供したり、起業を目指す学生さんたちに向けたトークイベントに参加したりしています。
弊社は現在、従業員数が25名と、大企業に比べると小規模な組織です。こうした交流を通してものづくりに興味のある学生との接点を増やし、採用活動につなげたいと考えています。
ーー社内改革について注力している点を教えてください。
平松朋弥:
入社時から着手したかった、生産管理システムの導入を進めようと考えています。システムの導入には購入コストや教育コストもかかり、中小企業には大きな負担となります。ただ、作業を自動化しなければ効率が悪いままで、人的ミスも減りません。
そこで生産管理業務のDXを推進し、業務改善につなげようと計画しています。ただ、急に切り替えてしまうと現場が混乱してしまうので、社員と相談を重ねながら少しずつ進めていくつもりです。
また、担当者が変わってもこれまでと同等のサービスを提供できるよう、社員教育にも力を入れていきたいですね。いずれは世代交代をしていかなければならないので、今のうちから若手の教育に力を入れていこうと考えています。
ものづくり大国・日本の底力を発揮する一助になりたい
ーー今後の目標についてお聞かせください。
平松朋弥:
私は台湾の半導体産業やドイツの自動車産業のように、ものづくりは国の強みになると考えています。ものづくりで復活を遂げた国として、日本もこの強みを活かすことが重要だと思っています。
弊社もものづくりを行っているメーカーとして、日本の成長に貢献したいというのが私の思いです。これからも地域に根ざした企業として、社会に貢献したいと考えています。昨年から新卒採用を始めました。20代の若手社員が50年後も働き続けられるよう、会社を守っていきたいと思います。
ーー最後に読者の方々に向けてメッセージをお願いします。
平松朋弥:
弊社はものづくりが盛んな西三河で創業し、設計・製造・据付まで一貫して行える技術力が強みです。公正な評価制度に基づいた人材育成を行っているため、着実にスキルアップができます。ものづくりが好きな方、自分で考え行動できる方をお待ちしています。
編集後記
幼少期は製造業に対してネガティブなイメージを持っていたという平松社長。しかし、ものづくりの魅力に気付き、今では経営者として企業のさらなる成長をけん引する存在となった。さらにはロボットコンテストなどの社会貢献活動も行い、地域に根ざした活動にも注力している。株式会社ダイマツウは時代に合わせた変化を遂げ、日本のものづくりの現場を支える一助となることだろう。

平松朋弥/1980年愛知県生まれ。東京大学文学部卒業。新卒でシステム会社に入社し、人事総務に従事。創業者である父の体調不良を機に、2008年に株式会社ダイマツウへ入社。協力会社へ出向し数年の現場経験を経て、2022年に代表取締役に就任。














