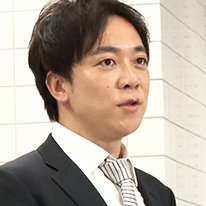岐阜県多治見市に本社を構える株式会社井澤コーポレーションは、明治33年(1900年)の創業以来、日本最大の陶磁器生産地である美濃を拠点に活動する陶磁器専門商社として、その歴史を刻んできた。
創業以来一貫して陶磁器のオリジナル商品の企画・販売に注力し、美濃焼の価値を国内外に広く発信してきた同社。美濃焼を世界に届けるための取り組み、直面する課題、そして未来への展望について、代表取締役社長の井澤秀哉氏にうかがった。
美濃焼の継承と変革への道程
ーー創業以来の美濃焼への取り組みと、貴社が掲げるビジョンについてお聞かせください。
井澤秀哉:
弊社は、美濃焼の産地として知られる岐阜県多治見市を拠点に、徳利や盃の製造販売から事業を開始し、その後、時代のニーズに応えながら食器の開発へと業態をシフトしました。現在では、「うつわの可能性をひろげ、五感で味わう食文化をつくる」という理念を掲げ、美濃焼を主力に皆様へお届けしています。
美濃焼の特徴は、和食器、洋食器、中華食器といったさまざまな種類の焼き物を生産できる多様性にあります。この強みを最大限に活かしながら、従来の流通構造を見直し、新たなマーケットへの進出を模索してきました。私たちが特に注力しているのが、地域の素材を活用した製品づくりと、伝統を尊重しつつも現代のニーズに応えるデザインの融合です。
美濃焼を単なる伝統工芸品としてではなく、生活の中で息づく実用性と美しさを兼ね備えた文化として広めることが、創業以来の弊社の使命です。
ーー長い歴史の中で、どのような課題に直面し、どのように克服したのでしょうか?
井澤秀哉:
1990年代、陶磁器業界全体が大きな変革期を迎え、私たちは大きな転換を迫られました。これまでの伝統的な流通構造に依存した方法から脱却し、問屋を介さない直販の仕組みを模索する必要があったのです。その過程で、マーケットのニーズを的確に把握しながら、産地商社としての役割を再定義していきました。
さらに、国内市場の縮小に伴う海外市場への進出も大きな課題でした。この難題に対しては、製品そのものの魅力だけではなく、その背景やストーリーを丁寧に伝えることで、異なる文化圏の顧客が共感を得られる価値を生み出すことに取り組んできました。
同時に、デジタルツールの導入による業務効率化や、地域の職人たちとの連携体制の構築にも注力し、美濃焼の産地全体を巻き込む形でこれらの課題を克服してきたのです。
価値創造への挑戦と事業の強み

ーー貴社の事業における強みや、美濃焼の可能性を広げるための取り組みについてお聞かせください。
井澤秀哉:
美濃焼の強みは、実用性と美しさを兼ね備えた製品を提供できる点にあります。弊社は創業当初、徳利や盃などの製造販売を行っていましたが、現在は製造部門を持たず、商社として、デザイン、マーケティング、流通を通じて陶磁器の価値を高める「伝え手」としての役割を担っています。現在特に力を入れているのは、土の調合やデザインにこだわった陶磁器の可能性を広げる取り組みです。
「蛙目粘土」と呼ばれる岐阜特有の粘土を使用することで、軽量でありながら丈夫な製品を生み出すことができるのですが、この技術は世界的にも珍しく、美濃焼ならではの強みともいえるでしょう。さらに、顧客ごとのニーズに応じたオーダーメイド製品の提供や、飲食店向けのデザイン性と耐久性を兼ね備えた器を提案し、多様な市場に対応しています。
また、弊社ではSDGsへの貢献を意識した取り組みも行っています。廃陶磁器の再利用や地域資源を活用したサステナブルなプロダクトの開発に力を入れ、美濃焼を単なる商品ではなく、環境や文化に貢献するツールとして位置づけることで、業界全体の価値向上を目指しているのです。
ーー今後さらに発展させていきたい分野や新しい挑戦について教えてください。
井澤秀哉:
私たちが掲げる「五感で味わう食文化をつくる」という理念の実現のためには、単に器を提供するだけではなく、食空間全体をデザインすることが重要です。その代表的な例が、総合芸術である「茶の湯」を参考にした、器や料理、空間が調和する体験を創出するプロジェクトです。この取り組みを通じて、美濃焼を食文化の一部として再定義し、そのブランド力を国内外で高めていきたいですね。
さらに、デザインだけではなく、実際に器を手に取ったときの質感や使い勝手を重視した商品開発にも力を入れています。
持ちやすさや洗いやすさといった、日常での使いやすさを追求しながら、美的価値を損なわないデザインを提供することで、器そのものが生活を豊かにし、日々の暮らしに溶け込む存在となることを目指しています。理念を具体化するためのこれらの挑戦が、美濃焼を次のステージへ進化させる原動力になると考えています。
世界に広がる美濃焼の新たな物語

ーー地域ブランディングとグローバル展開に向けて、具体的にどのような取り組みをしていますか?
井澤秀哉:
美濃焼の地域ブランディングでは、行政と連携し、「セラミックバレー美濃」というコンセプトを展開しています。この取り組みを通じて、地域全体で美濃焼の価値を見直し、世界に向けて発信するための基盤を築きました。
欧米やアジア市場においては、日本の食文化とともに美濃焼の魅力を一体として伝える活動を展開しており、単に器を販売するだけではなく、デザインや使用方法を含めた総合的な提案を進めています。
これを実現するため、グローバルなネットワークを構築し、現地の文化やニーズに即した展開を進めています。さらに、地域の伝統を大切にしながらも、現代的なデザインや新素材を取り入れることで、国際市場での競争力を高めているのです。
ーー美濃焼の未来を見据え、どのようなビジョンを描いていますか?
井澤秀哉:
弊社の目標は、陶磁器を通じて日本の食文化をさらに豊かにすることです。そのビジョンの実現に向けて、地域と世界をつなぐ「架け橋」としての役割を担うとともに、サステナビリティの観点から、廃陶磁器のリサイクルや地元の原料を活用したエコロジカルな製品の開発にも取り組んでいます。このように、環境保護と地域活性化の両立を図ることが重要だと考えています。
また、次世代の陶磁器産業を支える若手人材の育成にも注力していきたいですね。美濃焼が持つ可能性を最大限に引き出し、新しい価値を創造し続けることが、私たちの使命です。
それを実現する為に、デジタル技術を活用した市場分析やECプラットフォームを活用し、新たな顧客層の開拓への挑戦も行っていく計画です。これらの取り組みを通じて、美濃焼をより多くの人々に届けるとともに、地域産業のさらなる発展を目指していきます。
編集後記
井澤社長の言葉からは、美濃焼の伝統に対する深い愛情と、それを未来につなげる革新への強い決意が伝わってきた。井澤コーポレーションが目指すのは、地域の文化や環境への貢献を込めた「美濃焼」の新たな価値の創造だ。その挑戦には、地域産業の可能性を大きく広げる力が宿っていると感じた。
サステナブルな製品開発やグローバル展開を通じて、同社が世界にどのような物語を紡いでいくのか、これからも注視していきたい。

井澤秀哉/1968年岐阜県多治見市生まれ。愛知学院大学卒業後、総合商社での経験を経て、1995年に株式会社井澤コーポレーションに入社。同年、代表取締役社長に就任。当時の食器業界では珍しかった問屋を介さない販売を開始し、直営店の開設や地域ブランディングなど革新を進めている。