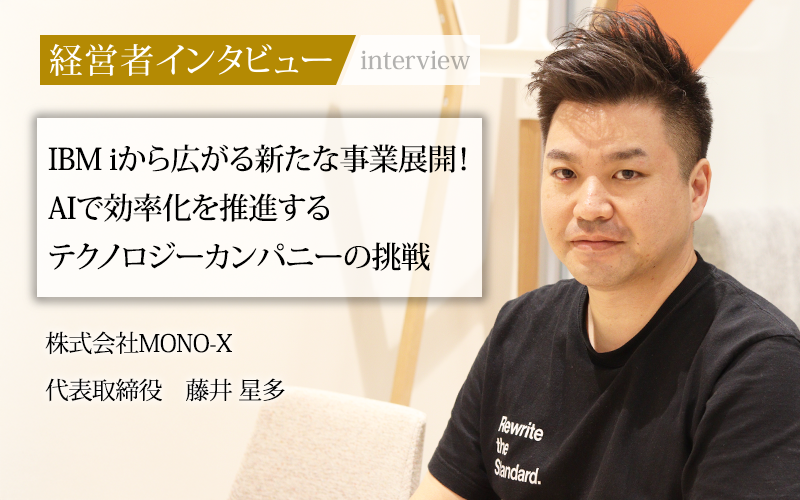
製造業や物流卸業の基幹システムとして長年使われ続けているIBM iと、最新のAI技術を組み合わせた独自のソリューションを展開する株式会社MONO-X。日本の製造業の基盤を支え続けてきた同社は、古いシステムと新しい技術の橋渡しという希少な価値を提供し、企業間取引のアナログ業務の効率化にも取り組んできた。「すべての産業に、新次元のデータ連携インフラを創造する」というビジョンを描く同社の代表取締役、藤井星多氏に話をうかがった。
社長就任後にプロダクト開発事業のスケール化を実現
ーー社長就任に至るまでの経緯をお聞かせください。
藤井星多:
2005年に大学を卒業後、SIerを経てITベンチャー企業に転職しました。転職先のITベンチャーでは多くの仲間たちが独立・起業していく流れがあり、私自身も起業に挑戦しました。しかし、思うように成果を出せず悩んでいた時期があり、そんな私を見かねて、父が声をかけてくれたのです。
そして2008年、当時は「株式会社オムニサイエンス」という社名だった今の会社に、まるで拾ってもらうような形でジョインしました。その後は仲間と共に地道に努力を重ね、業績も着実に伸ばすことができ、2017年には代表取締役社長に就任いたしました。
ーー入社後はどのような取り組みを行いましたか?
藤井星多:
株式会社オムニサイエンスはもともと私の父が2005年に立ち上げた会社で、その営業と製品開発を10年以上行ってきました。しかしながら、オーダーメイドの請負やエンジニアの派遣事業は、人材の数によって売上が頭打ちになってしまいます。そこで、2008年に私が入社してから、プロダクト開発やクラウド移行支援サービス事業への切り替えを進め、2017年の社長就任後はプロダクトを主力としてスケール化できるビジネスモデルに転換する方針を打ち出したのです。
しかし、経営方針の急な変更に伴い社員の退職が相次ぎ、2015年に約50名いた社員は、2017年にはおよそ25名と半数にまで減少しました。私自身の判断や進め方に至らない点が多く、結果として社員が離れてしまったのだと思います。私が社長に就任して以降、少しずつ社員数は回復し、現在の社員数は40名ほどとなっています。
これは余談ですが、事業売却に伴い、株式会社オムニサイエンスから株式会社MONO-Xに社名も変更しています。
レガシーとAIをつなぐ希少な技術力

ーー貴社の現在の事業内容について、詳しく教えてください。
藤井星多:
弊社はIBM iと呼ばれる領域でビジネスを展開しています。サービスの具体的な内容は、基幹システムのクラウドへの移行と、企業間取引のアナログ業務を弊社のノーコードツールでなめらかにすること、そしてAIを活用した省力化・効率化製品の拡販の3つです。
IBM iというのは30〜40年前からあるオフィスコンピューターの基幹システムで、使用している企業の約8割が製造業やものを運ぶ物流卸業です。弊社は製造・物流卸などのものづくり産業を支える業務アプリケーションをIBM iで展開していますが、今後は弊社が開発したソリューションを、IBM i以外を使用しているお客さまにも拡大したいと考えています。
ーー貴社にしかない強みや選ばれる理由は、どのようなところにあるとお考えですか?
藤井星多:
30〜40年前からあるシステムをAIに接続できるスキルとノウハウを持っているところが、弊社の強みです。こうしたシステムは、設計思想やテクノロジーが古いままなので、AIに接続する手法を知らない企業も少なくありません。
弊社は会社として20年の歴史があり、古いシステムにAIを接続するスキルを持つメンバーと、新しい技術を持つメンバーの両方が在籍しています。このようなハイブリッドなテクノロジーを持つ会社はなかなか珍しいのではないでしょうか。古いものと新しいものをつなげて解決できるという希少性が、弊社が選ばれる理由なのではないかと考えています。
2030年に向けて人材確保と成長を促進
ーー貴社が大切にしているビジョンをお聞かせください。
藤井星多:
私たちは「すべての産業に、新次元のデータ連携インフラを創造する」というビジョンを掲げています。このビジョンの根底には、企業間のアナログ業務やボトルネックを解消し、働く人が本来の価値を発揮できる世界をつくりたいという意図があります。
今後はAIの進化により、あらゆる業種・業務が根本から変わっていく中で、人間の存在価値も改めて問われる時代が来ると考えています。そうした時代においても、私たちはAIテクノロジーを軸に、このビジョンの実現に向けて挑戦を続けていきます。
ーー今後、事業をどのように成長させていきたいですか?
藤井星多:
今後は、AIを軸にした事業と組織づくりに本格的にシフトしていく予定です。AIは、IBM iに蓄積されてきたプログラム資産や、弊社のプロダクトそのものさえも置き換える可能性を秘めています。これまで多くのマンパワーを必要としていた業務も、AIによって置き換えられる領域がいくつもあります。まずは、そうした分野に向けたプロダクトを積極的に展開していく予定です。
さらに、私たちは「AIとともに進化する組織」を目指しています。たとえば、開発プロセスではAIがコードを生成し、営業ではマーケティングデータや過去実績をもとに最適な提案をAIが導き、バックオフィス業務の自動化はもちろん、組織マネジメントにおいても、人材配置・評価などをAIと人間が協働で行う仕組みづくりに取り組みたいと考えています。
私たちは、AIを「人間の思考や記憶を拡張する存在」と捉えています。だからこそ、これからの時代に必要なのは「問いを立てる力」「責任を持つ覚悟」「自ら動く行動力」こそが人間にしかできないことであり、そういった価値を発揮できる人が集まっている組織でありたいと考えています。
編集後記
事業承継後に大胆な方向転換を決断し、社員が半減するという苦境を乗り越えてきた藤井社長の決意が印象的だった。IBM iという領域で培った技術力と知見を基盤に、AIという新たな領域へと踏み出す。その背景には、日本企業の基幹システムが抱える構造的な課題があり、それを解決しようとする強い使命感が感じられた。同社の挑戦は、製造業のデジタル化における重要な一手となるだろう。
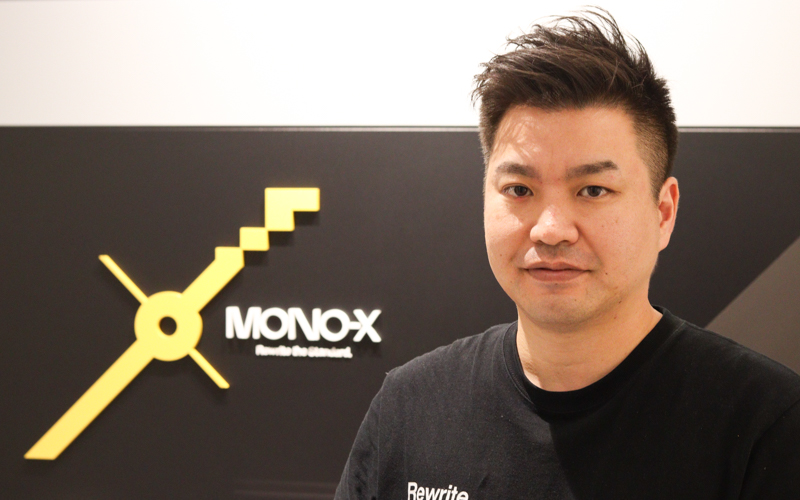
藤井星多/2005年に大学卒業後、SIerにてIBM iソリューション営業を経験。その後、ITベンチャー企業に転職し、SNSを活用したソリューションを業種・業界問わず幅広く提案。2008年より株式会社MONO-X(旧株式会社オムニサイエンス)にて、IBM iユーザー向けにOSSを活用したモダナイゼーションを10年以上にわたり支援。2017年に代表取締役就任。














