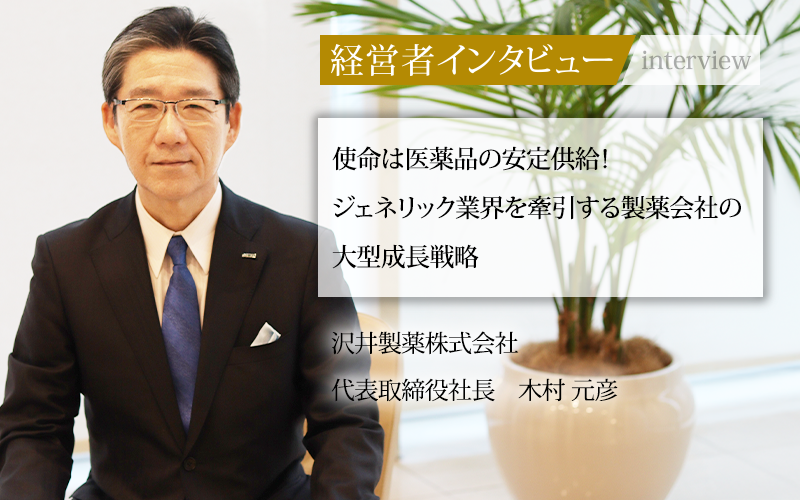
1929年に創業した沢井製薬株式会社。ジェネリック医薬品(後発医薬品)の製造・販売事業で成長してきた国内有数の製薬会社だ。「なによりも患者さんのために」という企業理念のもと、ジェネリック医薬品の品質を追求し続ける同社。代表取締役社長の木村元彦氏に、就任の経緯や医薬品開発・製造にかける思い、今後の展望をうかがった。
製薬会社で組織運営を学び、成長過程の業界へ
ーー貴社に入社した経緯をお話しいただけますか。
木村元彦:
ジェネリック医薬品が世の中に浸透した頃、沢井製薬は生産能力を一気に上げていくフェーズにありました。その上で生産本部を動かす人財が必要となり、私に声がかかり、2016年に沢井製薬へ入社した次第です。
私は研究員として住友化学工業に入社したのち、住友製薬や大日本住友製薬(現・住友ファーマ社)にて、生産工場の立ち上げや重要部門の統括、数ヶ国での海外勤務も経験しています。
いろいろな知見を沢井製薬の発展に活かす働き方は、58歳からのセカンドキャリアとして非常に魅力的に感じましたね。先発医薬品メーカーが、新製品の開発に苦しんでいる一方で、沢井製薬のジェネリック業界は成長の真っ只中という真逆の状況も刺激的でした。
ーー入社後はどのような経験をされたのでしょうか?
木村元彦:
まずは1年間、生産本部で生産機能を統括する生産統括部長を務め、その後は本部長となり、全国6ヶ所の工場と連携しながら、約2000人を擁する生産本部を運営しました。
ジェネリック医薬品は毎年、何十品目もの新製品を市場に出すため、生産本部は迅速な意思決定が求められます。体感としては、先発医薬品メーカーで5年かける仕事を1年でこなすイメージです。忙しいけれど、経験値をもとにトライアンドエラーを重ねる日々は充実していました。
生産本部での最大の課題は、年1回の薬価改定を上手く乗り切ることでした。国が定める薬価は、毎年10%近く市場価格が下がっていきます。仮に1000億円分の薬を販売した場合、100億円の利益が削られることになります。
私は各工場と相談してコストダウンを実現するなど、ビジネスが成り立つ方法を考えていき、ほぼ同じ設備のまま生産性を1.6倍アップさせました。
生産能力を大幅アップさせる2大プロジェクト
ーー役員時代や社長就任後の取り組みもお聞かせください。
木村元彦:
複数社の薬機法違反に起因する製造停止により供給不安が発生し、ジェネリック医薬品業界における供給の問題に対応する必要があると考え、立ち上げたのが2つの巨大プロジェクトです。
1つ目は、2021年にグループ会社として設立したトラストファーマテックです。福井県あわら市でジェネリック医薬品の製造・販売をしていた企業から、生産設備と400人の人財を引き継ぎ、新たな製造拠点として整備を行いました。
2つ目の大型投資は、福岡県飯塚市にある第二九州工場に新設した新固形製剤棟です。2021年に建設を決定した新固形剤棟が2024年に竣工をむかえました。トラストファーマテックでの生産能力30億錠と、今回完成した新固形剤棟の生産能力20億錠を合わせると、グループ全体の生産能力は205億錠となります。引き続き、グループ全体の生産能力を高めるための投資を行っています。
業界随一の生産力で医薬品の供給不足をサポート

ーー改めて、事業内容を教えてください。
木村元彦:
弊社は、ジェネリック医薬品を製造・販売している会社です。毎年多くの製品を開発し、2025年時点の販売品目数は約800品に及びます。
業務としては、薬の処方設計や分析法の確立といった研究開発はもちろん、安定供給に向けて工業化への取り組みがあります。弊社は取り扱い品目数は業界トップクラスなので、完成した製品を広く世の中に提供するほか、医療機関にも行き渡らせるなど、仕事の幅広さが面白いといえますね。新規事業として医療機器の開発もあります。
ーーメーカーとしての強みもうかがえますか?
木村元彦:
安定的に多品目を供給できる、生産力の高さです。2020年にジェネリック医薬品メーカーの品質不正問題が発覚して以来、一部の医薬品は限定出荷や供給停止が続いています。
弊社は以前からジェネリック医薬品の患者さんのニーズに答えられるよう生産力を高めていき、業界でトップクラスの生産力を有します。継続して安定供給できるよう、その強みをさらに伸ばしていくつもりです。
不祥事の再発防止策として、ジェネリック医薬品業界ではデータの管理方法も見直されています。人的ミスや情報の改ざんが発生しないように、試験機器をコンピュータに直結させるなど、DXの取り組みも弊社の一つの強みだといえるでしょう。
試験データの正確性を指す、データインテグリティ(DI)を重視したことで、オペレーターのミスが防ぎやすくなった上に生産性もアップしました。私が入社してから最初に導入した関東工場の成功例を活かして、全国の拠点に同様のシステムを展開しています。
新卒・中途を問わず、自分らしく働ける企業風土
ーー仕事において大事にしている考えをうかがえますか。
木村元彦:
若手時代は、とにかく目の前にある仕事に一生懸命でした。知らない分野にも自分なりにチャレンジしていくという精神で、多くの学びを吸収していったと思います。
中間管理職となり、組織に対する思いや責任感が増す中でも、大きく変化したのは部門長に昇進した時ですね。一人ひとりの人財がベストパフォーマンスを発揮できるようチームを構成し、組織全体をつくり上げるべきだと考えるようになりました。
社長に就任してからは、組織運営におけるビジョンを短期・中長期で明確に分けています。短期間で物事を処理することが得意な人もいれば、中長期的に物事を考えるのが得意な人もいるため、個性を把握した上で誰にいつ・どのような仕事を与えるかが重要です。
また、「複数の情報源を参考にする」「リスクヘッジとして別のプランも用意する」など、心理的安定性が増す形で仕事を進める方法も社員に伝えています。
ーー社風についてもうかがえますか?
木村元彦:
中途採用をはじめ、外から来た人を受け入れる懐の深さや、早く馴染めるように接するカルチャーがあると思いますね。社内で行われる多様なディスカッションにおいて、個人の提案がしっかりと採用されるカルチャーも構築されています。
私は工場や研究所に足を運び、従業員の声を聞くことが大好きなほか、全社員を対象としたタウンホールミーティングも定期的に実施しています。経営層と現場の距離が近いことも、カルチャーの形成につながっているのではないでしょうか。
近年は情報の共有化という意味で、より風通しの良い企業風土づくりを進めています。上からの指示通りに動くのではなく、情報を集めて自分で考える人を増やそうという発想です。
ーー独自の社内制度や取り組みはありますか?
木村元彦:
人財の流動性を高めるため、2024年4月に社内公募制度を開始しました。人手が欲しい部署に声を上げてもらい、希望者とマッチングさせる制度です。一つの部署で経験を積んだ上でのジョブチェンジなど、新しいことにチャレンジできたと社員に喜ばれています。
社内の意見を採用したことから、勤務制度もフレキシブルです。育児休暇の取得率は男女ともに100%を目標としています。女性の育休取得率は100%を達成しており、男性育休の取得者も増えています。在宅勤務やフレックス勤務など勤務地や業務内容にあった柔軟なスタイルのため、ワークライフバランスはとても取りやすいといえるでしょう。
また、医薬品メーカーらしい社内イベントも充実しています。たとえば、ウォーキングラリーは、自社が取り扱っている健康管理アプリの「SaluDi(サルディ)」を使う社内イベントで、目標歩数の達成者に景品が贈られました。デスクワークも多い中で、みんなの運動不足を解消する取り組みです。
社会責任を果たせる企業を目指して採用活動に注力
ーー貴社で活躍している人財についても教えてください。
木村元彦:
開発や工業化にスピード感があり、1年間のうちに幅広い仕事ができることが弊社の魅力といえるでしょう。自己の成長と会社の成長をマッチングしながら、沢井製薬を通して社会に貢献する。会社と人財がお互いハッピーに、というマインドセットがある方は活躍しやすい環境です。
また、多様性・公平性・包摂性を大切にする「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)」の一環として、女性の活躍も推進しています。
女性の管理職を増やしていくことも私の目標です。組織運営に必要なのは、会社や社会に貢献したいと、強く思える人です。具体的な取り組みとして、ダイバーシティ推進のための「ID&E推進室」を設置し、まずは管理職を目指す女性や可能性を秘めた方に向けての研修を実施したり、社員自身がキャリアを構築できるような研修を実施しています。
ーー求める人物像や採用活動の方針をお話しいただけますか。
木村元彦:
さらなる生産性アップに向けて、工場の従業員はもちろん、現場の管理部門や品質試験の人財を充実させたいと考えています。
採用活動を活発化し、雇用を拡大することは社会貢献にもつながると考え、2026年も2025年と同規模となる200名前後の新入社員の採用を予定しています。弊社単体で約2600人という事業規模で、一気に人員を増やす負担は大きいかもしれません。しかし、多くの若手に活躍の機会を与えたいという思いがあり、確実に成長できる教育プログラムも用意しています。
新卒採用だけでなく、いろいろな経験をした人が集まり、知恵を出し合っている会社でもあります。薬学の専門家や機械に詳しい人、事務スキルを持つ人まで、あらゆる分野の経験者が活躍できるので、成長意欲の高い人にぜひ来ていただきたいですね。
ーー今後のビジョンをお聞かせください。
木村元彦:
沢井製薬は、国内有数のジェネリック医薬品メーカーとして社会的責任があり、寄せられている期待も大きいものです。社長を務めるにあたっては、私の残りの人生で大いに社会貢献できる場を与えてもらったと感じています。
会社としても経営者としても、求められていることにしっかりと応えていかなくてはいけません。目下の課題は、医薬品が不足している状況をいかに改善するかであり、その過程で日本の市場内で会社の存在価値を高めていきたいところです。
利益が増えれば、業界で生き残る会社になれるともいえます。社内では、ジェネリック医薬品において一番に選ばれる会社として、地位を確固たるものにしようと話しています。いろいろなプレイヤーが集まりながら、同じビジョンに向かって歩みを進められていることは心強いことです。
現在の国内シェア率は約17%なので、まずは20%を目指し、「2030年には国内シェア率25%」の達成を目標に掲げています。グループ全体の売上収益としても、今は2000億円弱のところ、2030年までに3000億円を達成したいと思います。目標を達成するには、まだまだ生産能力が足りないため、設備を充実させながら成長していく予定です。
編集後記
業界内の不祥事や感染症の流行といった、複数要因から始まった医薬品不足。ジェネリック医薬品は価格面だけでなく、供給量においても社会を大きく支える存在だといえる。その使命感を胸に、大型投資に踏み切った沢井製薬。世の中を安心させる製品づくりが会社の価値向上に直結する。この素晴らしい循環のもと、人財を輝かせる準備も万端だ。
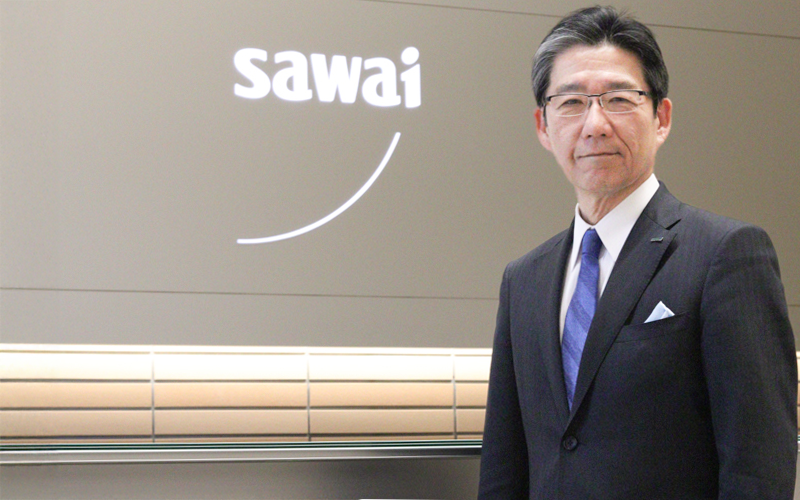
木村元彦/1957年生まれ。大阪大学大学院を卒業。1982年、住友化学工業株式会社(現・住友化学)に入社。大日本住友製薬(現:住友ファーマ製薬)を経て2016年、沢井製薬株式会社に入社。生産本部長、取締役を経て、2023年に代表取締役社長に就任。














