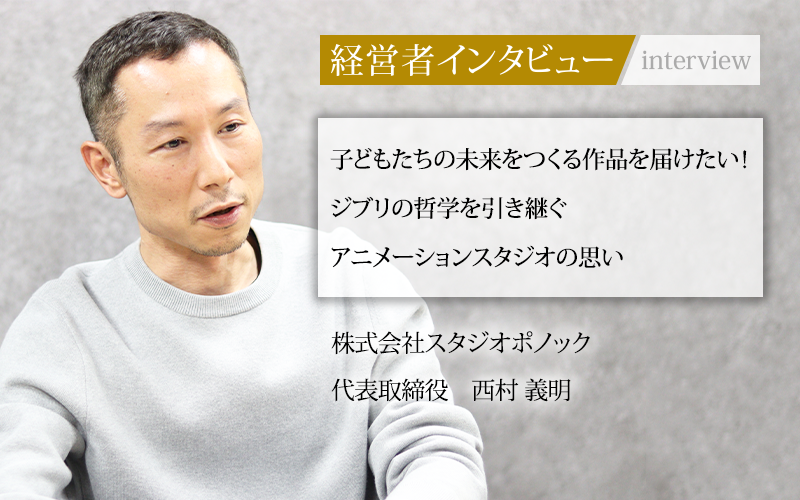
スタジオポノックは、スタジオジブリ作品『かぐや姫の物語』や『思い出のマーニー』でプロデューサーを務めた西村義明氏が立ち上げたアニメーションスタジオだ。これまで『メアリと魔女の花』や『屋根裏のラジャー』など、数々の作品を発表してきた。
自身の価値観を変えたエピソードや、アニメーションスタジオ立ち上げの経緯などについて、代表取締役の西村氏にうかがった。
正解がない問いの答えを提案する存在でありたいと思った自身の経験
ーーまずは、西村社長がアニメーション映画に興味を持つきっかけとなったこれまでのご経験をお聞かせいただけますか。
西村義明:
きっかけは、アニメーションではなく、実写映画です。私が若い頃は映画は非常に身近なもので、テレビ局でも多くの映画番組が放送されていました。アルバイトができる年齢になるとレンタルビデオ店で働き、映画に常に触れられる環境で過ごしていました。20代前半までに3千本近くの映画を観てきたと思います。
ーー今の仕事につながる原体験について教えてください。
西村義明:
中学2年生の時の疑問が根幹にあります。「人は死ぬのに、なぜ生きるのか」という問いです。答えの出ないこの問いに悩み、戦争体験のある沖縄の祖父に聞いたのです。祖父はその悩みに大笑いしました。その反応に救われ、「答えはない。ならば自分で決められる」と大きな自由を感じました。そして、子どものために生きることを人生の理由と決めたのです。
物語は、生や死への疑問の答えとして生まれることが多い。中学時代の私の疑問と無邪気な答えは、後に物語の作り手となる私の原体験とも言えます。
ーーそこからアニメーション制作の仕事に携わろうと思われたのですか。
西村義明:
大学ではテレビゲームを作る道を志し、電子情報工学科へ進みました。しかし、入力と出力が一対の自己完結的なメッセージ伝達では捉えきれない、複雑で曖昧なものこそ社会や世界を動かしていると感じてはいたんです。
自分と世界の間には常に情報の非対称性がありますから、現実世界を前にして的確に決断して行動するなんてできない。その時に、他人の人生を通した予期せぬ一方通行のメッセージが、救いになることもある。そうした認識から、ゲームではなく、映画という道に魅力を感じて、大学を中退し、映画制作を学ぶべく渡米しました。
最終的には、「映画」と「子ども」という二つの軸を重ね合わせ、アニメーション映画を選びました。アニメーション映画が持つ表現の可能性、世代も人種も越えうるメッセージ伝達の形態としての魅力に捉えられたのです。
希望だけでなく、世の中の現実も伝える作品づくりに携わるためスタジオジブリへ入社

ーースタジオジブリへ入社するまでの経緯を教えてください。
西村義明:
数あるアニメーション制作スタジオの中でスタジオジブリを選択したのは、夢と悪夢の両面を描こうとする姿勢に感銘を受けたからです。とりわけ、幼少期に観た『火垂るの墓』は、私の心に深く刻まれています。
当時、家計は楽でなく、朝夕にわたり働く母や家族を少しでも支えたいと考えながらも、幼い自分には為す術なく、もどかしい思いを抱えていました。その折、『火垂るの墓』の主人公に自身の姿を重ね合わせ、「これは自分のための映画だ」と、喜びと驚きを感じたのを覚えています。
そういう経験がありましたので、知人を介してスタジオジブリに手紙を書き、「夢や希望のみならず、苦悩や現実の厳しさをも臆することなく描こうとするスタジオジブリに入社したい」という思いを伝え、面接の後に採用していただいたという経緯です。
ーー入社後はどのような仕事に携わられたのですか。
西村義明:
配属されたのは著作権部門と海外事業部門で、契約書のファイリングなど事務的な仕事ばかりで、不貞腐れながら働いていました。
そんな私を見かねたプロデューサーの鈴木敏夫さんから、宮崎駿監督のCM制作の仕事を手伝うよう声がかかったのです。これに限らず、与えられた仕事はなんでもやりました。失敗ばかりでいつも怒られていましたが。
その後、『火垂るの墓』をつくった高畑勲監督の映画をつくれとの社命を受けて、『かぐや姫の物語』の制作に携わることになります。
ビジネスとして成立させながらも、売れることだけを目的にはしたくない
ーースタジオポノックを設立したきっかけを教えていただけますか。
西村義明:
スタジオジブリの制作部門の解散が決まったことが直接的なきっかけです。「高畑さんや宮崎さんの映画作りの志やクリエイターの技術を雲散霧消させてはいけない」という思いが強く、スタジオをゼロから立ち上げることを決意しました。何の後ろ盾もありませんでしたが、「とにかくやらなければ」という強い使命感のようなものに突き動かされていた気がしますね。
小さなスタジオということもあって、立ち上げ後は、企画を立て、資金を確保し、クリエイターとスタッフを集めて作品をつくり上げることの繰り返しです。毎作品、社内ベンチャーを立ち上げ、経営しているようなものでしょうね。
ーーアニメーションスタジオを経営する上で苦労している点をお聞かせください。
西村義明:
経営における難題は多岐にわたりますが、特に注力すべきは芸術性と商業性の均衡をいかに実現するかという点でしょうね。私たちのような規模のスタジオでは、数年の歳月をかけて創り上げる単一の作品の成否が、そのまま会社の命運を左右します。継続的な作品制作のためには、一定の成果が不可避だというプレッシャーは常にあります。
もっとも、映画ビジネス、特にアニメーション映画は、その特性上、市場の予測が極めて困難です。企画立案から完成に至るまで、四年以上の期間を要することも稀ではありません。このような状況においては、むしろ市場への過度な迎合を悪手で、人間にとっての普遍的な価値をいかに映像表現として昇華させるかという、純粋な映画制作の本質に立ち返らざるを得ない。そのため、私たちは常に真摯に作品と向き合い、全力を尽くしてその実現に邁進しています。
ーー人材育成についてはいかがですか。
西村義明:
専門学校や美術大学で研鑽を積まれた方でも、プロとして質の高い映像を生み出すには、アニメーションの基礎を着実に習得する期間が不可欠です。ポノックでは、第一線で活躍する熟練スタッフ陣が、将来を担う原画アニメーターへを育成する一年間の体系的なプログラムを設け、修了者には正社員登用制度を用意しています。
また、私自身の海外での学びを活かし、企画立案から作品の届け方まで、映画制作の全工程を実践的に学べる一年間の独自研修カリキュラムを新入社員向けに構築・実施することで、次世代のクリエイター育成に注力しています。
クリエイターが働きやすい環境を整え、より良い作品を生み出す
ーー現在貴社が注力している点を教えてください。
西村義明:
就業面で言えば、現代社会の課題である少子化の進行を踏まえ、優秀なクリエイターを惹きつけ、その才能を最大限に引き出すためには、労働環境の整備と向上は不可欠です。ポノックでは、労働時間の適正化だけでなく、福利厚生の充実や貢献に見合う公正な報酬体系を確立することに尽力しています。これにより、クリエイターが安心して創造的な活動に専念できる環境の実現を心がけています。
ーー最後に貴社が大切にされている理念をお聞かせいただけますか。
西村義明:
私たちが情熱を注ぐアニメーション制作の仕事、つまり物語の作り手の仕事は、未来を作る仕事とも言えます。私たちの魂を込めた作品が、一人の子どもを励まし、勇気づけ、時に慰め、新たな扉を開く鍵ともなることがある。それはもはや、単なる映画制作という仕事ではないのです。子どもが変わるとは、10年後の未来の世界が変わることを意味します。その責任と歓びを両方感じながら、一枚づつ描き、一作品づつ送り届けるのがスタジオポノックの本質であり、理念と言えるでしょう。
編集後記
「私たちの仕事は、保育士に近いと思っています。これからもひとつひとつの作品を通じ、子どもたちの感性を育てていきたいですね」と話してくれた西村社長。スタジオポノックはアニメーターの労働環境改善に取り組みながら、子どもたちの豊かな感性を引き出す作品を届けていくことだろう。

西村義明/2002年スタジオジブリ入社。製作業務、宣伝業務に携わった後、『かぐや姫の物語』(2013)、『思い出のマーニー』(2014)でプロデューサーを務め、二度の米アカデミー賞にノミネート。2015年スタジオポノックを設立し、代表取締役兼プロデューサーとなる。これまで『メアリと魔女の花』(2017)、『ちいさな英雄-カニとタマゴと透明人間-』(2018)、『Tomorrow’s Leaves』(2021)、『屋根裏のラジャー』(2023)の企画・プロデュースを行っている。














