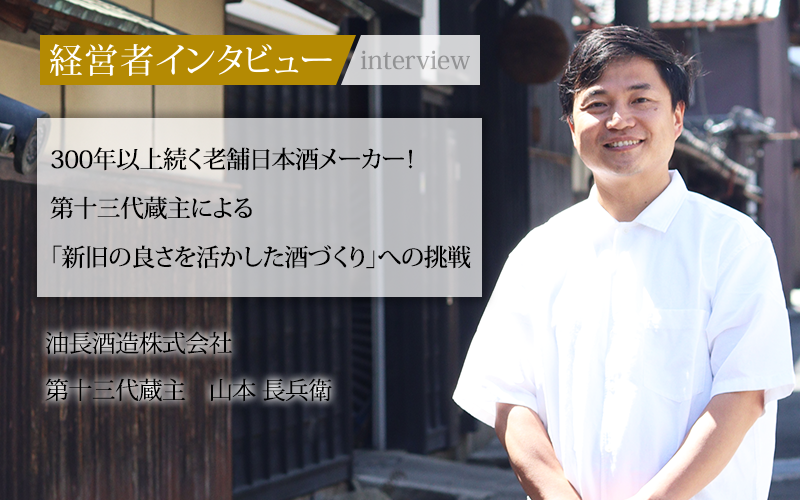
1719年(享保4年)に日本清酒発祥の地といわれる奈良県で創業した日本酒メーカー、油長酒造株式会社。加熱処理をせずにつくる「生酒」ブームの先駆者であり、また地元農家との契約栽培を行うなど、地域農業に貢献する会社としても知られている。今回、第十三代蔵主の山本長兵衛氏を取材し、人々から愛され続ける同社の製品の魅力や裏側に迫った。
入社後5年間で「日本酒づくりのノウハウ」をゼロから学んだ
ーー今までの経歴を教えてください。
山本長兵衛:
食品や流通の仕事に興味があり、大学卒業後は阪急百貨店へ就職しました。お店の最前線に立ってお客様対応をしたり、それぞれのお客様に合った商品を提案をしたり、百貨店勤務を通してコミュニケーション能力が鍛えられたと感じています。
その後、家業を継ぐため2008年に弊社に入社し、5年間ほどはお酒の製造業務を経験しました。代表取締役に就任したのは2014年のことで、それから現在に至るまで、第十三代蔵主として会社の経営を担っています。
ーー入社してから蔵主になるまでに、どのような経験を積みましたか。
山本長兵衛:
特に最初の5年間は、お酒づくりのプロセスを先輩から教えてもらい、それと並行しながら経営を学ぶことに必死でした。
また、私が入社した2008年頃は、焼酎ブームが続いていたタイミングで、当時は主力商品である「風の森」の売れ行きも思わしくない状況でした。
ただ、このときに酒屋さんたちが弊社のお酒の魅力を広めてくれていたようで、そのおかげで、その後日本酒の需要に追い風を感じるようになって「風の森」の売り上げが少しずつ伸びてきたのです。
急な需要増に応えるために、少しでも多くの製品を市場に届けられるよう、酒づくりに全力を注いだことを覚えています。
水と米にこだわった「地域を代表するお酒」を製造

ーー事業内容や製品について教えてください。
山本長兵衛:
弊社は1719年に創業したお酒づくりの会社で、主力商品は「風の森」という日本酒です。このお酒は1998年、先代の蔵主である父が「地元の人々に搾りたての生酒を楽しんでもらいたい」という思いで開発し、現在にいたるまで非加熱に特化した酒づくりを行っています。
仕込み水に使用している地下100mから湧き出る硬度250の深層地下水は、日本でも有数の超硬度の水として知られています。そして米には、透明感のある酒質を表現できる「秋津穂(あきつほ)」と、酸味や適度な渋みのある「露葉風(つゆはかぜ)」を使用しています。
使用する水と米にこだわり、非加熱によって出来上がる「ユニークな日本酒」を提供している点が、弊社の特徴です。
ーー酒づくりにおける貴社ならではの取り組みについても教えてください。
山本長兵衛:
弊社ならではの取り組みとして、文化財の研究をするための国の施設「奈良文化財研究所」と協定を結び、同研究所が持つ古代の酒造に関する知見を参考にしながら、酒づくりを行っています。
また、日本清酒発祥の地と言われる、奈良市にあるお寺「正暦寺」や五重塔でも有名な「興福寺」にあった室町時代の酒づくりのレシピをもとに「水端(みづはな)」という日本酒も手がけています。これは、まさに「奈良を代表するお酒」だといえるでしょう。
このように、昔の酒づくりを通して学ぶことも多く、私は「過去と現在の両方の良さを活かした酒づくりをしながら、美味しいお酒を提供したい」という思いで、このような活動をしています。
酒造を起点に地域貢献するのが今後のテーマ

ーー会社としては、どのような特徴がありますか。
山本長兵衛:
酒づくり業界は高齢化が進んでいますが、弊社では20代の割合が高く、若返りが起こっているのが特徴です。大変ありがたいことに、風の森を飲んだ方が、「このお酒が好きだ、このお酒をつくりたい」と、全国各地から集まってくれたのです。
若手が活躍できる環境も整っています。弊社には風の森の他にも、小規模に水端を仕込む「享保蔵」や棚田の真ん中に位置する「山麓蔵」で酒造りを行なっています。小さな酒蔵では、分業ではなく、一から十まで酒づくりに携わることができるので、早い段階で幅広い知識と技術を身につけることが可能です。
さらに、人生を賭けて酒をつくりたいという人がいても、この業界では新規の酒造免許は基本的に認められていません。そのため、他の業種のように、暖簾分け・独立はできません。しかし、弊社では主体性がある方であれば、いずれかの酒蔵で責任を持った経営を行なっていくことも可能です。
会社としても、社員たちがやりがいを持ち、主体的に働けるような組織づくりをさらに目指していきたいと思っています。
ーー最後に、今後実現したいことを教えてください。
山本長兵衛:
これから実現したいのが、他社とのコラボを通して、より多くの人に日本酒の美味しさを知ってもらうことです。
たとえばクラフトビール会社とコラボしたイベントを開催し、クラフトビールファンに日本酒の魅力を伝え、もともと日本酒にあまり興味がなかった層を日本酒ファンを取り込むことも考えています。
また、米農家の方々など、地域への貢献にもより一層力を入れるため、何かお手伝いできるような環境づくりができたらいいと思い、新しく立ち上げたのが酒蔵、「葛城山麓醸造所」、通称「山麓蔵」です。
この「山麓蔵」では、日本酒の増産が目的ではなく、日本古来の美しい環境を、地域の農業と深く関わり合いながらお酒とともに100年先に一緒に伝えていきたい、そのような思いでプロジェクトがスタートしました。お越しいただいたお客様にはこんな美しい場所があるんだと感じていただき、それをきっかけに、農家が主催する農業体験といったイベントに参加する方もいらっしゃいます。
酒蔵と農家が一体になり、酒屋さん、消費者、レストラン、と共にコミュニティを形成し、美しい風景、この地域の農業がまた100年先も続くことができる手伝いをする、そのような形を理想像として、今後もこういった活動を続けていきたいです。
編集後記
酒づくりという伝統的な産業でありながら、20代が多い油長酒造。伝統を守りつつも、今の時代に合った酒づくりを追求できるのは、若手人材によって常に新たな風が吹いていることが要因かもしれない。日本酒を起点に地域に貢献する同社は、ただの蔵元ではなく、今や地域にとって欠かせない企業だといえるだろう。

山本長兵衛/1981年11月生まれ、奈良県御所市出身。関西大学工学部を卒業後、株式会社阪急百貨店に就職。2008年油長酒造株式会社に入社し、2014年から同蔵の13代目として代表取締役に就任。














