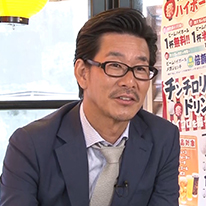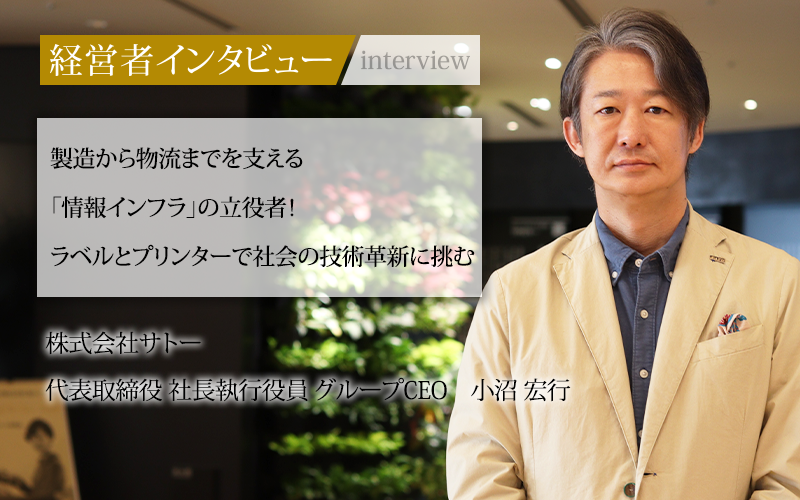
株式会社サトーは、バーコードやRFIDなどの自動認識技術を活用したさまざまなソリューションを提供するリーディングカンパニーだ。同社の製品は、製造・小売・食品・物流・医療など社会の根幹を支えている。
2023年から代表取締役社長執行役員グループCEOを務める小沼宏行氏は、現場出身ならではの視点と大胆な改革で、新たな挑戦に取り組み続けてきた。同社はこれからどのような成長を目指しているのか。これまでの歩みや事業の進化、そして今後の展望を聞いた。
「現場に根ざした経営」で改革を実現。営業職からヘルスケアの要職、そして社長へ
ーーまずは小沼社長のこれまでの経歴を教えてください。
小沼宏行:
私は2000年にサトーに入社し、最初は地方の営業職として働いていました。それらの営業成績が評価され、次に配属されたのが営業本部内の製品推進部門でした。ここでは営業と開発をつなぐ役割を担い、メーカーのイロハを学びました。その後、2010年に新設されたメディカル事業部(現在のヘルスケア部門)の初代事業部長に抜擢されました。このことが、今振り返るとこのキャリアを大きく変える転換点だったと思います。
その後、2014年にはサトーヘルスケア株式会社の社長に就任。さらに2015年からは、サトーホールディングス株式会社(現・株式会社サトー)の執行役員に就任し、組織統合やグローバル戦略の推進に尽力しました。
サトーグループのCEOに就任したのは2023年のことです。それ以来、長年にわたる経験と現場感覚を武器に、トップとしてグループ全体の新たな価値創造に挑んでいます。
ーーこれまでに行ってきた社内改革を教えてください。
小沼宏行:
最初に取り組んだのは、グループ会社間に生じていた機能の重複を整理し、全体最適を図るための構造改革です。国内外の複数拠点を再編し、海外事業部門も本体に統合しました。これにより、シナジーを最大限に活かしながら、グローバル規模で一体的な事業運営ができる体制を整えました。
子会社の社長として多くの現場を見てきた経験があったからこそ、この大胆な改革を実行できたのだと思います。現場の実情を理解していたため、スピーディーに実効性のある判断が可能だったのです。
また、改革を進める中では「冷静な視点」を保つことを常に意識してきました。特定の人や部署に偏ることなく、組織全体の最適化を重視することで、客観的かつ持続可能な成長につなげることができました。
ーーヘルスケア部門が貴社の現在の事業規模へと成長していった背景には、どのような経緯があったのでしょうか?
小沼宏行:
ヘルスケア分野に参入したのは2000年ごろのことです。最初に注力していた事業はオーダリングシステムや電子カルテ導入を支援するプリンターの提案で、それを足がかりに現場の課題に耳を傾けながら、さまざまなソリューションを形にしていきました。
その代表例が、母親と新生児のリストバンドをプリンターで同時発行して赤ちゃんの取り違え事故を防止する母子一体型リストバンド「koDakara(こだから)」です。koDakaraのアイデアを考え始めた当時は、ちょうど取り違え事故が社会問題になっていて、現場からも「忙しい中でもミスをなくせる、根本的な仕組みが欲しいがどうしたらいいかわからない」という切実な悩みが上がってきていたのです。
そこで、当時お世話になっていた病院の看護部長と意見を交わしながら、ミスをなくし看護業務をシンプルにするためのアイデアを出していき、特許を取得できるほどの革新的な商品として完成させました。
このように現場から生まれたアイデアを一つずつ具現化しながら、ヘルスケア事業は拡大を続けており、その甲斐あって売上高も、事業部化した当初の15億円からグローバル合計100億円規模にまで成長しています。
製造から医療・流通まで網羅。プリンターとラベルで社会の情報インフラを支える

ーー改めて貴社の事業内容を教えてください。
小沼宏行:
弊社は、製品や商品に情報を付与するラベルやタグ、そしてそれらを印字するプリンターを製造しています。これらの製品は、製造・小売・食品・物流・医療といった幅広い分野で活用され、情報の可視化や流通の最適化を通じて、社会の情報インフラを支える役割を担っています。
たとえば店頭の商品や宅配便の荷物に貼られているバーコードやICタグは、いずれも弊社の技術が関わっていることが多いです。こうした識別手段がなければ宅配便の出荷や賞味期限、トレーサビリティなどの確認は困難です。つまり、弊社の製品は目立たないところから社会を支える「縁の下の力持ち」といえるでしょう。
また、弊社はグローバルにも展開しており、2024年時点で26カ国に120を超える拠点を構えています。多くの国や業界で共通して使える製品を提供していることも、弊社の特徴のひとつです。
ーー貴社独自の強みについて教えてください。
小沼宏行:
弊社の最大の強みは、ラベルやタグを発行するプリンター本体だけではなく、そこで使われるラベルやタグといった消耗品までも自社で製造している点にあります。多くの会社はプリンターと消耗品を別々に調達しており、品質の安定性や運用効率に課題が生じるリスクを抱えています。しかし、弊社には一貫した製造体制が備わっているので、高い品質を安定して維持・提供することが可能です。
さらに、ラベルやタグといった消耗品は定期的に補充が必要となるため、導入後もお客様との継続的な接点を得られるという強みもあります。その中で自然と顧客との関係が醸成されていくので、アップセルやクロスセルといった新たな提案へとつなげる機会も生まれています。
また、業界間でのノウハウの応用が可能な点も大きなポイントです。医療機器や医薬品業界では高水準の品質管理や厳格なトレーサビリティが求められますが、そこで培った管理手法やラベル設計の知見は、比較的レギュレーションが緩やかな他の分野にも横展開する余地があります。こうした知見の展開は、弊社ならではの強みといえるでしょう。
ーー貴社のサービスはどのような場面で利用されていますか?
小沼宏行:
まず代表的なのが、製造業界です。さまざまなメーカーでの原材料や素材管理、製造工程の可視化やトレーサビリティのためにバーコードやRFIDと情報を管理するシステム、プリンターが活用されています。
ほかには、先ほど紹介した「koDakara」に代表される医療現場です。ここでは、患者の安全を確保するために欠かせないバーコードやRFID付きリストバンドを提供して本人確認の間違い防止に貢献しています。
また、物をラベルで管理する物流分野でも活躍しています。個人情報を守る剥がしやすいラベルや、冷凍食品にもしっかりと貼れる特殊ラベルなど、細やかなニーズに対応した製品により、物流業界の効率化に貢献しています。
多くの方が身近に感じるところでは、アパレル業界において、買い物かごを置くだけで商品点数や金額を読み取れるRFIDタグを提供していたり、さらにはインフラ関連業界では、屋外で10年以上使い続けるメーターなどに貼る経年劣化がしづらいラベルを提供していたりと、社会のあらゆる場面で弊社の製品を見ることができます。
こうした多様な現場ニーズに柔軟に応えてきた経験と技術の蓄積こそが、弊社の強みの土台そのものです。目立たない領域にありながら、社会全体の安心・便利・快適を支えることで多くの分野と密接に関わっています。
現場の声が革新を生む。新たな価値を創造する組織文化の育み方
ーー現在、特に力を入れていることについてお聞かせください。
小沼宏行:
現在、最も注力しているのは、新しい挑戦を歓迎する企業文化の醸成です。創業者が掲げた「あくなき創造」という理念のもと、ゼロから価値を生み出せる組織を目指しています。
その象徴的な取り組みが、全社員が毎日3行で社長に提案・報告を行う「三行提報」という制度です。これは、会社をより良くするための創意・工夫や気づきを、提案・報告するというもので、社員一人ひとりの問題意識と創造性を引き出す仕組みとして機能しています。
実際に、商品や業務の改善策から組織運営に関する提案まで、多様な声が日々寄せられており、現場の意見を経営に素早く反映する環境が築かれています。こうした日々の取り組みを習慣化することで、社員が自ら考え行動する風土を醸成し、持続的な成長を支える基盤づくりにつながっていくと確信しています。
今後は、こうした文化をさらに発展させ、積極的な挑戦とイノベーションが生まれやすい組織づくりを目指していきます。私自身も、過去に挑戦がうまくいかなかった経験がありますが、その過程から多くを学んできました。だからこそ、社員には「まずはやってみよう」という姿勢で、自分の発想に自信を持って取り組んでほしいのです。
社員たちのアイデアを力に新たな市場へ。創業100年を見据えた成長戦略

ーー今後、特に力を入れたいことは何ですか?
小沼宏行:
特に注力したいのは「新領域への挑戦」です。現在、社内では「CEOプロジェクト」という社長直轄のチームを立ち上げ、既存の事業領域では拾いきれない分野に積極的に踏み込む体制を整えています。
これまでは特定領域の深掘りによって成長してきましたが、企業規模が拡大する中で、他業界との連携による新たな価値の創出が求められていると感じています。
その一例として挙げられるのが、特殊なRFID技術を活用した医療現場での血液管理と、廃棄物処理におけるトレーサビリティの強化です。
前者では、血液の情報と流通を厳密かつ自動に管理することで、輸血時の安全性を大幅に高めることが可能になります。後者では、廃棄物の発生から再資源化までの流れをデータで可視化することで、再生資源の品質担保や生産予測、資源循環の促進といった社会課題の解決に寄与できます。
これらのテーマはいずれも国際的なニーズが高いので、今後は国内外の医療や環境関連機関との連携を強化し、より実用的かつグローバルに通用する仕組みを構築していきたいと考えています。
ーー今後、貴社をどのように成長させたいとお考えですか?
小沼宏行:
2030年に売上高2000億円、営業利益210億円という数値目標を掲げていますが、目指すのは単なる規模の拡大ではありません。本質的には、社会にとってなくてはならない存在としての価値を高めていくことこそが、弊社の真のゴールだと考えています。
そのためには、ブランディングにより弊社の姿勢や価値を社会に伝え、共感を得ることが欠かせません。これまでは縁の下の力持ちとして社会を支えてきましたが、これからは表舞台に立ち、私たちが果たす役割を広く知っていただくことが重要です。
さらに、製品やサービスの提供を通じて得られるデータを活用し、IoT技術と組み合わせて現場の改善に貢献する仕組みづくりにも注力していきます。サプライチェーンを横断した自動化によってお客様のオペレーション効率を高めたり、潜在的な経営課題を可視化することができれば、弊社は単なる機器メーカーではなく、価値を共創するパートナーとして、より深い関係性を築いていけるはずです。
ーー最後に、読者にメッセージをお願いします。
小沼宏行:
企業の成長にとって、事業の拡大は重要な要素です。しかし、私がより重視しているのは、社会にとっての存在意義を高めていくことです。
弊社は創業から85年を迎え、100周年という節目を見据えて新たな歩みを進めています。この大きな節目を間近に控えているからこそ、社会から必要とされ続ける企業であるための努力を止めず、より挑戦的であるべきだと考えます。
私の役割は、来たる100周年に向けて企業としての責任を自覚しながら、次の世代へ良い形でバトンを渡す準備をすることです。その中で、弊社のビジョンや活動に共感し、ともに未来を創る仲間が一人でも多く加わってくれることを願っています。
編集後記
小沼社長が先導する、現場の声に根ざした開発力と、挑戦を後押しする文化。この2つを兼ね備える同社は、社会の裏方を支える存在でありながら、社会構造の変化を先導する存在に映った。グローバル展開や新領域への挑戦を経て、今後は社会にとって不可欠な存在として多くの人から認知される存在になるだろう。その成長は確実に社会を変えていくはずだ。

小沼宏行/1973年、東京都出身。2000年、株式会社サトーに入社。営業時代に医療従事者の現場の声と社会問題に着目して、母親と新生児のリストバンドをプリンターで同時発行する「koDakara」を企画開発(のちに特許取得)。医療業界のリストバンド普及に尽力・拡販した実績を持つ。2014年にサトーヘルスケア社長に就任、2015年からサトーHD執行役員などを経て、2023年より現職。