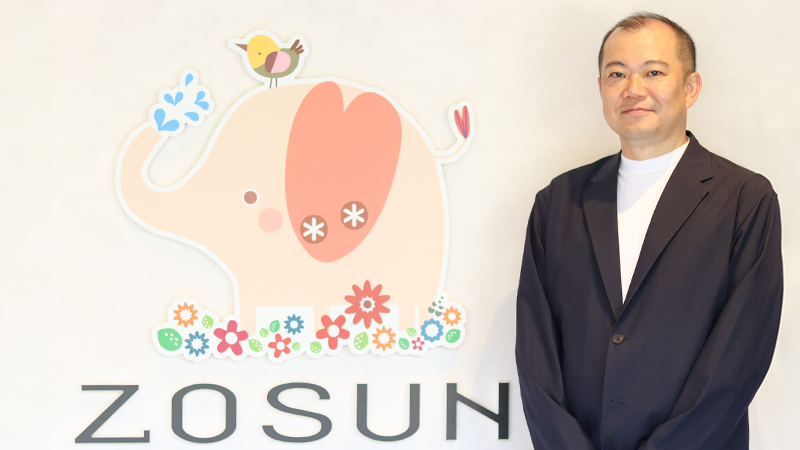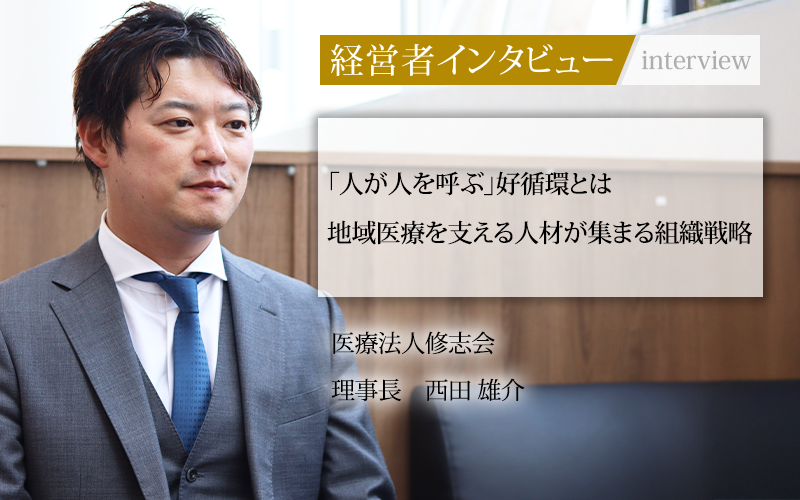
在宅医療を軸に、地域密着型の診療体制を広げてきた医療法人修志会。埼玉県越谷市での創業から始まり、現在では地方都市への展開や多職種との連携、柔軟な勤務体制の導入など、多様なニーズに応える組織づくりを進めている。
その根底にあるのは、理事長西田雄介氏が掲げる、患者の生活そのものに寄り添う医療への強い思いだ。では、西田理事長は在宅医療でどのような未来を目指しているのか。訪問診療で地域医療の未来をつくる取り組みや組織戦略について話を聞いた。
患者の暮らしそのものを支える姿に心を打たれ、訪問診療クリニックを開業
ーー西田理事長のご経歴をお聞かせください。
西田雄介:
私は東邦大学医学部の出身で、卒業後は東京女子医科大学病院での研修を経て、同病院の整形外科講座に入局。当時は手術に明け暮れる忙しい日々を過ごしていましたが、どこかで「このままの人生でいいのだろうか」という疑問も抱いていました。
そこで私が選んだのが、思い切って退職し、世界中を旅して回ってみるという道です。旅先では、障害を抱えながらも自分らしく生きる人や、行き先すら決めずに旅を続ける自由な旅人など多くの人たちとの出会いがあり、いつしか「自ら決断をして実行していくことが大事である」と心から思えるようになりました。
その後、日本に帰国した私は、先輩のクリニックで働き始めたのですが、ここで在宅医療との出会いを果たします。病気を診るだけでなく、患者さんの暮らしそのものを支えるこの分野に惹かれ、自分が目指す医療はここにあると強く感じました。
こうした経緯があり、2017年に訪問診療のクリニック「ファミリークリニック越谷」を開業。その後、ありがたいことに少しずつ患者さんの信頼をいただき、拠点も徐々に増えております。
ーー開業後、特に印象に残っている苦労や転機について教えてください。
西田雄介:
開業して最初に直面したのは、人材の問題でした。幸いにも患者さんからの信頼は厚く、集患での苦労は少なかったのですが、人を雇い、組織を回していくという面では多くの課題にぶつかりました。
特に忘れられないのがコロナ禍の始まりの時期です。当時は「病院に行きたくない」という患者さんの声が多かったことから、訪問診療のニーズが急激に高まり、患者さんから市役所への問い合わせの電話が当院にそのまま転送されるという状態が続いていました。
多くの患者さんに対応したい気持ちはあるのですが、あまりの忙しさと感染への恐怖からか、スタッフから「これ以上対応しきれない」と告げられて、スタッフが大量退職してしまったことがあります。そのときは、さすがに心が折れかけました。
しかし、共感してくれる新たな仲間が一人、また一人と増えていきました。おそらく、「私一人でも診療を止めない」と私がどんな状況でも訪問診療をやめなかった姿を見て、その姿勢に共感してくれたのだと思います。
この時期に訪問診療の本質を再確認したと同時に、自分自身の経営観も大きく変わっていきました。1人の力では限界がある、チーム力を高めることが地域医療に貢献するために必要であると強く感じました。
医療の質を支えるのは人の力。信頼の連鎖でつながる現場と仕組みづくり

ーー貴法人の組織としての強みはどこにあるとお考えですか?
西田雄介:
一番の強みはドクターとスタッフの質の高さです。基本的な診療能力が高いのはもちろんですが、スタッフ一人ひとりが患者さんが求めていることをキャッチアップしながら働いている点が大きいです。ニーズを適切に汲み取り、最大限応える努力をしています。
そして、各拠点に信頼できる人材が配置されていることも強みです。各拠点に“要”となる人材がいることで、現場の管理や採用、研修などがスムーズに行われています。また、この“要”となる人材がさらに人を呼び込んでいくという、人材確保の良い流れができつつあります。
さらに、各拠点の理念や方針を統一するために、院長会議や事務長研修も定期的に開催。普段は現場に任せつつ、意思の統一はしっかりしていくことで、現場の力を最大限に活かせる組織づくりが実現できています。
目指すのは「地域医療の活性化」。事業承継を活用しながら全国30拠点を目指す
ーー今後、特に注力していきたい取り組みについてお聞かせください。
西田雄介:
特に力を入れたいのが地方医療の活性化です。医師の数が少ない地方では、一人の医師が昼夜を問わず対応しているケースも少なくありません。そうした状況を少しでも改善できるように、期間限定の地方勤務や週2日だけの出張といった柔軟な働き方を導入しながら、チーム力で地方医療を支える施策を行なっています。
また、精神科や小児科など、これまで在宅医療が届きにくかった分野への対応も推進中です。さらに、地域のインフラとしての役割をより高めるため、カフェの併設や地域イベントへの参加など、非医療の活動にも積極的に取り組み、今より一層身近な存在になれればと思っています。
そして、地域の医療を維持していくためにM&Aによる事業承継も進めています。年齢や後継者不足により廃業する医師から事業を受け継ぎ、スケールメリットを活かしながら各地に質の高い医療サービスを提供することを目指しています。
ーー5年後、10年後のビジョンについて教えてください。
西田雄介:
2030年までに「年商100億円・30院・50拠点体制」を実現し、医療が必要とされる場所にサービスを届けられる体制を整える方針です。そのために自前での医師確保に加え、事業承継なども柔軟に活用しながら、地域に根差した医療の拡充を目指しています。
また、未経験者にも垣根が低く、成長を実感できる環境を構築するために、大学との提携や実習・見学の受け入れ、そして人材開発を担う専門部署の整備も積極的に行なっています。
これから共に働く仲間として、職種や経歴にとらわれず、「医療の枠を超えて地域に貢献したい」という思いを持つ人を歓迎しています。志を同じくする仲間と共に、医療と地域をつなぐ仕組みをさらに広げ、次の10年をつくっていきたいですね。
編集後記
修志会の強みは、ドクターとスタッフが患者の思いを的確に捉えようとする姿勢にある。そこから生まれた信頼の積み重ねが、各拠点内で浸透し、人のつながりによる自然な組織形成を可能にしている。地域医療の担い手不足が課題となる中、信頼を軸にしたこの循環型の運営は、地域医療の活性化に向けた一つの解をもたらしてくれるかもしれない。

西田雄介/1984年広島県生まれ。修道高校卒業、東邦大学医学部卒業。2008年東京女子医科大学病院での研修ののち同病院整形外科講座に入局。専門医取得後に退局し、バックパッカーとして世界を回る。その後在宅医療と出会い、2017年埼玉県越谷市で訪問診療クリニックを開業。