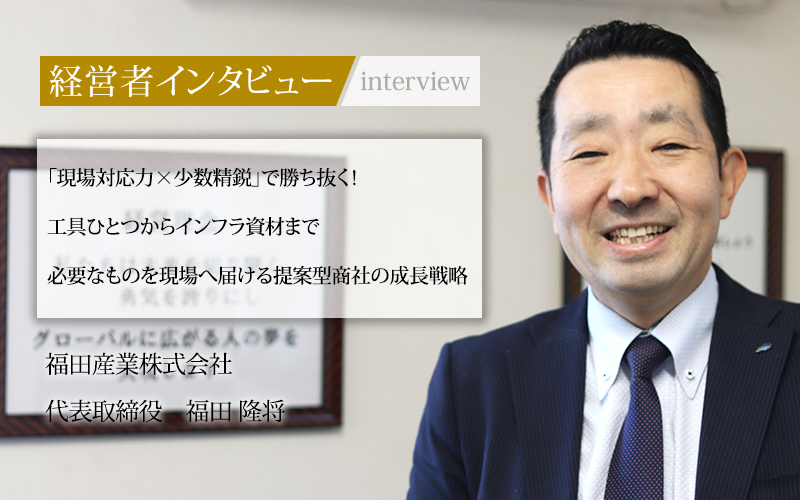
「爪楊枝からロケットまで」と語られるほど、あらゆる建材・梱包資材を扱う商社、福田産業株式会社。1971年の設立以来、横浜を拠点に全国の現場に寄り添いながら成長を続けてきた。現在では海外調達ルートの開拓や、在庫リスクと向き合う柔軟な営業体制など、変化の激しい流通業界において独自の立ち位置を築いている。
今回は、二代目として現場感覚を重視しながらも、次世代を見据えたリーダー育成や評価制度の再構築にも取り組む代表取締役の福田隆将氏に、組織づくりの哲学と今後の展望を聞いた。
現場感覚を武器に歩んだ二代目社長のキャリアと、海外での経験がもたらした視野の広がり
ーー社長の経歴をお聞かせください。
福田隆将:
私は大学卒業後、家業である福田産業に入りました。幼い頃から周りに「将来は社長になるのだろう」と言われていたこともあり、「将来は家業を継ぐんだろう」と自然と意識していましたが、内心では別の生き方にも惹かれていました。
将来の自分の仕事について考える中、当時日本中が景気も良く、当たり前だった大量生産・大量消費を前提とした働き方には違和感があり、もともとのんびり屋の私は「価値観の異なる環境で生きたい」と考え、20代の頃、イギリスへ渡りました。現地の暮らしは自分に合っており、しばらくはそのまま海外で生活することも考えていたほどでした。
しかし、父の体調悪化を知らせる母の手紙を受け取り、会社の状況も厳しいと知ったため帰国を決断。最初は「少し手伝うだけ」のつもりで戻ったのですが、気づけば本格的に業務に関わるようになっていました。
なかでも、英語力を活かして中国をはじめ、ドイツ、オーストラリア、アメリカなど各国のメーカーと直接交渉し、国内では入手しづらい商品を調達することで商品力を強化し、自社の強みをさらに引き出せたことが、大きな転機でしたね。
これにより、価格競争力と利益率の向上を実現できたうえに、輸入商材を拡充したことで、海外ルートの確立や会社の事業基盤を広げることにも成功しました。
ーー組織を運営するうえで意識していることや、実際に行ってきた社内改革について教えてください。
福田隆将:
私が社長として意識しているのは、理想とするリーダー像を描き、その姿に近づく努力を続けることです。先頭に立つ力に加え、俯瞰的に状況を見極めて判断する視点が求められる中、自分のありたい姿を言語化し、日々の行動に一貫性を持たせることを大切にしています。
この考えを軸に、部門ごとに自律的に動ける人材の育成にも注力しています。現在は人事評価制度の再構築にも取り組んでおり、評価基準の明確化や1on1面談などを通じて、社員との信頼関係を築き直しています。
こうした組織づくりの根底にあるのが、「人」に宿る価値です。お客様との信頼関係は、営業担当の姿勢や心配りによって育まれており、商品や価格では代替できない“人”起点の信頼こそが、弊社の競争力の源だと考えています。
価格や商品力だけではない“人”を起点にした商社としての信頼と多様性が強み

ーー貴社の事業の特色や、他社と差別化できる強みはどこにあるとお考えですか?
福田隆将:
弊社の最大の強みは“人”だと考えています。中でも営業担当が顧客と築く信頼関係は、商談の成否を左右する重要な要素です。実際に、「福田産業だから」ではなく「この営業マンだから取引する」と言ってくださるお客様が多くいらっしゃいます。同じ価格、同じ商品であっても、そこに添えられた一言や気配りによって信頼が深まっていくのです。
加えて、弊社は多品種・小ロットに柔軟に対応できる点も特徴です。取り扱う商材の幅は広く、建設や梱包などさまざまな業界を横断しており、現場で必要とされるものを即座に届ける体制を整えています。こうした対応力や現場感覚に根ざした機動力は、画一的な物流モデルではカバーしきれない価値だと考えています。
一方で、社会や市場の変化にも目を向けなければなりません。従来のやり方が通用しづらくなっている場面も増えるなかで、公共工事をはじめとしたインフラ系の需要に目を向け新たな事業の柱を育てていくことが、今後の成長に欠かせないと感じています。
リーダーを育てて組織強化につなげる。少数精鋭で機動力のある商社に成長するには
ーー今後の成長戦略や、目指している組織の姿について教えてください。
福田隆将:
将来的には、売上100億円規模を見据えつつ、持続可能な成長を実現していきたいと考えています。とはいえ、むやみに拠点を増やすのではなく、少人数でもしっかりと利益を生み出せる“コンパクトで強い組織”が理想です。人員や在庫をいたずらに増やさず、効率よく回る仕組みを整えていくことが、今後の成長に不可欠だと感じています。
また、私一人がすべてを決めるのではなく、現場ごとに判断し行動できるリーダーを育てていくことが、これからの組織づくりには欠かせないと考えています。自然とリーダーシップを発揮する人材は組織の中で必ず現れてきます。そうしたメンバーの力を引き出し、適性に応じて拠点や部門を任せられるよう育てていくことで、それぞれが活躍できる場を広げ、組織全体の力を高めていきたいと考えています。
そうした体制を実現するためには、幹部層の育成と同時に、バックヤードの強化も欠かせません。現在は在庫管理や受発注など、アナログな業務が残っている部分も多く、IT化を軸とした業務改革が急務です。「在庫を滞留させず効率的に回す」という考えを軸に、無理のない規模感で、長く続けられる堅実な組織づくりを進めていきます。
編集後記
福田産業の特筆すべき点は“現場に根ざした柔軟性”と“人に宿る営業力”によって、競合と一線を画しているところだ。単なる物流ではなく、必要な時に、必要な場所へ、必要なものを届けるという姿勢が、顧客の信頼を生み、リピートにつながっている。資材流通の現場から新しいスタンダードを形づくる企業として、今後の展開に注目が集まる。

福田隆将/1974年生まれ。東海大学卒業。父である福田隆雄(現会長)が経営している福田産業株式会社に入社、入社後、配達ドライバーとして働いた後渡英。現地でメディア関係の専門学校に入学し、卒業後は現地ケータリング会社のARAMRK社に入社。2002年に帰国し、同年再度福田産業株式会社に入社。取締役を経て2014年に代表取締役に就任。














