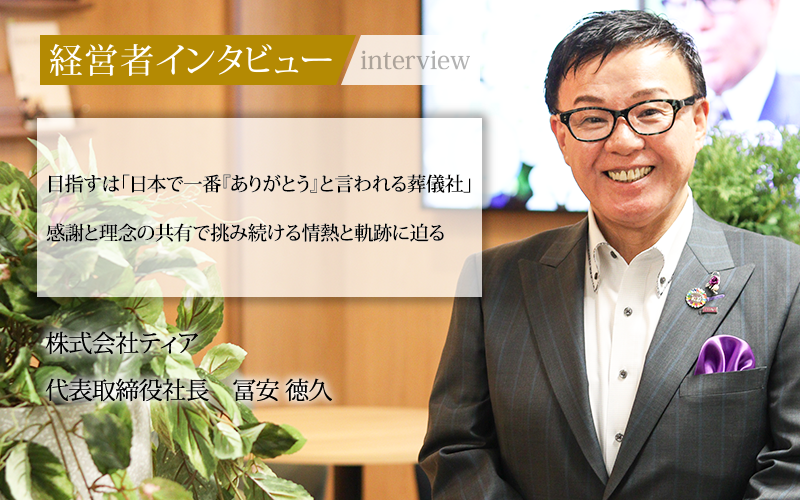
「人の死を扱うからこそ、誠実でなければならない」。そう語るのは、株式会社ティアの代表取締役、冨安徳久氏だ。18年間の葬儀現場経験で感じた業界の不条理と矛盾を胸に、30歳で独立を決意し、37歳で起業。「『ありがとう』の数で日本一」を目指す異端の葬儀社は、今や東海地区で圧倒的な存在感を放つまでに成長した。時代に応じて進化を遂げながらも、冨安氏が貫いてきた信念とは何か。その情熱と軌跡を辿る。
起業の原点にあった「怒り」と「使命感」
ーー葬儀業界に入ったきっかけをお聞かせください。
冨安徳久:
大学入学直前の春休みに、生活費を稼ぐために紹介されたアルバイト先が、葬儀社でした。最初は特別な思いもなく始めた仕事でしたが、やがて、ご遺族の深い悲しみに寄り添い、時には涙を流しながら感謝の言葉をいただく場面に出会い、「こんなにも深く人に感謝される仕事があるのか」と心を動かされたのです。
振り返れば、祖母はとても厳しい人で、幼い頃から常に「人の役に立ちなさい」と言われて育ちました。そのため、眼の前で困っている人に手を差し伸べることが、人としての本分だと教えられてきたのです。その教えと、葬儀の仕事で感じた使命感は、私の中で自然と重なりあっていきました。
ーーその後、どのような経緯で本格的に業界へ進んだのでしょうか。
冨安徳久:
最初に勤めた山口県の葬儀社を3年ほどで退職し、地元である愛知県の大手互助会系の葬儀社に勤めました。30歳の頃には店長やマネージャーとして現場を任されるようになりました。
しかし、その会社が「生活保護を受けている方の葬儀は引き受けない」という方針を打ち出したことで、私の価値観と深く衝突することになります。とくに、初めに勤めた会社で、「持てる者も持たざる者も、仏様の前では平等だ」と教わってきたため、その姿勢には納得ができなかったのです。
こんな理不尽なことが許されていいのかと強い憤りを感じたと同時に、「私が変えなければ、誰がやるのか」という使命感が芽生えました。そこから独立に向けて準備を進め、37歳の誕生日に株式会社ティアを設立。人生を賭けた挑戦が始まりました。
価格の透明化と理念の徹底がもたらした信頼
ーー創業にあたり、大切にされていたのはどんなことですか。
冨安徳久:
最も重視したのは、価格の透明化です。当時の葬儀業界は、料金体系が不明瞭なまま進行し、あとから高額な請求をするというケースが少なくありませんでした。さらに、生活保護受給者を露骨に切り捨てるような方針を掲げる企業もありました。
初めて働いた葬儀社では、経済的な事情に関係なく受け入れる体制で、私の中には誰に対しても丁寧に寄り添う精神が根付いていました。ですので、「お金がないから断る」といった方針は、どうしても納得がいきませんでした。そして、「人の死を扱う仕事に、分け隔てがあってはならない」「死の前では、すべての人が等しく、尊い存在であるべきだ」と強く感じるようになりました。
ーーその想いから「ティアらしさ」が生まれたのでしょうか。
冨安徳久:
まさにその通りです。すべての価格をオープンにすることで、お客様に安心して選んでもらえる葬儀社を目指しました。また、もう一つ大切にしたのが、スタッフと理念を共有し、徹底することです。創業時に掲げた「日本で一番『ありがとう』と言われる葬儀社」というスローガンは、売上や利益ではなく、人からの感謝の想いを軸に会社を成長させていこうという決意の表れでもありました。
価格の透明性と理念の徹底がお客様からの信頼につながり、その信頼が社員にも波及していく、そんな好循環を築きたかった。業界の構造的な問題に対して、誠実な仕組みで応えることが、自分にできる変革だと信じていました。
理念経営で突き進んだ「ありがとう」の葬儀社

ーー創業当初に掲げた目標を教えてください。
冨安徳久:
弊社を創業したとき、「10年で上場・20店舗・シェア10%」という3つの目標を掲げました。そして、売上ではなく「『ありがとう』の数で日本一」を目指すという、業界の常識からすればかなり異端な方針も打ち出しました。正直、無謀だと笑われることもありましたが、私は本気でした。
自分がこの仕事に出会ったとき、「こんなにも感謝される仕事は他にない」と感じたとお話しましたが、その感動を一人でも多くの人に味わってほしい。そして、重く捉えられがちな葬儀を、感謝の気持ちで包むことができるなら、業界全体のイメージを変える力にもなると考えていました。
ーー起業から上場までは、どのような道のりでしたか。
冨安徳久:
簡単な道ではなく、苦難や挫折も数え切れないほどありましたが、掲げた目標は一度もブレませんでした。結果として、創業から8年11ヶ月で名証セントレックスへの上場を果たし、さらには20店舗、シェア10%の目標も達成しました。「言ったことは必ずやり遂げる」という信念が、社員たちの士気にもつながったと感じています。
理念を根幹に据えた人材教育と仕組み化
ーー人材教育において、どんなところに力を入れていますか。
冨安徳久:
人財教育において、理念はすべての出発点です。創業以来、私が直接、社員に対して理念の意義と背景を徹底的に語りかける「社長セミナー」を継続して行っています。これは、トップの言葉でしか届かないものがあると考えているからです。
また、教育の場として、本社の隣には人財教育を担う育成専用施設として「THRC(ティア・ヒューマン・リソース・センター)」を構えています。実際の会館を模した研修スペースを備えており、祭壇や親族控室などは会館と同じ仕様です。新卒社員を中心に、葬儀の流れをより実践的に学べる環境を整えています。
加えて、採用、教育、評価の三大人事領域すべてを、経営理念に基づいて運用しています。たとえば採用では理念への共感を重視し、教育では理念を軸に行動を導き、評価でも理念に沿った姿勢が反映されるような仕組みにしています。
ーーなぜここまで理念にこだわるのでしょうか。
冨安徳久:
理念がない組織は方向性を見失いやすいからです。私は過去に、理念を持たない役員が経営している会社で働いたことがあり、そのとき感じた違和感が原体験になっています。同じ目標に向かって団結するには、全員が理念を共有し、常に意識していることが不可欠です。そのため、弊社では経営理念の暗唱も推奨し、頭と心に深く刻み込むようにしています。
ーー採用方針にも、理念を強く反映させているのでしょうか。
冨安徳久:
以前は経験者を積極的には採用していませんでした。今は経験の有無にこだわらず採用活動をしており、新卒採用も行っています。入社後の人財育成と徹底的な理念共有がブレない組織づくりになると考えています。
「感動」が生み出すリピーターとティアらしさ

ーー貴社の強みについて教えてください。
冨安徳久:
弊社では、葬儀は単なるお別れの儀式ではなく、人生の最期に人が人に感謝を伝える大切な場だと考えています。だからこそ、哀悼だけでなく“感動”を届ける必要がある。その感動が、心の奥深くに届いたとき、「この葬儀社に頼んで本当に良かった」「またお願いしたい」と思ってくださるのではないかと思います。
どこの葬儀社でも最低限のセレモニーは提供できます。でも、ご遺族の心にささる、「ありがとう」と言われるような体験を提供できるかどうか。そこに、ティアの真価があると思っています。「感謝を伝える場を、感謝で満たす」ことが私たちの使命です。
ーー貴社の「感謝想」というサービスも、その延長線にあるのですか。
冨安徳久:
「感謝想」は、生前にご家族やご友人に感謝の気持ちを伝える新しい文化として弊社が提案しているものです。お客様から「こんなかたちでお礼が言えるとは思わなかった」と涙を流して喜ばれたこともあります。「感謝想」のことをより多くの人に知ってもらい、死の間際ではなく、生きているうちに感謝を伝える意義を、社会に広めていきたいと思っています。
「感謝想」などの新しい挑戦に取り組むのは、時代の流れに対して受け身ではなく、自らが潮流をつくる側でありたいからです。これからの日本社会に必要なのは、心を通わせ合う機会を意図的につくっていくこと。その一端を、弊社が担っていきたいです。
人生に寄り添い、社会とつながる企業へ
ーー貴社では生活支援事業にも力を入れているそうですね。
冨安徳久:
ティアの会員様向けに、生活関連サービス、相続・不動産などの支援事業を展開しています。「葬儀だけではなく、人生の節目に関わるさまざまなシーンでお客様を支える存在になりたい」という想いが出発点です。お客様の人生に長く寄り添い続けることが、ティアの大きな強みになると考えています。
今後は、人生の最期だけでなく、「人生そのもの」に向き合う企業へと進化していきたい。そのため、「感謝想」や生活支援サービスを通じて、亡くなる前の段階からお客様との関係を築いていくことを大切にしています。それにより、「ティア」というブランドに対する信頼も高まっていると感じます。
ーー事業拡大にあたって、どのような戦略を描いているのでしょうか。
冨安徳久:
全国展開に向けて、直営店舗の出店に加え、企業連合やフランチャイズ、M&Aといった多様な手段を用いています。事業パートナーとともに業界全体のサービス品質を底上げすることで、社会全体に貢献できると信じています。
「命の仕事」としての誇りと、未来への願い
ーーその他に、注力されていることはありますか。
冨安徳久:
「命の授業」と題した講演活動を、全国の学校で続けています。これまで、数多くの自死遺族と向き合い、亡くなった本人がどんなに苦しかったか、ご遺族がどれほど深い悲しみに暮れるかを目の当たりにしてきました。
日本は若年層の自殺者数が世界で最も多い国です。どんな理由であれ、自殺した若者の話を聞くと胸が痛み、自分にできることはないかと考えていました。そこで、死に立ち会う仕事をしてきた者として話をすることにしました。講演では、子どもたちに“生きる意味”を伝えるため、自殺してはいけない理由、人が人の役に立つことの尊さを語っています。悲しみを未然に防ぐために何ができるか、常に考えて行動してきたつもりです。
また、大人がもっと楽しそうに働く姿を見せないと、子どもたちは未来に希望を持てないと本気で思っています。だからこそ、まず自分自身がワクワクしながら働き、社員にもそうあってほしいと願っています。そのために会社としても、やらされる仕事ではなく「やりたい仕事」を任せられる環境づくりに力を入れています。
ーー今後、どのような会社に成長させたいですか。
冨安徳久:
「自分の子どもを働かせたいと思える会社」が理想です。業界で一番給料が高く、休みが多く、残業が少ない。それでいて、社会的意義のある仕事に誇りを持てる。そんな会社づくりをしています。働く環境が整えば、社員はもっと成長できるし、その成長がまたお客様の感動につながる。だから、仕組みと理念の両輪で、「命の仕事」に挑む会社であり続けたいと思っています。
ーー最後に、伝えたいことはありますか。
冨安徳久:
実は、今年の秋にTBSスパークル様の制作で私の半生を描いた書籍『最期の、ありがとう。』がドラマ化されることが決まりました。18 歳で葬儀業界に飛び込み、さまざまな人の「死」に立ち会いながら成長し、東証上場を成し遂げる、事実を元にした物語です。主演の永田崇人さんや市原隼人さんなどにも出演いただく本格的なドラマですので、ぜひご覧いただきたいですね。
(※)ショートドラマ:『最期の、ありがとう。』
編集後記
怒りや疑問を原動力に、感謝と誠実さで突き進んできた冨安氏の歩み。業界の常識を覆しながらも、人に尽くす姿勢を貫くその姿勢に、心を動かされる取材だった。理念が人を育て、組織を育て、社会を変えていく。どの発言にも、揺るぎない信念とあたたかな人間味が通底しており、この会社がこれから先、どんな未来を築いていくのか、楽しみでならない。

冨安徳久/株式会社ティア代表取締役社長。葬儀社での現場経験を経て、1997年に株式会社ティアを創業。創業当初から「日本で一番『ありがとう』と言われる葬儀社」を理念に掲げ、価格の透明化や人材教育に尽力。現在は全国展開を視野に、生活関連事業や感謝想などの新規事業にも積極的に挑戦している。














