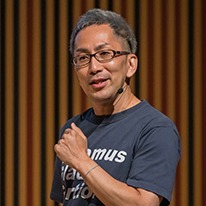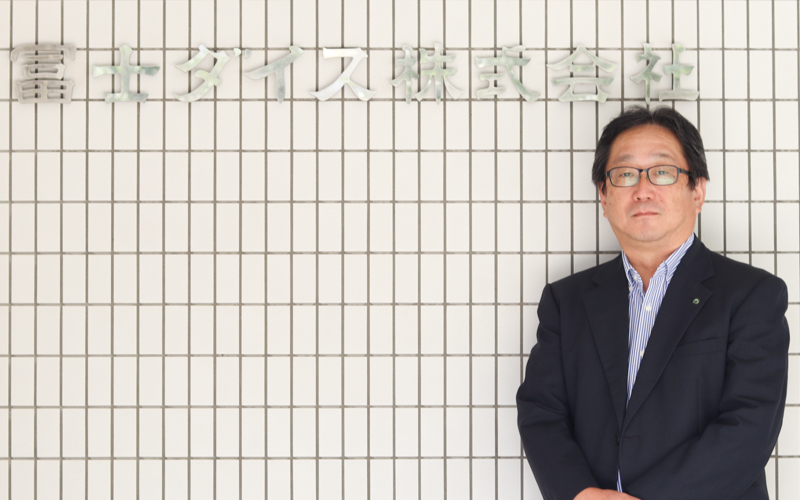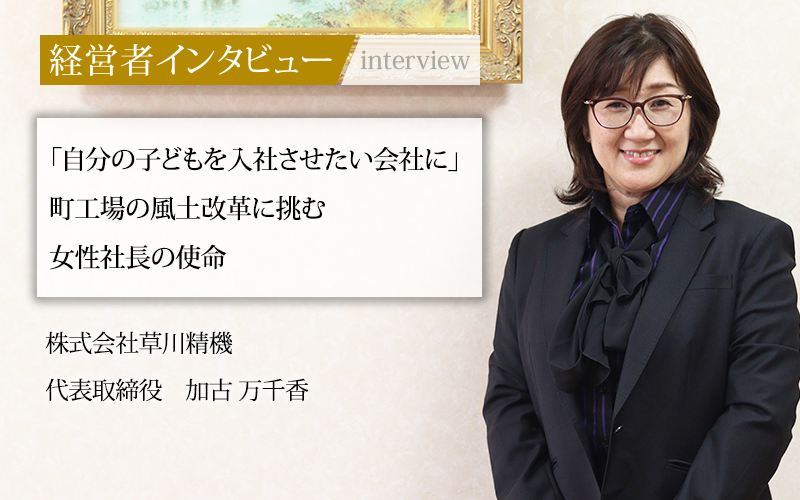
日本の製造業は今、デジタル化による大きな変革期にあり、今や町工場でもデジタル技術の導入が欠かせない。1962年創業の株式会社草川精機も、半導体や液晶装置向けの精密部品製造を軸に変革を進めている。
2023年に社長に就任した加古万千香氏は、職人技に依存した体制から、若手が活躍できるチーム型の組織への移行を推進。分業制やDXの導入により社内の風土も変わりつつある。「自分の子どもを入社させたいと思える会社にしたい」と語る加古社長に事業内容や、変革への取り組み、今後のビジョンについてうかがった。
決断力で成長し日本のものづくりを支える草川精機の軌跡
ーー貴社の沿革と飛躍することになった転機について教えてください。
加古万千香:
草川精機は1962年、京都市下京区梅小路で創業しました。創業当初は家族で営む小さな町工場として、金属を削って精密部品をつくる切削加工を手がけていました。やがて親戚や近隣の人々が加わり、徐々に規模を拡大していったのです。
草川精機の大きな転機となったのが、二代目社長による半導体や液晶製造装置への着目です。まだ多くの町工場が対応できなかった時代に、大型マシニングセンターを導入し、高精度かつ高難度な部品加工に挑戦。この先見性が、液晶テレビの普及とともに会社を飛躍的に成長させました。
ーー現在の事業内容について詳しくお聞かせください。
加古万千香:
弊社では精密部品の切削加工を行っています。主にアルミやステンレスなどの金属を扱い、売上高の約60%が半導体・液晶製造装置の部品です。また、スマートフォンのフラットパネルディスプレイ製造装置の部品も手がけています。この実績が世界シェアトップを誇る製造装置メーカーに評価され、その技術力と品質保証体制が草川精機の最大の強みとなっているのです。
他にも食品関係の部品として、お酒や牛乳などの充填機の部品や、薬のパッケージング機械の部品も製造しています。また、人工衛星や航空機の部品なども手がけています。弊社のような町工場が、大手メーカーを支え、ひいては日本のものづくりの一端を担っていることが誇りです。
ISO取得を目指し組織体制を刷新

ーー貴社に入社されてからの経緯を教えてください。
加古万千香:
1999年に歯科医療機器メーカーからキャリア採用で入社しました。当時の社内は、家族経営ならではの結びつきが強く、当時の草川社長(現会長)、会長(創業者)を中心とした意思決定が主流だったのです。職人気質の社員も多く、熟練の技術に支えられた現場でしたが、その一方で、若手社員が活躍し定着していくには、少しハードルが高い側面もありました。
二代目社長は実直なものづくりに徹し、私は経理や人事を任されるようになりました。
2002年にISO9001の認証を取得したことも、草川精機にとって転機となりました。ISOの取得には「組織としての機能」が求められるため、それまで社長や会長に判断が集中していた体制を見直す必要があったのです。
当時の草川精機は、明確な役職や部門の区分が曖昧な状態でした。しかしISO取得に向けて、部署ごとに責任者を置き、業務フローを文書化。社内の工程や役割を明文化することで、ようやく「組織としての企業」基盤が整い始めたのです。
この取り組みにより、社内の見える化が進み、品質管理体制の強化や、属人性の脱却にもつながりました。また、責任の所在が明確になることで、若手社員の定着率も徐々に改善し始めました。
ISOの認証取得は単なる制度導入ではなく、草川精機が「家族経営の町工場」から「継続可能な製造企業」へと成長するきっかけとなった、象徴的な出来事だったといえます。そこから風土改革が始まり、一人ひとりが活躍できる会社を目指して、幹部研修や全社員への面談を実施するようになったのです。
また、製造現場も大きく変革しました。それまでは職人が個々のやり方で加工を行い、新入社員には教えるより見て覚えろの風潮がありました。また、若手が自由に道具や工具を使えないといった状況でもあったのです。
こうした体制では、若手が育ちにくく、入社しても短期間で離職してしまうケースが多発していました。また、技術が属人的で共有されないため、誰かが欠けると業務が滞るというリスクも抱えていたのです。
その問題を解決するために、社内の標準化、共有化、データ化、そして分業制を採用し、職人に依存しないものづくりの改革を行いました。今では未経験入社の若手が活躍できる職場となりました。
一方で、弊社では「事業の承継」という経営課題を抱えていました。2014年に草川前社長(現会長)から、従業員から経営者を育成する方針が出されました。そのことを一任された私は、教育研修と面談を実施して、草川前社長のカリスマトップダウン経営から、チームで経営を行うボトムアップ支援経営を目指し、風土改革を推進することにしたのです。
ーー具体的にどのような変革を進められたのでしょうか?
加古万千香:
最大の課題は、社員が指示待ちの状態から自ら考えて行動する組織に変えることでした。そのために、定期的な幹部研修と全社員への面談を続け、財務会計の研修も取り入れました。数字を理解することで、部門間の壁を取り払い、当事者として会社全体のことを考えられる社員を育てようとしたのです。
コロナ禍ではさらに、チームワークとリーダーシップが発揮されました。「ローラー大作戦」という新規営業施策を展開し、売上目標の353%を達成しました。この成功体験も社員の自信につながったようです。2023年5月に社長に就任しましたが、私一人で経営を担うのではなく、財務、営業、製造、生産管理、品質管理の各分野を担当する幹部5人でチームを組み、協力しながら運営しています。これは、前社長が長年にわたり担ってきた多岐にわたる役割を、分担しながら継承していくという考え方に基づいています。
“3K”のイメージを覆す。若手が誇れる職場を目指した現場改革の全貌
ーーDXや採用強化についての取り組みをお聞かせください。
加古万千香:
現在ほどDXが叫ばれる時代ではなかった約20年前に「ファクトリーマネージャー」というソフトを導入し、職人の技術をデータ化して分業制を確立しました。プログラマーがプログラムを作成し、機械オペレーターがそれを使用することで、未経験者でも精密部品の製造ができるようになったのです。
工具も全てシステムで管理し、リスト化することで、専門知識がなくても作業ができるシステムを構築しています。
最近ではこれまで紙で管理していた図面や工程をデータ化するCADDi Drawerを導入し、図面の資産化とペーパレスを推進し、情報の共有化と効率化を図っています。AIによる加工プログラム自動生成システムを試験導入したほか、GoogleストリートビューやSlackなどのコミュニケーションツールも充実させています。
さらに、道路工事用のロードカッターで発生する廃材の積載量を測定する装置の開発など、新規事業にも挑戦しています。ベンチャー企業と協力し、動くコンベア上の廃材重量をリアルタイムで測定する技術を開発中です。
採用面では、製造業のイメージを変えることに力を入れています。3Kといわれる職場環境から脱却するために、作業服のデザイン変更や職場環境の改善を行いました。「町工場」ではなく「クリエイティブ集団」としてのイメージづくりを目指しています。
工具のシステム管理やファクトリーマネージャーの導入により、未経験者でも精密部品の製造ができるようになったことが、採用と定着につながっています。
若手社員の意見を、積極的に取り入れる風土も定着してきました。以前は考えられなかったことですが、今では社員が自分たちの職場環境を良くするための提案を積極的に行ってくれています。社長室に社員が相談に来ることも増え、社内の雰囲気が大きく変わりましたね。
次の世代にバトンをつなぐ、「橋渡し役」としての経営ビジョン

──今後の展望について教えてください。
加古万千香:
私の使命は「橋渡し役」だと考えています。現会長が掲げた「100年続く会社にしたい」という思いを受け継ぎ、次の世代にしっかりとバトンを渡すことが私の役目です。そのためには、次代を担う世代が自らチャレンジできる環境を整えることが欠かせません。その一環として、新しい技術や仕組みを積極的に取り入れ、若い社員たちが無理なく活躍できる体制づくりを進めています。次世代の経営者がスムーズに経営を引き継げるよう、今から土台を築いていきたいですね。
また、パッケージソフトの活用も重視しています。自社で専用システムを開発するよりも、世間で広く使われているパッケージソフトを導入することで、常に最新の機能を利用できると考えているからです。今後は画像処理やAI技術なども取り入れつつ、さまざまなアプリケーションを連携させた効率的なシステム構築を目指します。
営業戦略としては、弊社の強みである半導体・液晶分野に注力しつつも、安定した経営のために分散した事業ポートフォリオを維持していく方針です。新規顧客開拓は年に1社程度を目標とし、キャパシティを考慮しながら着実に取引先を増やしていきたいと考えています。
一方で、次の世代へバトンを渡すためには、乗り越えなければならない課題もあります。特に中小企業を取り巻く情勢は非常に困難で、このままでは社員に十分な待遇を提供することが難しくなるでしょう。だからこそ、日々の業務の中で、どうすれば生産性を高められるのか、どうすればもっと働きやすくやりがいのある環境がつくれるのかを考え続けています。
私は社員一人ひとりの存在価値を見出し、イキイキと活躍できる職場を目指しており、必ず実現できると信じています。個々の強みや能力が発揮でき、弱みの克服を支援、また、チームでカバーやフォローできる体制をつくりたいと考えています。
将来的に社員が、自分の子どもを入社させたいと思えるような会社にすることが私の夢です。そのために、DXの推進や職場環境の改善、人材育成に引き続き力を入れていきます。
編集後記
職人文化が根付いた町工場を、次世代が活躍できる企業へと変革しようとする加古社長。その挑戦には、社員一人ひとりの成長を支え、組織の在り方を根本から見直すという強い意志が感じられた。
「自分の子どもを入社させたい会社に」という言葉には、単なる経営者の視点ではなく、働く人々の未来を見据えた温かい思いが込められている。これからの草川精機が、どのような進化を遂げていくのか、引き続き注目していきたい。

加古万千香/1969年京都府生まれ。1992年龍谷大学卒業。1999年歯科医療機器メーカーの勤務を経てキャリア採用にて株式会社草川精機に入社。主に経理、人事業務担当。2008年総務・経理課課長・業務課課長(兼任)に昇格。2018年専務取締役就任。2023年代表取締役社長就任。