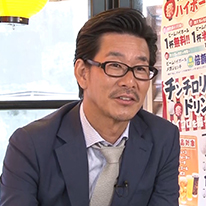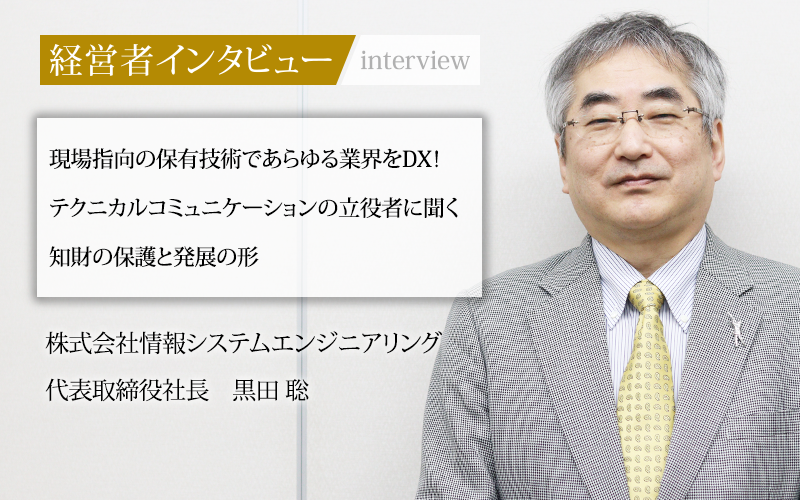
1979年に設立された株式会社情報システムエンジニアリングは、システム開発やコミュニケーション基盤の構築の構築を通じて、さまざまな業界のDX推進を支援してきた企業だ。会社を飛躍させたのは、デジタル社会の発展に伴い、複雑さを増したコミュニケーションを解決する独自の技術。代表取締役社長の黒田聡氏に、事業の変遷や自社技術の強み、今後の展望をうかがった。
ITの知見を活かし、父のソフトウェア開発企業で新規事業を創出
ーー入社の経緯やこれまでの取り組みについてお話しいただけますか。
黒田聡:
学生時代、父が創業した弊社でアルバイトをしていました。マニュアルの改善策を研究するコンピュータ分野の技術として、テクニカルコミュニケーションの知見を私が持ち込み、弊社で事業化したことが入社のきっかけです。
当時はワープロが世の中に広まる一方で、「使い方がわかりにくい」という問題があったため、製品に関する情報や技術プロセスなどを言語化するテクニカルコミュニケーションが求められていたのです。時代にマッチした事業は順調に成長していき、今ではテクニカルコミュニケーション業界で一等名の知れた会社となり、大手メーカー様との直接取引も実現しています。結果として、祖業であるソフトウェア開発も下請けから直請けに移行できました。キャリアを振り返ると、私がテクニカルコミュニケーションに出合い、弊社に持ち込んだタイミングも良かったと言えますね。
2017年以降は「固定資産を持つ会社になる」という目標を掲げ、自社技術の特許権取得に注力しています。日本・アメリカ・ドイツ・スイス・中国における産業財産権は自社サイトでリストを公開中です。
下請け企業から自社技術を誇る情報通信業の会社へ進化

ーー自社技術を権利化していくきっかけがあったのでしょうか?
黒田聡:
受託開発という立場上、あらゆる成果物の権利がお客様にあるため、会社の将来を危惧したことがきっかけです。また、コンピュータが安価になったことで競合が増え、プロキュアメントセンター(購買部門)からは「自社技術の独自性が認められなくなる」と警告を受けました。銀行から「黒田社長がいなくなったらブランド力がマイナスに転じる」と忠告されたことも大きいですね。
ソフトウェア開発の世界は、大手がトップにいるピラミッド構造です。同様の構造がある建設業界で特許化が進み、各社の技術が守られていく様子を見た私は、IT業界もそれに倣わなければ生き残れない会社が出てくると考えました。
これは、経済産業省が公開した「DXレポート」という報告書でも指摘されている、日本のソフトウェア産業の大きな問題点です。海外企業の多くは受託開発が少なく、固定資産でビジネスをしています。日本はアメリカに次ぐGDP規模でありながら、世界とは真逆の構造になっているのです。
技術の特許化にあたっては、過去の受託開発とは無関係の場で生まれた独自技術であると証明する必要があります。その一環として、近年は医療分野への技術応用という形で大学と共同研究を進めています。
特許を持つ独自技術「worktransform」を各種DXに応用
ーー現在の事業内容や貴社の強みを教えてください。
黒田聡:
特許を取得した独自技術「worktransform(ワークトランスフォーム)」(※)を軸に、情報システムの設計・開発、デジタルコンテンツ制作、技術コンサルティングといった関連事業を展開しています。独自技術の特徴として、「トラブルの予兆を察し、その芽を摘む」という画期的な思想があります。
たとえば、交通事故データを収集し、将来の事故対策をするのが従来のソフトウェアだとすると、日常を維持するのが弊社の技術です。何事もない時間を逸脱する動きがあれば、異変とみなして、人がその逸脱から復帰できるように知らせます。
「worktransform」はコンピュータ関係に始まり、デジタル家電や産業機器、現在は見守りの観点から医療・介護の世界でも活用されています。知識量や分野の異なる人同士が介護施設や病院などの現場で意思疎通を図る技法を提供するのが弊社の仕事です。ですから、新規開発には現場のデータが必要です。弊社は開発メンバーが現場で研修を受けるなど、お客様のニーズを形にできる体制が強みとなっています。
(※)「worktransform」は株式会社情報システムエンジニアリングの登録商標です。
ーー人材の能力はどのように伸ばしていますか?
黒田聡:
自社技術にもとづく高度な評価体系を用いて、人材に特許技術を習得させています。一般的なIT企業では、情報処理技術者試験の成績を目安に人材の能力を評価しますが、最近は学校の授業に情報科目があり、試験の特殊性が薄れてきたことが理由の一つです。
他社と差別化するには、先端技術を扱うユーザーではなく、技術や技法の提供者にならなければいけません。この方針から、自社の特許技術に対する理解を最初のステップとし、学びを活かして新しい技術を生み出す能力を評価項目に加えています。
大学・メーカーとの共同開発で新たなビジネスチャンスを模索
ーー今後の展望をお聞かせください。
黒田聡:
大学や医療機関と接点のあるメーカー様とつながり、共同開発する形で取引先を広げていきたいです。特に、医療・介護施設や工事現場、物流業界など、DXが浸透していない市場で研究を進めているメーカーと弊社の技術は、相性が良いと思っています。
新規事業のマネタイズを成功させて、2030年には自社技術を絞り込み、数字を狙っていくステージへ移りたいですね。今は事業の幅をなるべく広げ、可能性を模索しています。
また、社会的な課題として積極的に取り組みたいのは、介護の分野です。高齢者が増えていく国だからこそ、海外のようにビジネスが成り立つ領域にしなければいけないと言えるでしょう。
弊社が挑むのは常に新しい領域であるため、強い好奇心・向学心が求められます。異業種のマッチングに興味のある人や、過去の経験を下地にして未知の技術を学んでいきたい人に、ぜひ来ていただけるとうれしいです。
編集後記
事業を通して、さまざまな業界にイノベーションを起こしてきた情報システムエンジニアリング。下請けである限り、どんなに優れた技術を開発しても、自社の保有知財としてアピールできない。かつての状況を必死に変えたからこそ、企業は損失を免れ、未来を掴めたのだろう。顧客開拓と固定資産づくりを両立する黒田社長は、自身の構想も特許と解釈し、会社の価値を高めた上で次世代に事業承継したいと語った。

黒田聡/1963年生まれ。1986年、中央大学商学部を卒業。1987年、株式会社情報システムエンジニアリングに入社。2003年に代表取締役CTO、2011年に代表取締役社長に就任。京都大学大学院医学研究科非常勤講師、大阪大学大学院工学研究科招へい准教授、大阪大学大学院医学系研究科招へい研究員、大阪大学健康スポーツ科学教育研究環招へい准教授として、現在もコミュニケーション技法の研鑽に努める。