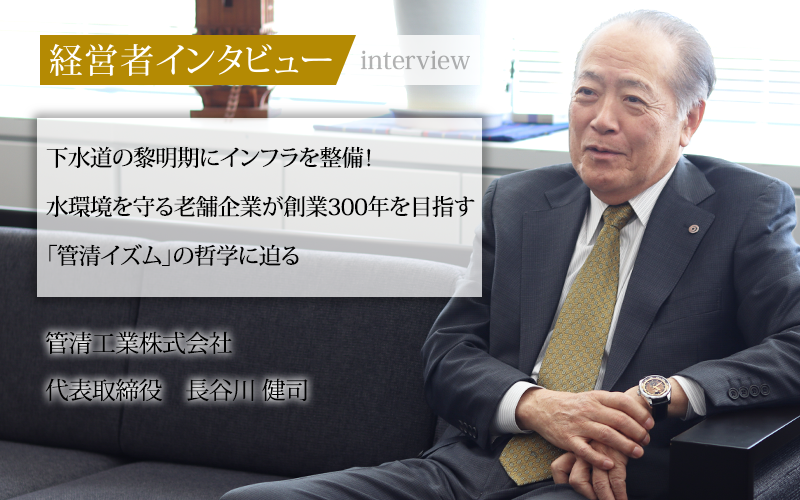
1962年に設立された管清工業株式会社。上下水道施設の維持管理をメインに、給排水設備や空調設備の設計・施工、測量・土木工事、さらに技術者の派遣事業、自社のノウハウを活かしたコンサルタント事業など、その事業は多岐にわたる。会社の前身は、建物の排水管や下水道管路の清掃・管理・機器販売事業で日本のインフラを支えてきた株式会社カンツールだ。同社の代表取締役を務める長谷川健司氏に、グループ企業ゆえの強みや今後の展望についてうかがった。
アメリカの下水道の管理事業を経験したのち家業へ
ーー入社前のご経験をお話しいただけますか?
長谷川健司:
大学を卒業後、広い世界を見たいと思い、ロサンゼルスへ渡りました。渡米したきっかけは、弊社を創業した祖父の生き方に感銘を受けたことです。祖父は日本への輸出業を営む中で、上下水道の清掃器具の取り扱いに携わっていました。
アメリカに20年滞在した後戦前に帰国し、その後、弊社の前身にあたるカンツールを創業しました。
その影響もあり、私はアメリカナイズされた家庭で育ちました。祖父はいつもコーヒーを飲んでいて、食卓にはオートミールが出てくる。そのように、幼少期からアメリカの文化が身近だったので、自身の渡米も「見知らぬ海外へ行く」というイメージではありませんでした。
渡米後は語学学校へ通いながら、日本人の方が営む写真用品店でアルバイトをしていました。その後、現地の下水道管理会社に約5年間勤めました。学生時代はずっと家業を手伝っていたので、英語が達者でなくても仕事ができたことがこの会社で働けた一番の理由ですね。
帰国するまでの期間で、日常会話で困らない程度の英語力だけでなく、発言力が身に付いたことが大きな収穫だったと思います。アメリカでは、日本のように他人に察してもらうことは難しく、自分の主義を主張しないと生き抜けません。
ーー帰国した理由もうかがえますか。
長谷川健司:
そのままアメリカで下水道関連の会社を立ち上げるつもりでしたが、私は3代目ということもあって、両親は帰国を望んでいました。海外で得た知見を家業発展のために伝える役割があると思い、恩返しという意味でも帰国して、家業を継ごうと決めました。
もちろん、家業へのリスペクトは昔からあり、学校が休みの日は、飲食店の厨房やトイレの水回りトラブルに駆けつけ、長期休みには公共工事の現場も手伝いました。最初こそ「変わった事業をやる会社」という認識でしたが、祖父が販売する機械が大学の教科書に載っているのを見て、社会の役に立っている仕事だと強く感じたものです。
時代を先読みできる経営者として3代目に就任
ーー入社当時の思いをお話しいただけますか。
長谷川健司:
弊社は、私の祖父が設立したカンツールという会社から、工事部門を切り離す形で誕生しました。カンツールは、下水道・排水施設の維持管理機器を取り扱う総合商社です。
3代目として入社した以上、どうしても他の社員と比較され、「社長の息子」という見られ方をしますよね。最初は悔しい気持ちになったものの、その状況を良しと思えたことが転機となりました。
当時の社長だった父・長谷川清の名が業界内で知られているのなら、「長谷川清の息子です」と言うだけで顔を覚えてもらえる。いわば発想の転換です。その一方で、いつか絶対に「長谷川清は長谷川健司のお父さんだったのか」と言わせたいとも思いました。自分の名を上げて、父や祖父を超えてみせる、という思いから仕事に打ち込むようになったのです。
ーー社長就任後の意気込みや取り組みもお聞かせください。
長谷川健司:
私は3代目として、会社を潰すか成長させるかのどちらかだと考えていました。その上で、会社をもっと大きくしなければと覚悟を決めたのは、守るべき社員たちがいたからです。
新しいトップとして、市場を先読みできる自信があり、その自信は今でも変わりません。私はアメリカでの経験を活かすことで、政治的・社会的な変化も含めて、業界の次なる展開を読むことができました。必要な設備投資など、具体的な予測が経営判断に役立っていますね。
管清工業の事業は、日本国内でこれから下水道を本格的に整備しようという時代に幕を開けました。その先進的なマインドは、世代を越えて受け継がれてきたといえるでしょう。
親会社・カンツールとの巧みな連携と営業力が強み

ーー改めて、事業内容や貴社の特徴を教えてください。
長谷川健司:
管清工業は、創業当時のトイレの詰まりを直す仕事から始まり、今では公共下水道の維持管理という大仕事に携わる会社となりました。民間向け排水事業としては、トイレ・台所から下水道を通り、処理場まで生活排水を運ぶ「パイプの管理」に特化しています。
その他、鉄道会社の排水・水道施設のメンテナンス事業や、下水道管内を清掃・調査する機材の開発・適用も行っています。
下水道の管理事業にはマニュアルがないため、創業から60年以上かけて培った経験値は絶対的な強みです。たとえば、新規参入したい会社が機械を購入する場合、まずはカンツールへ足を運ぶことになります。さらに、グループ企業の弊社で機械操作や現場の仕事を覚える必要があるため、自動的に私たちが下水道管理業界におけるリーディングカンパニーになるという仕組みです。
ーー開発における強みもうかがえますか?
長谷川健司:
開発においては、技術力の高さはもちろん、営業力も大きいと言えます。事業の種は現場に落ちていて、「こんな機械があったらいいな」というお客様の要望を聞き出し、具現化していくことが大切です。
お客様としては、新しい機械を採用する事業の成果が関心事となります。弊社の営業担当はそこを考慮し「3年程度の時間をください。」と提案します。そしてすぐに会社に連絡して、3年間で成果を上げる事業計画を立て、確実に実現できるという方向性で営業を進めるのです。
3年というのは一つの例ですが、数字をはじめ、具体例を出す重要性が営業部門に浸透しています。その営業部門が冗談で「お客様に長谷川マジックを見せる。」と言うほど、提案する営業力は絶大ですね。
目先の利益を追わない「正直な人材」を育て、外部の知見も活用
ーー独自の社風やルールはありますか?
長谷川健司:
社長就任の際に伝えた「300年続く会社にしたい」という思いは、全社員が意識していると思います。会社を存続させるためには目先の利益を追わず、ミスは隠すなという心得も伝えました。正直な姿勢で向き合えば、お客様はたとえミスがあっても、リベンジするチャンスを与えてくれるものです。
私自身も、赤字を出した週があればそれを正直に話し、「次の週で挽回できるよ」と社員を励ましていますので、社内全体で「正直が一番」「後悔せずに前を向く」という心がけが浸透しています。
ーー前向きな生き方は長谷川代表のポリシーでしょうか?
長谷川健司:
くよくよする時間は無駄と考え、どんな時でも後ろを振り向かないようにしています。失敗や不運が続いたら、神様が「上手くいかないからやめなさい」と言っているだけ。一生懸命やってもできない仕事は諦めていい。そう伝えると、社員も「気が楽になった」と言ってくれました。
日頃の顧客対応も実直だと自負しています。下水管の掃除をした翌日に雨が降ってしまうのは、不運な事例と言えるでしょう。しかし、「本当にちゃんと掃除したの?」と問い合わせをいただいた時に、言い訳をしてもメリットはありません。
もし下水管に土砂が入ってしまったのなら、再び掃除をしに行くのが弊社のスタイルです。会社と無関係のトラブルがあったとしても、問答無用ですぐに駆けつければ、お客様のお役に立つことができ、その結果リピーターになっていただけると考えています。
ーー人材育成の方針もお話しいただけますか。
長谷川健司:
グループ全体の従業員数は現在700名を超え、毎年30人ほど新入社員を迎えています。人材の成長においては、中途採用など外部から来た人の影響力も重視しています。
特に、管清工業の仕事しか知らない社員には良い刺激になりますね。仕事のやり方は一つではないのだから聞く耳を持ちなさい、と社内でよく言っています。歴史が長いからこそ、自分たちだけが正しいとするような会社は前進できないと言えるでしょう。
システム管理部門は、人工知能(AI)など最新のテクノロジーを取り入れやすいので、他の業界の手法も参考になります。賢く使い分ける形で、新しいスキルを持つ人とベテランの現場側が、上手く融合していく流れがベストですね。
営業部門も昔は足で稼ぐことが基本でしたが、今はそれだけではありません。SNSをはじめ、いろいろな媒体を活用しながらネットワークを広げています。
「清く正しく健全に」を基本に管清イズムを進化
ーー海外での取り組みもうかがえますか?
長谷川健司:
私たちは、発展途上国の水環境の整備と水管理人材の育成を支援するCWP GLOBAL株式会社という会社を2022年に出資設立しました。東ティモール民主共和国の大統領が「国民が手に職をつける形で国民を自立させたい」と話したことが、プロジェクトの発端です。
私たちならトイレの詰まりを直す仕事を教えられる、と手を挙げたところ、現地の国立職業能力開発センターに参入する運びとなりました。研修生は日本に来て、いろいろな現場で実務を経験することも可能です。海外展開については、ニーズがある社会的分野にどんどん入っていきたいと思っています。
ーー読者に向けて会社のアピールをお願いします。
長谷川健司:
弊社の取り組みや社員たちの働きについては、創業60周年記念として発刊した『日本の下水道を守る! 地下の勇士たち』という書籍でもおわかりいただけると思います。
当初は、私の経営理念を書籍化するという企画でしたが、社員のインタビューを中心に掲載してもらったところ、同業者の間で「とても面白い」と評価をいただきました。日本に下水道管理の概念がなかった頃に始めた事業が「ブルーオーシャン戦略」と称されたのも、この本がきっかけです。
ーー今後の展望をお聞かせください。
長谷川健司:
3代にわたって継承されたこの会社が、さらに後世に受け継がれていくことが夢ですね。企業の哲学や私なりの考え方を共有しながら、どのように事業継承するかが当面の課題です。
弊社には、「清く(二代目:長谷川清)、正しく(一代目:長谷川正)、健全に(三代目:長谷川健司)」という哲学があります。
社員に「会社が300年続いたあとはどうなりますか?」と尋ねられた際、私は「その次の300年を目指せばいい」と答えます。理想のガバナンスを実現し続けるにあたって、一番大事なことはこうした哲学の確立だと思います。企業理念をしっかりと持っている人がトップになれば、それが誰であっても周りが支えていく組織になるのではないでしょうか。
今後の弊社は「清く正しく健全に」という理念を会社存続の哲学として、どんな局面でも「管清イズム」と向き合っていく所存です。企業のイズムにはそのままで良いものもあれば、時代に合わせて変えていくべきものもあるでしょう。それぞれの特徴をきちんと理解して、管清イズムをつくり続ける中でも、哲学だけは受け継いでほしい。これが、私が遠い未来の話をする理由の一つです。
編集後記
正直な姿勢を貫く組織運営や、中途採用の新しい風を受け入れる向上心など、学ぶところが多いインタビューだった。記念誌を読んだ同業者に絶賛されただけあって、「こんなトップのもとで働けたら幸せだ」と思う人は少なくないはずだ。長谷川氏の語る言葉は、経営術である前に、人として忘れてはいけない真摯な生き方と揺るぎない哲学が込められている。その基礎を守り抜くことが、業界内で信頼を築き、300年先をも見据えた事業と日本のインフラを支えていくのだろう。

長谷川健司/大学を卒業後に単身渡米。現地の下水道管理会社へ入社。1983年に帰国し、管清工業株式会社へ入社。1987年に取締役、1998年に代表取締役に就任。














