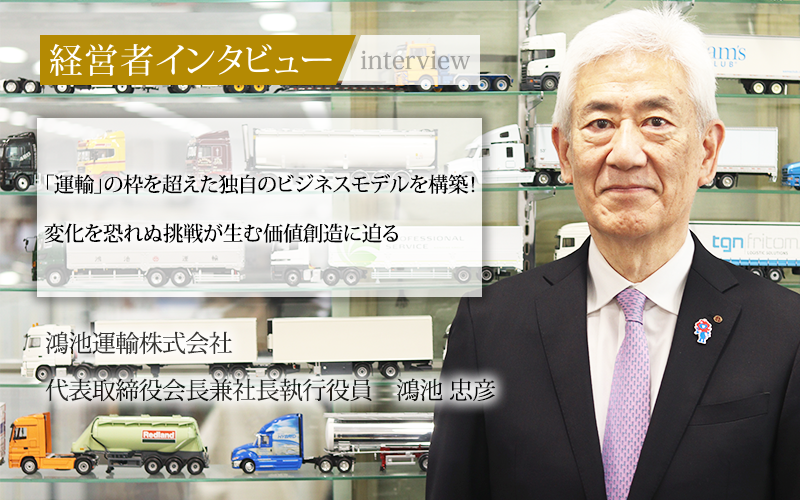
鴻池運輸株式会社は、社名にある「運輸」に縛られず、KONOIKEグループ全体を通して鉄鋼、食品、メディカルなどさまざまな分野で製造現場の請負やサポートを行ってきた。さらに近年は、鴻池忠彦社長の指揮のもと、デジタル技術によるサプライチェーンの効率化ソリューションの提供や、海外進出にも意欲的に取り組んでいる。鴻池社長はどんな未来を見据えているのか。今回、鴻池社長の狙いや思いをうかがった。
「NO」と言わずに何でもやる会社で、ものづくりの魅力を体感
ーー鴻池運輸に入社されるまでのご経歴を教えてください。
鴻池忠彦:
鴻池運輸に入社する前に、鴻池組に入社しました。当時の私は建築に関心がありましたし、建設現場を見ていて面白そうだと感じていたので、業界に飛び込んで自分でも体験したいと考えていました。鴻池組に入社後、しばらく現場の仕事を担当。その後は財務、経理、人事などの部門を回りました。鴻池組では5年ほど働き、その後、1981年に、父が社長を務めていた鴻池運輸に転職しました。
父が社長として働く姿を近くで見ていたので、「いつか自分が会社を継ぐんだ」という自覚はもちろんありました。ただ、自分としては社長の息子として気負いはあったものの、周囲の方はごく自然に接してくれました。
また、入社当時、弊社はまだ上場もしていませんでしたし、地域に根づいている運送会社というような感じの小さな会社でした。売上規模も今ほど大きくはなかったので、私自身、「この会社を背負っていくんだ」という気負いのようなものはまったくありませんでした。
ーー入社されて、鴻池運輸に対してどんなことを感じられましたか。
鴻池忠彦:
非常に突破力のあるパワフルな会社だと感じていました。特に営業マンは怖いもの知らずで、とにかく「NO」は言わない。仕事を受注したあとのことを深く考えずに、「顧客からの要望に全力で応えよう」と言って仕事を取ってくるので、実際に仕事が始まってから、現場の方々に無理をいうこともありました。
ーー入社後はどんな仕事を担当されましたか。
鴻池忠彦:
最初の一年間は鹿嶋の支店で基幹事業のひとつである鉄鋼事業に携わりました。製鉄所は大きな音と熱、振動、ほこりが相まって、厳しい労働環境ではあるんですが、迫力があって、日本の「本当のものづくり」を体感できました。鉄鋼の厚板を加熱して薄くのばす「熱延」という工程があるんですが、それを見るのが大好きでした。
そのあとは、日本空輸株式会社という航空貨物を扱うグループ会社で現場の仕事を経験しました。空港で花や生鮮食品などをトラックから空輸用のコンテナに積み替えたりと、体力的に大変な業務も多かったですが、仕事は楽しかったですね。1年ほど働いたあと、また鴻池運輸に戻りました。
「従業員の彼らがいてくれるから、この会社がある」

ーー鴻池運輸に戻られてから、どんな取り組みをされたのでしょうか。
鴻池忠彦:
1983年に常務になり、2003年に社長になるまでの20年間、業績にはものすごくこだわっていました。月に一度、朝8時から業績の報告会議を行っていたのですが、赤字の報告があった部署には必ず訪問して、現場のメンバーと一緒に数字を見たり、なぜ赤字になっているのか原因を探るようにしていました。
具体的には、日本と台湾の間で運行している国際物流事業が大幅な赤字になっていたことがあり、原因を調べると、どの港で荷物を積むかによって収益が変わることが判明。自社の施設がある大阪港に船をつけて、自分たちで荷役すると収益が良いのですが、他の港で荷役すると採算があまりよくないことに気づきました。そこで営業を強化し、大阪港での集荷拡大を行いました。
このように、現場に行って原因を分析して一つひとつ解決していくという方法で、各部門を確実に収益化させ、業績は改善していきました。今、思い返してみると、私がいろいろと細かく聞くので、現場の社員は大変だったと思いますが、よく応えてくれたと感謝しています。
ーーその他に取り組まれていたことはありましたか。
鴻池忠彦:
当時は今と比べると、人に対する配慮や気遣いがほとんどできていない時代でした。ですが私は、「従業員の彼らがいてくれるから、この会社がある」と思っていたので、従業員を大事にするように心がけていました。
当時、私が車を運転して従業員を送迎していた際、現場で「送るから乗って」と声をかけると、みんな「こんなに汚れているのに乗っていいの?」とすごく気にしていました。仕事のあと、安全靴は油でドロドロになるので、シートもフロアマットも汚れるからと。でも、作業服は私たちの制服みたいなもので、仕事をすれば汚れるのは当たり前。それで車のシートが汚れても別に構わないと思っていました。
ルーツが建設業だからこそ生まれた新ビジネスモデル

ーーそのような20年間を経て、社長に就任なさったときはどのような心境でしたか。
鴻池忠彦:
私がちょうど50歳を迎える2003年に社長に就任しましたが、非常に責任を痛感しました。副社長のポジションで仕事をするときに感じていたプレッシャーとは雲泥の差でした。
社長というのは、会社に何かあったら最後に責任を取らなければなりません。さらに、私が受け継いだバトンは、いずれ次の代に引き継がなければいけない。そのときに、「大きかったものを小さくして引き継ぎたくはない、もっと大きくよりよいものにして引き継いでいきたい」と決意しました。その決意は今も持ち続けています。
ーー改めて、現在の貴社の事業の特徴や強みを教えてください。
鴻池忠彦:
弊社は社名に“運輸”とついていますが、運輸、物流だけにとどまりません。売り上げの半分は製造業とサービス業の請負の売上で構成されていて、それが最大の特徴です。
原材料を運び、できた製品を運んで保管するという運輸事業だけを行っている同業他社はたくさんあります。今風に言えば「サードパーティー・ロジスティクス/3PL」です。私たちは、その「3PL」に製造などの請負を加えて「サードパーティー・プロダクション/3PP」と表現しています。受け入れた原材料を使って何かに加工したり、製品にラベルを貼ったり、品質検査をしたりということまで一気通貫で請け負える会社は少ないでしょう。
弊社が「3PP」を実現できるのは、鴻池運輸のルーツが建設業の鴻池組だからです。鴻池組は明治時代に、政府から淀川改良工事を請け負ったのをきっかけに、本格的に建設業に参入しました。その後、大阪で鉄鋼や紡績など新しい産業が興って、鴻池組が工場を次々と建設したんですが、社内に運輸部という部署があって、完成した工場に製造設備を搬入して据え付けていました。
ところが据え付けが終わると、次は製造ラインに原材料を運んでほしいと言われ、それも請け負った。すると次は、運んだ原材料を製造ラインに乗せるよう頼まれました。そうしてどんどん上流工程を請け負うようになっていった。その結果、ものづくりの分野にまで業務が広がったわけです。今はこの「3PP」をひとつのビジネスモデルとして、食品分野などいろいろな事業に参入しています。
従業員の声から浮き彫りになった「期待を超えなければ、仕事ではない」という想い
ーー貴社独自の理念や価値観といったものがあれば教えてください。
鴻池忠彦:
2018年、KONOIKEグループとしてブランド力を強化するために、企業理念等を見直して「私たちのブランド」を策定しました。その中でお客さまへ向けた「私たちの約束=ブランドプロミス」として、「期待を超えなければ、仕事ではない」を第一に掲げました。
この言葉は、現場の従業員の声から生まれたものです。「私たちのブランド」を策定する際に、外部の方に、現場の従業員から私を含めて数十人にインタビューしていただいたのですが、その内容を整理したところ、浮かび上がってきたのは「なんとしてもお客さまの期待に応えたい」という非常に強い使命感でした。これは、従業員の心に共通してある鴻池運輸の価値観であり、DNAのようなものなのかもしれません。
ーーその約束は、順調に果たされていますか。
鴻池忠彦:
「期待を超えられるんですよね?」と、従業員はときどきお客さまから試すような言葉をいただくこともあるようですが(笑)、「大丈夫です!」と答えているそうです。
自分たちがどれだけの価値を提供できているかを正確に測ることは難しいものです。しかし、各部門、「期待に応えたい」という思いで一生懸命仕事をしています。
DXや海外展開を果たし、「鴻池の幸せの木」にたくさんの果実を実らせたい

ーー今後の事業展開についておうかがいできますか。
鴻池忠彦:
先ほどお話しした「3PP」に、新技術を活用したコンサルティングサービスも加えた「4PP」を目指しています。特に、技術の中でもこれからはデータの活用がキーになると考えています。
たとえば、現在、輸送用トラックの4割くらいはカラで走っていると言われていますが、実際は中にどれだけ貨物が積まれているか目に見えていません。ですが、デジタル技術でトラックの空き状況などをデータ化すれば、どこに無駄があるのかが可視化できるので、それを改善することでさらに効率化していくことができる。また、倉庫の中に効率的に製品を配置する際にも、データを活用してシミュレーションすれば最適化できるでしょう。このように、デジタル技術を活用したソリューションで期待を超える仕事を提供していきたいとチャレンジしているところです。
ーーこの他にも、何か計画されていることはありますか。
鴻池忠彦:
中期経営計画の一環として海外展開も推進しており、現在はインドとASEAN諸国、アメリカ、カナダ、メキシコに力を入れています。特にインドについては、“鴻池第2の創業の地”にしようと計画中です。
2024年、インドで鉄鋼スラグ(鉄を生産する工程で産出される廃棄物・副産物)を処理する国営会社が民営化するということで入札があったんですが、弊社が落札することができました。先日私も視察に行ってきたのですが、日本のスラグ処理と比べるとまだまだ非効率なやり方をしている状況。改善すれば生産性や安全性の向上が図れますし、回収できる有価物の量も増えると予想しています。私たちが蓄積してきた知見を活かし、インドでの事業拡大を目指します。
他にも、メキシコやカナダでは、自動車部品の梱包事業なども今後拡大していくとともに、ヨーロッパでは、ドイツのデジタルソリューション開発グループと合弁会社もつくりました。
ーー今後、どのような人材を求めていらっしゃいますか。
鴻池忠彦:
先ほどもお伝えしましたが、弊社はチャレンジ精神旺盛な社風で、「期待を超えなければ、仕事ではない」というブランドメッセージを掲げています。さらに、ビジネスモデルの面でも、お客さまのニーズをくみ取りながら、進化し続けています。
ですので、チャレンジし続ける夢や情熱といった未来への熱量を持って、縦横無尽にチャレンジしようと目をキラキラ輝かせている、そんな人に来てほしいですね。
ーー最後に、鴻池社長が大切にされている思いを教えてください。
鴻池忠彦:
弊社は、従業員とその家族、協力会社のみなさんの幸せを実現することを大切にしています。それを私は「鴻池の幸せの木」と例えていて、「鴻池の幸せの木」にたくさんの「幸せの果実」を実らせたい。そのためには会社が、土台となる安全の場をつくっていかなければならないと思っています。
それと、KONOIKEグループが2030年に目指す姿「2030年ビジョン」として、「技術で、人が、高みを目指す」という目標も掲げています。お客さまに高価値のサービスを提供し、お客さまに納得していただいた上で、価値に見合う対価を受け取れるよう、これからも取り組んでいきます。
編集後記
物流業界は、人材不足をはじめとして「2025年問題」と呼ばれる多くの課題を抱えている。その中で、デジタル技術の力によって業務効率化を図るだけでなく、そのソリューションをコンサルティングによって広く他社にも提供しようとする鴻池社長の姿勢が印象的だった。それは自社の従業員のみならず、協力会社の関係者まで幸せにしたいという社長の願いとも重なる。「幸せの木」の果実がどれほど大きく実るのか、楽しみにしたい。

鴻池忠彦/1976年、株式会社鴻池組に入社。1981年には父・十郎氏が社長を務める鴻池運輸株式会社に入社する。常務取締役、専務取締役を経て1989年に代表取締役副社長に、2003年に代表取締役社長に就任する。2021年からは、代表取締役会長兼社長執行役員を務めている。














