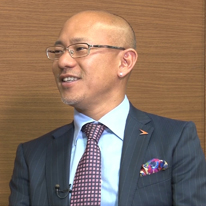介護保険制度の黎明期に介護業界へ飛び込み、26歳という若さで起業した中村祐介氏。ニーズは追うのではなく、先回りして生み出す――。その想いで常に「革新」に挑んできた。今では業界のスタンダードとなった特化型にしたサービスも、かつては類のない挑戦だった。顧客の信頼に支えられた創業期のエピソードや、「あらたかっぽい」と評される独自の経営理念などについてうかがった。
理学療法士の資格を、介護のフィールドへ
ーー介護業界に進んだきっかけは何だったのでしょうか。
中村祐介:
僕らの時代は就職自体が厳しい、いわゆる就職氷河期でした。普通のサラリーマンは自分には向いていないと思っていたので、家族から「こういう仕事があるよ」と理学療法士の道を勧められたのが最初のきっかけです。特別な憧れがあったというより、社会に出るための切符を手に入れる感覚でした。
2000年から介護保険制度がスタートすることは理学療法士の学生時代からわかっていました。医療と介護の住み分けが曖昧になっていく中で、多くの同級生は病院勤務を志望しましたが、私は当時としては新しいフィールドだった介護分野に将来性を感じました。介護保険事業は株式会社も参入可能で自由度が高い。そこで勝負した方がおもしろいし、やりがいもあると考えたのです。
原点は、小さな訪問看護ステーション
ーーその後、起業に至った経緯や当時の思いについてお聞かせください。
中村祐介:
理学療法士として、急性期から在宅支援まで一通り経験する中で、一人のプレイヤーとしての限界を感じました。当時も今も変わらず、1人の理学療法士が1日に算定できる報酬には上限があり、このままではいけないと思ったのです。起業するなら早い方が良いと考え、26歳で起業しました。周囲からは「その年齢で起業するのは早い」と言われましたが、むしろ、このまま病院に勤めている方が自分にとっては不安でした。
ーー創業当初はどのような事業から始めたのですか?
中村祐介:
資本金300万円で会社を設立し、最初は7万2,000円のワンルームで訪問看護ステーションを開設しました。そして、私自身が原動機付自動車で利用者さまの元へうかがいました。初期投資を抑えるためです。
当然、最初は「お前は誰だ」というところから自分で利用者を集めなければならなかったのですが、その後、営業専門のスタッフを雇い始めてからは、私はプレイヤーに専念できるようになりました。そのためには人件費がかかりますが、結果的にそれが最も事業の成長に繋がる方法だと思ったのです。
創業期ならではの苦労もいろいろありました。スタッフも増えて事業は順調になりつつありましたが、ある日スタッフが骨折して入院したため、急きょ私が朝7時から夜8時まで全ての患者さんを診るという経験もしました。人材への投資もかなり先行させていましたので、資金的に厳しい時期もありましたが、給料の遅配は一度もありませんでした。
一枚の看板からの直感
ーー事業が軌道に乗り始めたきっかけについて教えてください。
中村祐介:
創業して間もない頃、伊丹市の介護予防事業のコンペで私たちが選ばれたことが、一つの転機となりました。収益も安定しはじめたある日、事業用地を探して伊丹市を歩いていたときに、空きテナントの看板が目に留まったのです。その瞬間、訪問系のサービスをさらに広げるのではなく、「箱もの」を構えるべきだという直感が働きました。
今動かなければ遅い——そんな危機感も背中を押しました。
ーーデイサービスの立ち上げは順調に進んだのでしょうか。
中村祐介:
私の構想は、他にはない新しいかたちのデイサービスでした。介護事業が活況になる中で、革新的なことをやらないと、すぐに大きな資本に飲まれてしまうと感じていたからです。
当時、他に類を見ない斬新なものだったため、伊丹市からは「デイサービスとして開設を許可することはできない」と通達されました。しかし、ルールの枠内でどんなサービスをつくるかは私たちの自由だと信じていたので、行政にきちんと説明を重ねたうえで計画を推し進めました。
ところがテナント契約を済ませ、内装工事も始まっているのに、銀行から「実績不足」を理由に融資を断られ、万事休すの状況に陥ってしまいました。私は「実績がないのはわかっています。でも、実績を積むためには、まず先行して融資していただくしかない。今、私に貸さなければきっと後悔しますよ」と懸命に訴えましたが、結果はNG。
本当に困り果てていた時、日頃訪問していたある利用者さまが、私のやつれた様子に気づいて「まぁ、これでも食べてください」と差し出してくれた昆布のおにぎりとあおさの味噌汁の味を今でも鮮明に覚えています。身に沁みるとは、あのことですね。
そして、ある利用者さまとのエピソードです。その方はすべてを察しておられたのでしょうね。「もし私の父が生きていたら、きっと中村さんを応援していましたよ。私ももう少し若ければ、一緒にやりたいくらいですよ! ――それで、おいくら必要なのでしょうか?」と……。
私は咄嗟に「お願いします」と答えていました。何十万、何百万という金額ではありません。でも、そのときの私は「これしかない」と思ったのです。もちろん、約束通りに3年後には利息も含めてすべてを返済しました。このエピソードは、絶対に誰にも話さない約束だったのですが⋯⋯もう時効ですね。あの経験は、本当に大きなものでした。
地域に根ざすという選択

ーーその経験が、中村社長の「あらたかっぽさ」という経営スタイルに繋がっているのでしょうか。
中村祐介:
そうですね。「何にも失うものはない」という気持ちでしたし、1日でも早く、新しいことに投資をしたいという思いが強くありました。既存のサービスと同じことをしていては淘汰されるだけです。他社がやっていないこと、利用者さまにとって本当に価値のあるサービスを提供すること、それが「あらたかっぽさ」だと思います。
自分たちが「良い」と信じることを追求した結果、それが他とは違う独自性として認めていただけることになりました。周りから「あらたかっぽいね」と言われることは、地域に根付いている証だと受けとめています。
ーー事業を展開する上で、阪神間というエリアに限定しているのはなぜでしょうか。
中村祐介:
特定のエリアにリソースを集中させることで、効率を上げ、サービスの質を高める狙いがありました。そのため事業エリアを伊丹から神戸にかけて絞り込み、地域内での知名度やサービスの密度を高めることが成功の鍵だと考えています。あちこちに手を広げるのではなく、「この地域で一番を目指す」。それが最も効率的であり、地域に貢献することにもなると信じています。
「最期まで幸せだった」と思ってもらえるサービスを
ーー社員の方々とのコミュニケーションで大切にされていることは何ですか。
中村祐介:
ゆるやかな繋がりを大切にしています。たとえば、グループウェアというコミュニケーションソフトを活用して、数百人在籍する社員全員がコミュニケーションできる仕組みを作ってきました。また、社員の誕生日には会社からプレゼントを贈ります。その際に、私からメッセージを添えるのですが、そうやって社員みんなとの対話を心掛けています。
すべてを把握することは難しくなってきましたが、アンテナを張って、社員が困っている時に会社は助けの手を差し伸べる――ロープのような存在でありたいですね。
ーー最後に、今後の展望についてお聞かせください。
中村祐介:
会社を大きくすること自体が目的ではありません。しかし、質の高いサービスを提供し続けるためには、ある程度の規模も必要です。私たちの究極の目標は、この阪神間で暮らすお客様が、「あらたかのサービスを受けて良かった」「この地域に住んでいて良かった、最期まで幸せだった」と心から思ってもらえるようなサービスを提供すること。そして、それを提供した従業員たちが、「この仕事をしていて良かった」「この会社を選んで良かった」と誇りを持てる会社にしたい。それが実現できれば、26歳で起業して、今日まで事業に取り組んできて良かったと思えるはずです。
編集後記
中村社長の歩みは、逆境を好機に変える洞察力、常識に挑む「あらたかっぽさ」、そしてチャンスを逃さない「スピード感」に彩られている。特にデイサービス立ち上げ時の資金難を利用者からの深い信頼によって乗り越えたエピソードは、同氏の人柄と事業への情熱を感じた。
阪神間という地域に密着し、利用者と従業員双方の「最期の瞬間までの幸せ」を真摯に追求する姿勢は、企業の社会的な存在意義を改めて問いかける。その原動力には、創業期の苦楽を共にした仲間への感謝と、一個のおにぎりに込められた人の温もりを忘れない心根があるのだろう。

中村祐介/理学療法士としてキャリアをスタート。2000年の介護保険制度開始を機に介護分野へ進出し、2005年に26歳で有限会社あらたかを立ち上げ。訪問看護ステーションを開設後、新しいアプローチのデイサービスの展開などで事業を拡大。2019年にARATAKA STAR HOLDINGS 株式会社を設立し、CEOに就任。現在は、介護事業全般に加え、医療法人や保育園の運営も手がけながら、阪神間に暮らす方々に企業としてどう寄り添い、根ざしていけるかを日々探究し、挑戦を続けている。